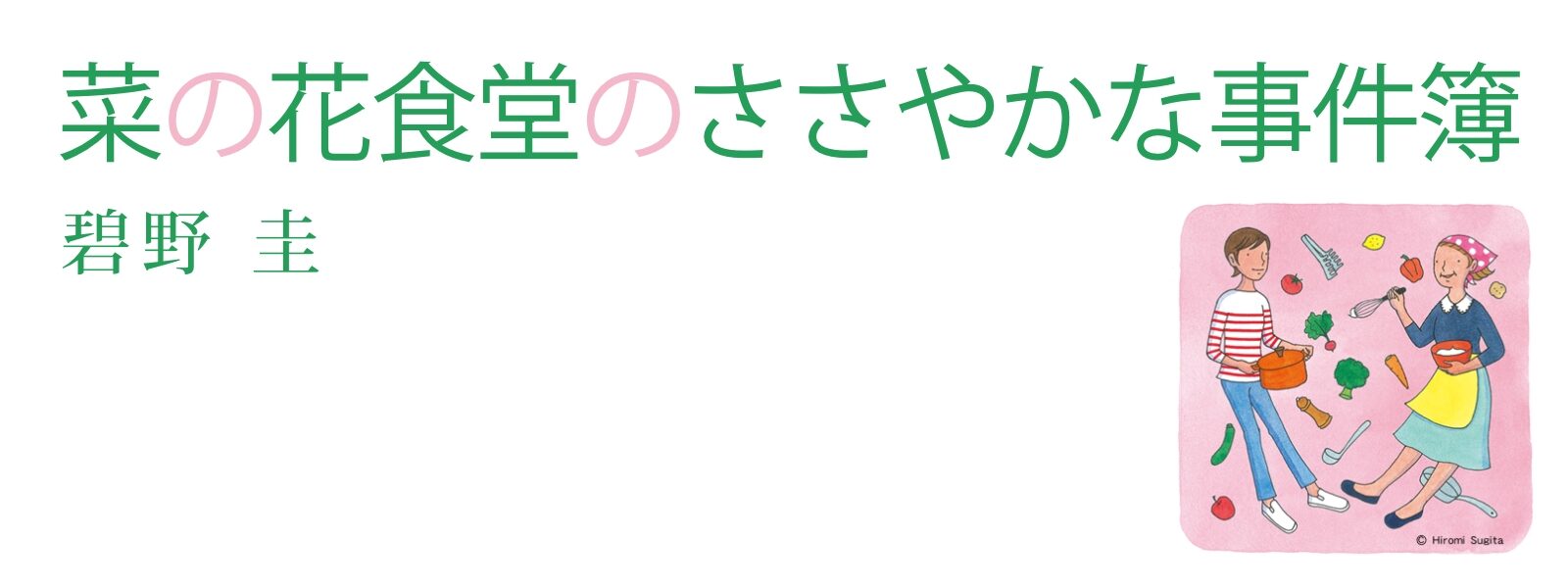蕎麦と思いやり 前編
「ここでは蕎麦は出さないの?」
ある日のランチタイムが終わる頃、常連の守屋正一さんに聞かれた。
この日のランチは珍しく素麺を出していた。魚の出汁で溶いた胡麻だれに、ネギやミョウガ、大葉、きゅうりなどを混ぜ、素麺を付けて食べる。冷や汁のアレンジだそうだ。冷たく冷やしているので、のど越しがいい。このところ暑い日が続くので少しでも食べやすいものを、という工夫だ。ほかに炊き込みご飯の小さめのおにぎりふたつと温泉卵、ナスと鶏胸肉の甘酢漬けがついている。夏バテで食欲が減退しているというお客さまにも大好評だ。
「私が知る限りでは、出したことがありませんが」
私、館林優希は守屋さんのコップに水を注ぎながら言う。ランチタイムも終わる頃、お客さまは少ない。守屋さんはひとりなので、カウンター席に座っている。
「一度もないの?」
守屋さんはカウンターの内側にいるオーナーシェフの下河辺靖子先生に確認する。靖子先生と私が言うのは、先生は料理教室の先生でもあるからだ。私は料理教室では先生の助手、普段は菜の花食堂のホール担当をしている。
「ええ、ありません。蕎麦はやはり蕎麦屋の方にはかないませんから。ほんとに美味しい蕎麦を出すとなったら、麺を作るところからやらなきゃいけないでしょう?」
靖子先生が笑顔で言う。人を和ませるような優しい笑顔だ。この笑顔も、菜の花食堂の名物と言ってもいい。
「素麺はお嫌いですか?」
私が聞くと、守屋さんは首を横に振る。
「そんなことないよ。これは実に美味い。こういう食べ方は初めてだけど、つけ汁にコクがあるからさっぱりした素麺が引き立つ。いくらでも食べられそうだ」
そう言って守屋さんは素麺を手繰って口に運ぶ。素麺を呑み込むと、美味しいというようにっこり笑った。
「美味いから、蕎麦でもこんな風にできないかと思うんだよ。俺は蕎麦が好きなんで」
「素麺はクセがないから、めんつゆ以外とも馴染みがいいんですよ。それに乾麺を手軽に使える。蕎麦は手打ちが好きな方には、乾麺や袋麺では物足りないでしょうし」
「俺は蕎麦ならなんでもいいんだけど。乾麺でも茹でた麺でも。週に一度は蕎麦を食わなきゃ落ち着かない。毎日だっていいくらいだ。一緒に出されるものも、なんだっていいんだよ。煮物でも揚げ物でも。ここのお店なら何でも間違いない」
「やはり守屋さんも蕎麦好きなんですね」
靖子先生は微笑んだ。
「俺もって、どういうこと?」
「いえ、東京の人は蕎麦がお好きだなって思うんですよ。私は関西出身だし、蕎麦よりもどちらかといえばうどんの方が馴染み深いので、東京の人の蕎麦好きには感心させられるんです」
「まあ、そうだね。蕎麦は江戸の頃から名物だからね。江戸の屋台で広まった、いわば江戸時代のファストフード。江戸っ子なら蕎麦嫌いはまずいないと思うよ」
守屋さんはちょっと得意そうに胸を張る。守屋さんは代々この地で酒屋をしている家で生まれ育った。この辺りは東京二三区よりもずっと西にあるので江戸には含まれないはずだが、幕府の直轄領だったからここで生まれ育てば江戸っ子だ、と守屋さんは主張している。二三区に住んでいても三代前から住んでいなければ、江戸っ子ではないのだそうだ。
靖子先生は調理する手を休めず話を続ける。
「うどんは他とも馴染みやすい。でも、蕎麦はそれ自体個性がある。それを活かす食べ方となると、やっぱりオーソドックスに出汁の利いたそばつゆと合わせるのがいちばん馴染むと思うんですよ。合わせるのは天ぷらとかかまぼことか定番がいい。蕎麦好きの人ほどシンプルな食べ方を好む気がするんですよ」
「むむむ、確かにそうだけど、北口の方には創作蕎麦を売りにしたお店もあるよ」
「あの店は蕎麦から手作りしてますよね。蕎麦自体のつなぎを工夫して、ほかの具材とあうようにしています。うちではそこまでの事はできませんよ」
そう言って靖子先生は柔らかく微笑む。守屋さんのこだわりが子供じみているように思えるのかもしれない。
「そうなのか。この店だったらまた新しい蕎麦の料理を作ってくれると思ったんだけどなあ」
「この辺にだっていい蕎麦屋はあるじゃないですか。餅は餅屋ですよ」
「それはそうだけど」
「それに乾麺や茹で麺でよければ、おうちでも作ってもらえるでしょう?」
「それが、うちの奴は残念ながらうどん派なんだ。週末は簡単に済ませたいからとうどんをよく使う。それこそ肉と野菜をたっぷり混ぜた焼きうどんとか、夕べの残り物のカレーを使ったカレーうどんとか。もちろん麺はスーパーで買った茹で麺だ。蕎麦はまず作らない。蕎麦については茹で麺や乾麺と手打ちの麺とでは差があり過ぎるんだそうだ。手打ち以外は蕎麦じゃないって言う。そういう意味では、あいつも蕎麦へのこだわりが強いのかもしれないが」
「だったら、守屋さんが蕎麦を打てばいいんじゃないでしょうか。蕎麦打ちをやる男性も最近では増えているでしょ?」
「うん、そう思って一度トライした事あるんだけど、茹でてるうちにボロボロ崩れてきちゃってさ。上手く打てるようになるまでは時間が掛かるんだよ。家族はボロボロのは食べたがらない。蕎麦打ちが上手くなるには、下手な蕎麦でも黙って食べてくれる家族の協力がないと無理だと思うなあ。ひとりでは食べ切れないし」
守屋さんは不満そうだ。年取ってから蕎麦打ちを始める男性は多いけど、上手くなるまでは周りの忍耐が必要ということだ。蕎麦好きの家族なら、多少出来が悪くても食べてくれるかもしれないが。
「確かに、家族皆さんの好みが同じだといいけど、なかなかそうはいきませんからねえ。奥さまが食べないとなると、お子さんもあまりお好きじゃないのでは?」
「そうなんだよね。子どもたちも蕎麦よりうどんが好きだと言う。そうなるとますます家では蕎麦の出番が無くなる。家族旅行でたまに蕎麦の名産地に行った時に有名な店で食べるくらい。そういう時は美味いって言ってるんだけどなあ」
「だとすると、奥様もお蕎麦がまったくダメというわけではないんですね」
「そうだと思う。ただ、こだわりが強いんだよ」
守屋さんはあきらめたように言う。
「それがなきゃ、奥さんは料理上手だし、文句はないんだけどね」
蕎麦の好みは違うというけど、守屋さんの家族は仲がいい。よく家族で遊園地に行ったり、旅行に出掛けたりしている。うちにもたまに家族で食事に来る。蕎麦の好みの違いは数少ない不満なのかもしれない。
「まあまあ、それならいいじゃないですか。蕎麦以外にも美味しいものはたくさんありますからね」
「そうだけどさ、出来れば家でも蕎麦を作ってほしいんだよ」
その時、「ごめんください」と声がした。入口のところに視線を向けると、そこには農家の保田俊之さんがいた。手にはニンニクがいくつも入った網袋を持っている。
「あ、わざわざすみません」
私は保田さんの傍に行き、袋ごとニンニクを受け取る。大きな粒の新鮮なニンニクだ。今日の夜の料理に使うものを、保田さんに持って来てもらったのだ。
「ちょうど切らしてしまったんです。持って来ていただいて、助かりました」
「お代はいつものように月末にまとめて請求するから」
「はい、ありがとうございます」
私が立ったまま保田さんに応対していると、守屋さんが声を掛けてきた。
「おや、俊ちゃんじゃないか」
「誰かと思えば正一」
保田さんと守屋さんがお互い名前で呼び合う。
「お知り合いですか?」
私は受け取ったニンニクをカウンターの内側にいる先生に渡すと、座っている守屋さんに尋ねた。
「もちろん。坂上と坂下で住む場所は違ったけど、中学は一緒でそれ以来の付き合い。今でもたまに囲碁をやる。囲碁仲間っていうか碁敵ってやつさ」
なるほど、両方とも生粋の地元民ということだ。この辺は住宅地で人の入れ替わりも激しいが、代々農家をしている保田さんや、駅前で代々続く酒屋を営む家で育った守屋さんは先祖代々ここに住んでいる。
「今日のランチは冷や汁素麺? 美味そうだね。俺もここでランチにすればよかった」
保田さんがうらやましそうに言う。
「保田さんも蕎麦がお好きなんですか?」
私はふと聞いてみた。私自身も静岡出身なので、さほど蕎麦にこだわりはない。子どもの頃はうどんの方が身近だった気がする。
「蕎麦? どうして?」
保田さんはきょとんとした顔をしている。
「東京の人は蕎麦好きだって話していたんですよ」
「もちろんそうだよなあ、蕎麦は江戸っ子の誇りだし」
守屋さんが同意を求めるが、保田さんは憮然とした顔で答える。
「俺はうどん派だよ」
「うどん派? 江戸っ子の風上にも置けないな」
守屋さんが不満そうに言う。
「俺は江戸より古い武蔵国(ルビむさしのくに)出身を誇りにしているからな。武蔵国といえば武蔵野うどんだ」
武蔵国は古代から伝わる行政区分のことで、現在の埼玉県、東京都、神奈川県の一部を差す。八世紀頃には東京西部の府中市に国府が置かれたので、江戸以前は府中の方が武蔵国の中心だった。府中はここからすぐ南にある。
「武蔵野うどん? あの固くて食べにくいやつ」
守屋さんが馬鹿にした口調で言う。
「なんだと。武蔵野うどんはこの辺りで取れた小麦を使い、この地で発展したまぎれもない地元の特産品だ。冠婚葬祭何かというとうどんを振る舞うのがこの地の習わしだ。昔はうどんを上手に打てないと嫁に行けないと言われていた。商工会議所の人間がそれを馬鹿にするっていうのは、よくないんじゃないか」
「蕎麦だって深大寺蕎麦って名物がある。深大寺はお隣の調布にあり、地元で採れた蕎麦粉を使って作っていた。調布とは地続きのこの辺りだって、蕎麦は採れただろう。だから蕎麦だって地元の特産品だ」
「何をめちゃくちゃなことを」
保田さん同様、さすがにそれは無理がある、と私も思う。今現在、この辺りで蕎麦を作っている農家はない。調布でもごく一部で作られているだけだと聞く。
「そもそも蕎麦の方が美味い。武蔵野うどんより多くの人にも愛されている。だから蕎麦を好きになるのは当たり前の話だ」
「そりゃ、美味い武蔵野うどんを食べたことがないからだろう。蕎麦なんてモソモソして美味くないじゃないか」
「そっちこそ美味い蕎麦を食ったことないんだな。どうせスーパーで売ってる乾麺か袋麺でしか食べたことないんだろう。打ち立ての蕎麦の品のある味わいは、他じゃちょっとないものだぞ」
五〇代過ぎたいい大人が額に青筋立てて、まるで中学生の男の子同士みたいに言い争っている。私はつい吹き出したくなった。
「そんなにおっしゃるんなら、美味しい蕎麦と美味しい武蔵野うどんの食べ比べでもしたらいいんじゃないですか?」
私は思わず言ってみた。
「食べ比べ?」
「お互いがこれぞいちばん美味い蕎麦、あるいはいちばん美味いうどんと思うものを持ち寄って、それぞれに食べてもらえばいいじゃないですか」
「つまりうどんと蕎麦の味比べってわけか」
私の思いつきに、保田さんは目を輝かす。
「もしその場で麺を打ちたい、作りたいということであれば、ここを使ったらどうでしょうか。ねえ、先生?」
私は先生に同意を求める。
「そうね。定休日なら店も空いてるし、料理教室の部屋を使えば蕎麦でもうどんでも打てるだけのスペースはありますね」
先生も興味深そうだ。
「それは面白そうだ。俺はかみさんにたのんで、武蔵野うどんを打ってもらう。うちのかみさんの武蔵野うどんはちょっとしたもんだからな」
保田さんが得意げに言う。それを聞いて守屋さんは悔しそうに唇を噛む。
「そっちもかみさんに蕎麦を打ってもらったらどうだ?」
「うちのかみさんは蕎麦は打てない。でも、俺の蕎麦の師匠に頼んでみる」
「蕎麦の師匠?」
「俺、江戸蕎麦愛好会のメンバーなんだ」
「江戸蕎麦愛好会?」
「昔ながらの手打ち蕎麦の店を訪ねて食する、まあ蕎麦グルメの会みたいなもんだが。そこのリーダーが趣味で蕎麦打ちをしている。これが絶品なんだ。俺が頼めば蕎麦打ちに来てくれると思う」
「へえ、それは奇特な友人がいるもんだな」
「蕎麦についての本も何冊か出している。彼ならきっと喜んで引き受けてくれる。蕎麦本来の良さを広めるのも江戸蕎麦愛好会の役目だからな」
守屋さんは胸を張る。
面白そうだが、思ったより大事になりそうだ。
「で、蕎麦とうどん、どっちが美味いかをこの際、はっきりさせよう」
守屋さんが言うと、保田さんも言い返す。
「蕎麦対うどんの頂上決戦だ」
「頂上決戦?」
私が思わず聞き返す。食べ比べするだけなのに、なぜ頂上決戦になる?
「みんなに食べてもらって、どっちが美味いか投票してもらうんだ。それで美味いのがどっちか、はっきりさせる」
「いいねえ、やろうじゃないか。そして蕎麦の美味さをみんなに知らしめる」
守屋さんも乗り気だ。
「投票なんて、そこまでやらなくても」
靖子先生は止めようとするが、乗り気になった男たちは聞く耳を持たない。
「靖子さんも参加してくださいよ。審査員として」
「審査員?」
「そうだ、来てくれる人にどっちが美味いか、審査してもらう。靖子さんはもプロの料理人として審査に加わってもらいたい」
「来てくれる人って、何人くらい呼ぶつもりですか?」
靖子さんが守屋さんに聞く。
「多けりゃ多いほどいい。蕎麦の美味さをできるだけ多くの人に知ってもらいたい」
すると、それには保田さんが反対した。
「いや、そういうわけにもいかんだろう。プロじゃないんだから、打つ量にも限界がある。武蔵野うどんは打つのも大変なんだ。うちのかみさんだって、そんなに暇じゃないし」
「そうだな。打つのは俺たちじゃないし。あんまり大勢ってわけにもいかないか」
「せいぜい十人分ってとこかな」
「じゃあ、審査員は十人?」
「いや、それだと俺らの分がない。俺らが審査員ってわけにはいかんだろう。審査は公明正大に行わないといけないし。それに打ってくれるふたりの分も必要だ」
「そうか。身内だから審査員にはなれないけど、うちの嫁にも食べさせたいな。そうなると、審査員は五人くらいかな」
「うん、五人で十分だ。プロの料理人として靖子さんが審査委員長、同じくプロの香奈ちゃんと優希ちゃんで三人」
「私が審査委員長ですか?」
靖子先生は目を丸くする。困惑しているようにも見える。
「私も審査員なんですか?」
キッチンにいた和泉香奈さんも驚いている。香奈さんは調理スタッフだ。先生と違って面白がっているようだ。
「そう。場所もここをお借りするわけだし、乗りかかった舟だと思ってお願いしますよ」
「はあ」
「で、あとふたりはそうだな。優希ちゃん、悟朗ちゃんを連れてきたら? 香奈ちゃんも彼氏を連れておいでよ。そうすると五人になるから、審査員の数としたらちょうどいい」
悟朗ちゃんというのは私の彼氏、川島悟朗さんのことだ。悟朗さんは保田さんが経営するアパートの住人なので、保田さんとも親しい。
「えっ、悟朗ちゃん? 彼は俊ちゃんところの店子だろ? それじゃ俊ちゃんの方が有利じゃないか」
「大丈夫。ちゃんと言っておけば彼はちゃんと公正に票を投じるから」
「ほんとかな?」
「大丈夫ですよ。悟朗さんはずるい事は嫌いな人だから」
私が言うと、守屋さんが冷やかすような口調で言う。
「おや、さすがに優希ちゃんは悟朗ちゃんに肩入れするね。優希ちゃんを信じて、悟朗ちゃんも審査に加わってもらうか」
「でも、時間があえばですよ。校了前は土日でも出社したりしてますから」
私は念を押す。悟朗さんが来るのは嬉しいけど、仕事の邪魔はしたくない。
「もちろん仕事なら仕方ない。で、香奈ちゃんの方は大丈夫かな?」
「はい。日にちが合えば、ダメとは言わないと思います」
「よし、決まった。じゃあ、あとはスケジュールだ。みんなの予定を聞いて、スケジュールを合わせよう。早ければ来週の日曜日とか、どうかな?」
守屋さんがみんなに聞く。
「俺の方は大丈夫だ。お店はどうですか?」
「来週の日曜日は、いまのところ予約はないです」
私は予約表を見ながら言う。
「じゃあ、第一候補は来週の日曜日で。師匠に聞いて都合がよければその日にしよう」
「わかった」
「じゃあ、かみさんにはせいぜい腕を磨いてもらって、対決に備えるようにって伝えといてくれ」
「おまえんとこの師匠にもな」
保田さんと守屋さんはテンション高く、楽しそうだ。私自身も武蔵野うどんを食べたことがないし、打ち立ての蕎麦も美味しそうだ。なんだかおもしろいことになりそうだ、と内心ワクワクしていた。
「そうか、それで俺も審査員に選ばれたっていうわけか。保田さんに聞いて、どういうことかと思ってたよ」
その次の休日、私は悟朗さんと駅の北側にある創作蕎麦屋に来ていた。守屋さんから蕎麦の話を聞いていたら、無性に食べたくなってしまったのだ。
「だけど、ほんとはその対決はちょっと不公平だね。蕎麦といったら蕎麦全般なんでもありだけど、武蔵野うどんはうどん全般の中からごく一部だ。うどんと言ったら、有名な讃岐うどんや稲庭うどん、水沢うどん、最近有名になってきた伊勢うどんなんていうのもある。名古屋の味噌煮込みうどんもうどんの一種だし」
「味噌煮込みうどんは食べたことがある。かなり麺が固いよね。半生かと最初思ったくらい」
「うん、そう。逆に伊勢うどんは腰がなくてふにゃふにゃに柔らかい。うどんも腰が大事と思っていたら、概念が覆される」
「へえ、ちょっと食べてみたい」
「その中で武蔵野うどんといったら限定的だ。だけど、蕎麦は何でもいいというのでは、条件が合わない気がするけど」
「一応、深大寺蕎麦ということらしいよ。地元対決っていうことで」
「深大寺蕎麦か。なるほどね」
「でも深大寺蕎麦自体は深大寺近辺で採れた蕎麦の実から作った蕎麦、というくらいで特に変わったところはなかったような」
私も以前深大寺やその近くの植物園に遊びに行った時、蕎麦屋で蕎麦を食べた。その近辺には深大寺蕎麦という幟を掲げた店が何軒もあった。昔は深大寺そのもので蕎麦を作っていたそうだが、いまは名前だけ残っていて寺では作っていない。
「深大寺蕎麦は白っぽくて甘味があり、湧き水を使っているのが特徴だったと思う」
「悟朗さん、詳しいのね」
「雑誌の特集で蕎麦は何度か扱ったことがあるからね。付け焼刃の知識はある。蕎麦は割と人気がある企画なんだよ」
悟朗さんは照れたように笑う。悟朗さんは出版社で働いており、男性の趣味を扱う雑誌の編集部に所属している。中高年層をターゲットにしており、蕎麦打ちの特集なども時々扱っているそうだ。
「それに会社の同僚が蕎麦好きでね。よく蕎麦の名店に連れて行かれるんだ」
「へえ、やっぱり名店の蕎麦ってふつうとは違うもの?」
「ん、まあ、そうだと言えばそうだけど」
悟朗さんは珈琲カップを持ったまま口ごもる。
「たとえば珈琲だと値段が高いものほどいい香りがするよね。香りのよさも値段のうちというか。だけど、蕎麦は逆なんだ」
「というと?」
「蕎麦って上等なものになればなるほど特有の色も香りも薄まる。蕎麦の実を製粉する時、最初に砕けやすい真ん中の胚乳部分が粉になる。それが一番粉あるいは更科粉と呼ばれ、その粉だけで作ると白くて甘味が強いけど、香りはあまりない」
「それが高級な蕎麦ってこと?」
「製粉の時に取れる量が少ないからね。更科粉にならなかった部分を再度ローラーに掛けると胚乳の外側や胚芽が粉になる。これは淡い緑色になり、二番粉と言われる」
「じゃあ、私たちがいつも食べているグレーっぽい蕎麦は?」
「二番粉にならなかった部分をさらにローラーに通した三番粉とよばれるものを使っているんだ。蕎麦の実の成分をそのまま粉にする。なので篩に掛けても種皮や胚芽の成分が残る。つまり白パンと全粒粉のパンの違いみたいなもんだよ。僕らが蕎麦らしい香りと思うのは、実の胚芽や種皮やそれに近い部分を砕くことで生まれる。なので、上等な蕎麦ほど香りが薄いとも言える」
「そうなんだ。知らなかった」
「僕も特集のために調べたり、同僚に聞くまで知らなかった。実際、更科蕎麦と言われるものはのど越しを楽しむもので、香りは後からふっと立ち上がるものだそうだ。ほんとのところ、それが僕にはよくわからない」
「そういうものなの? だったら高いお店で食べる意味がないんじゃない?」
「でもまあ、歯ごたえというか、麺の存在感というのが、いい店のものは確かに違う。見た目も艶があって綺麗だと思うし。だけど味の差と言われるとねえ。たとえばフレンチとかイタリアンとか普通の和食なら、素材とか味の違いが値段の違いだとすぐわかるけど、蕎麦については知識なしではわからない気がする。一般には手打ちがいいとされるけど、実は機械を使っても大きな差はない。名店と言われる店でもまったく機械を使わない方が少ないんじゃないかと思う。流行っている店ほど機械に頼らないと量はこなせないからね」
「それは意外。手打ちの方が絶対いいんだと思っていた」
手打ちを売りにしている店はわざわざそれとわかるように店頭で掲示している。有名なお店はみんな手打ちなのかと私は思っていた。
「たとえ機械を使ったとしても、店で自家製粉し、打ち立ての蕎麦を出す店はやっぱり違う。挽きたて、打ち立て、茹でたてが美味しい蕎麦の基準と言われているけど、確かにそうだと思う。だけどその差はすごく繊細だし、味に劇的な違いがあるわけではないから、意識していないとわからないかもしれない」
「じゃあ、普通に考える蕎麦と実際は違うもんなんだね。うどんや素麺と同じで、手軽に作って食べられる麺の一種だと思っていた。江戸時代のファストフードだって守屋さんは言っていたし」
「そうだよね。でも、だからこそ蕎麦には深みがあるって蕎麦好きの人ははまるんだと思う」
「はい、お待ちどう」
店の人が注文した品を運んで来た。男性ひとりで切り盛りしているので、シェフが自ら運んで来る。悟朗さんは魚介マリネの蕎麦、私は地元野菜を使ったラタトゥユ蕎麦だ。魚介類のマリネの蕎麦は海老、イカ、ムール貝に野菜が蕎麦の上に載っており、フレンチレストランのようにバジルソースで模様が描かれている。ラタトゥイユ蕎麦の方は大きく切ったブロッコリーやトマト、カラーピーマンが載ったトマトソースに別盛りの蕎麦を浸して食べる。初めて見る蕎麦料理だ。
「美味しそう」
色どりもきれいで、まるでイタリアンのようなおしゃれな盛り付けだ。添えられている蕎麦もパスタの中でも一番細いカッペリーニのように見える。
「この蕎麦、白っぽいけど、これが更科粉を使った蕎麦ってこと?」
私が聞くと、悟朗さんは首を傾げる。
「どうだろ。通常の蕎麦粉を使った蕎麦に比べると白っぽいけど、更科粉よりは色がついている。マスター、こちらはどこの粉を使っているの?」
「今日の粉は福島のものです。更科粉は切れやすくなるし、捏ねる時に湯ごねでないとうまくいかないんですよ。そうなると作業の手間が掛かるので、うちでは使いません」
「マスターは蕎麦職人だったんですか?」
「いや、もともとは洋食の店で働いていました」
「じゃあ、蕎麦は後付け?」
「まあ、そうも言えますね。自分でお店を開こうと思った時、たまたま蕎麦打ちを体験して、これをメニューに取り入れたら面白いと思ったんです。特に蕎麦屋で修行したわけではありません」
「そうなんですか。でも、蕎麦を捏ねたり、切ったりは自分でやってるんですよね。修行していないにしては、麺がうまく切れていますね。ちゃんと細さが揃っている」
「種を明かすと、切るんじゃなくてパスタマシーンを使っているんです。そうすると楽に細さを一定にできる」
「なるほど、考えましたね」
「まあ、そんなことより麺を食べてください。作りたてがいちばんだから」
マスターに促されて麺を口に運ぶ。まずはつけ汁につけずに麺そのものを味わう。蕎麦の蘊蓄を聞いて食べるので、いつもより繊細な味わいに感じられる。それから蕎麦をラタトゥイユの汁につけてみる。ラタトゥイユのトマト味がしっくり蕎麦に馴染んでいる。
「あ、美味しい。蕎麦とラタトゥイユって意外と合うんですね」
「魚介類のマリネもなかなかいいよ」
「蕎麦にもこんな食べ方があるんですね。うどんはカレーうどんとか味噌煮込みうどんとか焼うどんとか、いろいろ変化を付けて食べるけど、蕎麦はせいぜいサラダ蕎麦くらいしかないのは不思議ですね」
「うどんは小麦粉だし、パスタの親戚みたいなもの。主張が少ないし、いろいろなものに馴染むけど、蕎麦は蕎麦粉から作るので独特の風味がありますからね。うちの場合は雑味の少ない上等の粉を使ってるし、つなぎも食材と馴染むように工夫している。ふつうはそこまで手間は掛けられないだろうね」
店主はちょっと得意げだ。私は思い切って聞いてみる。
「なんでそこまで蕎麦にこだわるんですか? パスタでやったらもっと楽なのに」
「どうしてかなあ」
私が質問すると、店主はちょっと考える。
「パスタでこういうメニューを出すと、当たり前で面白くないじゃないですか。工夫してほかにはないものを出したい、っていうのもあるし、結局蕎麦が好きなんだと思う。蕎麦つゆだけが蕎麦の食べ方じゃない。もっと自由な食べ方ができるはずだ、って。それにいままでにないメニューを出されると、お客さまもびっくりするでしょう? それが嬉しいんですよ」
そうして店主は目じりの皺をくしゃくしゃにして笑う。普通の蕎麦好きとは違うけど、この人もやっぱり蕎麦への愛着が強い人なんだな、と思う。
「しゃべり過ぎましたね。すみません。どうぞ食事進めてください。食後のデザートには蕎麦粉のガレットもありますよ。よければそちらも召し上がってください」
壁には蕎麦粉のガレットの写真が貼ってある。はちみつと粉砂糖が掛かっていて美味しそうだ。ラタトゥイユ蕎麦でも十分お腹いっぱいになりそうだけど、そちらも食べたいな、と私は思った。
*後編に続く
愛知県生まれ。東京学芸大学教育学部卒業。フリーライター、出版社勤務を経て、2006年『辞めない理由』で作家としてデビュー。
『菜の花食堂のささやかな事件簿』シリーズのほか、ベストセラーとなりドラマ化された『書店ガール』シリーズ、『凛として弓を引く』シリーズ、『スケートボーイズ』『駒子さんは出世なんてしたくなかった』『書店員と二つの罪』『レイアウトは期日までに』等、多数の著書がある。
伝統的な日本の食文化への興味から、江戸東京野菜コンシェルジュと江戸ソバリエの資格を取得。