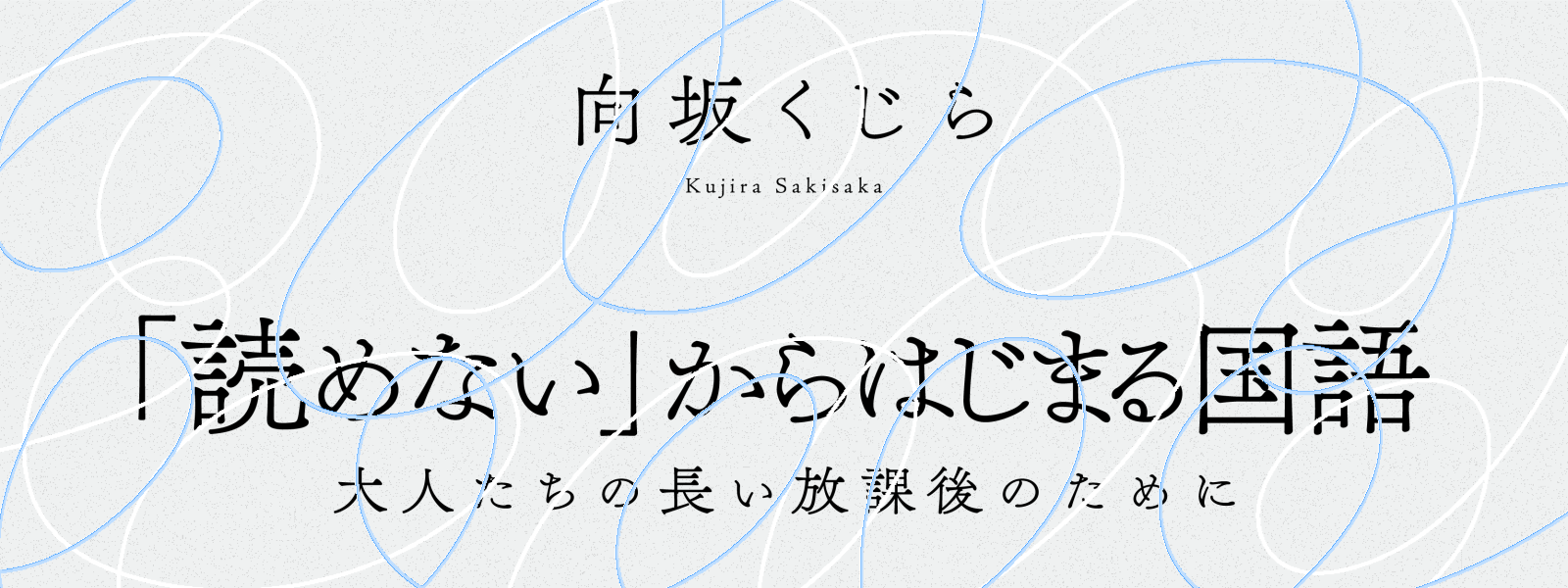子どものころは読書が大好きだったのに、気が付けば本と疎遠になってしまった、そんな大人のための課外授業です。
詩で、小説で、エッセイで、国語教室「ことぱ舎」で――。
さまざまな形で言葉に向き合い続ける、文芸界注目の詩人・向坂くじらさんによる、読むことと書くことをめぐるエッセイ連載。
塩こうじの食品表示
大人になると、たとえばスーパーマーケットに行って、食べものなんか買ってくる。売られている肉や魚は、だいたい袋かパックに入っている。そこには加工者や値段の情報、食べられる期限が書かれている。大人だから、賞味期限と消費期限の違いが、言われなくともわかる。食材だけではごはんは作れないもので、ときには調味料も買う。
わたしがそのとき買ったのが、塩こうじだった。わたしにとって塩こうじというのは、食べたことはあるが常備するほどでもない、ちょっとよそよそしく思っているような調味料である。特売だったからなんとなく買ってみる気になったのだ。手のひらくらいのスタンドパックに入っていて、開け閉めできる小さなキャップがついている。そこに、いかにも重要そうな太字でこう書いてある。
「開封後 要冷蔵」
わたしの話したいのは、そのときわたしたちはどうするのか、ということなのだ。それはつまり、そのときどうするのが、この短い文字の並びが読めていることになるのか、ということである。
そのときわたしは、その文字を見つめてわずかに考えた。それからキャップを一度開けて閉め、冷蔵庫のドアも開けて、塩こうじをしまって、閉じた。うしろで一部始終を見ていた夫が「えっ」と言う。
「いま、なにしたの?」
そこでようやく、自分がまちがっていたことに思い至った。
なにを言っているか、わかっただろうか。
しばしこのくだらないまちがいにつきあってもらいたい。まず、「開封後 要冷蔵」というのは「開けてから冷蔵庫に入れる必要がある」という意味ではない。「開けた場合には冷蔵庫に入れる必要がある」という意味だ。「要」は「冷蔵」にのみかかっていて、つまり「要冷蔵」は指示だが、「開封後」の部分は指示にかかる条件を示しているだけで、それ自体が指示であるわけではない。「要 開封後冷蔵」ではないのだ。
わざわざ開封してから冷蔵庫に入れたものがなにをえらそうにと思われるかもしれないが、元よりそんなことはわかっている。わかった上で開けたのだ。だからなおさら、考えてみたくなる。
それでは、わたしはなにをわかっていなかったのか。
●
「ちょっと、実況中継してもらえますか。どうやって読んでいって、どこでわからなくなったのか」
わたしがそう言うと、中学生はむずかしい顔で机の上の問題集に目を落とした。わたしの運営する国語教室でのことだ。ただでさえ定員三名の小さな教室には、そのときその中学生とわたししかいなかった。読んでいたのは物語文の読解問題だった。わたしも同じページを覗きこんで、本文の前に小さく書いてあるあらすじを指さして見せる。
「たぶん、ここから読みはじめたでしょ。それで、どこまではすらすら読めた?」
「ことぱ舎」という名前の小さな国語教室をひらいて、四年目になる。「自学自習式」の学習塾で、授業はしない。やってきた子どもたちはひとりずつ机に向かい、参考書や問題集を使って自分のするべき勉強をする。だから小学生と高校生が同じ教室で勉強していることもよくある。国語の得意不得意に関しても、読書家で自分でも小説を書いているような生徒から、小学校六年間ずっと不登校で、まずは自分の名前をひらがなで書くところからはじめた生徒まで、あれこれだ。
先生であるわたしの仕事は主に、それぞれに適した教材を選ぶこと、そしてつまずいたときの手助けをすること、のふたつだ。むずかしいのはふたつめで、しかもふたつめができていないとひとつめに差し障る。生徒のほうから質問をしてもらえたら一番いいけれど、はじめから自分がつまずいているのをうまく見抜き、さらに適切な質問をできる生徒というのはほとんどいない。いたとしても、それはすでにかなり勉強ができているということで、そこまでわたしの助け舟を必要としていない。
本当に介入しないといけないのは、押しだまったまま、そして自分でも自分がどこでつまずいているのかわかっていないまま、ひとりでつまずいているような子のほうだ。だから質問を受ける以外のところでも、彼らがなにをわかっていてなにをわかっていないのかのヒントをつねに探さないといけない。
「実況中継」をしてもらうのも、そのためにはじめたことだった。問題を解いてもらっただけでどれほど読めているかが分かればいいけれど、そういい問題はめったにない(市販されている問題集の多くは、定期試験や入試によく出る形式の問題を解き慣れることを目的としていて、読む力そのものを鍛えたり評価したりすることを目指しているわけではない)。その生徒にとって読みやすいと思われるレベルの文章なら一段落ずつ、もっと苦戦していそうならときに一文ずつていねいに、どこまでは読めたか、そして、どこで読めなくなったかを確認する。
ちなみにそのときの中学生は、小さい声で「えっ……」と言った。
「そこは……読んでなかったです……」
わたしも「えっ……」と返す。
「いきなり、本文から読んだの……?」
「はい……」
「じゃ、知らない人の名前がいきなり出てきたでしょ……?」
「はい、だから、誰? と思って……」
「えっ? もしやこういうあらすじ、今まで読まずにやってた?」
「なんか……あんまり関係ないことが書いてあるのかな、と思ってました」
あんまり関係ないことが書いてあるわけないじゃん!
と言いたいのをこらえて、「そうか……」と答えた。読むことが苦手で、それ以上に強い苦手意識を持っている生徒だった。これまで文章を読むたび、知らない登場人物やキーワードが説明なく出てきたとしても、自分がどこかで読み落としたせいだと思ってきたのかもしれない。そう思ったらやるせない。
しかしそもそも、生徒が内容を読んで理解しようとしている、という前提そのものが、わたしの思い過ごしだったかもしれない。つまり、生徒は読もうとしているわけではなく、問題を解こうとしているのだ。
すると「あんまり関係ないことが書いてある」というのは、「本文の内容に」ということではなく、「設問に」ということだったのではないか。それならいくらか納得がいく。あらすじに傍線が引いてあったり、空欄がふくまれていたりすることはないからだ。ふだん、テストという時間の制限がある環境で読むことに慣れていて、まして読むのが苦手なら、あらすじを読まずに解きはじめようとするのは、コストカットのための合理的な選択と言えるかもしれない。
●
そんなふうに考えるようになったのは、数学者の谷口隆さんの著書『子どもの算数、なんでそうなる?』を読んで、たいへんに刺激を受けたからだ。子どもが算数にふれ、どのように理解するかを観察するエッセイ集である。より正確に言うと、谷口さんは、「どのように間違えるか」を観察している。たとえば子どもが、二枚の百円玉を指さして「ヒャクニエン」という。読んでいる大人のわたしには、これが単なる間違いにしか見えない。しかし、著者の谷口さんはこのように考える。
もともと日本語の自然な語順は「100が2つ」であり,「2つの100」と表現することはあまりない。たとえば入場料を払うときに人数を伝えるには「大人4,子ども3」のように言うのであって,「4大人,3子ども」とは言わない。そのように,幅広く一般的に用いられている統語の規則である。であれば、100が2つある状況が,二百ではなく百二となるのは,子どもにとっては当然のことではないだろうか?
谷口隆(2022)『子どもの算数、なんでそうなる?』岩波書店、63ページ
このように推測されて、読んでいるわたしもはじめて谷口さんとともに「ヒャクニエン」に納得をすることになる。そして、さっき「考えなくてもわかる、当然ニヒャクエンである」と思った、その「当然」のほうがあやしくなってくる。この、ぐるっとひっくり返るような納得がおもしろい。いわば、誤りに対して反射的に「どうすれば誤りを正せるか」と考えてしまいそうになるところを、「どうすれば自分もそのように誤ることができるか」と考えているのだ。その視点を借りてはじめて、「なんとなく」で納得してしまっていた「ニヒャクエン」のふしぎさを発見することができる。
それで、読み書きを教えるときにも、その考えかたを頼りにするようになった。生徒がつまずく文章が、わたしには読める。読解の解説をするというのは第一に、「なぜ、わたしに読めるものが、この人には読めないのか」と考えることである。実況中継はそのためにやっていることで、あらすじを読んでいないことを発見できたのは、それ自体とてもよかった。しかし同時に、「なぜ、この人に読めないものを、わたしは読めると思い込んでいるのか」とも考える必要がある。いまも、わたしはなにかを「なんとなく」見落としているかもしれないと思っている。当然、「あらすじを読んでいない」以外の、もう少し入り組んだ「読めない」も、毎日のようにわたしのところにおとずれる。そのたびに考えている。
その「読めない」はなんだろう。どうしたら、わたしにそれができるだろう。
●
だからここでも、「読めない」からはじめてみたい。この連載をはじめるにあたり、大人の人に向けて「読む」ことについて語ってみませんか、というお題をもらい、話せることはそれしかないように思っている。
教室で、「くじら先生にも、読めない文章ってあるの?」と聞かれてのけぞったことがある。あるに決まっている。けれど同時に思う、この人には、わたしにはあらゆる文章が読めるように見えているのだ。それはひょっとしたら、世の中には「読める人」と「読めない人」がいて、「先生」たるわたしはその前者、そして自分は後者である、と思っているのかもしれない。「ある、ある、死ぬほどあるよ!」と答えたら、えーっと言って笑っていた。それから子どもに対しては、わざと読めなかった本の話をたくさんするようになった。するとおもしろいもので、子どもはわたしの読めなかった本を手に取って開いてみたがる。茶化しているだけかと思ったら、案外静かになって読みはじめたりする。一節が短い、詩集や箴言集みたいなものだったりすると、なんとわたしに向かって、「これってこういう意味じゃない?」と教えようとしてくることさえある。
そしてどうやら、「自分は『読めない人』である」と思っているのは子どもだけではないみたいだ。
国語の教室を開いてから、ときどき大人の人からも相談されるようになった。「本が読めるようになりたいんですけど、どうしたらいいですか」。そういうときにも「わたしも読めない本がいっぱいあるんです」という話をしたくなる、けれどなんとなく遠慮してしまっていた。それが、向坂はむずかしい本も読んでいてすごい、というような望まない受け取られ方をすることをおそれているのだ。
しかし実態わたしときたら「開封後 要冷蔵」が読めないのである。
ここでいまさら、そのときわたしの頭のなかで起こっていたことを「実況中継」してみたい。
前提として、わたしはそのとき冷蔵庫の前にいて、次のアクションをどうするべきかを考えていた。そしてもっと大きな前提として、食品を適切に保存したいと思っていた。だから読んでいるわたしの目は、その段階ですでに適切なアクションの指示を求めている。そこで「開封後 要冷蔵」を読む。そこには、開封後のことは書かれていても、開封前のことは書かれていない。しかしいまは開封前である。そこで迷った。開封後は冷蔵する、それはわかった。しかし開封前はどうしたらいいのかわからない。
そんなはずはない、と思われただろうか。たしかに、暗に書かれているという見かたもできる。「開封後 要冷蔵」は「開けたあとでなければ冷蔵しなくてもいい」と読むことができる。しかし「冷蔵しなくてもいい」は特定のアクションを指示していない。そして、わたしは思う。
ひょっとすると、開封前は冷蔵してはいけないのかもしれない。
いま思い返すと、ここが明らかにまちがっている。「冷蔵しなくてもいい」には、一般に「してもいい」意が含まれている。しかしそのときわたしは、「開けた場合には冷蔵庫に入れる必要がある」ということしか言われていない以上、「開けていない場合」のことには言及されていないと判断した。結果、「開けていない場合には冷蔵庫に入れてはいけない」が「開けた場合には冷蔵庫に入れる必要がある」と同時に成立する可能性もある、というふうに考えたのだった。
まあ、よくよく考えてみれば、開封前と開封後で適切な保存方法が変わるという時点で雑菌の繁殖にそなえての指示であることは明らかであり、もっと言えば「開封前は冷蔵してはならず、開封後は冷蔵しなくてはならない」という食品はあまり想像できない。
しかしともかくそのときはまちがえた。「なにをするべきか」だけを読もうとしていた頭は、「するべき」を「開封前」に対しても求め、その答えがないことにおびえて、「するべき」が少なくとも明らかである「開封後」の状態にすることを選んでしまったのだった。
このように……というにはあまりに卑近な例だったけれど、ともかくわたしにも読めないものがたくさんあるのだ。「国語教室を運営する詩人」というものものしい肩書きを持っていながらなさけないような気もするけれど、明るくとらえればそれは、一度読めれば見えなくなってしまうものが、わたしにもまだ見えている、ということでもある。読めないものには、教えるときにあんなに欲しい、読めないものの視点が与えられているのだ。そして、「いかに読めなかったのか」を考えるのは、「いかに読めるか」を考えるよりも、ずっとおもしろい。
だからこの連載では、わたしの「読めない」本とその経験について語ることにしたい。
●
ちなみに、「開封後 要冷蔵」について書くにあたり、いちおう食品衛生法を参照した。それによると、「一括表示における保存方法は、「開封前」について表示」し、「開封後に保存方法を変更することが望ましい食品については」別のところにその旨を表記することが求められている、とのことで、ちゃんと探せば開封前についてもちゃんと書かれていたらしい。なんということ。さらには後日、しょうが焼きを作っていて、愕然とした。生まれてこの方そこらに常温でほっぽっていた醤油に、「開封後 要冷蔵」と書いてあるのだった。
「読めない」より前に、まず「読んでいない」がある。あらすじにしてもそうだった。次回はそのあたりからはじめてみよう。遠回りがすぎる気もするけれど、さいわい大人になったから、時間制限はない。寿命があると言われたらなにも言いかえせないけれど、まあ、テスト時間よりはずっと長い。
向坂くじら(さきさか・くじら)
詩人・小説家・エッセイスト・国語教室「ことぱ舎」代表
1994年、愛知県名古屋市生まれ。Gt.クマガイユウヤとのユニット「Anti-Trench」朗読担当。主な著書に詩集『とても小さな理解のための』、エッセイ『夫婦間における愛の適温』『犬ではないと言われた犬』(百万年書房)、『ことぱの観察』(NHK出版)など。初の小説『いなくなくならなくならないで』(河出書房新社)が第171 回芥川龍之介賞候補となる。