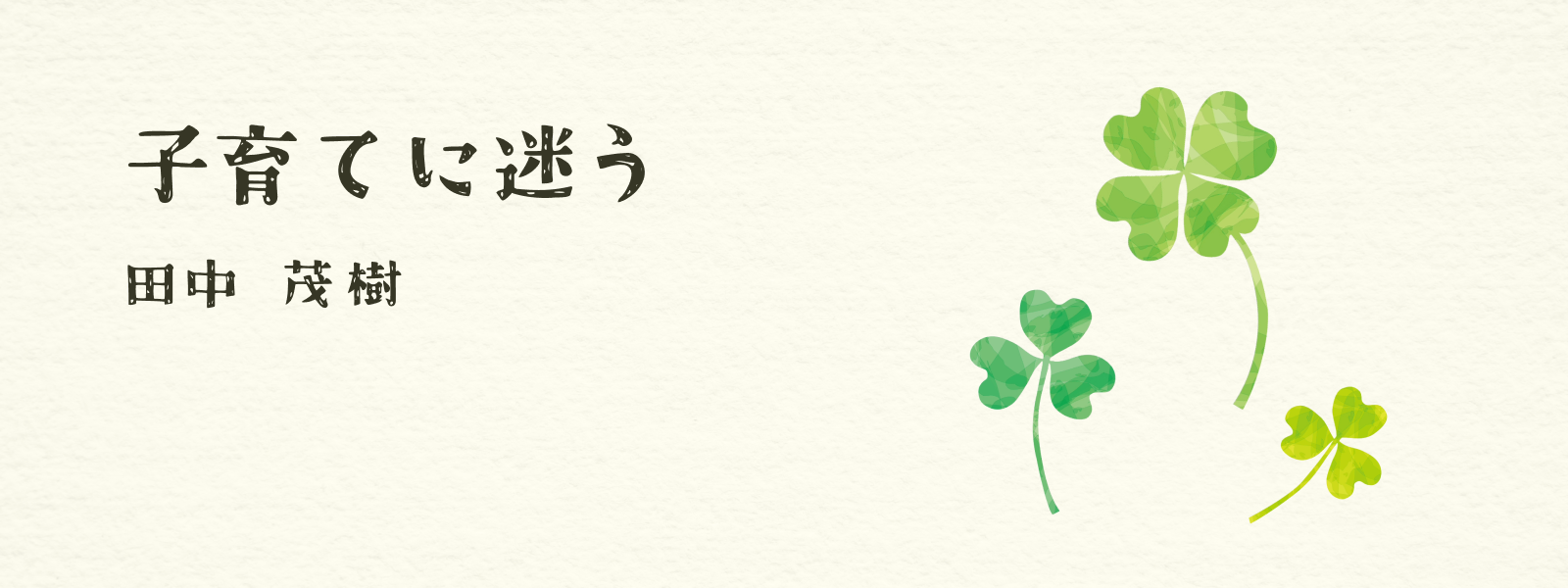自分も子育てでいろいろ悩みながら、子どもの問題について親のカウンセリングを長年続けてきました。また、地域の診療所で外来診察や訪問診療も担当しています。育児の悩みや家庭でのコミュニケーション、そのほか臨床の現場で出会ったこと、考えたことなどを書いてみます。
人材という概念のない国
夏休みになると、家でダラダラしている子どもに対して、ついイラッとしてしまう。そういう悩みが職場でもよく話されます。休みだし、子どもがのんびりしていることは、まして、こんなに暑いのだから、何も悪いことではないのだけれど、親としてはつい、「やるべきことがあるだろう」と思ってしまう。
それは、「あるべき姿」というイメージがあって、それから子どもが外れている、そういうことからくる怒りなのでしょう。あるべき姿とは、たとえば夏休みの宿題を自分からどんどんやるとか、課題の絵を描く、読書感想文を書くとか。もしくは塾に行っているのであれば、その宿題をするとか。そういう、かつて自分が子どもだったときに親から言われたようなことを、子どもにしてほしい、やらせたいと思ってしまうようです。
「ようです」と他人事のように書きながら、自分だって、自分の子どもたちが夏休みにごろごろしているのを見たとき、「やるべきことをやったらいいのになぁ」と思ったことがもちろんあります。
先日、おもしろいことを聞きました。妻は社会人向けのスペイン語講座に通っています。先生は近くの大学で哲学を教えているロペス先生。スペインのガリシア地方出身。授業のあとの雑談で、ロペス先生がこんなことを言っていたそうです。
「日本の大学はおもしろいですね。大学生なのに体育の授業をしたり、語学の授業をしたりする。スペインではそういうことがありません。大学に来るのは、自分のしたい専門的な勉強をするためです」
「日本の大学で働くようになって、初めて知った言葉が『人材』です。スペインではまったく聞いたことがありませんでした。そういう言葉もありません。日本では大学のパンフレットなどにも、『グローバルな人材を育てる』『社会に役立つ人材が育つ』などの言葉が並んでいます。不思議です。大学のほうも就職支援にすごく力を入れていますよね。スペインの大学には就職支援課がないんですよ」
それを聞いて妻は、「では、スペインでは人々は何のために大学に行くのですか?」と聞いてみました。するとロペス先生は、「あったりまえでしょ」という表情で、「それはもちろん、勉強するためですよ」と答えたそうです。習いたい先生について、1年生から専門の科目を勉強する。大学に行くのは就職するためではなくて勉強するためなので、大学を出たからといって、就職には何の役にも立ちません。そういう話でした。
これを聞いてとてもおもしろいと思いました。調べてみると、日本の大学でいう「一般教養」のようなことは、スペインでは高校の間に終わっているらしいのです。
どちらの仕組みが良い、悪いという話をするつもりはありません。それはややこしいので。そこではなく、私が感じたのは、なんとなくですが、大学教育だけではなく、日本の子育て自体が、就職支援のようになっているのではないかということです。子育てが「人材育成」のようなことになっているんじゃないか。小学校教育からしてそうではないか。たくさんの宿題を出すのも、中学受験をして「いい学校」に行くのも、最終的に良い会社に勤めるためや、良い職業に就くため。それが知らぬ間に教育の目的・目標になっているのではないか。
好きでもない勉強をがんばって、いい成績をとるのは、良い職業に就くため、高い収入を得るため。それが幸せにつながるから。そういう価値観が根底にあるような気がします。子どもが、今を楽しむよりも、未来に備えて勉強をする。
栗原康さんの著書『働かないで、たらふく食べたい』のなかに、栗原さんが婚約者と口論する(その後別れることになる)場面があります。博士論文をなかなか仕上げられず、就職先も決まらない栗原さんに、教師として働いている婚約者は愛想をつかしている。
「もう我慢できない。おまえは家庭をもつ、子どもをもつということがどういうことなのかわかっているのか。社会人として、大人として、ちゃんとするということでしょう。正社員になって、毎日つらいとおもいながら、それをたえつづけるのが大人なんだ。やりたいことなんてやってはいけない。仕事なんていくらでもあるのに、やりたいことしかやろうとしないのは、わがままな子どもが駄々をこねているようなものだ」。わたしも売りことばに買いことばで、やりたいことをやらないなら、なにがたのしくて生きているんだときくと、かの女は即答だ。「ショッピングにきまっているでしょう。おまえは研究がたのしいとか、散歩がてらデモにいってくるとか、カネをつかわなくてもたのしいことはあるとかいっているけど、貧乏くさくて気持ちわるいんだよ。そんなことをいっているからはたらかないんだ。大人はみんなつらい思いをしてカネを稼いで、それをつかうことに誇りをもっているんだ。貧乏はいやだ、貧乏はいやだ」
『働かないで、たらふく食べたい』栗原康著、タバブックス 38–39ページ
ここまで極端ではないけれど、勉強したがらない子どもに、とにかく勉強しろと押しつける親。その親に、「なんでそんなに勉強させたいの?」と子どもがもしも尋ねたら、返ってくるかもしれないひとつの価値観の究極の形なのかなと思って、記憶に残っている文章です。
教育の考え方は、昔と変わってきていますね。昔は富国強兵でしたから、国の繁栄と社会に役立つ国民を、できるだけたくさん、できるだけ少ない予算で養成する必要があった。だから、画一的な授業を、大人数の教室でやってきたんですね。自分の意見を言うよりも、教えられたことを素直に聞いて、言われたことができる人間をたくさん作ること。それが国の繁栄に役立った時代。それで高度成長を成し遂げた。
でも、そうやって日本が豊かになって、先進国といわれる国になってきたら、教育の目的が変わってきた。同じようなことができるたくさんの人を作ることを目指すのではなく、一人一人の個性に合った教育が受けられるようにしましょう、と。それぞれが自分に合った人生を送ることができるように、それを支援すること。それが国が国民に与えるべき教育だという考え方。
そういう点から見ると、「人材」という考え方のベースには、昔の教育に近いものがあると思います。その子らしさを大事にするよりも、役に立つ人材に仕上げるほうを目指している感じがします。
夏休みにごろごろしている子どもに対して、「宿題をしなさい」とか「塾の勉強をしなさい」とか、親は言いたくなってしまう。その根底には、「子どもは、やがて良い人材にならなければならない。そして良い仕事に就かなければならない。親は子どもを育てなければならない」──そういう価値観があるようです。
スペインでは違うんですね。大学に行くことは就職には役に立たない。勉強したい人、勉強の好きな人が行く。親は子どもに、宿題をしなさいぐらいは言うのかもしれませんが「しっかり勉強して大学に行きなさい」とは、あまり言わないようです。
「スペインでも、子どもを医学部に行かせようとして、夏休みに塾に行かせたり、しっかり勉強させようとする親もいるのでしょうか?」
妻がそう聞くと、ロペス先生曰く、
「スペインにも、子どもを医師や弁護士にしようとして、家庭教師をつけている親は、少数派ですがいます。それでも、勉強をがんばるかどうかは、結局子ども次第です。それらの仕事は、働き出してからも勉強することが求められる職業ですから、勉強が嫌いな子がそちらに進んでも、幸せにはなれませんから」
私の勤めている地域の診療所にも、医学部の学生が実習にやってきます。このごろは男女の比率は半々くらいです。医師の仕事にしっかりした興味があり、やりたいことも決まっている。そういう学生は診察についていても、あとでいろいろな質問を自分からしてくるものです。患者さんとも積極的にコミュニケーションをとります。患者さんが出て行かれようとすると、椅子から立ち上がるのを助けたり、ドアを開けてあげたり。言われなくても体が動きます。
一方で、そうではない学生さんもたくさんいます。退屈そうにしていたり、眠り込んでしまったり。名門の進学校出身で、親も医者。子どものころから医学部に行くように言われたり、期待されたり。そういう道を進んできた学生さんも毎年のようにいます。しかし、自分から進んで取り組める人でなければ、大学の授業も、実習も、そして国家試験も、その先の研修医生活も……勉強は続きます。しないといけないことがどこまでもあります。それを楽しいと思えるかどうか。子どもをがんばらせて、ここまで進ませてきた親たち、大人たちは、やる気が出なくて苦しんでいる彼ら・彼女らの姿を見て、どう思うのでしょうか。
「人材」という概念がない国もあるんだということに驚き、それは、日本の親が抱えている子育ての不安や不満と、どこかでつながっているような気がして、しばらくいろいろなことを考えました。
1965年東京都生まれ。医師・臨床心理士。京都大学医学部卒業。文学博士(心理学)。4人の男の子の父親。
現在は、奈良県・佐保川診療所にて、プライマリ・ケア医として地域医療に従事する。20年以上にわたって不登校やひきこもりなどの子どもの問題について、親の相談を受け続けている。
著書に『子どもを信じること』(さいはて社)、『子どもが幸せになることば』(ダイヤモンド社)、『去られるためにそこにいる』(日本評論社)、『子どもの不登校に向きあうとき、おとなが大切にしたいこと』(びーんずネット)がある。