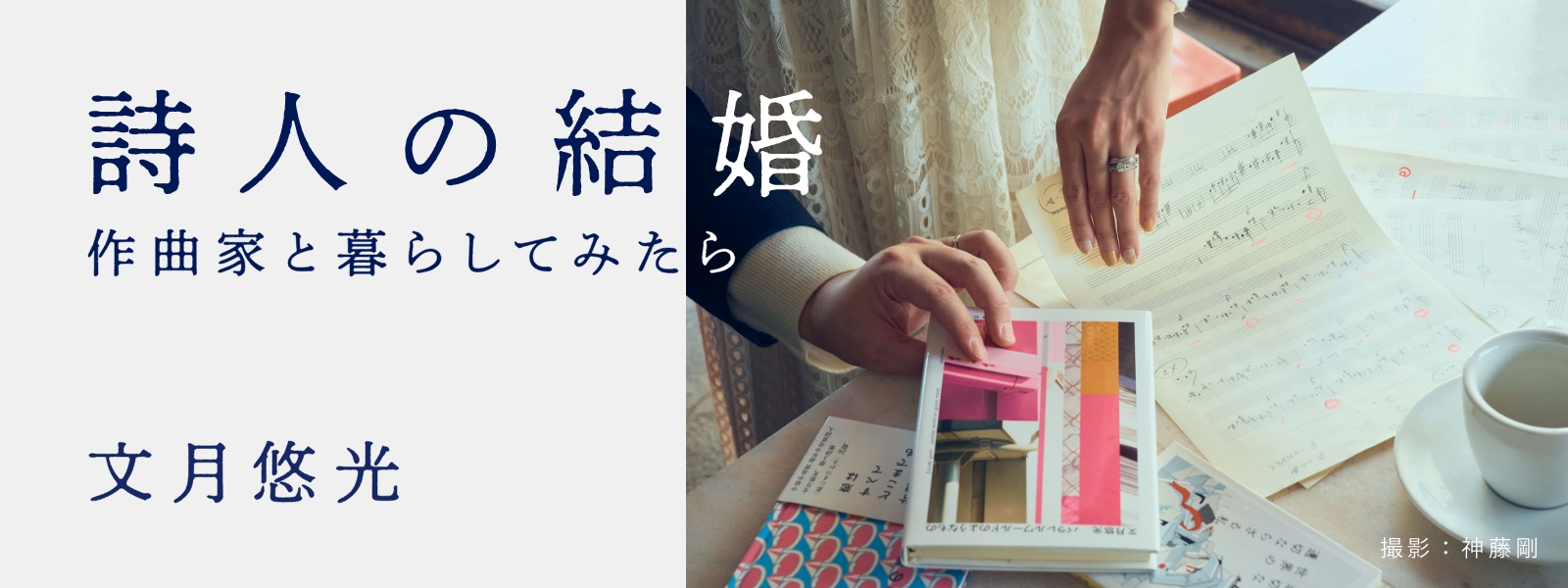詩人が、ひょんなことから作曲家と結婚した。詩人と作曲家。ことばと音楽が紡がれる、さぞかし優雅な日々になるかと思いきや……。二人のユニークな結婚生活と創作の日々をお届けします。
“天才”作曲家はつらいよ
あなたは世に言う「天才」が、どんな自意識を持っているか気になったことはないだろうか。天才って何考えてるの? 他の人をどう思ってるの? メンタルのケアはどうしてるの? 元来ミーハーな私は知りたくて仕方がない。
っていうか、天才って大体「変な人」じゃないですか?
SNSで結婚を報告した直後、なぜか我々の2ショット写真がスポニチのウェブ版でニュース記事として取り上げられ、身内でちょっとした話題になった。見出しには(誰がつけたか不明の)「芥川作曲賞×最年少中原中也賞の天才夫婦に」という文字が踊る。ニュースのコメント欄で「天才夫婦って呼び方は優劣をつけているみたいで嫌だな」という声を見かけ、だよね、と思う。我々も裏で「『天才夫婦』はちょっと……」と困惑していた。うまく言えないが、こちらは作曲家&詩人の「面白夫婦」くらいのノリでいるのに、持ち上げ方が過剰なのだ。
確か、関西に住む従姉妹も「坂東さんについてすごいびっくりしたことがあって!」と報告の連絡をくれたことがあった。何かと思ったら「お名前で検索して『天才』って出てくる人、初めて見た!」ということだった。確かにGoogleのサジェストには「坂東祐大 天才」が出てくる。世の中の人は何かと「天才」というワードに反応してしまうようだ。
夫の坂東が世間一般的な基準から浮いているのは確かだ。それゆえに「特有の生きづらさ」を抱えているように私の目からは見える。
一緒に暮らし始めた頃、夜中に坂東が暗い顔で訴えてきた。
「僕は才能がない! 音楽向いてない!」
いや、あなたに才能がなくて誰にあるんだ、と私は内心引いていた。藝大首席(東京藝術大学音楽学部作曲科を首席で卒業)が言う台詞と思えない。「もう作曲家を廃業する……」とまで言い出す。何やら大ごとだ。働きすぎでノイローゼ気味なのか? 私は慌てて「そんなことないよ!才能あるよ!」「みんな褒めてたよ!」と両手に握りこぶしを作って全力で慰めに入る。そのときの坂東の一言が忘れられない。
「僕は才能がない……、モーツァルトより、才能がない!」
口から人生最大の「は???」が出た。
「モーツァルトは本当に作曲が上手い。僕はモーツァルトほど作曲が上手くない」と彼は真顔で言うのだ。
はあ???(2回目)
BAKKAJANAINO!(おっと、つい本音が)
「比較対象がおかしいよ!! 私だって夏目漱石に比べたら文才ゼロだよ!!!」
そのとき、文月は叫んだという……。
坂東とはここ数年、誰より時間を共にしていて、それなりに相手の考え方や価値観をつかめたはずだ。
しかし、そんな私でも完全には理解できない点がある。
坂東曰く「僕は音楽を好きではない」のだという。初めて聞いたときは正直、耳を疑った。「なに自分だけカッコつけて」と少々腹立たしく思ったほどだ。
なぜなら、我々は作家業。「好きを仕事にできていいね」と言われがちな職業代表だ。音楽なんて「好きを仕事にする」の最たるものではないか。にもかかわらず、坂東は「別に作曲好きじゃないよ」と言い放ち、「いいなあ、先生は。好きなことを仕事にできて」と、横にいる私を羨むような発言までする。なんなのだ。
(※読者の方々へ)我々はお互いのことを「先生」と呼び合っている。二人とも「先生」と呼ばれることもある肩書きなので、初めは照れ隠し半分、ふざけて呼び合っていたが、今ではすっかり定着してしまった。なので、この連載でも時折「先生」が互いの愛称として登場します。
坂東は常に音楽の情報をリサーチしている。海外のヒットチャート、TikTokでバズった曲はもちろん、気になるプロデューサーが手がけたアルバム、若手のトラックメーカーの曲、YouTubeで再生回数が百程度しか回っていない現代音楽作品まで。私が「こんな感じの曲が聴きたいんだけど」(「詩が書けるような気がしてくる曲ない?」「疲労感を麻痺させてくれる曲は?」などの無茶振り)とリクエストすると、すぐに「おお、これこれ♪」というドンピシャな曲を探し出してきてくれる。あるジャンルについて掘ることを「ディグる」と呼ぶらしい。坂東は「ディグ」を極めている。だが、彼にとってそれは単なる趣味や楽しみではなく、「勉強」らしい。そう、坂東は「勉強が大好き」。そこで磨いた解像度の高さで、自身の仕事(作曲)にあたるのだ。
にしても心外だ。作曲家と結婚したのに「僕は音楽が好きじゃない」「いいなあ、詩人は」なんて。世間から見たら、かなり滑稽な会話をしている。でも近くで観察する内に、それも嘘ではないのかな……?と半信半疑ながらも感じるようになってきた。
坂東は「できてしまう」のだ。しかも、自分の能力について決して卑下したり謙遜したりしない。
私の周りにも才能に溢れた人(主に物書きの知り合い)は多いが、異様に腰が低く、「私なんて」が強くてストイック。だからこそ努力して成功できるのだが、どうも自分の価値を低く見ている。「もっと自分と自分の作品を大事にして!」と周りが心配してしまうような人ばかりだ。
だが、坂東は初めて会うタイプだった。思わず、ぎょっとした発言がある。
「僕、作曲家じゃなくて、本当は建築家になりたかったんだよね。僕、建築ならできたと思う!」
それも著名な建築家についての番組や展示を観た後にそういうことを言い出すので、クラクラする。
かと思えば、「僕、本当は映画監督になりたかった!」と言い出すので、ひっくり返りそうになる。ついていけない。
「あのさ。やってないことについて、『僕はできると思う』って、その自信はどこから溢れてくるわけ!?」とさすがに突っ込まざるをえない。
当の本人は「え?だって僕できるもん」と一切動じない。何をするにしても「僕できるもん」がベースにあるのだ。その根拠なき自信家ぶりに「大丈夫か?」と身内はつい心配になる。
ある日、ヴァイオリニストの友人Hくんがうちに泊まりに来たときのこと。坂東がHくんの前で再びその話を始めた。私は「いやいや、なんでできると思えるのよ!?」といつものように笑っていた。
でもHくんが「何かを始める前に『できるかも』って思えることは大事だと思う」とたしなめてくれて、はっとした。その通りだ、と私は急に恥ずかしくなった。平然とした顔で「だって僕できるもん」と言う坂東が眩しい。私には眩しすぎる。
私は逆に子供の頃から「自分には書くこと以外取り柄がない」と思い込んできたタイプだ。第一、「〇〇になりたい」なんて簡単に口にすることはできない……。モヤモヤと思い出す出来事がある。小六の頃、小林カツ代のエッセイ集を読み、「将来は料理研究家もいいなあ」と漏らしたところ、母と兄に「あんたが?」と腹を抱えて爆笑された記憶だ。あまりに恥ずかしくて消えてしまいたい気持ちになった。
私は(過去に一部作品で明かしているが)子どもの頃、「普通に食べる」ことに困難を抱えた時期があった。健康を取り戻すため、自主的にカロリー計算や栄養学の本を読むようになった。レシピ通りに調味料を測って作ると、ちゃんと美味しい。それが魔法みたいに感じて、料理する楽しさに目覚めたばかりだった。普通の食事さえままならない当時の私が「料理研究家になりたい」なんて言い出したのは、家族からすると確かに滑稽だし、ありえなさすぎて笑えたのだと思う。
今思うと、「料理研究家の将来を夢見ること」は、母の想定から大きく逸脱していたように思う。母はそれ以前から「女の子だから」と私を毎晩台所に呼び、料理の支度を教えていた。母にとって料理は、女性が担うべき役割であり、「嫁に出ても恥をかかないように」伝えておくべき技術。「家族のケア」のための料理だった。
一方、私は「料理に関すること」が将来の職業の選択肢に入るように感じていた。レシピ開発や食エッセイの出版。料理の延長線上に、自己実現の可能性を見ていたのだ。前提がこれだけ違えば、齟齬が生まれるのも仕方ない。
あれから二十年以上経って、長谷川あかりさんら若い世代の料理家の活躍を目にするようにもなり、先日唐突にその記憶が蘇った。あのとき、坂東のように「だって私できるもん!」と力強く言えたなら、私は少し違う今を生きていたんじゃないか?
私が国内の同世代の作家と自分をつい比較してしまうのに対し、坂東は海外のレジェンド級の作曲家や映画監督の能力を分析して「自分もこういう作品が作りたいなあ」「かっこいいよね、僕もこういうおじいさんになりたい」とよく話してくれる。私は今まで、そういう比較はおこがましい気がして、逃げてしまいがちな面があったのだが、彼を見て「そんなすごい人と自分を並べていいのか!」と新鮮だった。視野が広がって、潔く色んなエンタメ作品に触れられるようになり、自分の中の評価軸がより確かなものになったような気がする。
彼はいわゆる「天才」に幻想を抱いているタイプではない。作品からそのクリエイターの能力をつぶさに見極める。「僕には才能がない!」と嘆くのも、むしろ徹底的な能力主義ゆえに、その厳しい目が自分にも向いてしまう、ということなのだろう。
にしても、坂東の発言は「さすがにちょっと高慢では?」と感じるものもあるのに、どうしてか全く嫌な感情が湧いてこない。自信家ぶりが鼻につかないのだ。「この人の自信が尽きることはないのだな」と少し呆れることもあるが、むしろ最近は「もっとください、高慢発言!」と思っている(失礼)。
先日も近所のスーパーに寄った際、私は何気なく彼に話しかけた。「(制作中の映像音楽について)先生の得意そうなジャンルだね。楽しみ」。すると彼はこう告げるのだった。
「こういう曲を作らせたら、僕は日本一上手いからねえ」
日 本 一 。
それもドヤ顔するわけでもなく、当たり前のテンションで言ってくる(まあ実際上手いのだが、「それを言うかね?」という話ではある)。ちょっと気持ちがいいくらい、こちらの想定を超えてくる。
この自信を裏打ちするだけの「努力」を、彼は幼い頃から重ねてきたようだ。私はほんの一部分だが知っている。坂東は疲れた日もインプットを欠かさず、多忙の合間を縫ってコンサートやライブに足を運ぶ。クラシックの名曲や現代音楽のスコア(楽譜)を読んだり、英語でしか発信されてない音楽機材の情報を収集したり。
能力を高めるために、今も勉強を続けているのが日常から見える。これだけ努力していて自信を持つのは当然だし、だからこそドラマや映画のような大きいプロジェクトにも挑めるのだろう。才能以上に努力の人だ。
それには、彼の非凡な学生時代が大きく関係しているらしい。あの東京藝大の音楽学部。音楽エリートたちが集結する、芸術系の最難関。彼らは特殊なコミュニティを形成していて、とにかく面白い。
次回はそんな話をお届けしたい。
ふづき・ゆみ
詩人。1991年北海道生まれ。10歳から詩を書きはじめ、高校3年の時に発表した第1詩集『適切な世界の適切ならざる私』で中原中也賞、丸山豊記念現代詩賞を最年少18歳で受賞。詩集に『屋根よりも深々と』『わたしたちの猫』『パラレルワールドのようなもの』(富田砕花賞)『大人をお休みする日』。エッセイ集に『臆病な詩人、街へ出る。』『洗礼ダイアリー』。夫は作曲家・坂東祐大。2023年度より武蔵野大学客員准教授。