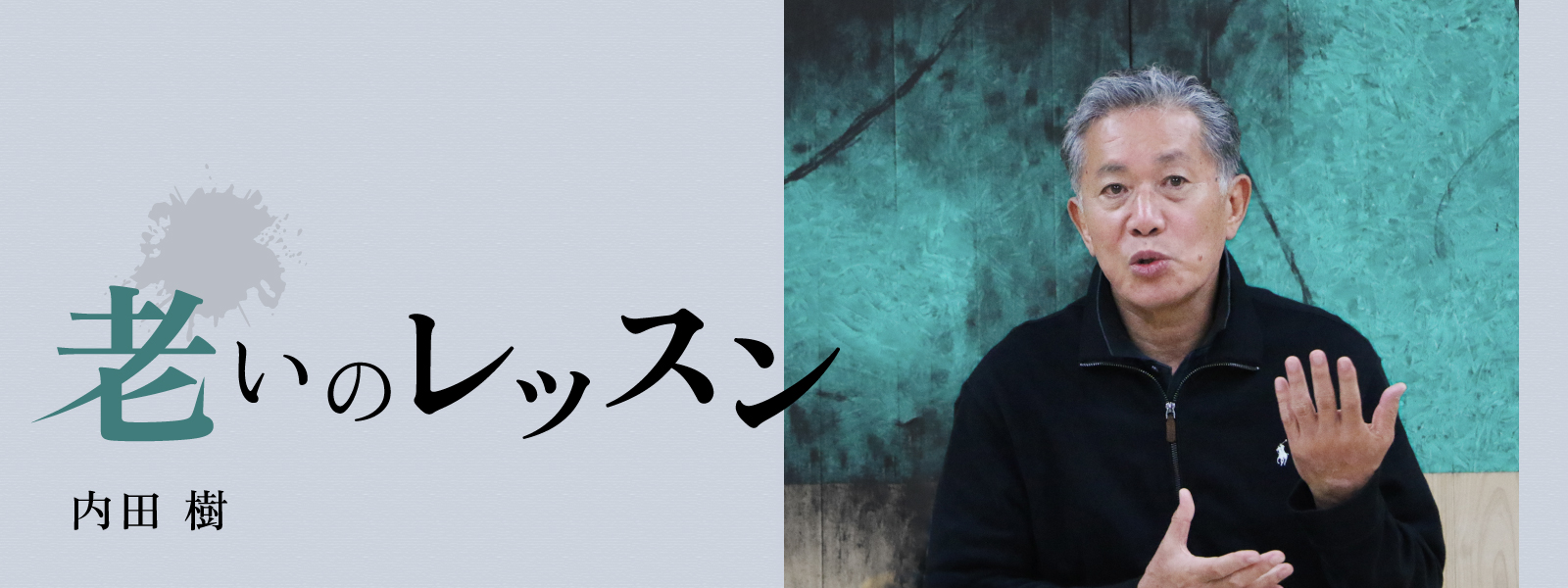「高齢化」が社会問題として語られるようになって久しい現在。約3割が65歳以上の高齢者で占められる日本は今後ますます高齢化が進むと予測され、若者の社会保障の負担増や経済の衰退など、数々の課題が声高に叫ばれています。
また、男女ともに平均寿命が80歳を超える現代では個人が「老い」とどのように向き合うかも重大な課題となっています。
社会全体の「老い」、そして個人の「老い」と、人類が経験したことのないフェーズに進み続けています。
先の見えない時代だからこそ、社会と個人の両面から「老い」とはなにかを考え、どのように老いと向き合っていけばよいかを思想家と武道家の2つの顔をもつ内田樹氏と模索していきます。
26年かけて、ゆっくりと死んでゆく
<担当編集者より>
内田先生、こんにちは。今回も力強いお言葉をいただき、とても励みになりました。
同世代の友人と、「日本がどんどん衰退していくなかで、子をもつのは不安だ」という話をすることがあります。子どもがいないのに子どもが生まれたあとのことを心配したり、まだ幼児なのに大学までの受験・進学について心配したり……。
先生のお返事を拝見して、いかに頭でっかちに物事を考え、そして実感を蔑ろに過ごしてしまっているのか反省しました。
カオス化する世の中に、普段は敏感な人でなくても、先行きに不安を覚え、取り越し苦労をしやすい状況になっているのではないかと感じました。
だからこそ、改めて、「今日を精一杯生きる」ことの大切さをかみしめる必要があるのですね。
***
「老いのレッスン」の連載も12回目となりました。
毎回、私から質問をお送りするという形式は、先生のアイデアでした。はじめの頃こそ、「老い」というテーマを強く意識していましたが、お返事を頂戴するたびにお伺いしたいことがどんどん押し寄せてきて、気が付けば、私の人生相談のような質問ばかりになってしまいました。高校生の頃からの先生の読者として、なんとも贅沢な体験をさせていただきました。改めて、深くお礼申し上げます。
***
さて、今回は誰もが避けては通れない「死」について質問させてください。
幼いころ、初めて「死」というものを理解したとき、あまりにも恐ろしくて、疲れ果てるまで延々と泣いたことを鮮明に覚えています。人生で最も大きな恐怖を感じたのは、もしかしたらこのときだったのかもしれません。
一方で、ある記憶が蘇ります。
小学生の頃、テレビで映画「グリーンマイル」を観ました。刑務所を舞台に、無実の罪を着せられた、不思議な力をもつ死刑囚の男と、彼が冤罪であることを知る主人公の看守の男を描いた映画です。古い映画なので、読者の方にはネタバレを許していただきたいのですが、結局看守は死刑囚を救えず、刑を執行します。私が衝撃を受けたのは、看守にその罰として無限とも言えるほどの寿命が与えられたことが明らかになる最後のシーンでした。死ぬのは怖いが、死ねないのも恐ろしいという矛盾、そして終わりのないことの恐ろしさを、初めて考えました。死とはなんとも複雑な存在なのだろうと、子ども心に思ったことを覚えています。
いつか必ず死ぬことが分かっていながら、いまを生きることに理不尽さと言えばよいのか、なんとも言えない耐えがたさを感じます。
だからと言って、明日、急に死んでも後悔のないような毎日を送るには、(幸運なことに)私はあまりにも健康で、平和な生活を送っていて、一生を長く感じてしまい、ダラダラと無為に過ごしてしまう日も少なくありません。
前置きが長くなってしまいましたが、「死」についてお伺いしたいことが3つあります。ひとつは、死と向き合い、よりよく生き、よりよく死ぬために人類がどのような知恵を働かせてきたのかということを知りたいです。
もうひとつは、先生ご自身が「死」をどう捉えていらっしゃるかです。
最後に、31歳(いまの私の年齢です)の頃のご自身に「死」について、なにか伝えるとしたら、何を伝えたいのかを知りたいです。
最後までまとまらない質問でお恥ずかしい限りですが、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
こんにちは。最終回の質問は「死について」ですね。
老いるということはどんどん死に近づいてゆくということです。時々、一年以上先の講演を頼まれることがありますけれど、そういうオファーには「生きていたら参ります」とご返事します。ほんとうにその時まで生きているかどうかわからないから、先方にご迷惑をかけてはいけないと思ってそう言うのです。ジョークじゃなくて。
前にも書きましたけれど、僕は後期高齢者になる自分の現在の状態を「死に始めたけれど、まだ死に切っていない」過渡期というふうにとらえています。原理的な言い方をすれば、すべての人間は生まれた瞬間から「死に始めている」わけですから、赤ちゃんと老人の間には「程度の差」しかないと言えばその通りなんです。
だから、小さい子どもでも「死ぬのが怖い」と言って泣き出すことがあります。僕もそうでした。僕は6歳の時に重篤な心臓疾患のせいで死にかけたことがあるので、「子どもでも死ぬ」ということは実感として知っていました。死ぬときは心臓が止まって死ぬのだと思っていたので、夜寝る前に自分の鼓動をずっと聴いていました。心臓って「どく・どく」とリズミカルに鼓動するはずなんですけれど、僕は心臓弁膜症だったので、微妙にリズムが狂うんですよね。だから、「どく」と打った後にしばらく間があるのです。次の「どく」がなかなか来ない。そのときにほんとうに短い瞬間ですけれど「あ、今死ぬんだ」と思って泣き出したことがありました。父親が心臓に手を当てて「心臓は動いているから大丈夫だ」と言ってくれたので泣き止んだことを覚えています。7歳か8歳の頃だったと思います。
でも、不思議なもので、子どもでも、どこかで「いずれ死ぬ」という事実と折り合いをつけるんですね。「いずれ死ぬけれど、今ではない」ということで自分を安心させる術を身につけた。これは「術」という言い方をしていいと思うんです。人間は誰でも死ぬ。だから、自分もいつか死ぬ。でも、とりあえず今日ではない。だったら、今日一日は楽しく生きる。「いつか」と「今日」の間にはそれだけの「程度の差」があります。「五十歩百歩」の間には五十歩の差があるのと同じです。そして、その「五十歩」を一人の人間に与えられた寿命だと思えばいい。僕はそんなふうにして「いつか死ぬこと」と折り合いを付けました。でも、折り合いのつけ方はひとりひとり違うし、年齢によっても違ってくると思います。
僕が60代以降になって手に入れた「死と折り合うの術」は、前にも書きましたけれど、生物学的に死ぬ十三年前くらいから「死に始め」、死後十三回忌で「死に切る」という「死ぬのに26年かかる説」です。
26年といったら結構長いですよ。いろいろなことができる。生まれて、赤ちゃん時代を過ごして、学校に行って、友だちと遊んで、卒業して、働いて、その気になれば結婚して子ども持つことができる。うっかりすると年下の人間をつかまえて「オレが若い頃はな……」と説教する「おじさん」になっているかも知れない。26年と言ったら、それくらいの長さです。死に始めてから死に切るまではそれくらい長い。
死を「原液」で服用するととても濃くて飲めない。でも、「希釈」すると割とするすると飲める。カルピスとかコカ・コーラとか同じで、原液で飲んだらまずくて吐き出してしまうけれど、ソーダや水で割って、氷を入れて、洒落たグラスに入れて飲むと「美味しい」と感じることがある。死もそれと同じではないかと僕は考えるようになりました。
生と死の間にデジタルな境界線があって、100%生きている状態から100%死んだ状態にいきなり切り替わると考えると、「死を原液で飲む」ことになります。とてもつらい。でも、生と死はアナログな連続体であって、ある意味私たちはつねに「部分的に死につつある」のだと思うと、死の痛みを「希釈」することができる。
それに、生きている時間はそのつどすでに少量の死を含んでいるからこそ僕たちは「生きがい」を感じることができるのではないかと僕は思います。
美しいグラスがここにあるとしますね。落とせば割れる。雑に扱うとひびが入る。だから扱いがていねいになる。もう一つ、造形的にも、触感もまったく同じだけれど、プラスチックでできた「割れないグラス」があります。これは落としても平気です。さて、どちらのグラスで飲んだ方が飲み物は美味しいと感じるでしょうか。
これは絶対に「落としたら割れるグラス」で飲んだ方が味わいが深い。そういうものなんです。この唇とグラスの触感やグラスを持つ指先の微妙な緊張は「落とすと割れる」と知っているから生まれる。こんなふうに美味しく飲み物を味わうことができるのは「これが最後かも知れない」と思うから、その「一期一会」感が美味に加算される。
これが人生最後の経験かも知れないと思うから、スキーをしていても楽しいし、海で泳いでも楽しいし、鰻を食べても美味しいし、シャンペンを飲んでも美味しい。「あと何百年でも何千年でも、いつでも好きな時に鰻食えますよ」と誰かに保証されても、僕はぜんぜんうれしくないです。そんな保証されたら今食べている鰻がそれほど美味しく感じられなくなるから。
いつかはこの楽しみも終わると思うから楽しいんです。始まったものは必ず終わる。だから、終わりの接近をカウントダウンで感じながら経験する。それが「味わい」をより深く、奥行きのあるものにしてくれる。そういうものなんです。
ときどき、冬眠装置に入って、100年後に蘇生したいというようなことを言う人がいますね。100年後だと医療技術が発達していて自分が今罹患している病気が治せるかも知れないとか、不老長寿のテクノロジーが発見されているかも知れないとかいう理由で冬眠したい、と。僕にはとてもじゃないけれど、そんなのはごめんです。だって、100年後にはもう知っている人が誰もいないんですから。それに、自分が生きている間に身につけた知識や技術のほとんどがもう無用になっているかも知れない。そうでしょ。例えば、今、1925年に冬眠した人が蘇生してきたとして、僕とその人はいったいどんな話をすればいいんですか? まあ、大正デモクラシーがどういうものだったかとか、治安維持法の制定をどんな気分で迎えたのかとか、質問すれば興味深い答えが得られるかも知れませんけれど、この人を僕たちはどうやって社会に受け入れたらいいんでしょう。どんな仕事をしてもらったらいいんでしょう。「奇人」として標本のように扱われてしまうんじゃないかな。
『エイリアン2』という映画がありました。主人公のリプリー(シガニー・ウィーヴァー)は前作『エイリアン』の最後で、エイリアンを宇宙空間に吹き飛ばした後、冬眠装置に入りますが、地球軌道をそれて、なんと57年間も宇宙を漂流した末にサルベージされます。覚醒したら57年後だったんです。劇場公開版では使われなかったオリジナルシナリオではリプリーには娘がいたのですが、もう年老いて死んでいた。血縁が誰一人いない世界にリプリーは取り残されます。さいわい、テクノロジーはあまり進化していなかったので、リプリーは重機を扱う労働者として就職できます。仕事があってよかったです。でも、テクノロジーが進化していて、リプリーの知識や技能が無価値になっていたら、彼女にはこの世界にいよいよ居場所がなかったでしょう。
うかつに冬眠なんかするものじゃないというのが僕がこの映画から得た教訓の一つでした(そんな教訓を引き出した人はあまりいないと思いますけど)。それは言い換えると、ただ長生きしても、別にそれが特に「いいこと」であるわけじゃないということです。
僕は毎日音楽を聴いて暮らしていますけれど、聴くのはほとんど1960年代から70年代にかけてのアメリカのポップスです。エルヴィスやニール・ヤングやビーチボーイズの曲を繰り返し聴いています。2000年代以降に流行った曲はほとんど知りません。レディ・ガガとかテイラー・スウィフトとかは名前だけは知っていますが、楽曲は聴いた覚えがない(聴いたことがあるかも知れませんが、リコグナイズしていない)。
年を取って同世代の友人たちを鬼籍に送るということは、例えば僕が小学校六年でフォー・シーズンズの「シェリー」をはじめてラジオで聴いた時の驚きについて話しても、その感動を共有してくれる人が年々少なくなるということです。今ならまだキャロル・キングとかハル・ブレインとかいう固有名詞を口にしても、その含意を理解してくれる人がちらほらといますけれど、あと20年もしたら(僕がそれまで生きているとして)、僕の話の意味が分かる人はほとんどいなくなるでしょう。それは「円朝の『牡丹燈籠』を聞いたら背筋が凍った」とか「桃中軒雲右衛門の『赤穂義士伝』は絶品だよ」とか今言われても、「何すか、それは?」というリアクションしか返ってこないのと同じです。
僕の父親は89歳で亡くなりましたけれど、80歳過ぎたころにしみじみと「80歳を過ぎて長生きするとつらい」と慨嘆しておりました。友だちが一人また一人と鬼籍に入ると、そのたびに自分の人生のうちのある部分についての記憶の共有者がいなくなることがつらいというのです。
父は満洲事変の年から敗戦の翌年まで中国大陸で過ごした戦中派でした。ですから、「家族にも言えない記憶」をいくつも抱え込んでいました。父にとって、同じ時に同じ場所にいて同じことを経験した友人たちは文字通り「自分が生きてきたことの証人」だったのです。彼らがいなくなってしまうと、自分はほんとうに「そのこと」を経験したのかどうか、それが父自身にとってさえ曖昧になる。自分が生きて経験したことについては、やっぱり「その場にいた他者からの承認」が必要なのです。
刑部さんは『グリーンマイル』をご覧になったそうですけれど、主人公が受けた罰は自分の愛する人たちを次々と見送る喪失感を何度も繰り返し経験するというだけでなく、自分がいったいこれまでどんな人生を送って来たのか、それについての「記憶の共同署名人」たちがいなくなるということをも意味しています。例外的な長寿を得るということは、自分が何者であるのかの保証人が次第に少なくなるということなのです。
だから、例外的な長寿を願う人たちは、自分の子ども時代についても、自分の青春期についても、成熟した自分についても、それを知っている人が一人もいなくなるということの孤独と不安についてあまりに想像力が欠けていると僕は思います。
内田家は四人家族でしたが、父も母も兄も亡くなったので、もう僕以外に下丸子の小さな家で暮らした日々についての記憶を保持しているメンバーはいません。結果的に僕は1950年から1970年頃にかけての(家族が四人同じ家で暮らしていた時期の)家族一人一人の相貌についての「記憶管理人」のようなものになりました。こういう回顧的な文章を書き連ねているのも、「記憶管理人」としての僕の仕事の一つなのです。そして、僕が死ぬとその「家族の記憶」を語り伝える人もいなくなる。
ある人が生きたことの「証」はそういうふうに「記憶管理人」がいなくなるにつれて、だんだんおぼろになって、やがてかき消えてしまう。そういうものだと思うんです。
でも、だからと言って虚無的になる必要なんかありません。生きている間からすでに誰にも印象を残さない人もいるし、死後も長い期間にわたって語り継がれる人もいる。僕はそれもある意味でその人の「寿命」にカウントしてよいと思います。
自分が死んだら数年で誰も自分のことを忘れてしまうだろうと思って死ぬのと、死んでも数十年は折に触れて懐かしく思い出話を語ってもらえるだろうと思って死ぬのでは、死ぬことの「つらさ」が違う。さきほど「死」は誰にでも訪れるけれども、それを「原液で服用」しなければならない人と、「希釈して服用」できる人の間には、死を迎える時の「つらさ」に程度の差があるという話をしました。
死を迎えることの「つらさ」は「死に始めてから、死に切るまでの時間の長さ」の関数です。早くから「死に始めて」、死んだ後も「なかなか死に切らない」人は、死を希釈して服用していることになります。ですから、いざ死ぬ時もそんなにつらくない(身体的な痛みはともかく、精神的な痛みはずいぶん軽減されるはずです)。
たぶんそうじゃないかと思います(まだ死んだことがないのでわかりませんが)。
とりあえず僕たちが「死を迎える」ために準備することがあるとしたら、それはできるだけ早くから「死に始める」こと。それは先ほど書いたように人生のあらゆる瞬間における「一期一会」の経験を味わい尽くすということです。そして、もう一つは、できるだけ長く人々の記憶にとどまって、語り継がれるように配慮することです。
長く語り継がれると言っても、それは必ずしも例外的に英雄的でカラフルな人生を送るという意味ではありません(ふつうの人の身にはジュリアス・シーザーやナポレオンのようなカラフルな出来事は起こりません)。それよりは生きている間に周りの人たちにできるだけ親切にしておくことの方が死後語り継がれるチャンスは高いと僕は思います。
「他人に親切にしたって、何も得になることなんかない」とシニカルに言う人がいますけれど、そうでもないですよ。死ぬときに「あまりつらくない」という素敵な「贈り物」があるんですから。
「親切な人」とか「頼りになる人」というのは、言い換えると、死んだ後も生き残った人たちに繰り返し「あの人が今も生きていたらなあ」という喪失感をもたらす人ということです。「あの人が今も生きていたらなあ」という喪失感は死者をしてなかなかきっぱりと死なせてくれません。いつまでもことあるごとに人々の記憶に甦る。そういう死者は「死に切るまで」に時間がかかる。「死に切るまでの時間が長引くように生きる」というのが死を迎えるための準備だと上に書きましたけれど、その理路はおわかりになりますよね。
死を心穏やかに迎えるためには「死を原液で服用しないように、希釈しておく」ことがたいせつであるというのが僕の「死と折り合う術」です。
希釈というのは「早く死に始めて」「なかなか死に切らない」という生き方をすることです。「早く死に始める」というのは今日一日をこれが生涯最後の一日かも知れないと思って味わい尽くすことです。「なかなか死に切らない」というのは、とりあえず人に親切にして、家族や仲間から頼りにされる人になることです。これが一番簡単です。
以上がそろそろ「お迎え」が近くなってきた内田の「死を迎える」に当たって若い人に伝えたいことです。これでたぶん刑部さんの三つの質問のうち最初の二つについては答えたと思います。最後の質問は「31歳の自分に死について伝えたいこと」があるとしたら、何かというものでした。さて、31歳の内田樹君に何を伝えたらいいのかな。
僕はその年齢の時にはもう合気道の多田先生の門下に入って6年経っていて、黒帯二段になっていました。仏文の博士課程にいて、フランスの現代の哲学や文学の研究に打ち込んでいました。それに、娘がもうすぐ生まれるというところでしたから、「ちゃんと稽古に通って、研究もして、子育てもがんばってね」というくらいしか言うことがないですね。「そんなこと言われなくてもやってるよ。つうか、あんた誰?」というご返事が31歳の僕からは返って来るはずですから、「いや、よけいなこと言ってごめんね」と74歳の僕は笑顔で退散することになると思います。
というところで、「老いのレッスン」の最終回はおしまいです。刑部さん、長い間、変な話にお付き合いくださってありがとうございました。これから年齢を重ねてゆく上で、僕の話が少しでも役に立ってくれたらうれしいです。ご多幸をお祈りします。
1950年東京都生まれ。神戸女学院大学名誉教授。東京大学文学部仏文科卒、東京都立大学人文科学研究科博士課程中退。東京大学文学部仏文科卒、東京都立大学人文科学研究科博士課程中退。専門はフランス文学・哲学、武道論、教育論。主著に『ためらいの倫理学』、『レヴィナスと愛の現象学』、『寝ながら学べる構造主義』、『先生はえらい』など。第六回小林秀雄賞(『私家版・ユダヤ文化論』)、2010年度新書大賞(『日本辺境論』)、第三回伊丹十三賞を受賞。近著に『街場の米中論』、『勇気論』など。神戸市で武道と哲学研究のための学塾凱風館を主宰。