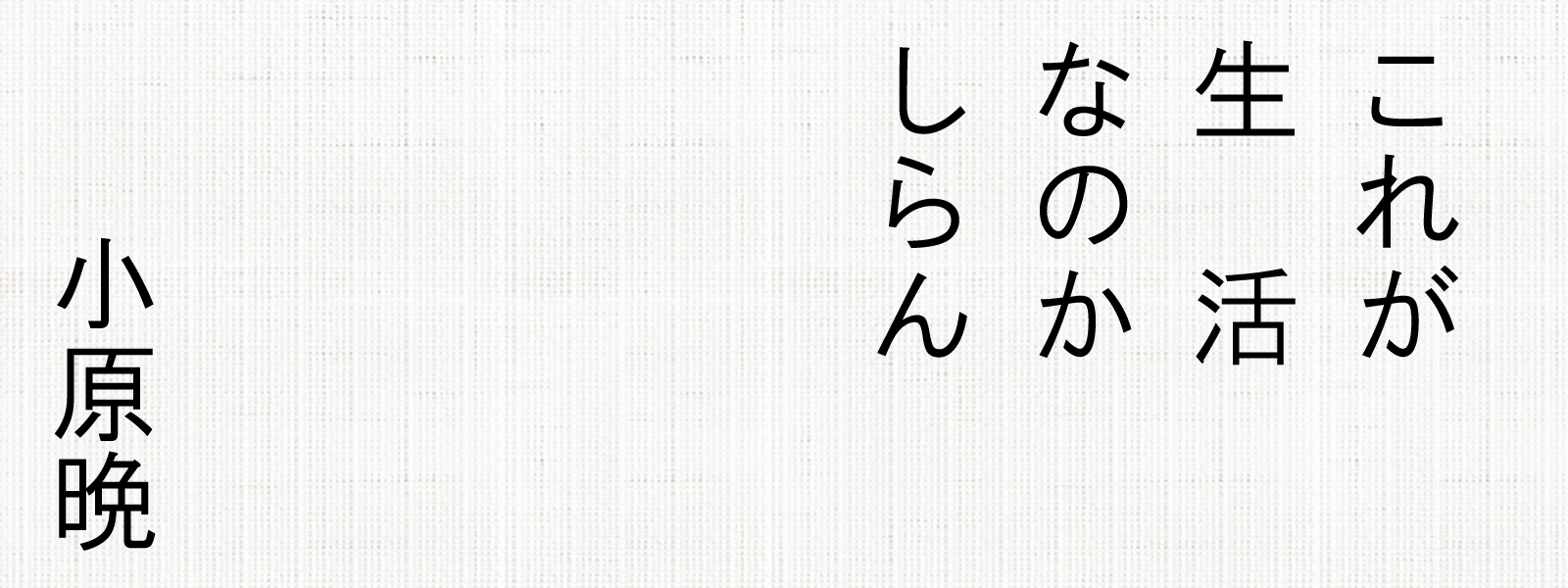まさかこれが自分の生活なのか、とうたがいたくなるときがあります。
それは自分にはもったいないようなしあわせを感じて、という場合もあれば、
たえられないほどかなしくて、という場合もあるのですが、
それはもちろん自分の生活であるわけです。
その自分の生活というものを、つまりは現実を、
べつだん、大げさにも卑屈にもとらえず、そのまま受けいれたとき、
みえてくるのは「ほのおかしさ」ではなかろうかと思います。
ままならない生活にころがる「ほのおかしさ」を私はずっと信じています。
結婚体験
☆このたび、9月23日に小原晩さんのエッセイ集『これが生活なのかしらん』が刊行されます。
ひとり暮らし、ふたり暮らし、三人暮らし、寮暮らし、実家暮らし……
いままでのさまざまな暮らしについて綴ったエッセイのなかから、
発売を記念して1つの詩と5編のエッセイを公開いたします。
最終回となる第5回は、住み慣れた東京を離れ、大阪へと引っ越した小原さんと恋人のふたり暮らし
の日常を描いた「結婚生活」です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
結婚生活
恋人の地元へ越してきた。ここは大阪。
恋人の家はきれいな一軒家で、おおきな冷蔵庫があり、ドラム式洗濯機があり、ダイソンがあり、たっぷりとした湯船がある。私ひとりの生活能力では今後一生を考えても手に入ることのない贅沢な暮らしがここにはある。
恋人の家族はずっとこの街に住んでいて、近所の喫茶店は恋人のおじいちゃんの行きつけで、スーパーマーケットに行くと休日のお父さんと出くわすことしばしばである。
表札には彼の苗字と私の苗字が入っていて、ここまでくると居候とは言わないのかもしれない、という気がしてくる。私はふわふわとしたきもちでここまでやってきたのだ。それなのに、こんなに堂々書いてもらっていいのだろうか。
近所のおばさまや子どもたちにご挨拶へ行くと「あら、奥さん?」と聞かれる。私は一瞬フリーズして、彼は「まだなんです」と答える。私は彼のうしろに隠れながら頭を下げる。
ふたり暮らしの日常は、たとえばこんな一日である。
恋人よりも一時間くらいはやく起きる。それからインスタントコーヒーをいれて、ソファーにもたれる。読みかけの本をめくることもあるし、ネットフリックスやユーチューブをながめていることもある。そうこうしていると、寝癖姿の恋人が起きてきて「寝すぎたなあ」というようなことをもぞもぞと言う。
私も彼も決まった時間に決まったところへいく仕事ではないので、ぐうたらが生活の基本姿勢である。
朝ご飯をどうする? パン食べる?
彼はうなずく。
甘いのにする? しょっぱいの?
しょっぱいの。
私は食パンにチーズとウィンナーを斜め切りしたものをならべて、トースターで焼く。
このパンは、父が私によくつくってくれたもので、私はこのパンがだいすきだった。
彼にできたてのトーストを届けるのだけれど、テレビにうつる大谷翔平さんのホームランに夢中でなかなか食べはじめない。彼はできたてに執着がないのだ。
あんまりにも食べはじめないものだから、食べないの? とつい聞くと「俺、猫舌やから」というのだけれど、食べものには、いちばんおいしい温度があるような気がするのは私だけだろうか。私なんか野菜から食べたほうが健康によいと、どれだけ根気づよく教えられても、とんかつ定食の主役はなんといっても揚げたてのとんかつなのだから、意地でもキャベツを後回しにしてしまう。でも、誰もがあつあつで食べたいわけではないものね。
朝食を食べ終わると、私は寝室にある作業机に座り、事務作業や書くことをはじめる。
彼も自分の部屋に行き仕事をはじめる。
ときどきベランダで煙草を吸うために彼は寝室までやってきて(寝室にはベランダがあるので)すこし喋り、作業に戻る。
時間はすこんと過ぎてゆく。
お腹がすいてくると、今度は私が彼の部屋に行き、夜ごはんは何時にする? と彼の腹の減り具合を確認する。
冷蔵庫には業務スーパーで買いためたものものがあるので、なにかしらつくる。私は色気のない料理が好きなので、豚しゃぶレタスとか、バーモントのカレーライスとか、茄子の豚肉巻きとかそういう茶色のものばかりをつくる。
作業が佳境を迎えていたり、とにかく休みたかったり、締め切り前で頭がぎりぎりしていると料理どころではなくなっているので、そういうときはコンビニのお弁当を食べることもあるし、出前をとることもある。
夜ごはんができると、下の階から恋人を呼ぶ。
野球の時期は野球を見ながら夜ごはんを食べる。
いままでの人生で私は自らスポーツをテレビで見ようとしたことは一度もなかったのだけれど、彼の趣味はスポーツ観戦なので、毎日見ている(私はごはんを食べながら血を見るのは苦手なので、ごはん中のボクシング観戦だけはやめてもらっている)。
そのあとはお風呂に入るか、また作業に戻るかする。
基本的には同じ時間にベッドに入る。
うまく眠りにつけないと、「顎の下を掻いて」と恋人にたのんで、顎の下を掻いてもらう。恋人は深爪なので、とてもやさしい掻きごこちなんである。しあわせってなんでもないものなんだなあ、と思いながら私は眠りにつく。
もともと私の結婚への興味関心というのは、好きなひとから、永遠に一緒にいたいと思っているという意思(結婚してください)がかたち(指輪)になって、目の前にわっとあらわれたとき、自分はどんなきもちになるのだろうという、そういう好奇心であり、その後の生活というのは、シンデレラが王子様と結ばれたところで物語が終わってしまうように、べつだん、考えたことがなかった。
その後、人生いろいろあって、結婚はおろか、恋愛なども、もうだめだ、むりだ、おそろしい、ひとりで生きていきたいと願うようになったのだけれど、やっぱり人生はいろいろであり、いまの恋人に出会ったわけだけれど、こうして、家があり、家電があり、家族に紹介しあって、有難い生活を得てもなお、私はやっぱり、結婚のことがよくわからない。
大阪に引っ越してくる前は、もしかすると一緒に住んだりしたら、すごく自然に結婚したくなるものなのかしら、と思っていたのだけれど、結婚わからん、まじわからん、というきもちは日々つのり、しかしこれは、もちろん相手になにかが不足しているとかそういうわけではなく、そして、私になにかが不足しているわけでもない。結婚してやっと一人前だなんて、いつの話をしているんだという感じであるものね。
そもそもプロポーズされる前提だったのも、いま考えればよくわからない。プロポーズは誰がしたっていいのだし。
二十五歳を超えると、結婚に関する話題が急に増えて、親、親戚、女友達と顔を合わせれば、あんた結婚どうするの、とかそういう話に必ずなるのだけれど、私はそのたびに結婚ってなんだろう。夫婦ってなんだろう。と考え込んでしまって、うーん、なんだかおそろしい、と思ってしまう。
きっと見つめるだけではわからないものなのだろうけど。
でも、こうして腹をだして眠っている恋人を見ていると、なんだかなつかしいきもちにくるまれるのも、またこれどうしてなのだろう。
☆書籍の紹介ページはこちらhttps://www.daiwashobo.co.jp/book/b10033028.html

一九九六年、東京生まれ。
二〇二二年、自費出版にて『ここで唐揚げ弁当を食べないでください』を刊行。
原稿を書くときはいつもアイスコーヒーとカルピスを用意します。
白いものと黒いもの、甘いものと苦いものがあるとなんとなく落ちつきます。