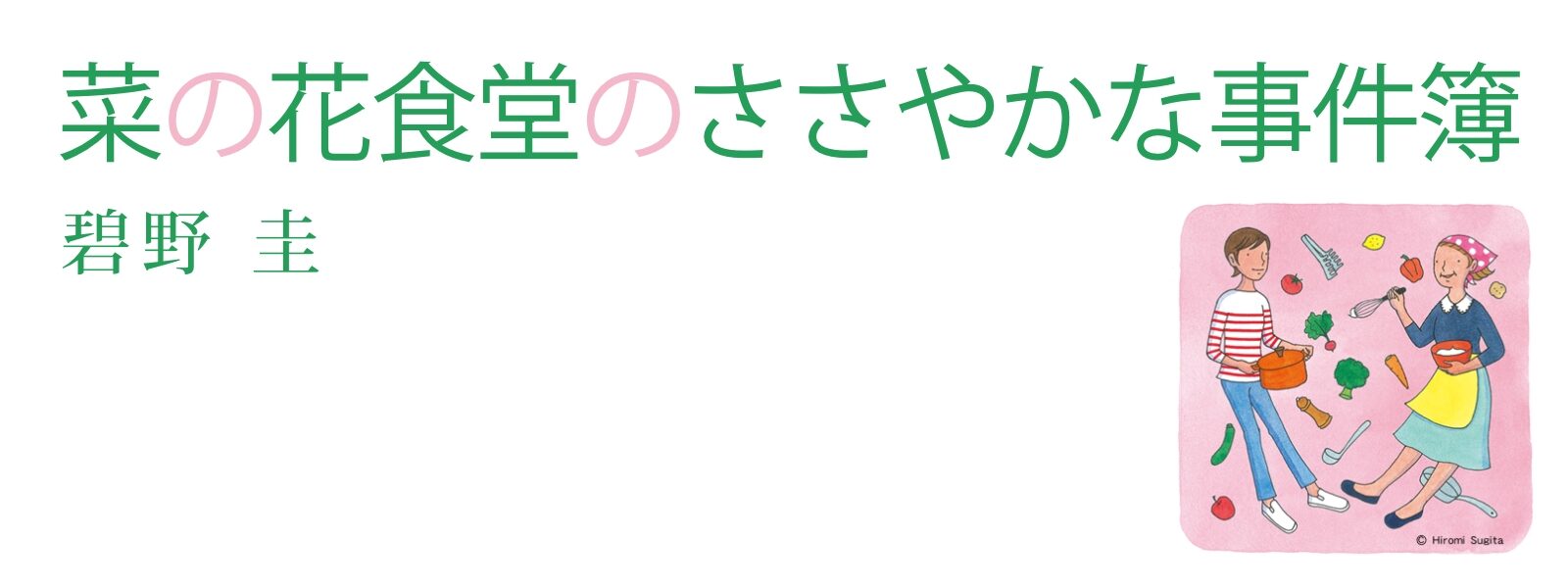疑惑のカレーライス 前編
「野川まつり? それなんですか? 野川マルシェとは違うの?」
川島悟朗さんは初めて聞いた、という顔で問い掛けた。川島さんは、つきあい始めたばかりの私、館林優希の彼氏だ。今日は私が勤めている菜の花食堂にランチに来ている。出版社に勤めている川島さんは、昨日校了で深夜遅くまで仕事していた。一区切りついたので、今日は午後ゆっくり出社していいという。食事が終わったらそのまま会社に向かうらしいが、ジーンズにシャツとおよそ仕事に出掛ける格好には見えない。もっとも編集者はみんなそんな格好らしい。
「知らないの? そうか、川島さんは線路の北側に住んでいるんだっけ。北側の人たちには野川も遠いし、あまりなじみがないかもしれないね」
会話している相手は、常連の守屋正一さんだ。
今日のメニューは五穀米のプレートランチ。サンマの竜田揚げをメインにして、野菜の小さなおかずをいろいろ載せている。きんぴらごぼう、里芋の味噌和え、カブとベーコンのハニーマスタードソテー、きのこのマリネ、豆腐とわかめの味噌汁。食後の珈琲と抹茶のシフォンケーキがつく。食堂のプレートランチはヘルシーだがボリュームもあるし、ご飯のおかわりもできるので、川島さんも気に入っているそうだ。
「野川マルシェは毎月第一日曜日に市内の有志のお店が集まってやるイベントだけど、野川まつりは毎年一〇月に二日掛かりで行われるお祭りなんだ。もう五〇年くらいは続いていて、市内だけでなく近隣のお店も出店する。野川沿いの広場と呼ばれる場所を知ってる?」
「広場?」
「じゃあ、ハゲ山は?」
野川に沿って広がる武蔵野公園は、遊具などは少なく、自然の景観に似せて樹々が植えられたり、緑の芝生だけ植えられたりしている。地面は真っ平ではなく、自然なくぼみがあったり、鯨の背中くらいの大きさに土が盛り上がっている場所もある。その小山を、地元のひとたちは親しみを込めて「ハゲ山」と呼んでいる。
「もしかして、道路建設問題でなくなるかもと言われている場所ですか?」
「そう。住民の反対運動が起こっているんで、何かと話題になってる場所」
「ああ、それならわかります」
川島さんが道路建設問題を知ってるとは意外だった。同じ市内でも北部に住む人たちはそういう計画があること自体、知らない事が多い。その私の疑問に答えるように、川島さんは補足する。
「大家の保田さんに頼まれて、反対の署名をしたんですよ。自然も多くていい環境なのに、つぶされるのはよくないって」
「そう、そのハゲ山の辺りが野川まつりの会場なんだ。今週の土日に開催される。屋台が百軒くらい出て、その横ではフリーマーケットもやっている。のんびりしたいい感じのイベントだよ」
「屋台ですか。じゃあ、神社のお祭りみたいな感じですか?」
「いや、うちの市はテキヤを排除しているから、ふつうのお祭りの屋台は一軒もない。出店するのは一般の飲食店か、地域で活動している人達がお祭りのために出店するケースかどちらか」
「地域で活動している人って?」
川島さんは食事をする手を止めて、興味深そうに守屋さんの話に聞き入っている。
「助産院が手作りのお菓子を売ったり、学童の父兄たちがカレーを売ったり、社会運動をやっている人たちが告知のためにブースを作ったり、いろいろだよ。子どものためのおもちゃの手作り講座とかもある。それに中央のステージではずっとバンドが入れ替わりで演奏しているんだ。音楽がずっと聞こえている」
「へー、学園祭みたいですね」
「うん、そんな感じ。手作り感満載だし。でも、プロの飲食店は若い人に人気のあるお店が中心で、インド料理とか中華とかアフリカ料理とか、エスニックも多い。レベルは高いよ」
「へー、同じ市内なのに、なんでそのイベント知らなかったんだろ」
「野川まつりは宣伝をあまりしないからね。人が集まり過ぎると困るからって、マスコミの取材は一切受けないんだ。いまの人数くらいでちょうどいいんだって」
「そうなんですね。欲がないんですね。あ、この店は出店しないんですか?」
ピッチャーのお水をコップに注いでいる私に、川島さんが尋ねた。
「勧められたんですが、二日あるイベントなので準備が大変だし、野川まつりは出店するより見に行く方が楽しいからって、うちは出ないことにしたんです」
私はそう答える。菜の花食堂は野菜中心の家庭料理を出す店だ。野菜料理は手間が掛かる。いつもお店で出すようなものは屋台には向かない。かといってカレーなどお手軽にできるものはほかの店でも売っている。競合してまで売る必要はない、というのが靖子先生の考え方だった。
「そうですか。じゃあ、一緒に見に行きませんか? 僕、今週末は予定がないし」
川島さんが守屋さんの前で言ったので、私はどぎまぎした。日曜日は夜の予約がないとお店はお休みになる。幸い今週は予定がなかった。
「お、デートの申し込み? いいねえ、若い人は」
「ええ、先週末は僕が校了前でバタバタしていたし、その前は優希さんの方がお店で貸し切りパーティがあったから忙しかったし、ふたりの都合が合うのは久しぶりなんです」
川島さんはそう言うが、そんな時でもモーニングを喫茶店で一緒に食べたり、リモートでふたり飲み会をしたりしているから、まったく会わないわけではない。
「そうか、でもいいの? こんな地元のイベントなんかじゃなく、コンサートや美術館でも行って、青山とか六本木の洒落たレストランで食事したりする方がいいんじゃないの?」
守屋さんがからかい口調で言う。
「あ、そうだった。ごめんね、自分の事しか考えなくて」
川島さんが慌てたように、そう言って私の方を見る。川島さんは以前つきあっていた彼女に『自分のペースで人を振り回す』と言ってふられたそうだ。それを気にして、すごく気を遣ってくれる。だけど、私自身は川島さんと好みが近いし、同じようなペースなので気にならない。
「いえ、私も日曜日には行こうと思っていましたし、川島さんと行けるならそっちの方が楽しいですから」
「おお、優希さんも言うね。こっちはあてられちゃうよ」
ひゅうひゅうと言って守屋さんがからかう。私は苦笑しながらピッチャーを持ってキッチンの方に下がる。
「ほんとにいいの? せっかくのデートなのに、野川まつりに行ったら、顔見知りの人にたくさん会うよ」
オープンキッチンなので、フロアの会話が聞こえたらしい。シェフの助手をしている和泉香奈さんが気づかうように言う。
「いいの。気取ったレストランや街の人混みに行くより、ふたりとも地元でのんびり過ごす方が性に合ってるから。川島さんは引っ越してきて日が浅いから、この辺のこともっと知りたいって言ってるし」
おしゃれしてハイヒール履いて、というデートも時には楽しい。だけど、それだけだと自分をうまく出せない。前につきあっていた彼氏とはそういうデートばかりで、いつも相手にいいところを見せようと気を張っていて、疲れてしまった。川島さんとはもっと素を見せられる関係でいたい。
「まあまあ、つきあいたての今は、何をやってもどこに行っても楽しいものよ。外野が気に病むことじゃないわ」
キッチンの奥にいた靖子先生が、笑顔で香奈さんをたしなめる。
「すみません、靖子先生」
「私じゃなくて、優希さんに言わなきゃ」
「いいですよ、そんなこと。ところで靖子先生も野川まつりに行くんですか?」
「ええ。奏太くんにぜひ来てくれって言われたから。奏太くんの通っていた学童の父母会で、カレーライスの店を出してるんですって。夏のキャンプの資金稼ぎのため、だそうよ。OBも参加するキャンプだから、奏太くんも当日手伝っているらしいわ」
奏太くんというのは、靖子先生の家にお手伝いに来ている小学生の男の子だ。一時間お手伝いをする代わりに、食事の作り方を教えてもらって、夕食もごちそうになっている。先生はお孫さんのようにかわいがっている。
「カレーライスって、西小の学童を見守る会のあれですか?」
私は先生に聞いた。ランチもそろそろ終わる時間なので、いまは少し余裕がある。
「そう、西小のお店はもうずっと前から毎年出ているわ。黒い幟を立てて、毎年ワンコインカレーを出してました。安いし美味しいので、いつも行列ができてましたよ。お皿を持って行くと、おまけにお菓子をひとつくれるというサービスも子どもたちが喜びますね」
「香奈さんも野川まつりに行ってたの?」
「うん、子どもの頃はね。坂下の子どもたちなら、みんな行ってたんじゃないかな。子ども向けのお楽しみも多かったし、友だちの家族と一緒にフリマにも何度か参加した。お店ごっこみたいで楽しかったよ」
「じゃあ、今年も行くの?」
私の問いに、香奈さんは笑って首を横に振った。
「昔散々行ったから、当分行かなくてもいいや。結婚して子どもでも出来たら、また参加したいけどね」
どきっとした。香奈さんはつきあってる相手と結婚も考えている。子どものいる未来というのもそんなに遠くないのかもしれない。
「私も、子どもが小さい頃はずっと行ってたけど、ここ何年も行ってない。二〇年ぶりくらいかしら」
靖子先生が昔を思い出すように遠い目をする。そういう靖子先生を見るのはなんだか切ない。先生には実のお子さんがふたりいるが、両方とも離れた場所に住んでいる。
「じゃあ、そんなに前から続くイベントなんですね」
「そうよ。始めたのはヒッピーだそうだから」
「ヒッピーってなんですか?」
香奈さんが不思議そうな顔をする。何度も行っていた香奈さんでも、祭の起源は知らなかったらしい。私は昔のアメリカ映画を見た時、ヒッピーが出てきたので、漠然と存在は知っていた。
「ああ、ヒッピーを知らない世代なのね。ヒッピーっていうのは一九六〇年代にアメリカを中心にさかんだったムーブメントのこと。愛とか自由とか平和を訴え、規制の社会概念を壊して、新しい価値観のユートピアを作ろうとした人たちの集まり。あのビートルズも、ヒッピーだと言うひともいるわ」
「へえ、なんか素敵なことのように聞こえますね」
「いい面も悪い面もあったの。彼らの運動が、アメリカのベトナム戦争からの撤退の大きな要因になった。環境問題や動物愛護、東洋思想などを多くの人に知らしめるきっかけも作った。菜食主義とかヴィーガンを広めたのもヒッピーたち。そういういい面はある」
「そうなんですね。ヴィーガンを広めたっていうのは素晴らしいですね」
料理人の香奈さんは、やはりそういう面に興味を持つ。
「一方で既存の社会や家族制度を否定し、麻薬やフリーセックスを好むということで、社会的な反発も大きかった。アメリカの軍事的な力を支持する保守的な人も多かったしね。男性でも髪や髭を伸ばし、男女関係なくぞろぞろ引きずるような清潔感のない服を着て、うるさいロックをかき鳴らす。そういうファッションやライフスタイルを嫌がる人も少なくなかった。結局、ベトナム戦争終結後にはムーブメントは下火になり、ヒッピーと言われた人たちも社会の中に組み込まれていったの」
「日本にもヒッピーっていたんですか?」
「少しだけどね。ヒッピームーブメントというのは古い価値観の打破ということで、先進国の若者に大きな影響を与えた。六〇年代に日本で盛んだった学生運動も、それと密接にかかわっている。新宿がヒッピームーブメントの中心的な役割を果たしていたけど、新宿に乗り入れている中央線沿線の高円寺、吉祥寺、国分寺は三寺って言われて、ヒッピーが多いことで知られていた。そこに定着して、自然食品を扱う店とかヴィーガンの飲食店を始めたのも彼ら。それが今でも一部に残っているのよ」
「ああ、確かに、中央線沿線はほかの路線よりナチュラル系のお店が多いですね」
「ガチなヒッピーはほとんど消滅しているけど、ヒッピーが残した自然志向の食品やファッションは、思想的な背景をなくして、うんとおしゃれにして生き残っている、と言えるかもしれないわね」
私は、通学に便利なのでたまたまこの地に住み着いた。三〇分も掛からず新宿にも行ける便利さと、そこここに畑や藪が残っているのどかさに惹かれて、もう一〇年近くもこの街に住んでいる。なのに、そういう歴史的な背景があるとは全然知らなかった。
「ヒッピーっていうのは、周りの人たちからはどう見られていたんでしょう?」
「さあ。ヒッピーがいた頃って私も子どもだったし、私の周りにはいなかったから、よくは知らない。だけど、反体制的な思想の人たちだから、彼らを嫌う人もいたでしょうね」
「そうなんだ」
反体制という言葉は私も抵抗がある。社会を覆そうという考え方は、なんとなく怖い。
「でも、始まりはそうでも、半世紀近く経ったいまは主催者も代替わりしてるし、ごく健全なイベントよ。ふたりで楽しんでくるといいわ」
「先生は何時頃いらっしゃるんですか?」
「そうね、カレーを食べるようにって奏太くんに言われたから、日曜日のお昼頃には行こうと思う。優希さんも、できれば奏太くんの店に顔を出してね。きっと喜ぶわ」
「わかりました。私もまだそのカレーを食べたことがないので、楽しみです」
おまつりに行く目的がひとつできた。おそらくほかの知り合いにも会えるだろう。地域との繋がりがこうして少しづつ増えて行くのが、私は嬉しかった。
野川まつり二日目の日曜日は、すっきりした秋晴れだった。一二時過ぎに坂上から来た川島さんは、食堂の裏手にまわり、乗っていた自転車を置かせてもらった。食堂からお祭りの場所まではそれほど遠くないのだ。そこからはふたりで歩いて行く。先生もご一緒にと誘ったが、遠慮されたのか、もう少ししたら行く、とおっしゃった。
「川島さん、お皿やコップ持って来た?」
「いや、持ってないけど。ないとダメなの?」
「事前に言えばよかったね。無くても大丈夫だけど、器を持参すると、おまけをつけてくれたり、盛りを多くしてくれるの。私、このためにランチボックスのセットを買ったんだ」
「へー、そうなんだ」
「このイベント、エコもテーマになっているんだって。だから、ゴミも基本自分たちで持ち帰りを推奨している。そういうことに賛同する人だけが出店してるんだそうよ」
「いいことだね。金儲け最優先ってことじゃないんだね」
「運営も基本はボランティア。出店料が安い代わりに、いろいろと参加者がお手伝いをするんだって」
食堂から南の方に歩くと、すぐに野川に出る。野川沿いには遊歩道が作られており、それに沿ってぶらぶら歩く。寒くもなく暑くもなく、ちょうどいい季節だ。この遊歩道は春には満開の枝垂れ桜が続く桜の名所でもある。残念ながら一〇月の始めの今は、桜も紅葉も見られないが。
住宅が途切れたあたりから、はらっぱのような広い敷地が現れる。短い草が生えたはらっぱと、それを取り巻くように樹々が植えられている場所だ。いつもはかけっこをする子供や犬を連れて散歩する人たち、河原の野鳥を観察する人くらいしか見られないが、今日は様子が一変していた。大変な賑わいだ。手前に何百台もの自転車を置くスペースがあり、旗を持ったボランティアが誘導している。その奥はフリーマーケットのスペース。通路を作り、その両脇に敷物を敷いた出展者が四十、五十組はいるだろうか。子連れも多く、使わなくなった洋服や本、おもちゃなどを安い値段で売っている。子どもが呼び込みをしている。
それを両脇に見ながら歩いて行くと、屋台が立ち並ぶ場所になる。ちょうど昼時のせいか、既にあたりはひとでいっぱいだ。真ん中のハゲ山の辺りは、敷物を敷いて座っている人達で埋まっている。人気のあるお店の前には、行列ができている。焼き鳥を焼く匂いや、醤油が焦げる匂いが漂っている。右手の奥では、マシュマロを長い串に刺して焚火で焼いているのが見える。
道路建設反対運動をしている人たちのチラシを受け取り、環境保護を訴える団体のアンケートに応えて。さらに進むと飲食のブースが並ぶスペースだ。手前は主にアマチュアの飲食店。さまざまに工夫した手作りの看板が並んでいる。それぞれのブースは日除けのテントを立て、その下に長机を置いてカウンター代わりにしている。
「いい感じだね。学園祭みたい」
私が思ったことを川島さんが口にしたので、思わず笑みが浮かんだ。手描きの看板などは、大学時代の部活の看板によく似ている。
「あ、あれが奏太くんのお店かな?」
川島さんが指さしたのは、「西小の学童を見守る会」という黒い幟のあるブースだ。カレーライスとハヤシライスを売っている。カレーは五百円だが、ハヤシライスは六百五十円と少しお高い。店の前には十人ほどの行列ができている。
「あ、奏太くんだ」
テントの奥の方で、父母や子どもたちに混ざり、手際よくご飯を盛り付けている奏太くんが見えた。こちらの方に目を向ける余裕はなさそうだ。
「忙しそうだから、声は掛けない方がいいね」
「どうしよう、このまま並ぶ?」
「もうちょっと後でもいいかな。初めてなんで、先に奥まで見てみたい」
川島さんが言うので、奥の方まで歩いて行く。真ん中の辺り、ハゲ山の前はステージが作られていて、そこでロックバンドが大きな音量で演奏をしている。ロックと言っても反戦歌っぽい感じで、ちょっと懐かしい感じがする。その前にひときわ広い本部のテントがあって、来場者の問い合わせに応じたり、パンフレットを配ったり、ビールやポトフを売っている。
私たちもそこで無料のパンフレットを貰った。今日の店の位置や内容を紹介したもので、冊子ではなくコピー用紙の裏表に白黒で印刷されたものだ。店の配地図は手描きだ。
「手作り感満載。ますます学園祭っぽいね」
「いや、大学の学園祭のパンフの方がもっと立派だよ。ちゃんと印刷された冊子だし、写真も使ってる。広告も載ってるし。これはひとつも載ってないね」
そんな話をしていると、「こんにちは」と、ビール売り場の方から声を掛けられた。人混みの中でもよく通る声だ。
「あ、川崎さん。こちらの本部の役員もやってるんですか?」
川崎さんは毎月開催される野川マルシェというイベントでも、本部役員をしている。川崎さんの紹介で、菜の花食堂も野川マルシェに参加したことがある。
「いいえ、出店者が本部のビール売りも手伝うことになっているので、いまの時間は当番なの。ビール、いかが? ビールはここでしか売ってませんよ」
川崎さんの声にはパワーがある。活動的な性格が声に出ていると思う。顔立ちも意志が強そうだが、いつも笑顔を絶やさない。
「いただきます」
「僕も」
「ありがとうございます。助かります」
「助かるって?」
「ここの売り上げが本部の収入になるの。このおまつり、運営はボランティア。出店料で儲けは出さないから、ビールの売り上げとポトフの売り上げで賄っているんです」
「そうなんですね。じゃあ、買わなきゃ。ポトフは去年いただきました。しっかり野菜の出汁が出て、美味しかった。おまけに安いし」
「でしょ? どう? 一緒にポトフも」
「いただきたいけど、もうちょっとお店を見てからにします」
「じゃあ、後ほどお待ちしていまぁす」
川崎さんは商売人っぽい、愛想のよい笑顔で返事した。それから、ビールをちびちび飲みながら、会場の奥の方を見て回る。こちらはプロのお店が集まっている。ケバブの店やアフリカ料理など、エスニックのお店が多い。名前を聞いたことのないような食べ物もあって、興味津々だ。占いや手作りの服を売っているお店もあって楽しい。地元で有名な珈琲屋台も出店していた。その店は店舗を持たず、日によって公園や契約している民家の軒先などに屋台を出す。
「これが有名な珈琲屋台か。初めて見た」
川島さんは感心したように屋台を見る。屋台の女主人が慣れた手つきで珈琲を淹れている。
「知ってたの?」
「うん。地元を紹介するブログか何かで読んだ。女の人が屋台を引いて移動するっていうんで、おもしろいな、と思っていたんだ。ほんとに火鉢を使ってお湯を沸かしているんだね」
屋台の後ろにはいくつか火鉢が置かれており、やかんが掛かっている。
「あれ、湧き水を使ってるんだよ」
「へえ、そうなんだ。せっかくだから、飲んで行きたいな」
既にビール瓶は空になっている。酔い覚ましに珈琲はよさそうだ。幸い列にはふたりくらいしか並んでおらず、すぐにオーダーが通った。屋台の奥にはちゃぶ台と小さな折り畳み椅子が並んでいる。椅子に座って珈琲を待っていると、人混みの向こうに担架を持った人達がいるのが見えた。彼らは慌ただしく本部のテントのところに行く。
「なんかあったのかな?」
じっと見ていると、テントから担架に乗った人が運び出された。連れなのか、女性がその担架に付き添っている。
「この人混みで、気分が悪くなった人が出たのかも」
川島さんも心配そうに言う。近くにいた人たちは、道を開けて担架が運び出されるのを注目している。だが、ほとんどの人はそれに気づいておらず、本部近くにいる人も、特設ステージの方を注目している。
「何事もないといいね」
人が運び出された後は、周囲にたむろしていた人たちもそれぞれの場所に戻って行った。私たちも担架のことは忘れ、おしゃべりに夢中になった。珈琲を飲み終わった後、事情を聞こうと思って、本部のビール売り場に出掛けた。
「こんにちは。ビールお代わりですか?」
川崎さんが笑顔で迎えてくれる。
「ビールのお代わりはもうちょっと後にします。食事をしようと思って。ところで、先ほど誰か具合の悪い人が出たんですか? 誰か、担架で運ばれていたみたいだけど」
私が尋ねると、川崎さんの表情が引き締まる。
「そうなの。お客さまのひとりが急に気持ち悪くなって、意識が朦朧としてきたそう。救急車はここまで入れないから、公園の先の道路の方に停めてもらって、担架で運んでもらったの」
「人混みで具合が悪くなったんでしょうか?」
「そこまで混雑はしていないと思うけど……」
「もともと体調悪かったんでしょうか?」
「そうかもしれない。でも、気になるのは、今日これで三人目なのよ」
「三人目?」
思わず大きな声が出る。すると、川崎さんが人差し指を口元にあてた。
「しっ、これは内密にね。まだ何かあると決まったわけじゃないから」
川崎さんが言うのもわかる。ただの偶然であれば、お祭りに来た人たちの興を殺ぐだけだ。原因がわからないうちに騒ぎ立てるべきじゃない。
「それは気になりますね。まさか食中毒ではないでしょうね」
私も小声で言う。
「食中毒なら、被害はもっと大勢、一斉に出ると思う。最初に体調不良を訴えられたのは二時間前。二人目は三〇分前。それに、いま」
「確かに、それだと判断が難しいですね」
「もちろん食中毒の可能性も考え、体調崩した方に何を食べたかは聞いているだけど、みなさんいろいろ食べているから、これと絞るのも難しい。三人ではサンプルが少ないし。それに、症状も一定ではないし」
「というと?」
「吐き気がする人もいるけど、動悸がしたり、意識が朦朧としたり、興奮したり」
「確かにばらばらですね」
「もし、このおまつりで出された食品が原因なら大問題だから、一刻も早く原因を突き止めないといけない。それで本部役員が飲食のお店に聞き込みに行ってるけど、故意にそんなことをする出店者がいるはずもないし、誰も心当たりはない。実は、このままおまつりを続けていいものかどうか、これ以上誰か具合悪くなるようなら、原因がわかるまでいったん中止にすべきではないか、という意見も出ているのよ」
「そんな事態になっていたんですね。でも、それで中止になるのは残念だな」
「それはそう。私たちも一年がかりで準備してきたし、中止にすることは、出店した方たちの売り上げをなくすことにもなる。何より、目の前でこんなにたくさんの人たちが楽しんでくれているのに、それを急に中断するのは本意じゃない。だけど、もしこのおまつりで問題があったとわかったら、来年から開催できなくなるかもしれない」
「えっ、そうなんですか?」
「そうなのよ。いまどきはイベントを開催するのもいろいろ気を遣うの。このおまつり、どこともタイアップしていないでしょ? 行政とも絡んでないし、代理店も使ってない。完全に市民のボランティアで運営されている。だけど、これだけのお客を集めることができるから、ビジネスチャンスと思う連中もいるし、目障りだと思う人もいるのよね。なんやかんや難癖つけて運営を自分たちのものにしようとする人もいるし、行政のコントロール下に置こうとする人もいる。自分たちの主催するお祭りよりにぎやかだからってやっかむ人もいるし、うるさいからやめてほしいと思っているご近所の人もいないわけじゃない。だから、運営は気を遣って、トラブルが起きないように、ご近所には事前に案内を配るし、車や自転車で歩行者の邪魔にならないように、終わった後のゴミが散らからないようにと、すごく気を付けているの。昔は夜通しテントを張って泊まり込みでお祭りを楽しむ人もいたけど、いまはそれも禁止されてるし」
「確かに、昔よりコンプライアンス的なことは厳しくなっていますものね」
「そうなの。時代とともに、こういう自由なおまつりを自主的にやるのは難しくなっている。でも、だからこそこの形のまま続けたい、と思っているんだけど」
「ああ、それはヒッピーの人たちの精神が生きているってことでしょうか?」
なにげなく私が口にすると、川崎さんはぎょっとした顔をした。
「あれ、何かまずいんでしょうか?」
「いや、まずくはないし、知ってる人は知ってるけど、ヒッピー由来ということを嫌うひともいる。六十年代を覚えている人たちにとっては、ヒッピーは反体制だし、フリーセックスとか麻薬とか、悪いイメージがついて回る。このお祭りも、昔は夜通し騒いだりする人もいてて、『これだからヒッピーの始めたイベントは』って、白い目で見られていたの。いまはもう運営も入れ替わったし、こんなにモラルの高いイベントもないと思うんだけどね」
「そうですよね。おかしなイベントだったら、半世紀も自主運営で続くなんて無理だと思います」
「ですよね。実際みんな楽しんでいるし。それに」
そう話していると、本部役員らしい男性が「ちょっと」と、こちらに声を掛けてきた。そして、川崎さんに奥の方へと目で合図する。おそらく関係者以外には聞かせたくない話があるのだろう。
「じゃあ、いまの話はくれぐれも内緒にしてね」
川崎さんは小声で言うと、役員の方に走り寄る。私と川島さんもその場を立ち去ることにした。
※後編に続く
愛知県生まれ。東京学芸大学教育学部卒業。フリーライター、出版社勤務を経て、2006年『辞めない理由』で作家としてデビュー。
『菜の花食堂のささやかな事件簿』シリーズのほか、ベストセラーとなりドラマ化された『書店ガール』シリーズ、『銀盤のトレース』シリーズ、『凛として弓を引く』シリーズ、『スケートボーイズ』『駒子さんは出世なんてしたくなかった』『1939年のアロハシャツ』『書店員と二つの罪』『レイアウトは期日までに』等、多数の著書がある。
地域の食文化への興味から、江戸東京野菜コンシェルジュの資格を取得。