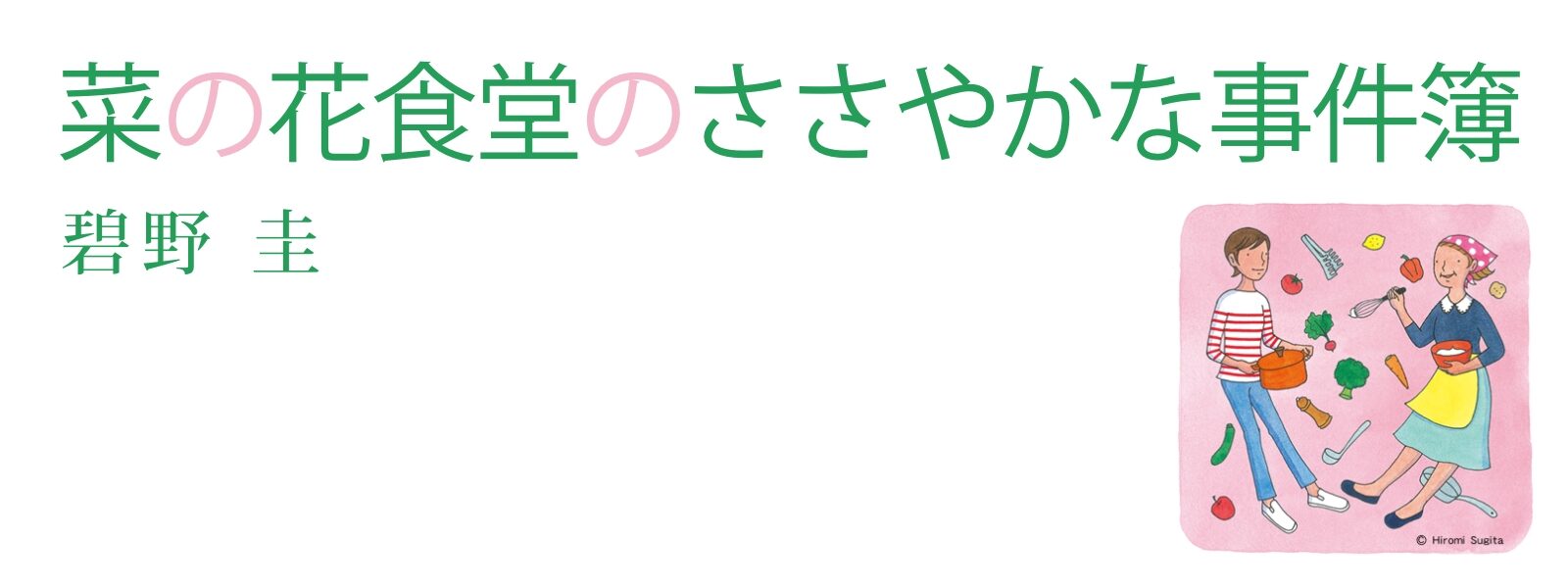筍の胸さわぎ 後編
先生の切羽詰まったような勢いに押されて、小瀧さんはリードを持つ手を緩めた。動けるようになった小太郎は迷いなくずんずんと前に進む。私たちはそれについて行く。
小太郎はアパートの前まで進み、さらに一番奥にある部屋の前に行くと、ここだというように「ワン!」と吠えた。
「ここでいいのね?」
先生が小太郎の目を見ながら話し掛ける。小太郎はその言葉を理解したように「ワン、ワン」と、返事する。
先生はそのドアをノックした。しばらく待ったが返事はない。その部屋の前には何も置かれておらず、曇りガラスからうっすら見える中にも灯りの気配はない。人が住んでいるような気配は感じられない。小太郎はガウガウと吠え続ける。その様子を見た先生が、決然と言う。
「ここを開けましょう」
「いいんですか? 勝手に」
小瀧さんの言葉に返事をする前に、先生はドアノブを回した。幸い鍵が掛かってなかったのか、扉は簡単に開いた。部屋の中は薄暗い。目がその闇に慣れる前に、小太郎が中に飛び込んでいく。その勢いにリードが外れる。小太郎は奥の部屋に行き、ひときわ大きな声で「ワン、ワン」と吠え続けた。靴を脱ぎ、一足遅れて中に入ろうとした私は、何かに引っかかって倒した。カランと軽い音がして転がったのは、細長い杖のようだった。それを避けて奥に近づくと、誰かがそこに横たわっていることに気が付いた。
「えっ、人がいるの?」
後ろにいた小瀧さんが、驚いたような声を出す。
その時、部屋が突然、明るくなった。小瀧さんが玄関の傍にあるスイッチをみつけて、それを押したのだ。
部屋の全貌が見えてくる。手前は二畳ほどの台所、その奥に四畳半と六畳の和室が続いている。部屋の中に荷物は少なく、大きな食器棚とその隣に和ダンスがひとつ。テレビと、和ダンスの上にはダイヤルでチューニングするタイプの古いラジオが一台。座布団が一枚。それ以外は何も出ておらず、装飾品は一切ない。殺風景なほどだ。そして、奥の六畳間にその部屋の住人らしい男性が倒れていた。背中側を上にしているので、顔は隠れて見えない。白髪なので、高齢者だろうと思う。小太郎は私たちに「ここだよ」というように「ワン!」と、吠えた。
「まさか、死体?」
思わず私が口走る。声が少し震えた。
先生は男性の傍に屈みこんだ。
「大丈夫ですか?」
先生が話し掛けると、その男性は囁くような声で「だい…じょうぶ」と、答えた。意識はあるが、動けないらしい。
「よかった、意識はあるようね。でも、すぐに救急車を呼んで」
先生の言葉が終わらないうちに、小瀧さんの声がした。
「男性がひとり倒れています。救急車を一台お願いします。意識はありますが、衰弱しているようです。場所はK市中町……」
小瀧さんは落ち着いた声で、冷静に状況を説明しはじめた。一方靖子先生は言う。
「それから、保田さんにもここに来てもらいましょう」
「保田さん? あの、農家の?」
「アパートの壁にあった名前を見なかった? 保田ハイツってあったでしょ? この建物は保田さんがオーナーだと思う」
「まったく、急に下河辺さんに呼び出されて、何事かと思ったよ」
その翌日、保田さんが菜の花食堂に来ていた。ランチタイムが終わる二時近くなので、お客はほかにいない。カウンター越しに先生と話している。
「突然のことだったし、誰に連絡すればいいかわからなかったから。保田さんが大家であれば、最初の契約の時に藤井さんの御身内などの情報も知らされているだろうと思ったの」
先生はティータイム用のお菓子を作りながら、保田さんの相手をしている。藤井徹さんというのが、アパートの中で倒れていた男性の名前だ。
「ともあれ結果的には、呼び出してくれたのはよかったよ。近くに親戚はいないし、付き添っていろいろ検査も受けさせられたし。藤井さんひとりだったら、いろいろと不自由しただろうから」
「それで倒れた原因はなんだったんですか?」
「医者によれば起立性調整障害って言うらしい。藤井さんはもともと血圧が低いそうだけど、薬も飲まないし、運動不足だったので血流が停滞してたんだろうね。それで、自律神経のコントロールがうまくいかず、食後に低血圧になって失神したんだそうだ。意識はすぐに戻ったものの、気持ち悪いし、倒れた拍子に腰を強く打ったので、その痛みで動けなかったらしい」
「それはお気の毒に」
「幸い骨には異常はなく、打撲だったそうだけど、頭でも打ったら大変だからね。また起立性調整障害が起こらないように、と医者にいろいろ指導を受けていた」
「じゃあ、そんなに深刻な状況ではなかったんですね」
「うん。失神には怖い病気が潜んでいることもあるので、いろいろ検査してもらったけど、血圧以外は問題なかった。それがわかっただけでもよかったよ。本人も、失神したことにショックを受けていたから、すぐに病院に行けたことに感謝していたよ」
「感謝されるほどのことじゃありませんよ。勝手に上がり込んで、救急車を呼んだだけですから」
靖子先生は首を振りながら、笑顔で言う。
「ところで、よく俺があそこの大家だってわかったね」
「壁に保田ハイツって書かれたプレートがあったし」
「だけど、保田の保が見えないくらい薄れているのに」
「実はポストの中の郵便物を見たの。そこにも保田ハイツって書いてあったから。保田さん、自分の経営するアパートには必ず保田って入れるでしょ。それに、隣に竹林があったし」
「竹林?」
「保田さん、毎年筍を届けてくれるけど、北側の保田さんの自宅周辺には竹林はないでしょ? どこか別の場所にあるんだと思っていた。竹林とアパートを隔てて反対側にあるのは保田さんの畑。だから、地続きのアパートから竹林まで全部保田さんの土地じゃないか、と見当つけたのよ」
「さすがだね。おっしゃる通りだ。あの辺一体はうちの土地なんだけど、日当たりがいまいちよくないし、全部更地にしてマンションか何かに立て替えたいんだけど、アパートには藤井さんが住んでいるだろ? 藤井さんが引っ越すまではまあ、そのままにしておこうかと思ったんだ」
「それは、藤井さんが視覚障害者だから?」
先生が尋ねる。その問いに、私も保田さんもびっくりした。
「どうしてわかったの?」
「あのアパートはお化け屋敷って言われるくらい人気がない。夜も灯りが点いているのを見た人がいない。それで、電気を点けなくても生活できる人って考えたの。藤井さんの部屋の玄関のところに杖も置いてあったから、ああ、そういう人だなってわかったのよ」
やはり靖子先生は洞察が鋭い。私はそこまで思い至らなかった。
「それに、チラシがよく散らかっているって言われていたでしょ? 住人がいるなら片付けるのが普通だけど、散らかったまま。それはもしかしたら気づいてないのかもしれない、と思ったの」
「なるほどねえ。下河辺さんにはかなわないな。お化け屋敷とか言われて、ゴミをわざわざ捨てるやつがいるから、困っているんだ。ほんとはアパートの持ち主の俺が掃除しなきゃいけないんだけど、毎日は行けなくてね」
保田さんが恥ずかしいのをごまかすように頭を掻く。
「ところで、藤井さんはいつからあそこに住んでいるんですか?」
私は気になっていたことを聞いてみた。
「もう十二年になるかな? 前に住んでいたアパートが取り壊しになるから、と追い出され、行き場がなくて困っている人がいるって知り合いの不動産屋から聞いて、うちのボロアパートでよければ、と紹介したんだ。年寄りだとそれだけでアパートを貸したがらない大家もいるし、まして藤井さんは視覚障害者で、身寄りもないと言うからね。こんなぼろアパートだけど、家賃も安いし、静かだと喜んで借りてくれたよ」
「藤井さん、今後はどうなるんでしょうね」
「無事に退院できたし、これからも一人暮らしを続けるんだろうけど、もういい年だから、一度倒れたとなると心配だな」
「隣近所に誰かいればまだいいけど、あのアパート、ほかに誰も住んでいないんですよね。心配ですね」
「どこか施設に入れるといいんだけどね。本人は身体が動けるうちは、そういうところには入りたくないって言うんだ。いままでも日常のことはひとりでやってきたし、散歩も買い物もひとりでやれるそうだからね。その気持ちはわかる。自分だって同じ立場だったら、そう言うと思うし」
保田さんはカップに残っている珈琲を飲み干した。
「お代わりはいかがですか? 珈琲が少し残っているので、よければどうぞ」
私が聞くと、保田さんはにっこり笑ってカップを持ち上げた。
「嬉しいね。じゃあ、もらおうかな」
ソーサーの珈琲の残りを保田さんのカップに注ぐと、ちょうど一杯分あった。
その時、カランコロンと音がして、お客が入って来た。小瀧さんだ。
「まだランチ、大丈夫ですか?」
「はい。おひとりであれば。お好きな席にどうぞ」
私が返事をすると、小瀧さんはカウンターの方にやってきた。
「ああ、あなたは病院で会った」
保田さんが小瀧さんを見て声を上げた。
「小瀧です。あなたはアパートのオーナーの方でしたね?」
「保田です。ばたばたしていたので、あの時はちゃんと挨拶もしませんでしたね。すみません」
「いえいえ。こちらこそ。……ここ、座っていいですか?」
小瀧さんは保田さんから二つ離れたカウンターの席に着いた。
「今日のランチは玄米と白米を選べますが、どちらになさいますか?」
私が尋ねると、小瀧さんは迷わず答えた。
「玄米をください」
私はカウンターの中の先生にそれを告げる。保田さんが小瀧さんに話し掛けた。
「この前はお手柄でしたね。あなたが藤井さんの異変をみつけたんでしょ?」
「いえ、私じゃありません。私が飼っている柴犬です。それも、靖子先生がいなかったら、アパートに入ったかどうかわからないし」
「藤井さんとその件についてちょっと話をしたんだけどね。もしかしたら、友だちの犬かもしれない、と言っていた。以前藤井さんはスーパー銭湯でマッサージ師として働いていて、そこの同僚だった人が近所にいるのだそうだ。藤井さんができないことをよく手伝ってくれていたらしい。手紙を読んでくれたり、宅配で頼めないものを買って来てくれたり、ずいぶん助けてもらったそうだ。友だちはよく犬を連れていたので、会うたびに撫でたり、餌をやったりして可愛がっていたらしい。その友だちは施設に入ってしまって会えなくなったので、犬がどうなったかは知らないそうだけど」
「その犬の名前は?」
「聞いたんだけど、なんて言ってたっけ? 太郎……そう、小太郎と言ってた」
私と小瀧さんは顔を見合わせた。
小太郎。やっぱり藤井さんは小太郎の前の飼い主と繋がりがあったのだ。
「じゃあ、同じ犬だと思います。うちの仔も小太郎という名前です。そうそうある名前じゃありません。それに、前の飼い主さんも、この近所に住んでいらした、と聞いています」
「ああ、知り合いだから助けたのか。でも、どうして藤井さんが倒れていることに気づいたんだろう」
「さあ。なぜかはわかりませんが、犬には人間の何倍も鋭い嗅覚や聴覚があるし、人にはわからないことがわかったとしても不思議じゃありませんよ」
「そういうことかもしれないね。どっちにしろ、助かってよかった」
その時、ランチセットができあがった。私は先生から料理の並んだお盆を受け取り、小瀧さんの前に置いた。
「わあ、美味しそう」
今日のランチメニューは豚の生姜焼き。ポテトサラダ、レタスとトマト、ほうれん草のおひたし、若竹煮、大根と人参の味噌汁、それに玄米だ。生姜焼きはどこのお店でも人気のランチメニューだと思うけど、はちみつを使ってタレの甘味を出した先生のレシピはどの店よりも美味しいと思う。
「若竹煮、料理教室でもやりましたね」
小瀧さんは真っ先に若竹煮に箸をつけた。
「おいしい。ほんと、お店のとは違いますね。これも採れたての筍を使ったんですか?」
「そうですよ。こちらの保田さんが昨日持って来てくださったものです」
「そうか、アパートの隣に竹藪がありましたね。そこから採ったものですか?」
「ええ、そうです。でも、あの竹藪もそろそろなくそうかと思っています。なので、来年は筍は採れないかも」
「ええ、そうなんですか?」
聞いていた私は、思わず声を上げた。
「保田さんの筍はいつも楽しみにしていたのに」
「それは申し訳ないんだけど、あのアパート、お化け屋敷とか言われて、物騒だろ? この際建て直そうかと思うんだよ。竹藪を撤去して敷地を拡げ、日当たりもよくしたいんだ。そうすれば店子も入ると思うし」
「藤井さんはなんておっしゃっているんですか?」
「できれば今のままがいい、とは言っている。部屋が変わると、いろんなことを一から覚えなきゃいけないから大変なんだそうだ」
「それはそうでしょうね」
「だけど、ちょうどうちの敷地に建ってるアパートの部屋がひとつ空いたからさ、ほら、川島くんの住んでる部屋のお隣」
川島くんというのは私のつきあっている相手だ。彼の実家から送ってくる野菜を私が料理していたこともあって、場所はよく知っている。
「あのアパートは家族向けなんじゃないですか?」
「それはそうだけど、広いに越したことはないだろう? 川島くんだってひとりで住んでいるわけだし。あそこなら日当たりもいいし、うちの敷地の中にあるから、何かと俺が気にしてやることもできるし。住民も皆いい人たちだから、藤井さんが困った時には助けてくれる。人目があるから、もし倒れたりしても、すぐに気づいて助けることもできる」
聞いていた私はなるほど、と思った。保田さんの敷地のアパートには何度も行ったことがあるが、住民みんな仲良しだ。たまに大家の保田さんがみんなと一緒に庭でバーベキューをする。落語に出てくる下町の長屋みたいな空気がある。子どもたちは保田さんの庭を我が物顔で走り回っているし、悪いことをすると、自分の子も他人の子も関係なくみんなで注意する。藤井さんが来ても、温かく迎えてくれるだろう。
「だけど、家賃は上がるんでしょう?」
「ん、まあでも、うちの都合で引っ越ししてもらうんだから、家賃もおまけしようと思う。もっとも藤井さん自身は乗り気じゃないけどね」
「どうしてですか?」
私が尋ねる。そちらに引っ越した方が、絶対いいと思うのに。
「私は藤井さんの気持ちがわかる気がします」
小瀧さんが言う。
「というと?」
キッチンにいた靖子先生が、興味深そうに尋ねた。
「いままでずっとひとりで頑張ってきたから、いまさら隣近所の世話になりたくない、と思っているんでしょうね。それに、保田さん個人の好意や周りの人の好意に甘えていると、条件が変わった時、成り立たなくなります。たとえばの話ですが、保田さんが急にお金が必要になった時、藤井さんの存在が重くなるかもしれない。周りの人も自分の生活があるから、藤井さんの頼みを聞ける時と聞けない時があるでしょう」
「じゃあ、このままでいいと思うんですか?」
さらに靖子先生が聞く。靖子先生は小瀧さんの考えを面白がっているようにも見える。
「いえ、もうちょっと生活を楽にする方法はあると思います。たとえばヘルパーさんに時々来てもらって、できないことをサポートしてもらう。ヘルパーさんに限らず、視力障害者の方のための公的サポートはいろいろありますよ。デイサービスが使えたり、盲導犬を利用することも可能です。藤井さん、現在はそういう制度を利用しているんでしょうか?」
「いや、そういう人が出入りしているって話は聞いたことがないな。藤井さん、若い頃に失明したので、ある程度のことは自分でできるように訓練しているし、そもそもサポートを頼む手続きが面倒でやっていないと言っていた」
「やはりそうだと思いました。家族がいれば手続きをしてくれますが、本人ひとりではそれも難しい。役所から通知が来ても、それすら気づかないこともあるだろうし」
私は藤井さんのアパートの郵便受けを思い出した。手紙やチラシでいっぱいで、郵便受けが閉まらないほどだった。
「確かにね。俺も親のために介護ヘルパーを頼んだことがあるんだが、書類を揃えるのがめんどくさい。支援が始まれば本当に助かるけど、それを頼むまでの過程がめんどくさすぎて、年寄りには無理だろう、と思ったよ」
「今後のことを考えれば、施設に入るという手もありますね。藤井さん、年齢はいくつですか?」
「確か、七十五歳だったかと」
「だったら、養護盲老人ホームに入る資格はあると思います」
「それはどういう施設なんですか?」
「文字通り視覚障害者のための老人ホームです。そういう障害のある人に配慮した設備になっているし、相談員や支援者、介護者なども通常のホームより多く配置されているんです」
「それはいいと思いますが、数はそんなに多くないんでしょう? 入所は難しいんじゃないでしょうか?」
「それは実際に当たってみないとわかりません。タイミングがよければすぐに入れるかもしれませんし。藤井さんは独り暮らしだし、有利だとは思いますよ」
「どっちにしても、手続きは大変じゃないですか? 藤井さんにできるでしょうか? 大家の自分が手続きするのもおかしいし、他人にそもそも代わってやる権利があるかどうか」
保田さんは懐疑的だ。
「私がお手伝いしようと思います」
小瀧さんの発言に、みんなびっくりした。
「ほんとうに?」
「小瀧さん、大丈夫ですか?」
小瀧さんは平然と答える。
「私、東京都の福祉局にいたんです」
「福祉局というのは?」
靖子先生が尋ねる。
「文字通り、都民が幸福で安定した生活を送ることを公的に達成しようとする部署です」
「つまり、老人福祉や障害者についての問題も取り扱う部署ってことですか?」
「その通りです。私自身は企画部にいたので、老人福祉や障害者福祉の対象者と直接的に関わっていたわけではありませんが、ふつうの人よりは知識はありますし、手続きのやり方もわかっていると思います」
小瀧さんは、そう言って微笑んだ。小瀧さんは長年仕事をしていた人特有の自信にあふれている。
「ああ、なるほど。それは適任だ。でも、ほんとにいいんですか? 縁もゆかりもない藤
井さんのために、そんなに手間や時間の掛かることをやるなんて」
「困っている人のための公的サービスって案外多いのに、それを知らない人が多いって思
うんです。それを利用すれば困難を乗り越えられたかもしれないのに、知らないために犯
罪に走ったり、より悪い事態に陥ったりする。それがとても残念なんです。今回藤井さん
とたまたま関わりあってしまったんだから、藤井さんが安心して生活できるような基盤づ
くりをお手伝いできたらと思うんです。前からボランティアがしたいと思っていたけど、
こういう事だって、ボランティアと変わらないですし。これなら自分の仕事の知識が役立
ちますし」
「それはご立派な考えですね」
「立派なんてとんでもない。ただの自己満足ですよ。それに、本人がどう思うか。お節介
はごめんだとおっしゃるかもしれませんし」
小瀧さんは照れたように言う。
「お節介、結構じゃないですか。お節介というのは、人と関わろうという意志の表れだし、
相手がそれを受け取るにしろ受け取らないにしろ、あなたに関心を持ってるよ、と伝える
ことになる。無理やり親切を押し付けるのはよくないが、何も言われないよりは相手には嬉しいことだと思うよ。相手がもし素直に受け取ってくれるなら、こっちも嬉しいしね」
保田さんの言葉は温かい。そう、この温かさに私も何度か助けられてきたのだ。
「じゃあ、藤井さんに話してみましょうか。公的サービスを使うかどうかは最終的には藤井さんの判断だけど、こういう選択肢がある、と知るだけでも、本人の気持ちが楽になるかもしれないし」
「そうですね。今度一緒に藤井さんに話しに行きましょう」
私は嬉しくなった。藤井さんというのは、近所に住んでいるというだけで、ほとんど縁のない人だ。それなのに、みんなで藤井さんがどうしたらいいか真剣に考えている。みんな優しいな、と思う。
「よかったわ。じゃあ、これを。優希さん、配ってもらえますか?」
先生が差し出したお盆の上には、ワインのようなものが入ったグラスが載っている。
「これはワイン?」
「いえ、まだお昼ですからぶどうジュースです。お店からのサービスです」
「いいんですか?」
「ええ。皆さんの優しい気持ちを伺って、素敵だと思ったので」
ぶどうジュースのグラスは、私の分も先生の分もカウンターの奥にいる香奈さんの分もあった。
「保田さん、乾杯の音頭を取ってください」
「俺が? じゃあ、簡単に行くよ。藤井さんの健康とみなさんの未来を祝して、乾杯!」
「乾杯!」
みんなが唱和して、グラスの中のジュースを飲み干した。ジュースはほんのり葡萄の香りがして、甘さとほんの少しのほろ苦さが舌の上に残った。
その翌日に、小瀧さんと保田さんは藤井さんに会いに行った。藤井さんの希望を聞いて小瀧さんが奔走した。本人は視覚障害者のための施設があるなら、そこに入りたいと言ったのだが、すぐには空きがないので、しばらくは公的補助を受けながら現在の暮らしを続けるという。ヘルパーさんや訪問看護の人が定期的に訪れることになり、配食サービスも受けられることになったので、生活は改善されるだろう。藤井さんは小瀧さんにたいそう感謝していたそうだ。
「ほんとによかったですね」
翌日の仕込みのために筍の下ごしらえをしながら、私は先生と藤井さんの話をしていた。
「ええ。視覚障害がなくても、老人のひとり暮らしは大変ですから。私も他人事じゃないわ」
さらっとおっしゃったことに私は胸がつまった。先生はまだ六十代だ。まだまだこの生活を続けてくださるように思っているが、本人は引退後の生活も既に視野に入れているのかもしれない。そんな気持ちを追い払いたくて、私は先生に尋ねた。
「ところで、奏太くんたちが肝試しに行った時、鈴の音を聞いたって本当なんでしょうか? 何かを聞き間違えたのでしょうか?」
「ああ、私たちが行った時も鈴の音は鳴ってたわよ。気づかなかった?」
「えっ、ほんとですか?」
「真っ先に小太郎が飛び込んで行って、その時に糸を引きちぎったので、最初しか聞こえなかったけど」
「糸を引きちぎった?」
「アパートの廊下に細い糸が渡されていて、その先には鈴がついていた。おそらく誰かが来たら気づくように、小瀧さんが仕掛けを作っていたのね。特に夜は物騒だし」
「ああ、そうだったんですか。全然気づきませんでした」
「お化け屋敷という噂が立って、面白がって夜に来るような人もいましたからね、そうやって自衛してたんだと思う」
その気持ちはわかる。夜中に、急に誰かが自分の住んでるアパートに入り込んだら、怖いと思うだろう。
「たまには灯りを点けるといいのよね。あるいは、敷地の周辺を歩くとか。人がいないと思うと、勝手に入り込む人もいますからね」
「それはそうですね」
「小瀧さんが引っ越すまでは、アパートはそのままだし。保田さんは大変だけど」
「大変?」
「アパートを建て直した方が、新しい店子も入って家賃収入も増えるでしょ? お金のためなら、そうした方がいいでしょうから」
それはその通りだ。保田さんは言わなかったけど、藤井さんが引っ越してくれた方が、大家としてはかえってよいのかもしれない。
「でも、世の中お金ばかりじゃないですからね。おかげで竹藪もしばらく残るから、こうして新鮮な筍も食べられる」
先生は筍を茹でている鍋からアクをすくい取っている。
「そういえば、筍泥棒の件はどうなったんでしょうね? また盗まれたそうだけど」
今朝筍を届けながら、『久しぶりに出たよ』と、保田さんは愚痴っていた。
「ああ、あれはね、そういうつもりじゃなかったと思うのよ」
先生のおっしゃることがわからなくて、私は聞き返した。
「そういうつもりって?」
「おそらく自分の住んでいる敷地に生えているものだから、自由に採っていい、と思ったんでしょうね」
「住んでる敷地ってことは……藤井さんが?」
「誰とはいいませんけどね」
先生はいたずらっぽく笑った。先生は名前を出したくないらしい。
「でも、あの方は……簡単な料理はできるそうですけど、筍を煮ることまでやれるんでしょうか?」
「だから、自分の為じゃないのよ。人にあげていたんでしょうね。たとえば小太郎の飼い主さんに。いろいろお世話になっていたんでしょう? あまり裕福でない人がなんとかお返しをしたいと思っていて、目の前に竹藪があったとしたら……ねえ?」
「ああ、確かに。本物の筍泥棒なら一回に一本しか採らないなんてありえないですし」
「もし、そういう事だとしたら、わざわざ私の方から言うこともないかな、と思って。保田さんに聞かれたら答えますけど、私の憶測でしかないですからね」
その時、店のドアが開いて、小瀧さんが入って来た。
「あら、まだお店は開いてませんよ」
「今日は食事じゃないんです。すみませんが糠が余ってないでしょうか? もしあったら分けていただきたいんですけど」
「糠? どうするんですか?」
「実は今朝、藤井さんから筍をいただいたんです。お世話になったお礼だと言って。掘りたてだと言うので、すぐに下茹でしようと思うんですが、スーパーで売ってる糠は多すぎるので、こちらで少し売っていただけないかと思って」
その話を聞いて、私と先生は目を合わせた。そして、どちらからともなく笑いがおこった。
「どうしたんですか?」
小瀧さんは笑いの理由がわからず、ぽかんとしている。
「いえ、なんでもないです。じゃあ、すぐに出しますね」
私は冷蔵庫の中に常備しているタッパーから米ぬかを取り出した。ビニール袋に必要な分だけ入れて、小瀧さんに手渡した。小瀧さんは一刻も早く料理に取り掛かりたいのか、お礼を言うと、走るように店をあとにした。
※連載第3話に続く
愛知県生まれ。東京学芸大学教育学部卒業。フリーライター、出版社勤務を経て、2006年『辞めない理由』で作家としてデビュー。
『菜の花食堂のささやかな事件簿』シリーズのほか、ベストセラーとなりドラマ化された『書店ガール』シリーズ、『銀盤のトレース』シリーズ、『凛として弓を引く』シリーズ、『スケートボーイズ』『駒子さんは出世なんてしたくなかった』『1939年のアロハシャツ』『書店員と二つの罪』『レイアウトは期日までに』等、多数の著書がある。
地域の食文化への興味から、江戸東京野菜コンシェルジュの資格を取得。