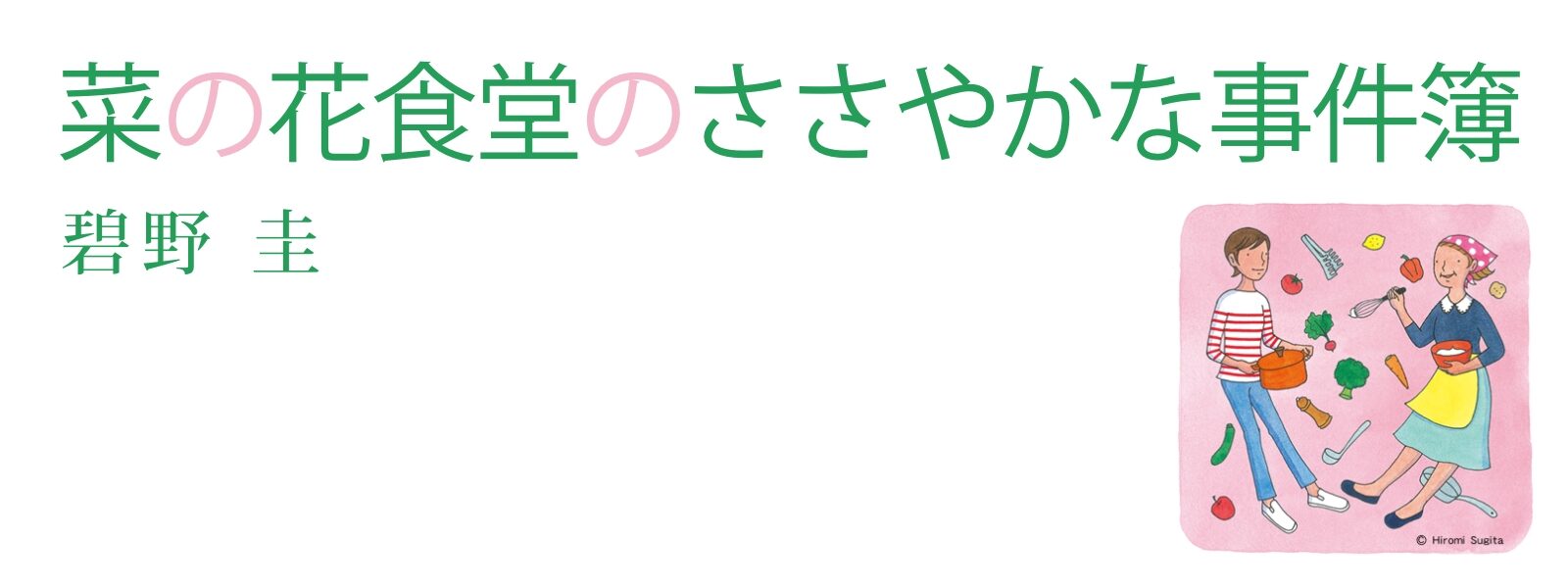筍の胸さわぎ 前編
「糠を入れて、吹きこぼれないように気をつけながら、一時間から二時間ほど茹でます。筍を柔らかくするだけでなく、アクを取るのが目的ですから、弱火で気長に茹でます。茹でっぱなしではなく、アクが出てきたら、こまめに取ってくださいね」
下河辺靖子先生の説明を聞きながら、生徒さんたちは鍋の中を覗き込んでいる。鍋の水は糠で濁っており、その中に皮つきの筍が浮んでいる。今日は菜の花食堂の料理教室の日だ。助手の私は目立たないように、説明を聞きながら隅の方に立っている。
「茹で上がってもすぐにはお湯から出さず、そのままの状態で一晩置きます」
「一晩も置かないとダメなんですか? いままで粗熱が冷めたらすぐに取り出していました」
驚いたような声を出したのは、常連の村田佐知子さんだ。村田さんは五十代半ばで、今日の生徒の中では最年長だ。
「冷ましている間にも、アクがさらに出ます。それに、冷ましている間に、茹で汁に溶け出たうまみも戻りますから、最低でも八時間は置いてほしいですね」
靖子先生の説明を聞きながら、生徒たちはメモを取る。
「筍を美味しくいただくには、えぐみが出ないようにすることが大事です。長時間掛けてせっかく茹でたのに、冷ますのを怠って台無しになったらもったいない。夜茹でれば、朝までほったらかしにするだけですから、ぜひ実行してください」
靖子先生はにっこり笑う。見ている人が嬉しくなるような、明るい笑顔だ。
「ああ、そういう事なんですね。だから、うちで茹でてもえぐみが残っていたんだ」
村田さんが感心したように言う。
「でも、一晩待っていたら料理教室が終わってしまいますから、今日はあらかじめ下茹でしたものを用意しました」
先生が目で合図したので、私は奥のテーブルに置いてあった皮つきの筍を、生徒さんたちのテーブルに配る。生徒さんたちの間から感嘆の声が上がった。
「わあ、私、皮つきの筍、触るの初めて」
若い生徒さんがそんなことを言う。茶色っぽい毛のついた皮に包まれた筍は、それぞれの調理台のパットにちんまりと収まった。
以前は食堂の中で料理教室を開催していたが、瓶詰作りの小屋を増築したので、そこで教室もできるようになった。前より生徒数は増えたが、評判がいいのでいつも満席だ。今日はまだひとり欠けているが、あとから来るという連絡を受けている。
「今朝、掘りだした筍です。大きさも手ごろで料理には最適ですよ」
昨日の朝届けてくれた保田さんは目を細めて笑っていた。保田さんは菜の花食堂に出入りしている農家さんで、食堂の野菜の多くは保田さんのところで採れたものだ。
「これで間に合うかな?」
いつもより早く、朝の八時ごろ食堂に現れた保田さんは、土の匂いがするような新鮮な筍を五つ、テーブルに取り出した。全体が茶色っぽく、少し歪んで形の悪いものもある。
「ああ、さすが。いい筍を持って来てくださいましたね」
靖子先生が嬉しそうに言う。
「いい筍?」
私がうっかり疑問を口にすると、靖子先生が説明する。
「お店に売ってるのは、もっとまっすぐで堂々したものばかりですものね。でも、こんなふうに根っこのところの切り口が楕円になっている方が、実は柔らかく茹で上がるのよ。それに、この根元のつぶつぶ。時間が経つとこれが赤くなっていくけど、まだ白いでしょ? 新鮮な証拠よ」
「さすが下河辺さん、わかってるね」
保田さんが嬉しそうに笑う。ちゃんと野菜の良し悪しがわかる相手に売れるのは、野菜の作り手としては嬉しいのだろう。
「掘り出して三十分も経っていないから、新鮮さは折り紙つきだ。掘り出して、すぐにこっちに持って来たんだよ。残念ながら五本同じ大きさにはならなかったけどね。揃えたかったんだけど、こればかりは掘ってみないとわからないからねえ」
筍の大きさはだいたい揃っているが、ひとつだけそれより小さい。
「大丈夫です。生徒さん用の分の大きさが揃っていればいいので。いつも無理を言ってすみません」
先生は軽く頭を下げた。
「いやいや、ちょうど間に合ってよかったよ。これとめぼしをつけていても、朝になると無くなってることもあるからね」
「無くなってるって?」
「筍泥棒だよ。他人の敷地に勝手に入ってきて、筍を取って行くんだ」
「そんな人がいるんですか?」
先生は目を丸くした。
「そうだよ。ちょうどいい育ち具合のものを、ちゃんと知ってるんだ。落ち葉で隠しても全然ダメ。明日採ろうと思ったものをかっぱらって行っちまう。それも真夜中に来てるらしくて、朝早くにこっちが見に行っても、既に盗まれた後。竹林は真っ暗なのに、よくまあ探せるよ、と呆れてるんだ」
「しょっちゅう盗まれるんですか?」
私も質問してみた。
「いや、そうでもない。泥棒と言っても一シーズンに三、四回くらいだし、盗むのも一本とか二本だから、かわいいものだ。ああ、そういえば今年は一件もない。いつもは出始めるとすぐにやられていたんだが。もう筍シーズンもピークなのに、全然ないね。もしかしたら、筍泥棒も河岸を変えたのかもしれない」
「私有地につき立ち入り禁止って看板は立ててないんですか?」
「立ててはいるけどね、それでひるむなら、筍泥棒なんかしないだろうね。ほんと、スーパーに行けば皮を剥いたものが安く売ってるのに、なんだって泥棒するんだろう」
「そりゃ、採れたてのものにはかないませんからね。私も、保田さんが届けてくれるようになってからは、お店で買わなくなりました。茹でるのは面倒だけど、味が全然違いますから。それに、保田さんはいつも手頃なものを持って来てくださるから、ほんとありがたいです」
先生に褒められて、保田さんは照れくさそうに頭を掻いた。
その後、すぐに筍を茹でた。掘り出してから、その時点で一時間くらいしか経っていないだろう。筍は鮮度が大事だから、ベストなタイミングのはずだ。
そうして一時間ほど煮て、一晩置いた筍が、まな板の上にある。
先生は筍の皮を剥いた。一枚ずつではなく、穂先と根っこをそれぞれ握って、逆方向にひねると、すぽっと外れる。先生がお手本を見せると、「わ、簡単!」「おもしろい」と、生徒さんたちが歓声を上げている。
「固い皮を何枚か剥くだけで、白い筍が出てくるなんて、面白いですね」
若い生徒さんが言う。
「さあ、これで下準備はおしまい。時間は掛かるし、ちょっとだけ手間が掛かるけど、その分味は段違い。美味しいものを食べるためだと思って頑張りましょう」
先生の言葉に生徒たちは「はーい」と返事をする。そうして、料理を作り始める。
今日の料理は筍ずくし。筍と豚バラ肉のルーロー飯、若竹煮、筍と牛肉の塩レモン炒め、筍の春巻き、筍とエノキダケ入り中華スープ。
いつものようにご飯もの、煮物、炒め物、揚げ物、汁ものと調理法がバランスよく入っている。ひとつの野菜を使って、いろいろな調理法で料理をするのが、この教室の特徴だ。
実は筍ご飯にしようか先生は迷われたのだが、ルーロー飯のレシピの方が知られていないし、いろんな味のバリエーションを作りたい、という事でこのメニューになった。ほぼ中華味でまとめられていて、若竹煮だけ和食。「筍のうまみをいちばん活かしているから、これは欠かせない」という先生のこだわりで、若竹煮もメニューに加えることになった。
「じゃあ、そろそろ料理を始めましょうか」
そう言いかけた時にドアが開いて、女性が入って来た。走って来たのか、息を切らせている。
「遅くなって、すみません!」
先ほど電話で遅くなると連絡を受けた小瀧さんだ。小柄だが、白髪交じりのショートカットで、赤い縁の眼鏡が似合っている。
「よかった、ちょうどきりのいい所でした。いま茹で方の説明をして、これから料理を始めるところです」
小瀧さんは都庁勤めのキャリアウーマンだったが、半年前に定年退職して時間ができたので、この教室に通い始めた。独り暮らしで、料理はほとんどやってこなかったという。近所に住んでおり、現役時代は土曜日のランチタイムの常連だった。
「手を洗って支度したら、そちらの窓際の班に参加してください」
先生がにこやかに言う。私は小瀧さんの傍に行き、今日のレシピと注意事項を書いた紙を渡す。
「茹で方については、こちらの方にも書いてあります。あとで口頭でも説明しますが、こちらを参考にしてくださいね」
「ありがとうございます」
小瀧さんは隅の洗面所で石鹸を使って勢いよく手を洗い、エプロンと三角巾を着けた。窓際の班のところに行き「すみません」と言いながら、空いている席に座った。
「じゃあ、全員揃いましたから、茹で上がった筍を使って実際に調理をしましょう。まずは各班で役割を分担してください」
そうして、班ごとに話し合いが始まった。
調理が終わると、おまちかねの試食タイムだ。我々スタッフも、先生が説明しながら作った料理を一緒に試食する。私と先生は見本で作った料理の入ったお盆を持ち、それぞれ生徒さんたちの席に座った。私は遅れてきた小瀧さんがいる班に参加する。
「あの、今日は遅刻してすみませんでした」
すぐ横に座った小瀧さんが、私に謝った。
「いいですよ。調理には間に合ったんだし」
「ほんと申し訳ないです。滅多に遅刻はしないのですが。……今日は出掛ける前に犬を連れて朝の散歩をしたんですけど、途中でなぜか動かなくなったんです。一生懸命引っ張ったんですが、うちの仔は柴犬だけど体重が一五キロあるし、私も腰を悪くしているので抱っこもできず、動かせなかったんです。餌で釣っても無反応だし、三〇分くらい押したり引いたりしたら、ようやく動き出したんです」
「それは大変でしたね。柴犬はマイペースで飼いにくい仔もいるそうですね」
お向かいに座った村田さんが質問する。
「いえ、普段は手の掛からないいい子なんですよ。うちに来てまだ二ヶ月ですが、おとなしいし、室内でもいたずらしないし。今日に限って急に動かなくなって、ウーって唸っていました」
「うちに来て二ヶ月って?」
「実は貰い犬なんです。引退したら運動不足になるし、犬を飼って散歩したらいいかもと思って、保護犬ボランティアの相模さんに相談したんです。そうしたら、ちょうど柴犬が相模さんの手元にいたので、その仔を勧められました」
相模さんは食堂の近くに住んでいる。自宅で保護犬を預かって、新たな貰い手がみつかるまで面倒をみる、というボランティアをしている。
「捨てられたり、酷い扱いを受けてきた保護犬は傷ついていて扱いにくいこともあるけど、この仔はちゃんと可愛がられた犬だから、初めて飼う人でも大丈夫だって。それに、仔犬は活発なので、おとなの犬の方がいいそうですから」
「犬の年齢は?」
「六歳です。なので、若い犬みたいにはしゃいだりすることはないし、頭のいい仔だから、私の言うこともよく聞いてくれるんですけど、今日はどうしたものか」
小瀧さんはほおっと溜め息を吐いた。
「こんな事があると、飼い主として自信を失います」
「何か理由があったのかもしれませんよ。話の続きはまたあとで。冷める前に試食にしましょう」
私はそう促した。小瀧さんの話ばかりしているのでは、ほかの生徒さんたちはつまらないかな、と思ったのだ。小瀧さんもそれに気づいたらしい。
「すみません、私ばかり話をして」
と、謝った。それから、班のみんなと両手を合わせて「いただきます」と言って試食を始めた。食事は美味しく、ボリュームもあった。
「ほんとに、売ってる筍とは全然風味が違いますね。えぐみもないし、柔らかいし」
「筍が食べられるって最初に発見した人は誰なんでしょうね。固い皮を剥いて、長い時間煮れば美味しくなるなんて、すごい発明ですよね」
「ルーロー飯美味しい! 今日の夕食は市販の筍を買って来て、これにしよう」
「牛肉と炒めるのは簡単だし、これなら子どもも喜びそう」
和気あいあいとそんな話をする。そうして、食事が終わり、最後のお茶の時間になって、私はまた犬の話を聞いてみた。なんとなく気になったのだ。
「さっきの話ですけど、小瀧さんの犬が立ち止まったのは、どこなんですか?」
「この先のキウイ畑の裏手、坂のふもとのあたりに古いアパートがあるのをご存じですか? そこなんです」
「ああ、知ってます。竹藪の隣にあるアパートですよね。小学生がお化け屋敷って言っている」
お化け屋敷という呼び名は、うちに出入りする山内奏太くんが教えてくれたものだ。アパートのすぐ傍まで竹藪が迫っていて日当たりが悪く、建物も築五十年は経っているだろう。壁にはヒビが入っているし、蔦が絡まっていて、いっそうひなびた状況を演出している。いつ壊されてもおかしくない古さだ。人の気配もない。
小学生たちはそこを「お化け屋敷」と呼び、夏休みに肝試しをしたそうだ。夜九時にアパートの前にクラスメイト五人で集まり、中を探検しようとした。しかし、みんながアパートの建物に足を踏み入れた途端、微かな鈴の音がした。それから真っ暗な中、どこからともなくコツ、コツ、という音がしたと言う。それでひとりが「わあっ」と叫んで敷地の外に向かって走り出した。その声を聞いてみんな怖くなり、口々に叫びながら最初のひとりの後を追った。それで、肝試しは中止。親に報告すると、
「怖がっていたから何かの音を聞き間違えたんでしょう」
と、笑って取り合ってくれない。肝試しから半年以上経っても、まだ奏太くんはその事を気にしているらしい。
「でも、あれ、絶対鈴の音だよ。コツコツという音も聞こえたもん。本当に不気味だったんだよ」
奏太くんはそう言って口を尖らせた。その真剣な表情が可愛くて、つい笑ってしまったのだ。奏太くんには「真面目に聞いてよ」と、怒られたが。
「お化け屋敷って、四丁目と三丁目の境にある、蔦が絡まった古いアパートのこと?」
村田さんが小瀧さんに聞いたので、私は我に返った。
「ええ、そうです。あそこ、もう誰も住んでいないんですよね」
「そうね。五,六年前までは住んでいる人がいたけど、もう誰もいないと思うよ。うちの近所だからよく通り掛かるけど、ここ数年は電気が点いたのを見たことないしね」
村田さんはこの地に住んでもう三十年以上。その村田さんが言うのだから、間違いないだろう。
「駅の近くにアパートも増えてきたから、ああいう古いアパートは住みたがる人がいないのかもしれないですね」
「人口は減っているから、アパートに限らず空き家も増えるよね。空き家は治安が悪くなるし、そこにゴミを捨てる人もいるから、困るんだけどね」
「ほんと、そうですよ。うちの仔が立ち止まったアパートの前にも、よくゴミが散乱してました」
「ゴミ?」
「私、犬の散歩のついでにゴミを拾っているんです。トングとゴミ袋を持って。あの家の前でもよくチラシやマスクが散らばっていました」
小瀧さんは少し照れたように言う。
「ゴミ拾いって、いつからやってるんですか?」
「つい最近ですよ。犬を飼い始めてからですから」
「わあ、えらいですね」
「そんなことないです。独身だから仕事ばかりで、社会のためになることは何もやってこなかったし」
「そんなことないですよ。公務員をされていたんでしょ? 社会のための仕事をされてきたんじゃないですか」
「お給料をもらってるから、それは当たり前。保護司とか子育て家庭の訪問とかをボランティアでやってる人もいる。普通の主婦だって、PTAや町内会の役員を無償でやるでしょ? そういう人の方が私はえらいと思う」
「そうでしょうか?」
「そうですよ。年老いた親の面倒をみるというのも、たいていは主婦が担っている。夫の両親と自分の両親と両方看取る人もいるでしょ? お金を貰うわけでもなく、献身的に家族に尽くすじゃないですか。そちらの方が人間としては私より上だと思う」
「そんなふうに思ってくれるのは嬉しい。みんながそう考えてくれる社会だといいのに」
村田さんの目が少し潤んだ。村田さんも家族の介護をずっと続けている人なのだ。
「幸い私の両親は弟夫婦が看取ってくれたし、自分も健康で生活費にも困らないから、ゴミ拾いくらいは、と思ったの」
「小瀧さんの考え方、素敵だと思います」
私は素直な気持ちで言った。そういう心掛けの人に自分もなりたい。
「偉そうに言いましたが、ゴミ袋を忘れた時はゴミ拾いもしないし、雨や風が強い日は散歩もさぼるし、そんなに毎日やってる訳じゃない。気まぐれなんですよ」
小瀧さんは照れくさそうに笑う。
「それでも偉いと思います」
「そんなに褒めないで。大したことやっていないのに」
小瀧さんが謙遜するので、話題を変えた。
「それで、そのアパートの前にはよくゴミが落ちているんですね」
「そうなんです。ゴミ拾いを始めてから気づいたんですが、人はきれいな場所にはゴミはあまり捨てないけど、元からゴミのある所には平気で捨てるんですね。ゴミがゴミを呼ぶというか。近くの野川公園にはゴミ箱がないから、そこに捨ててるのかもしれません」
「犬が動かなかったのは、何か変なものが捨てられていたのかもしれませんね」
私が思いついたことを言ってみる。
「ああ、そうですね。昨日までの小太郎はアパートの前でよく立ち止まってはいましたが、促すとすぐに通り過ぎていました。今日になって小太郎が動くのを嫌がったのは、新しいゴミに反応したのかもしれません」
「小太郎?」
「うちの犬です。私が名付けた訳じゃなく、もとの飼い主が付けた名前です。保護犬ボランティアの方は、好きな名前に変えていいって言ってくれたんですけど、飼い主が変わるだけでも犬にとっては大変なことなのに、名前まで変わったら可哀そうだと思って。それでそのまま小太郎って呼んでいるんです」
「古風な名前ですね」
「前の飼い主がお年寄りだったので、そういう名前がよかったんでしょうね。飼い主さんは散歩中に足を骨折して、それで入院してその後、すぐに施設に入られたそうなんです」
「ああ、そうなんですね」
「でも、ご主人が骨折した時、大声で吠えて助けを呼んだのは小太郎だったそうですよ」
「ほんとですか? それは賢い仔ですね」
きっと前の飼い主とはとてもよい関係だったのだろう。犬と人間はしばしば深い信頼関係で結ばれることがある。
「ええ。前の飼い主さんもすごく可愛がっていて、お別れが寂しくて泣かれたそうですよ。新しい飼い主にくれぐれもよろしくと伝えてくれ、とおっしゃったんですって」
「じゃあ、小太郎を小瀧さんは託されたんですね」
「ええ。そう思って、かわいがることにしたんです」
「だけど、前の飼い主さんといい関係だったのなら、なかなか新しい飼い主には慣れないんじゃないですか?」
村田さんが尋ねる。
「ええ、まあ。最初うちに来た時にはすごく緊張していたみたいで、トイレもまともにできないくらいでした。便秘になるんじゃないか、と心配したくらい。すぐに普通になりましたけど、まだちょっとよそよそしいというか、完全に私に慣れた感じではないです。でも、これも時間の問題だと思いますので、小太郎が打ち解けてくれるのを気長に待とうと思います」
「小瀧さんは優しい方ですね」
「そんなことないですよ。仕事辞めるとやることもないし、ついだらだらしてしまいそうになるんですが、小太郎のおかげで毎日散歩に出るから生活にメリハリができました。犬友だちもできたし、小太郎のおかげで助けられているんです。だから、小太郎も私との生活を楽しんでくれるといいな、と思ってるんです」
小瀧さんは優しい目でそう語る。
小太郎という犬は幸せだ。優しい飼い主に二度も恵まれたのだから。だけど、犬にとってはなぜ前の飼い主と離されたのか、理解できないのだろう。だから、どこかで元の家に戻ることを期待しているのかもしれない。
「今朝の事は初めての反抗なんです。どうしてなのか理解しないと、いい飼い主になれない気がして」
「じゃあ、靖子先生に相談してみたら、どうでしょう?」
「靖子先生に?」
「先生はそういうちょっとした謎とか不思議なことの原因を突き止めるのが得意なんです。いままでも、何度も生徒さんの悩みを解決したんですよ」
「そうなんですか。でも、犬のこともわかるかしら」
小瀧さんは半信半疑だ。
「ダメ元で聞いてみたら? 自分では気づかない事を指摘してもらえるかもしれませんよ」
「そうですね。じゃあ、お教室が終わったら、相談してみます」
私が強く勧めたので、小瀧さんはその気になったようだ。そうして食後の後片付けが終わって解散した後、靖子先生の所に近づいて行った。
「あの、先生」
「なんでしょう?」
靖子先生はいつものおっとりした口調で尋ねるが、小瀧さんは何から切り出そうというように、話しあぐねている。それで私が代わりに語った。
「小瀧さん、ちょっと悩んでいることがあるそうなので、私の方から、先生に相談することをお勧めしたんです」
「あの、そんなたいそうなことじゃないんです。飼い犬のことなので。お忙しければ今じゃなくても」
小瀧さんは遠慮したように言う。すると先生は言う。
「犬のことでも、そこから何かの問題に繋がることもありますよ。まだお時間があるなら、ここでお話し聞かせてください」
それで、私たち三人はテーブルを囲んだ。小瀧さんはかいつまんで状況を説明した。説明することに慣れているのか、よどみなく話をする。
黙って聞いているうちに、先生の顔がだんだん険しくなっていった。
「あの、小瀧さんのお宅はここから近かったですよね?」
「え、はい、五分くらいです」
「よければ犬をここに連れて来てくれませんか? いえ、私たちが行った方が早いですね。これから犬に会いに行きましょう。すぐに支度をしますので、ちょっと待っててください」
「先生、でも、片付けがまだ済んでいませんが」
食器などは各テーブルの生徒さんたちが洗っているが、最終的に鍋や食器の数や状態を確認し、しまう場所が正しいかチェックする。そして部屋全体の掃除までしないと私たちの仕事は終わらない。
「それはあとでもいいわ。この問題を先に片付けましょう」
そう言って靖子先生は立ち上がり、すぐにエプロンを取った。
「じゃあ、私がここを片付けておきましょうか?」
キッチンの奥にいた、もうひとりの助手の和泉香奈さんが言う。
「じゃあ、お願いします。優希さんも一緒に行くなら支度をしてください」
いつになく焦っている靖子先生の様子にあっけにとられながら、私は支度を始めた。
小瀧さんの家の門の前で、先生と私が待っていると、すぐに小太郎を連れた小瀧さんが出て来た。
「こんにちは」
私たちは小太郎に挨拶した。がっちりした体格の柴犬だ。寝ぼけまなこのような二重の愛嬌のある目をしている。私は小太郎を撫でようとしたが、伸ばした手から逃れるようにスッと後ずさりした。
「ごめんなさい。この仔、知らない人に触られるのが好きじゃないんです。最初は私が触るのも嫌がっていたくらいで」
「いえいえ、大丈夫です。柴犬にはそういう仔もいますよね」
「じゃあ、出発しましょうか」
先生はそわそわした様子で出発を促す。小太郎は門から一歩外に踏み出すと、ものすごい勢いで前に進み始めた。
「小太郎、ダメ、もっとゆっくり」
そう言って小瀧さんがリードを引っ張るが、おかまいなしにずんずん突き進む。その勢いに押されて、小瀧さんも速足になる。私たちも、その後ろからついて行く。
小太郎は迷いなく突き進み、たどり着いたのは古いアパートの前だった。壁には名前が書かれたプレートがあるが、風雨にさらされて文字がかすれ、ほとんど読めない。
「ここが今朝、小太郎が動かなかった場所?」
先生が小瀧さんに聞く。
「そうです」
そこはお化け屋敷という名前がぴったりくる、古めかしいアパートだ。周囲に住宅はなく、畑と保全緑地の竹林に囲まれてぽつんと建っている。竹林が傍まで迫っているので昼でも薄暗く、じめじめと湿気も多そうだ。先生はアパートの郵便受けを調べた。チラシやいろんなものが郵便受けにぎっしり詰め込まれているが、その一つは扉が開き、中身が地面になだれ落ちている。
「ああ、これが外の方まで飛ばされて、表通りまで散らかったのかもしれませんね」
先生はそう言いながら、下に落ちたチラシや郵便物を拾って壁際にまとめた。郵便物は主にダイレクトメールのようだ。
「こんな場所でもチラシが配られるんですね。読む人がいなければ意味ないのに」
アパートはよくある外階段の軽量鉄骨の二階建てだ。通路があり、部屋が四軒並んでいる。
「これじゃ、とても人は住めませんね。昼でも電気を点けないと、暗くて部屋に居られないでしょうから」
私は誰に話し掛けるともなく、感想を呟いた。
「ほんとにそうですね。どうしてここを取り壊さないのでしょう。お化け屋敷なんて評判が立つと、面白がって訪ねてくる人もいるでしょうし。そういう人たちがここで騒ぎを起こさないとも限らないし、物騒ですね」
小瀧さんが私の言葉に反応してくれる。呆然と建物をみつめる我々にはおかまいなく、小太郎はアパートの建物の中に足を踏み入れようとする。
「ダメよ。ここは私有地だから、勝手に入れないのよ」
小瀧さんがリードを両手で持ち、小太郎が進めないように止めている。すると小太郎は「ワン!」と大きな声で吠えた。
「小太郎が吠えるのは初めて聞いた」
小瀧さんはびっくりしている。小太郎はそれにはおかまいなく「ワン、ワン、ワン!」と、大声で吠え続ける。
「小瀧さん、小太郎の行きたがるところに行かせてあげて」
先生が言う。
「でも……」
小瀧さんは躊躇している。
「早く。一刻を争う状況かもしれない」
※後編に続く
愛知県生まれ。東京学芸大学教育学部卒業。フリーライター、出版社勤務を経て、2006年『辞めない理由』で作家としてデビュー。
『菜の花食堂のささやかな事件簿』シリーズのほか、ベストセラーとなりドラマ化された『書店ガール』シリーズ、『銀盤のトレース』シリーズ、『凛として弓を引く』シリーズ、『スケートボーイズ』『駒子さんは出世なんてしたくなかった』『1939年のアロハシャツ』『書店員と二つの罪』『レイアウトは期日までに』等、多数の著書がある。
地域の食文化への興味から、江戸東京野菜コンシェルジュの資格を取得。