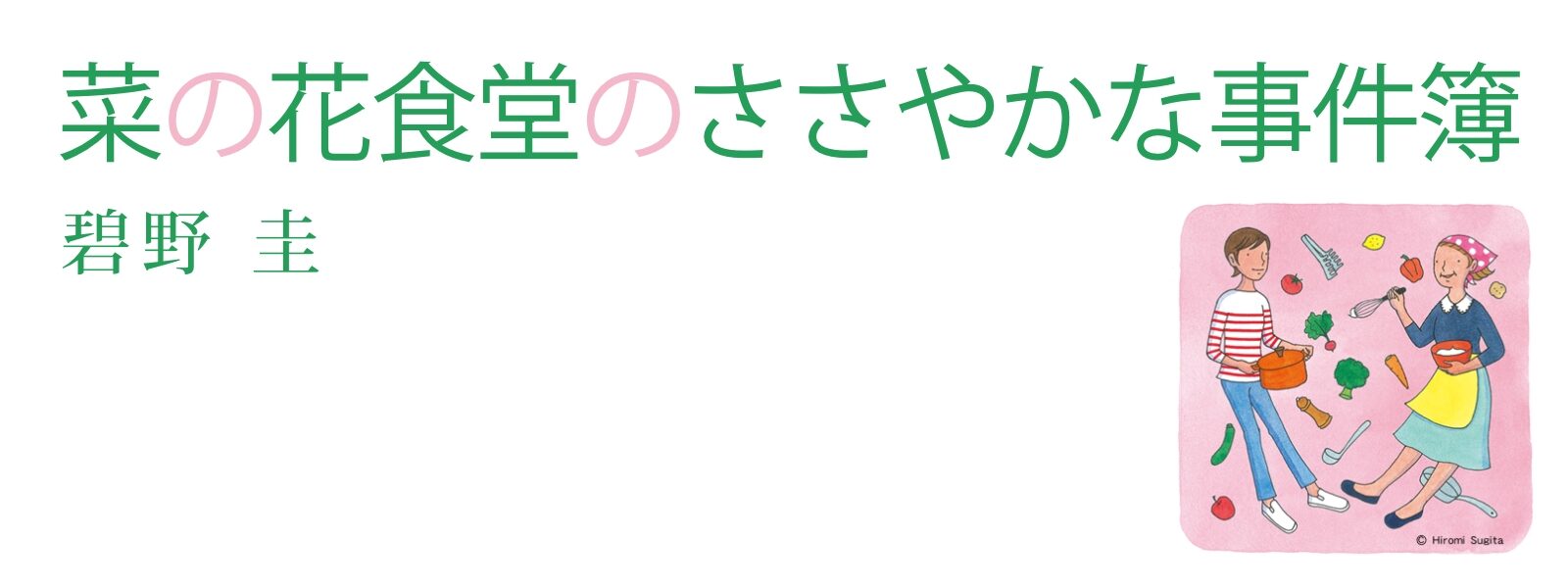疑惑のカレーライス 後編
「三人って、偶然にしては多いよね」
「うん、人命に関わるような重い症状ではなさそうだけど、ちょっと嫌な感じだね」
「どうする? もう帰る?」
川島さんに聞かれたが、私は首を横に振った。
「ううん。奏太くんのお店のカレーだけは食べて行かなきゃ。奏太くんたちの夏のキャンプの資金になるそうだし。それに、あの店でおかしなことはないと思う」
「そうだね。それだけは食べないとね」
私と川島さんは黒い幟のカレーの店に戻って行った。お昼のピークは過ぎているので、待っているのはふたりだった。
「あれ、先生?」
列の後ろにいたのは靖子先生だった。
「まあ、あなた方もカレーまだだったの?」
「はい、さっきまでここはすごい行列だったので、奥の方でビールや珈琲を飲んでました。ようやく人も少なくなりましたね」
「そう。じゃあ、私はちょうどいい時に来たのね」
前の人が終わって、先生の番になった。
「カレーをひとつ。普通盛りで」
「はい、カレー一丁」
中年の女性が注文を受け付け、奥の方に伝える。奥では四、五人が忙しそうに働いている。野菜を洗う者、切る者、カレーを煮込む者、ご飯をよそう者、そのご飯にカレーを掛ける者、と担当を分担している。奏太くんは午前中に来た時はご飯をよそっていたが、いまは野菜を洗う係に代わっていた。
「奏太くん」
先生が声を掛けると、奥にいた奏太くんは顔を上げた。
「靖子先生。それに優希さんに川島さんも」
その顔を見て驚いた。土気色をしている。
「大丈夫、顔色悪いよ」
「先生、僕……」
そう言ってこちらを見た奏太くんは、めまいを起こしたのか、そのままふらりと倒れそうになる。隣にいた男性が慌ててそれを受け止める。
「大丈夫?」
「奏太!」
「奏太くん!」
周りにいた子どもたちも、驚いて傍に駆け寄る。それを見ていた先生も、テントの奥へと入って行こうとする。オーダーを取っていた女性が注意する。
「あの、お客さま、大丈夫です。この子はこちらで面倒をみますから」
「私、この子の友人です。おかあさまが傍にいないのであれば、私の方で面倒をみますので」
「そうですか」
女性はほっとした顔になった。奏太くんのお母さんは看護師として働いているので、今日も会場にはいなかった。
先生が奏太くんに『大丈夫?』と、声を掛けた。私と川島さんも、先生と奏太くんの傍に行った。男の子がしゃがみこんで奏太くんの様子をうかがっている。その後ろから先生が尋ねる。
「具合はどう?」
「気持ち悪い……」
奏太くんは言う。
「本部の方に救護スペースがあります。そちらに僕が連れて行きますよ」
カレーを煮込んでいた男性が、手を止めずに言う。
「あ、でもみなさんお忙しそうですから、私たちで連れて行きます」
「僕はこのブースの責任者で内藤と言います。三年の清水達也の父です。そちらは?」
男性は少し警戒した顔をしている。責任者となれば、いろいろ気を遣うのだろう。
「中町で菜の花食堂という店をやっています下河辺と申します。奏太くんはうちに来て、手伝いをしてくれています」
「奏太が毎日通ってる店だ」
子どものひとりが言う。
「ああ、菜の花食堂の方でしたか。そういえば奏太から聞いたことがあります」
男性は表情を緩めた。
「では、奏太のこと、お願いしてもいいですか」
「もちろん。あとで様子をお伝えします」
「ダメだよ。……もう大丈夫。みんな忙しいから、僕も手伝わなきゃ」
奏太くんはそう言うが、顔色は悪い。身体を起こしかけて、すぐに頭を押さえてまたうずくまる。
「奏太、そんなふらふらしているのに、何を言ってるんだ」
「大丈夫、お昼食べてないから、空腹でちょっとふらついただけ」
「だったら、ちゃんと何か食べて休んでおいで。ここで奏太が倒れたら、戦力ダウンだからな」
清水さんに言われて、奏太くんは仕方なくうなずいた。
「じゃあ、奏太をお願いします」
「お願いします」
内藤さんに続いて、傍にいた子どもも頭を下げた。
「奏太くん歩ける? おぶった方がいいかな?」
川島さんが聞くと、奏太くんは頭を振った。
「大丈夫、歩ける」
と、言ったものの、足取りはふらふらしておぼつかない。川島さんは自分の腰に奏太くんの腕を巻き付け、肩を抱くようにして歩き出した。
本部のテントに着くと、川崎さんがいちはやく見つけてくれて、駆け寄って来た。
「どうされました?」
「この子の体調悪くて」
靖子先生が川崎さんに返事していると、ほかの本部の人も近寄ってくる。
「……気持ち悪い」
奏太くんはそう言って、「うっ」とえずく。とっさに川崎さんが近くにあったバケツを奏太くんに差し出す。
何度かえずいた後、奏太くんはそこに嘔吐した。
「全部吐き出しちゃいなさい」
靖子先生がそう言って、奏太くんの背中を強くさする。奏太くんはさらにえずくが、さほど吐き出すものはない。小麦色のものが少量吐き出されただけだ。
えずくのが止まると、川崎さんが水の入ったコップを差し出す。
「これでうがいをして」
言われた通りにうがいして、中身をバケツの中に吐き出すと、奏太くんは少し落ち着いたようだ。
「すごいめまいがして、気持ち悪くなっちゃった」
「この子は?」
本部役員の男性が聞く。大柄で髭を生やしている。サラリーマンというより肉体労働をしているような感じだ。しかし、どこかで見たような気がする。
「山内奏太くん。今日は西小の学童を見守る会のお店を手伝っていたんです」
「西小ってカレーの?」
「はい」
やっぱり、と言うように、役員の男性は川崎さんと目を合わせてうなずいた。
「カレーが何かまずいんですか?」
靖子先生が尋ねると、役員は「ええっと、それは」と言葉を濁す。
「あの、先ほど救急車で運ばれた方がいましたけど、それと何か関係があるんですか?」
私も聞いてみた。川崎さんから三人倒れたことを聞いているが、内緒という事だったので、それには触れない。それを聞いて、役員は困ったような顔をした。
「この方たちは信用できますよ。中町の菜の花食堂の人たち。ご存じないですか?」
「あ、ああ、そう言えば。何度か行ったことありますよ」
それを聞いてわかった。この人はうちの店にたまに来る人だ。いつもは小さい子どもふたりと奥さんを連れている。
「ありがとうございます」
先生は軽く頭を下げる。
「それに、靖子先生の評判をご存じないですか? 日本のミス・マープルって言われているんですよ」
「ミス・マープルって、アガサ・クリスティのあの?」
役員はミス・マープルを知っているらしい。読書家でなければ知っている人は少ないので、珍しい。
「そうなんです。靖子先生は身近な謎を解くのが得意なんです。いままでも何度か困った事態を解決しているんですよ」
川崎さんもうちの店に出入りしているので、その評判は知っている。
「謎解きですか。確かに、誰か探偵にでもこの謎を解いてほしい気持ちです」
役員は困り果てたような顔をしている。
「というと?」
先生が尋ねる。
「それはその……」
「私も奏太くんがこういう状態でなければ、無理に聞こうとは思いません。でも、奏太くんはうちに出入りしているお子さんです。おかあさんがいらっしゃらない時には、私が親代わり、と思って接してきました。なので、こうなった原因は私も知りたいのです」
いつもは冷静な先生が、珍しく感情的になっている。それほど奏太くんを大事に思っているのだ。
「そうでしたか……」
まだ躊躇している役員に、川崎さんが「大丈夫ですよ」と言うようにうなずいてみせた。
「いえ、あの、実は今日三人体調を崩して救急車で運ばれたんですが、その人たちの共通点は西小学童を見守る会のカレーを食べた、ということなんですよ」
「カレーですか?」
「なので、もしかしたらカレーに何か混入していたのではないか、という疑いがもたれているんです。三人ならまだ偶然かもと思いますが、四人目となると、やはりそうなのかと思わざるをえない」
なるほど、そういう事だったのか、と私は納得した。本部としたら円滑な運営をしたい。だが、疑いの段階で動くことはできない。間違いだったら、西小の関係者に汚名を着せることになるし、お祭り自体の楽しい雰囲気もぶち壊しになるだろう。
「ですが、それが本当なら、被害者はもっと増えますよね。朝から何十杯も売ってると思いますから」
先生は冷静に分析する。確かにその通りだ。夏祭りのカレーに毒物が混入していて死者が出た、という事件はかつてあった。だが、その時の被害者はもっと多かったはずだ。カレーは液体だけに、そこに異物が混入されていたら影響は四杯程度ではすまないだろう。
「だけど、ごく微量で、体質的に過敏な人だけが反応したとも考えられます」
「なるほど」
「西小の店の関係者が故意に入れたとは思いたくありません。何かの事故で偶然何かが入り込んだんじゃないかと思っています。とにかく、そういう疑いがある以上、西小のカレーの販売を中止すべきだと我々は思っています。保健所に持ち込んで、分析をしてもらわないと」
「確かにそうですね。安全性が確認できないものを売るのは、本部としたら許可できないでしょうね」
私がそう言った時、「ダメだ」と声がした。横になっていた奏太くんが、上体を起こしている。奏太くんは苦しそうに顔をゆがめたままだ。
「大丈夫? 無理に起きようとしないで」
私が屈んでもう一度寝かせようとしたが、奏太くんはその手を振り払った。
「カレーの販売を止めないで。カレーを売って、……みんなで奥多摩にキャンプに行くんだ」
その資金稼ぎのために毎年西小学童の父母が店をやっている。それは周知のことだ。
「みんな、楽しみにしているんだ。それで、協力して……野菜だって近所の農家を手分けして回って、安く売ってもらった。昨日から野菜を切ったり、みんなで仕込みをしたんだ。だから」
そこまで言うと、奏太くんは咳き込んだ。また苦しくなったらしい。
先生は優しく背中をさすった。まるで本当のお孫さんにするように。
「無理にしゃべろうとしないで」
「ほんと、衛生にも気を付けてきたんだ。マスクして、手をしっかり消毒して。だから……」
奏太くんは再び咳き込んだ。先生はゆっくりゆっくり背中をさすっている。
「言いたいことはわかる。だけど、事故はどんな時だって起こるのよ。もし、ほんとうにカレーに問題があるなら、販売を中止するというのは正しい判断だと思う」
役員の人が奏太くんに言う。
「だけど、カレーが悪いんじゃない。それに僕、今日はカレーを食べてないし」
「食べてない? ほんとうに?」
役員が驚いて聞き返す。
「忙しくて、食べる暇はなかったんだ」
「ほんとうなのか? みんなをかばおうとして、嘘を言ったらいけないよ」
役員は奏太くんの言い分を信じてないようだが、靖子先生はきっぱり言う。
「この子の言うことは本当です。嘘を吐くような子ではない」
「しかし……」
「それに、先ほどこの子が吐いた時、カレーらしきものは見当たりませんでした。お店が始まったここ数時間以内に食べたのであれば、吐瀉物の中にカレーが出てくるはず。だけど、カレーどころか米粒ひとつなかった」
みんな黙ってしまった。先生の言う通りだ。そう言えばお店でも、奏太くんは空腹で具合が悪くなったのでは、と言われていた。
「そうなると……原因探しは振り出しに戻る」
「困りましたね」
役員と川崎さんは困惑顔だ。
「いえ、そんなことはない。逆に原因がわかるかもしれない」
「どういうことですか?」
川崎さんの問いに答えずに、先生は奏太くんに聞く。
「奏太くん、じゃあ、今日食べたものを教えてくれる?」
「えっと……今日は遅刻しそうになったんで、朝ごはん食べずにうちを出た。たまにやるから平気だと思って。ここについたら忙しくて、お腹が減ったのも忘れていたし、食べる暇もなかった。……だけど、さっきちょっと手の空いた時に、おまけのクッキーをもらって食べた」
「おまけのクッキーって?」
「食器を持って来たお客さんにあげるやつ」
ゴミ削減をうたうこのイベントでは、食器を持参した人にそれぞれの店が何かサービスをすることになっている。盛りを多くしたり、おまけをつけたり。カレーの店では、お菓子をプレゼントしていたはずだ。
「お店では、みんなにクッキーを配っていたの?」
「うん。ほかにもチョコレートとか飴とか入っていて、お客さまに選んでもらうんだ」
「クッキーはむきだしだったの?」
「違うよ、ちゃんとビニールに包まれていた。むきだしは汚いし、一個一個取りやすいように包装したものしか配らないよ」
「わかった、そのクッキーに問題がありそうね」
「ほんとうに?」
靖子先生の指摘に、川崎さんは目を丸くする。
「急いでお店に行って、おまけの品を回収してきてください。たぶん大麻クッキーが混じっている」
「大麻クッキー?」
「急いで」
先生に言われて、役員と川崎さんは慌てて駆け出した。
先生の推理はあたっていた。回収されたお菓子ボックスの中にあったひとつに、大麻クッキーらしきものが混じっていたのだ。クッキーをラップした小袋に「HHCH Cokey」という表示がついている。HHCHというのは大麻に似た合成化合物で、それを摂取すると身体に悪影響を与えるという事で、法的にも販売が禁止された。禁止される前には一部の店で出回っていたが、これはそれと同じ商品らしい。見掛けはふつうのクッキーで、おかしなものには見えない。だが、西小の関係者は「これはうちが用意したものではない」と断言した。
「おまけのお菓子として用意したのは、市販されている有名メーカーのお菓子だけ。子どもたちがコスパを考え、自分たちで選んで購入しています。こんなふうに高級そうなお菓子は入ってなかった」
さらに、体調を壊した人たちが全員クッキーも食べていたことが本部の人たちの調べでわかった。警察に通報し、お菓子ボックスに残っていたクッキーは保健所の方に送られ、成分分析してもらうことになった。
「じゃあ、カレーは販売続けられるんだね。キャンプの資金集めはできるんだね」
奏太くんは真っ青な顔をしながら、本部役員に聞く。
「もちろんだよ。なぜ大麻クッキーが混入されたかは調査されるけど、おそらく西小の関係者じゃないと思う。わざわざ自分たちの店の評判を下げることをするとは思えないしね。それに、カレーを楽しみにしている人も大勢いるから、ここで中止にしたらみんなががっかりしちゃうよ」
「よかったー」
そう言うと、奏太くんは力尽きたように気を失った。
そこに救急隊員が担架を持ってやって来た。奏太くんは担架に乗せられる。
「病人がお子さんですと、できれば付き添いがあるとよいのですが。どなたか付き添いいただけますか?」
「では、私が」
先生がすぐに名乗りを上げた。
「私はこの子の保護者代わりですから」
「わかりました。じゃあ、救急車の方にご案内します」
そうして、先生と、担架に乗せられた奏太くんは、人混みの中を縫うようにして去って行った。
「とりあえずお客さまに説明と注意喚起のアナウンスをした方がいいでしょうね」
川崎さんは言う。
「ことを大事にして、お祭りを楽しんでいる人たちの興を殺ぎたくないけど、まだ犯人が捕まっていないですしね。それに、何度も担架が行き来しているのを見て、おかしいと思っている人もいるでしょうから」
「そうだね。ほかに、特典でお菓子を配っているお店はなかったっけ?」
「ないはずです。焼き菓子を扱っている店は多いですが、自分たちの商品以外は売るはずはないですし。一応すべての店舗に役員で手分けして今回の件を伝え、注意を呼びかけましょう」
そうして、川崎さんはアナウンスをした。
『お祭り真っただ中ですが、今日憂慮すべき事態が発生しました。何者かが配ったお菓子で体調を悪くされた方がいます。現在その原因の究明、犯人捜しをしているところです。みなさまもどうかお気をつけて、知らない人からお菓子をもらったり、出どころ不明のお菓子には手をつけたりしないようにお願いします。みんなが楽しむためのお祭りですので、安全には十分配慮していますが、みなさまもどうかお気をつけください。また、怪しい人物を見掛けたら、本部の方にお知らせください。繰り返します……』
アナウンスはされたものの、どのくらいのお客の耳に入ったのかはわからない。それぞれ自分の楽しみに夢中になっているようだ。
だが、アナウンスがあって間もなく、カップルが本部にやって来た。
「あちらに変な人がいるんです。もしかしたら、体調悪いのかもしれないですけど。なので、ちょっと注意してもらえませんか?」
「あちらって、どの辺りでしょうか?」
川崎さんが尋ねる。
「この道の先の、第二駐車場の手前にある林の中です」
カップルが示した場所は、お祭りの喧噪からは少し外れて、人があまり行かない辺りだ。
「じゃあ、行ってみます」
川崎さんはビール売り場に「準備中」の札を立てて、テントから出る。
「ひとりで大丈夫ですか?」
「ほんとは誰かと連れ立って行くといいんですが、本部役員はいま、売り場担当者以外は出払っています。それぞれのお店に注意喚起に回っているので」
「じゃあ、私たちも一緒に行きましょうか?」
私がそう言うと、川崎さんの顔がぱっと明るくなった。
「いいんですか?」
「はい。もし不審者だったら、暴れ出すかもしれませんし。私たち、時間がありますから。ねえ?」
私が川島さんに聞くと、川島さんも大きくうなずいた。
「女性一人では危険です。僕もご一緒します」
「ありがとうございます。お二人が来てくれると、心強いです」
そうして私たちは林の方に行った。言われた場所には、痩せた男がうつ伏せになっていた。黒っぽいリネンの上着に、汚れたジーンズを履いている。長い髪をうなじのところで結んでいた。
「あの、どうかなされましたか?」
川崎さんは男の傍に近づき、声を掛けた。男は動かない。
「もしもし」
川島さんが男の肩を揺さぶる。すると「うーん」と声を上げて、男はあおむけに転がった。私は内心ほっとした。もしかして、死んでいたらどうしよう、と思ったのだ。
「どうされましたか?」
男は目を半分開いたが、身体に力が入らないのか、ぐでっと倒れたままだ。
「大丈夫ですか?」
川島さんが声を掛けると、ケケケと甲高い声で笑った。その態度に、私たちは困惑する。
「もしかしたら、この人も大麻クッキーの犠牲者でしょうか?」
「わからないけど、このままにはしておけませんね。本部の方に連れて行きましょう」
男の腕を抱えて起こそうとすると、男の手から何かがこぼれた。それは、大麻クッキーの入った袋だった。
「結局、その男が大麻クッキーをカレーのおまけのおやつ箱に投げ入れた犯人だったのね」
翌日、私は食堂でランチの準備をしながら、その後の経緯を話していた。先生は病院で奏太君が回復するまで付き添って、家まで送り届けていた。なので、その後の騒動は知らないのだ。幸い奏太くんの症状は軽く、一時間もしないで元気になったらしい。
「ほんと、すぐに犯人がみつかってよかったわ。被害も広がらなかったし」
「先生がカレーではない、とすぐに見抜いてくださったから、お祭りにも影響が少なくてすみました。お礼を伝えておいてください、と川崎さんに言われました」
「いえいえ、私は何もしてないわ。カレーじゃない、と奏太くんが証言したから、いずれは誰でも大麻クッキーという結論にたどり着いたと思う」
「だけど、先生、よく大麻クッキーだとわかりましたね」
「何かを食べて中毒になったとして、めまいが起こるというのは普通考えられない。前に運ばれた人は失神したりしたそうだし、食中毒とは違うな、と思っていた。薬物中毒にしても、それほど重症ではないし。何が混入されたのか、と考えて、最近HHHCが禁止薬物に指定されたってニュースを思い出したの。お菓子の形で売られるし、症状もさまざまだっていうのをなんとなく覚えていたの」
「そうだったんですね」
「それで、犯人はどんな男なの?」
今日のメインは鶏肉のソテーだ。先生は鶏のもも肉の筋を丹念に取っている。筋があると食べにくいので、できるだけ取り除く。
「七〇代くらいで、髭も髪も伸び放題。なんかだらしない男でした」
私は付け合わせのジャガイモの皮を剝いている。
「七〇代だと団塊の世代くらいかしらね。いい年して、分別ないのかしら」
「ただ、捕まった男は、クッキーをおやつ箱に入れたことは認めたものの、入手経路については、見知らぬ男からクッキーの袋を渡され、中身を配るように言われた、と言い張ってるらしいです」
「つまり、真犯人は別にいると?」
「はい。そうやって自分の罪を軽くしようとしているのかもしれませんが。男はいちいち配るのが面倒だったので、目についたおやつ箱に五つほど投入すると、あとは自分で食べようと思って、人の少ない林の方に行ったそうです」
「自分で食べようと思ったのなら、これが何かは知っていたの?」
「ええ。もともと定職にも就かず、日雇いの仕事をしてその日暮らしをしているそうですが、クッキーの事は知っていたんだとか。前にも食べていい気持ちになったことがあるらしいです」
「定職に就かず、大麻クッキーを好む。まるで昔のヒッピーみたいな男ね」
「いまの時代にヒッピーがいるとは思いませんけど」
「それはそうよね。それで、彼にクッキーの袋を渡した男というのはどうなったの?」
「ごくふつうの、これといった特徴のない男だったと。なので、偽証じゃないかと疑われているらしいです」
「ふうん。知り合いではない、と」
「どっちにしても悪質です。なんのためにこんなことをやるんでしょうか? お祭りで騒ぎが起こることを期待した愉快犯なんでしょうか。のどかな住宅地で、みんなでお祭りを楽しんでいただけなのに、ほんと不愉快です」
禁止薬物を配った疑いで男は現行犯逮捕された。だが、男にクッキーを渡した男がいるとしたら、そちらの方が重罪だ。何が起こるか、わかって渡したのだから。
「変質者や犯罪者はどこにでも出没しますからね。ただ」
そう言いかけて、靖子先生は口をつぐんだ。
「何か気になる事が?」
「いえ、私の考え過ぎかもしれないんだけど、ただの愉快犯にしては、嫌な感じだな、と思って」
「どういうところが?」
「子どもが被害者になる可能性があるのをわかってばらまいたこと。本当の犯人がいるとしても、絶対にみつかりそうにないこと。市民の楽しむ場所を台無しにするようなことをやっていること」
「愉快犯だったら、人が大勢集まるところでやるのは当然なのでは?」
「それはそうだけど、これがただの事件じゃなく、忘れられたヒッピーを思い起こさせるような事件でしょう? それがちょっと嫌な感じがするの」
「嫌な感じ?」
「イベント自体の評判を下げるために仕組まれたような」
「仕組まれた?」
「まあ、私の考え過ぎかもしれないけどね。ともあれ、これ以上悪いことが起こらないよう、私たちも気をつけなきゃね」
「そうですね」
「でも、おまつりが中止にならなくてよかったわ」
その時、店の扉が開いて、「おはようございます」と言いながら、香奈さんが入ってきた。だが、私たちが既に下準備を始めているのを見て、慌てたようだ。
「遅くなってすみません!」
「大丈夫よ。まだランチタイムには時間があるから」
「今日は私が早めに来ただけだから、気にしないで」
先生と私が口々に言う。香奈さんは急いでエプロンを付けた。そして、手を洗いながら言う。
「私は何をやりましょうか」
「じゃあ、インゲン豆の筋を取ってください」
そうして、またいつもの一日が始まった。これからランチタイムが終わるまでは、忙しくなる。事件のその後は気になるが、考えても仕方ない。気持ちを切り替えて今日一日も頑張ろう、と私は思っていた。
※連載第2話に続く
愛知県生まれ。東京学芸大学教育学部卒業。フリーライター、出版社勤務を経て、2006年『辞めない理由』で作家としてデビュー。
『菜の花食堂のささやかな事件簿』シリーズのほか、ベストセラーとなりドラマ化された『書店ガール』シリーズ、『銀盤のトレース』シリーズ、『凛として弓を引く』シリーズ、『スケートボーイズ』『駒子さんは出世なんてしたくなかった』『1939年のアロハシャツ』『書店員と二つの罪』『レイアウトは期日までに』等、多数の著書がある。
地域の食文化への興味から、江戸東京野菜コンシェルジュの資格を取得。