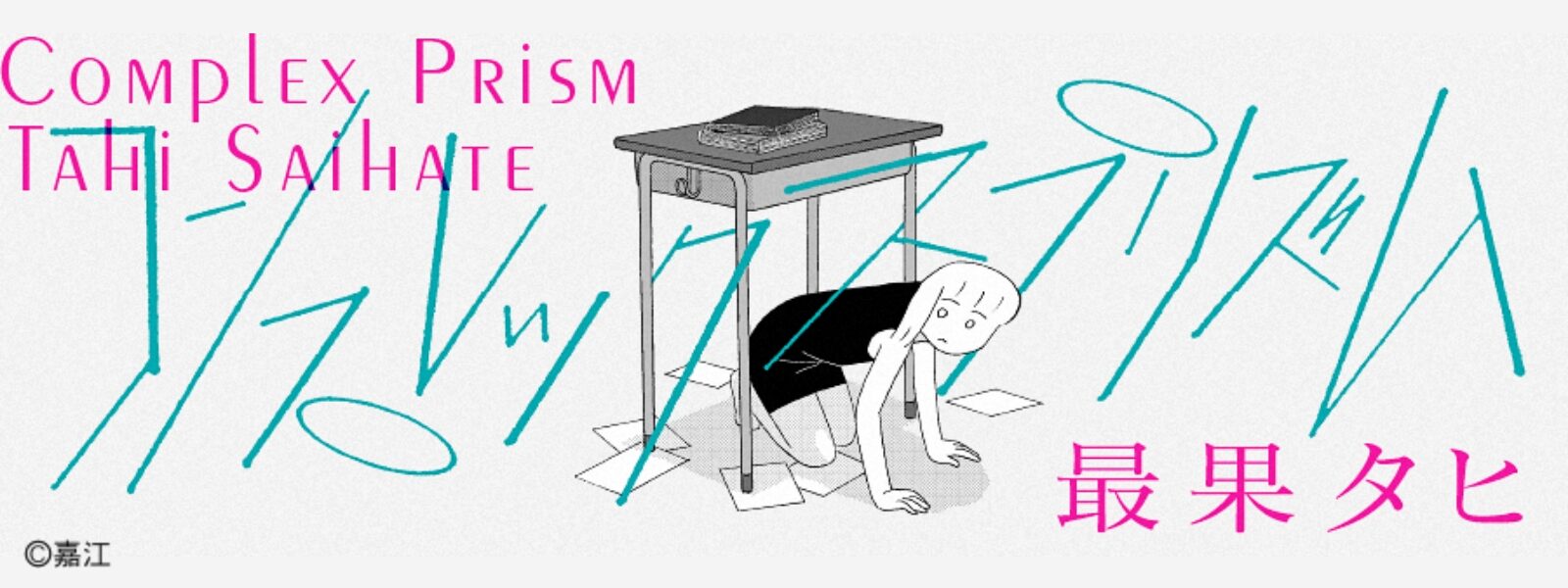劣等感とはいうけれど、それなら誰を私は優れていると思っているのだろう、理想の私に体を入れ替えることができるなら、喜んでそうするってことだろうか? 劣っていると繰り返し自分を傷つける割に、私は私をそのままでどうにか愛そうともしており、それを許してくれない世界を憎むことだってあった。劣等感という言葉にするたび、コンプレックスという言葉にするたびに、必要以上に傷つくものが私にはあったよ、本当は、そんな言葉を捨てたほうがありのままだったかもしれないね。コンプレックス・プリズム、わざわざ傷をつけて、不透明にした自分のあちこちを、持ち上げて光に当ててみる。そこに見える光について、この連載では、書いていきたい。
天才だと思っていた。
13歳。
一体なんの天才なのかはわからないけれど、でも自分は確実に、何かの天才なのだと信じていた。それは、自信があるとかそういうことではなかった、ひとりの人間として、世界をかろうじて直視し続けるために、どうしても必要な「言い訳」だったと今は思う。
当時の私には、何にもなかった。オリンピックを目指すほど、のめりこんだスポーツもなく、弁護士になると決めて今から猛勉強をするような、そんな友達に比べると、将来のことは考えていなかったし、考えても、そのために今を燃やし尽くそうなんて思うことはなかった。ただの13歳で、世間が認めるような結果を出したこともなかったし、それだけじゃなくて、自分を焼き尽くすような努力もしていなかった。自分という存在が、アイデンティティが、未来まで連続して存在している感じがしない。ただ私は今日も、だされた宿題をやって、授業を受けて、走って、友達と雑談して、1日をやりすごしている。私は未来の自分のために、何一つ行動を起こせていなかった。それは普通のことなんだけれど、でも、普通のこと、という言葉がなんの慰めになるんだろう。スポーツや将棋や勉強や芸術、そういうものに明け暮れて、その道を極めるんだと決めた同い年の子がまぶしい。必要な努力ならいくらだってしようとおもった、でも、なんの努力をしたらいいのかも不明だった。私にはそれなりに好きなことはたくさんあったけれど、極めたい、極めよう、と当たり前に思うものなんて、何一つなかったんだ。
そして、それでも自分を天才だと信じていた。
信じて、意味があったと思います。私の勝手な思い込みだけれど、ものを作っている人の中には、自分は天才だと盲目的に信じたことのある人、結構いるんじゃないのかなあ。そうでなければ、こんなにもたくさんの才能が、作品が、ある世界で、一から何かを作ろうなんて思えない。私は、そうだった。書かなくても、名作なんてたくさんあるじゃん。歌わなくても、名曲なんてたくさんあるじゃん。インターネットにつながれば、いくらでも面白い人がいて、それを追いかけていれば人生は充実し、終わっていくだろう。それでも私は作りたかったし、作りたいと思えたのは、無根拠に「天才」と信じていたから。石井裕也監督*1とラジオで共演した時、自然と、自分を天才だと思っていた時期のことが話題になった。石井監督にもそうした時期があり、なによりそうした話が当たり前にできるということが、私には随分と救いだった。私と、世界の間に橋がひとつかけられたような、そんな気がして安心したんだ。「天才」、私には、突き進むためにどうしても必要な言葉だった。ばかみたいだけど、でもばかみたいにそう信じた自分を今は褒めたい。ばかでありつづけたその勇気みたいなの、抱きしめてあげたかった。
ばかみたいだって、当時から、わかっていました。天才と自分を信じるだなんて、それこそ傲慢だと、わかっていたし、だから私は自分のそういうところが恥ずかしくて仕方がなかった。他人にバレていないか毎日心配で、「プライドが高そう」とかそんなことを少しでも言われたら泣きたくなるほど傷ついた。けれど今、むしろ傲慢だったのは、私から見た「世界」そのものだったと思うのです。完成されている世界、すばらしいものが本屋やCD屋で簡単に手に入って、テレビをつければ才能や天才という言葉が氾濫している。最年少受賞だの初出場で優勝だの。私の瞳には、世界は「認められた人」だけで構成されているように映っていた。私なんていなくても大丈夫な世界。そんなの、最初からわかっているのに、才能とか天才とか、最年少とか、そういう言葉まで使って、世界は傲慢なぐらい、私のことを一粒残らず消し飛ばそうとしていた。でも、私は、生きてかなくちゃいけないんです。だからどうしても、私は私を特別と思っていなくてはいけなくて、「これから大人になるというのに、私はいつまで無根拠に、私のことを守れるだろう?」不安で、泣きたくなる。この世界に紛れてしまって、いつか私も私を見つけることができなくなるんじゃないだろうか。私は、私を特別だと信じているだけじゃきっとダメなのだ、そろそろ世界にも、私を特別だと証明しなくてはいけないんだろう。子どもだから特別で、子どもだから愛されて、それが、今まで。それなら、大人になったら、私、どうなるのかなあ。このままならばきっと、溶けていくしかない、消えて、馴染んでいくしかない。だから私は、かけらでもいいから残りたいと願ったし、残ろうとする自分を諦めたくなかった。
何を作ってみても、それが世界を変えるすばらしい出来、と盲目的に信じることはできなくて、ただただ、たくさんの傑作がある世界の中で、私は一人もぞもぞと何をしているんだろうなあ、と思った。それでも、作るのをやめない、残そうとするのをやめない、そのために私は言い訳をしていかなくてはいけなくて、そこに必要な言葉が私にとっては「天才」だった。自信でもないし、傲慢でもなかった。自信過剰で恥ずかしいなんて、コンプレックスに思っていた当時の私に、違うよ、と言いたい。そんな強い言葉でしか、もうはげますことができないぐらい、私は特別というものを失いかけて、崖の上にいる気がしていた、はやく、私は何者にならなくちゃと雲の向こうを見つめていた。
石井裕也監督…日本の映画監督
詩人。中原中也賞・現代詩花椿賞。最新詩集『愛の縫い目はここ』、清川あさみとの共著『千年後の百人一首』が発売中。その他の詩集に『死んでしまう系のぼくらに』『空が分裂する』などがあり、2017年5月に詩集『夜空はいつでも最高密度の青色だ』が映画化された。また、小説に『星か獣になる季節』、エッセイ集に『きみの言い訳は最高の芸術』などがある。