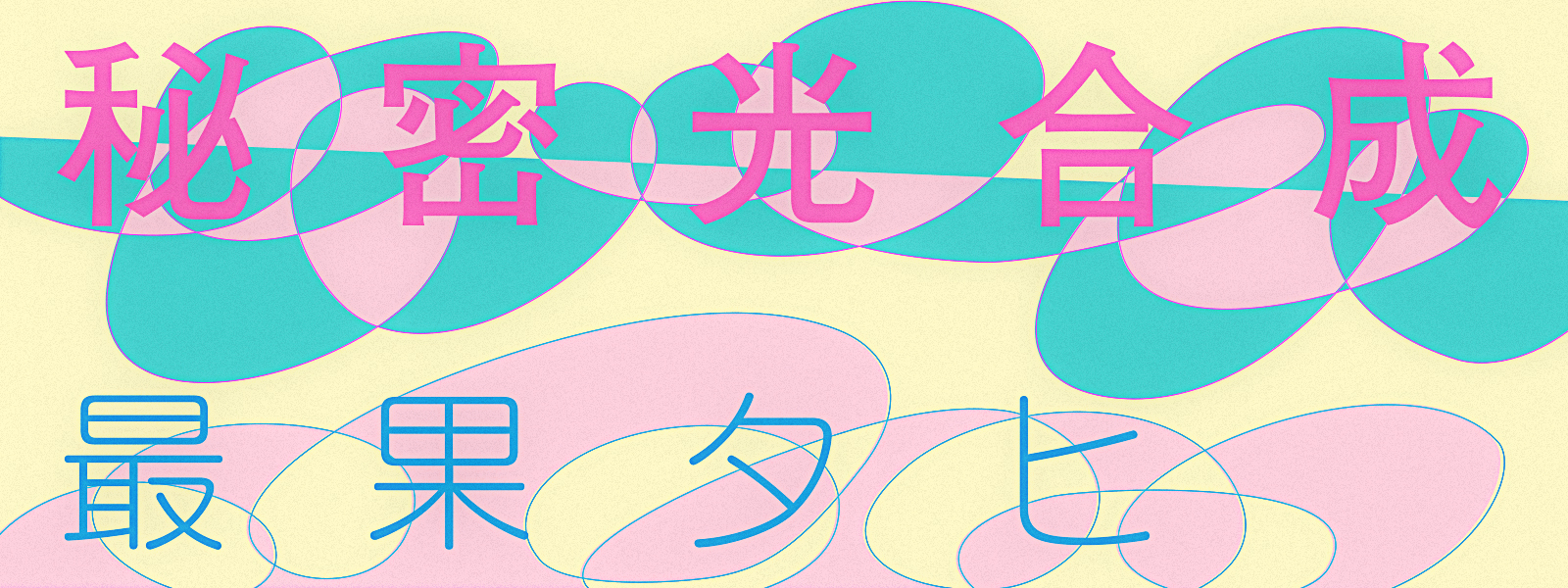その時に咲いていた、その花の花言葉を、最果タヒが詩で見つめ、新たに捉えていく連載です。花を見つめる時、いつもそれらは「私」の人生や生活の断片としてあり、その花に一つの象徴のような言葉を見出すとき、それはいつも人生や生活に重なっていく。その淡さを詩で描けたらと考えています。
桜
忘れないで、と散るたび、忘れないよ、と光は答える。忘れないよ、と言えることが光は嬉しくて、恋とは言ってしまわず、ずっとそう答えていたい、きみのさみしさをさみしさのままで受け取れる手のひらでいたい。わらってほしい、なんて言わない。きみのさみしささえも、春の美しさの一部で、何一つあなたの涙は汚さない、ぼくは何一つ汚れない、光だから。どんなに愛されてもさみしい人が行く地獄はありません。雨が降る日の桜もきれい。
――桜の詩
忘れないで、というフランス語の花言葉があるときいて、桜の散るところを思い出す。私は桜の散るところが好き。聞こえないのに拍手の音が聞こえてくる気がする。桜そのものが、春に拍手をおくりながら、散っているように思う。
桜は儚さの象徴とも言われるし(それこそ小野小町の歌のように)、確かにそのあっという間に終わってしまうさみしさはあるのだけれど、桜ほど約束を守ってくれる花、という感じがするものもない。必ず来年も咲いてくれると思える。それは、満開の桜の姿があまりにも美しくて、散ってしまった後も、その木が桜の木であることを忘れずにいられるからだと思う。春が来たらまた咲くはずだと信じられて、そしてそれが必ず叶う。その繰り返しの中で、儚さよりもそれに勝る約束を感じる。私はその、まっすぐな、儚さそのものを見つめ返すような誠実さがとても好きです。
春はおだやかすぎてどこからが春なのか、どこまでが春なのかもわからないけど、桜が約束を守ってくれている間だけは、春だと思える。儚さを包む光の誠実さ。