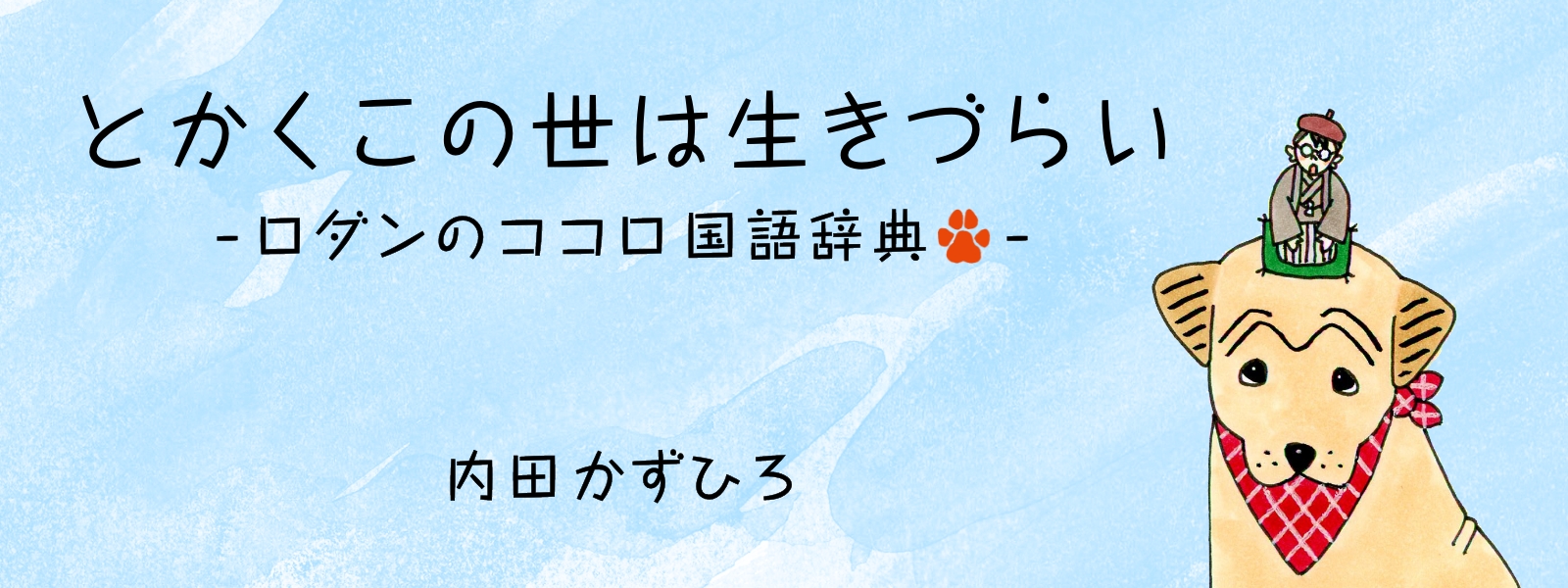小学一年生、六歳のときに初めて「あいうえお」を習ってから、その十倍近い人生を生きてきた内田かずひろ、五十八才。ひと昔前ならもうすぐ会社を定年する年齢だ。五十才を過ぎる頃には自分もちゃんとしているだろうと若い頃には思っていたと言う。しかし、マンガの仕事もなくなり、貯蓄もなく、彼女にもフラれ、部屋をゴミ屋敷にして、ついにはホームレスになり、生活保護を申請するも断念せざるを得ず…。だが、そんな内田でも人生で学んできたことは沢山ある。内田の描くキャラクター、犬のロダンの目線で世の中を見てきた気づきの国語辞典と、内田の「あいうえお」エッセイ。この連載が久々のマンガの仕事になる。
ない

例えば、恋をしている相手と話をする時は身体が熱くなったり、心臓の鼓動が速くなったりするだろう。
それは昔から記号のような表現としても使われているし、周知の事実だろう。それと同じように人は恐怖を感じた時や、悲しい事や辛い事があった時も身体に反応が現れる。
僕の場合、どうにもならないくらいお金がない時、頭から血の気がスーッと引いていき、身体がズーンと重く感じられ、心臓の鼓動が遅くなり呼吸も苦しくなる。実際にその時、血圧や心拍数を計ったことはないが、きっと数値にも表れてるだろうと思う。最初は急に病気が発症したのではないかと思っていたけど、そうではなかった。問題が解決すれば一瞬で症状は改善されるのだ。
「お金がない」症状の場合、病院の処方箋で『現金』が処方されれば特効薬だ。「病は気から」とはこういう事を言うのだろう。
気持ちが身体に影響を及ぼして病気を発症することも、逆に病気を回復に向かわせる場合がある事も、今では科学的にも証明されている。
だから初めて「孤独死」という言葉を聞いた時、僕は『孤独』の寂しさによって身体が蝕まれて死に至ることだと思った。実際の「孤独死」の意味は、一人暮らしの人が周囲の誰にも知られずひっそりと亡くなってしまう状態をいうということは、後から知ったのだ。僕の解釈は間違いであったが、孤独の寂しさが積もり募って、人の心を蝕んで死に追いやってしまう場合もあるのではないだろうかと思う。
突き詰めれば、自分自身が消えてしまえば、この世の孤独の寂しさも消えてしまうのだから。
だけど、寂しさも消えてしまう代わりに、喜びや楽しみももう味わうことはできない。そういうぎりぎりのところで踏みとどまって生きている人もたくさんいるだろう。
僕の大好きな、イランのアッバス・キアロスタミ監督の『桜桃の味』という映画がある。その映画では、そんなぎりぎりの気持ちが描かれている。
また、孤独で辛らく寂しかった若い頃に、ルイ・マル監督の『鬼火』という映画を何度も何度も観た。その映画の主人公も同じように辛くて寂しいのだが、そういう映画に、ぎりぎりの気持ちを救われたこともある。
芸術は時として、心を救ってくれる薬のようだと思う。
1964年、福岡県生まれ。高校卒業後、絵本作家を目指して上京。1989年「クレヨンハウス絵本大賞」にて入選。1990年『シロと歩けば』(竹書房)でマンガ家としてデビュー。代表作に「朝日新聞」に連載した『ロダンのココロ』(朝日新聞出版)がある。また絵本や挿絵も手がけ、絵本に『シロのきもち』(あかね書房)、『みんなわんわん』(好学社)、『はやくちまちしょうてんがい はやくちはやあるきたいかい』(林木林・作/偕成社)、『こどもの こよみしんぶん』(グループ・コロンブス・構成 文/文化出版局)挿絵に『みんなふつうで、みんなへん。』(枡野浩一・文/あかね書房)『子どものための哲学対話』(永井均・著/講談社)などがある。『学校のコワイうわさ 花子さんがきた!!』(森京詩姫・著/竹書房)では「怪人トンカラトン」や「さっちゃん」などのキャラクターデザインも担当した。