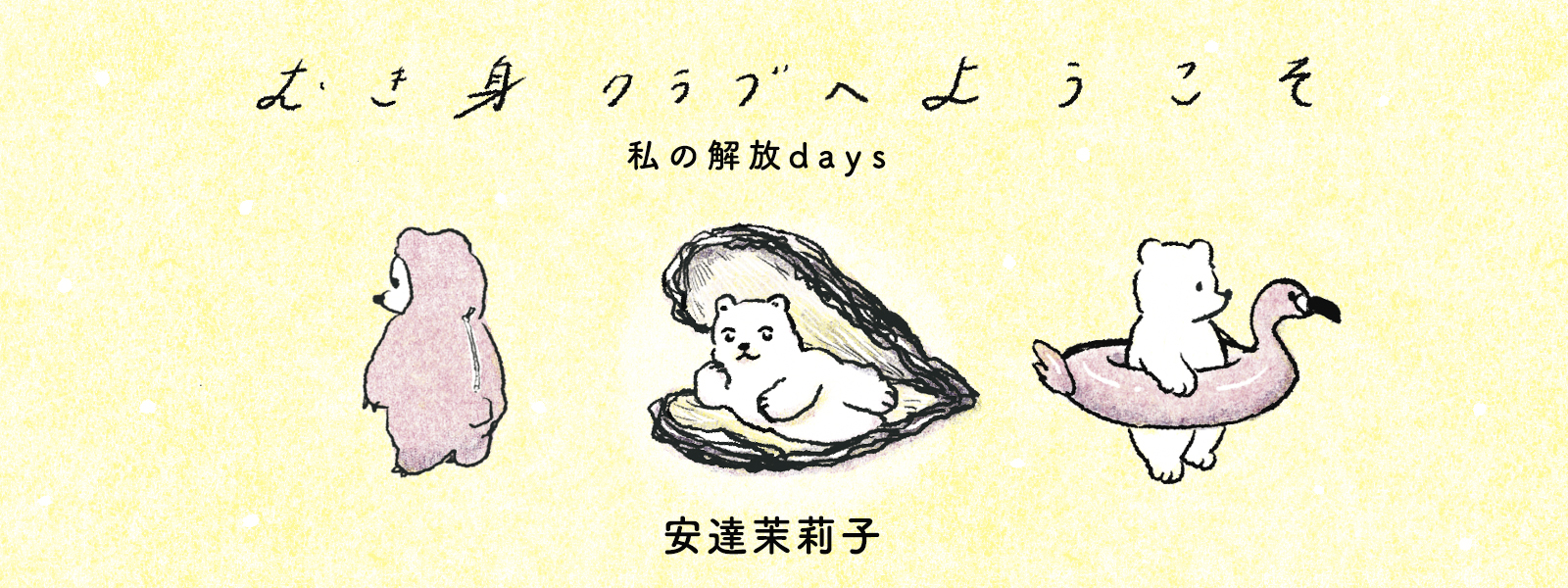むき身とは? 牡蠣をむいた時の中身のように、プルプルの震えている一番無防備な状態のまま、ただ存在している状態。身に纏ってきた不要なものをやさしく洗い流し、脱ぎ、ただ「むき身」になることを目指すクラブ。誰にも頼まれず結社し、むき身クラブと言い続けていたら、いつの間にか連載タイトルにまでなってしまいました。申告不要、出入り自由。それぞれの幸せをただ願い、自分を解(ほど)いて放っていく、日々の手立てを記します。
「自分のことが嫌い」からの解放:脳内の厳しい看守を全員クビにする
前回のむき身クラブでは、そもそも何から「解放」されたいのだろうか、という問いのもと、自分を「所有しようとしてくるもの」の話をした。具体的に束縛的な人だけではなく、社会規範や同調圧力もまた、内側からその人を縛り付けて所有してくる。何が怖いって、同調圧力にすすんで同調しようとしていたのは自分だった。
思えば30代の前半までくらいは、いつも不安で怯えていたと思う。
自分のことが大嫌い。いつもどこか寂しい。人にどう思われているか、どう思わせてしまったか気になってしょうがない。見捨てられる不安が常にある。信頼できないのに期待してしまう。期待してないしと言いながら、期待どおりにしてくれないと、怒り失望し嘆く。自分がめんどくさい。
めんどくさい自分のことがさらに嫌いだった。だけど、今になって思うのだ。自分という人格の欠陥だと思っていたけれど、ただそういう状態に追い込まれていただけだった。誰だってそんな心境に追い込まれる可能性がある(そもそもめんどくさくたっていい!)。あなたの問題ではない。何度でも子守唄みたいに歌ってあげたい。あなたが問題なのではない。
「あなたの性格ですね」
オーストラリア留学から帰国後、大学4年生の頃、いよいよどうしても苦しくなってしまって、誰にも言わずに予約し、初めて精神科を受診した。私はうつ病なんでしょうか、と聞いたら、疲れて不機嫌そうな精神科医に、投げやりに「というかあなたの性格ですね」と言われた。医師は続けた。「カウンセリングですか? お金かかりますよ」。今振り返るとさすがにひどい医者だったのではないかと思うけれど、当時はセカンドオピニオンを探すという発想もなかった。結局「そんなに死にたいなら薬を出しときます」と言われて処方された薬は帰り道で捨てた。
ショックだった。診断を受けることで救われるんだ、帰り道にはきっと少しは楽になっているんだ、と漠然と思っていた。だけど、医師が言ったように、この苦しみが私の性格なら、治らないではないか。だけど、その後心のどこかでずっと、こうも思っていたような気がする。
性格なら、変えていけるのでは?
それから私の地道な「楽になる活動」は始まった。自助努力の極みで、自己分析と、書店に並んでいる本を頼りに、自分と向き合う作業だ。今ならもっと、オンラインのカウンセリングや、同じ悩みを抱えた人が集まるお話会に参加するなど、他のリソースをうまく頼れるだろう。だけど今から10年以上前の私は、そもそもそうしたリソースの存在自体思いつかなかった。自分でやるしかなかったのだ。
楽になる活動
この頃始めた「楽になる活動」のテーマは、自分のことが嫌いで、ほぼ自動的に自分を責め続けてしまうのをどうにかしたいというものだった。ノートを持ち歩き、時間を見つけては喫茶店に入り、思ったことを書きつけた。
その中にはひとつ疑問があった。いつも、異様なまでに疲れていた。外では明るく楽しく振る舞っていても、家に帰ると立ち上がれないくらいどっと疲れている。一体何にこんなに疲れているんだろう? ノートに向かって考えてみた。
そもそも私はどのように24時間を過ごしているのだろう。そうやって自分の思考をたどってみると、ほとんどの空き時間を、自分を責めることに使っていたことに気づいた。また迷惑をかけてしまった。きっと嫌われた。あの人を傷つけたかも。いつも明るくてかっこいいあの子みたいになりたい。そうじゃないと、こんな自分とは誰も一緒にはいてくれないだろう。
そりゃあ、疲れるわけだよなあ。四六時中そんなふうに自分を責めていたら。とにかくこのノートには、何も否定せずに書いていいことにした。言うなれば、私の居場所だ。ノートに自分の思考をそのまま書いていると、深い哀しみがペンのインクにのって紙に吸い込まれていくようだった。
うん。まるで、自分の頭の中にものすごく勤勉な看守がいるみたいだ。24時間勤務で見張っていて、絶えず頭の中でダメ出しをしてくる。それは例えば「視野が狭い」だったり「表情が暗い」だったり、「人間として小さい」だったり、「だったらなんだっつうんだよ」みたいなささやかなことが多い。自己批判はまとめると「そのままのあなたでは何者にもなれないよ」、そして「そんなあなたと一緒にいたいと思う人なんていないよ」というメッセージを放っていた。だからもっと努力して、気を遣って、人に愛される人になって、と。
自分を否定することで得る「報酬」
自分を否定することで、どこかで安心感という報酬を得ていたと思う。自分を罰し、向上しようとしていますと示すことで許されようとしていた。まるでミスをした翌日自主的に丸坊主にしてくる社員みたいに、自ら「誠意」を見せようとしていた。いったい何に、誰に許してもらおうと思っていたのだろう? とにかくずっと許されたかった。自分を絶対に認めてくれないけれど、認めてほしい、そんな架空の大きな存在に。看守はおそらく、その架空の大きな存在の手下だった。
ある時、友人に言われた。「まりこは人に厳しすぎる」と。私の頭の中の厳しい看守は、いつの間にか表にも出てしまっていた。友人に言われたとき、反射的に、「そうしないと誰が正してやれるんだ」と思った。愕然とした。私はそんな人になりたかったわけじゃない。私の周囲には厳しいことで知られる人が何人かいて、私はいつの間にかそうした厳しさをそのまま受け止め、自分の内側に内面化してしまっていた。看守は、自分自身を常駐で罰するだけじゃなく、ついには外界に進出してしまっていた。これはなんとかしないといけない。だって私は厳しいことを言われてきた被害者だと思っていたのに、私自身が誰かに対して、また別の抑圧的な厳しい人になってしまう。
「厳しい看守、全員クビ!」のイメージワーク
よく「自分をあるがままに受け入れよう」という。そんなことできそうになかったけれど、せめて癖みたいに自分を否定するのはストップしようと思った。好きになるのは難しい。だったらせめて、嫌いになるのをやめることができたら少しは楽になるんじゃないか。
私の「楽になる」活動は、こうした脳内の厳しい看守を全員クビにすることからスタートした。もはや看守狩りといってもいい。頭の中で自己批判する声が生まれるたびに、「お前、クビ!」と頭の中で唱える。そして、実際に、指先でつまみ出すようなイメージをした。脳内でうるさい看守も、イメージすると指先でつまめるくらいの大きさなのだ。部屋の中から虫を外に出すように、有無を言わさず看守をクビにしてつまみ出す。いなくなってスッキリ、せいせいする感覚が起こるまでやる。
そして、代わりに優しい人を採用する。「推し」でも誰でもいい。脳内の人事異動をとにかく進めた。私の場合は、具体的なビジュアルはなく、ただやさしい光が人の形をしているようなものを想像していた。その光は、私を見守っている。私がどれだけみっともなくてダメな人間でも、私を見捨てたりしない。漫画でいうと、のび太のおばあちゃんをもっと永遠の存在にしたような感じだろうか。のび太がどれだけダメでも、おばあちゃんには関係ない。ただ、大切な孫なのだ。のび太がいることだけを無条件に喜んで、受け入れてくれる。同じように、その人は、私が生きているだけで嬉しい。うまく生きられなくても悲しまない。ただ、あるがままをそのままに認めてくれる。そして、励ましてくれる。看守だったら「そんなことじゃやっていけないぞ」と詰め寄ってくるところを、その人は「よくやってるね」と寄り添ってくれる。
そして気づいた。のび太のおばあちゃんじゃなくても、そんな人は私の家族や友人に、ちゃんといた。ただそうやって寄り添ってくれる人のことを、自分の中の看守がブロックしていたのだ。ちゃんとただ愛されていたのに、自分自身でそれを受け取っていなかったのだ。
看守はいなくても大丈夫
看守はどんどん湧いてくる。クビにしてもクビにしても気づけば勝手に復職してキリがない。まるでゲームのザコキャラみたいだ。どうやら、看守が湧いてくる土壌は、「自分は生きている資格がない」という自己認識だった。だからこそ、努力しないといけないのだと。この世に生まれてきて以来、誰にもそんなこと言われたことないはずなのに、いったいどうしてそんなことになってしまったのだろう。
今も、疲れている時は看守が雑草のように湧いて出てくる。自分ってダメだなあ。未来なんてないのかもしれない。そんな思考が湧いてきたら、すかさずむしりとる。あるいは、そんなことを考えているのだなあ、と自分を丸ごと眺める。そして言ってあげる。そんなことないのにね、よしよし。
看守をクビにするワークには思わぬ副産物があった。それまでにないひとつの力が自分の中で芽生えていた。自分のことを否定する言葉を浴びせて追い立てるのではなく、代わりに自分自身に慈愛の声をかけることがうまくなったのだ。
よくやってるよ。大丈夫。大したことないよ。今ちょっと元気がないだけだよ。人間はみんなそれなりに誰も不完全で、でもみんなそんなもんだよ。今の道がすべてじゃない、ほかの道があるよ。クビにした看守のかわりに、私は私に声をかけるようになった。雑草をむしっては土壌を手で撫でるように言葉で励ましているうちに、いつの間にか誰かをいたわる語彙が豊富になった。何より、私は私を否定してくる頭の中の声より強いのだと、私には私を変える権利と力があるのだと、わかっていった。自分を絶対に認めてくれないけれど、認めてほしい、そんな架空の大きな存在なんかより、私の方が大きい。私の肯定は、否定から生まれていったのだと思う。
自分のことをネガティブな人だと思っていたけれど、人は変わっていく。ワークを繰り返していくうちに、あるがままに受け入れて否定しない力が、いつの間にか私に備わっていた。
作家・文筆家。東京外国語大学英語専攻卒業、サセックス大学開発学研究所開発学修士課程修了。政府機関、限界集落、留学などを経て、言葉と絵による作品発表・執筆をおこなう。
著書に『毛布 - あなたをくるんでくれるもの』(玄光社)、『私の生活改善運動 THIS IS MY LIFE 』(三輪舎)、『臆病者の自転車生活』(亜紀書房)、『世界に放りこまれた』(ignition gallery)ほか。