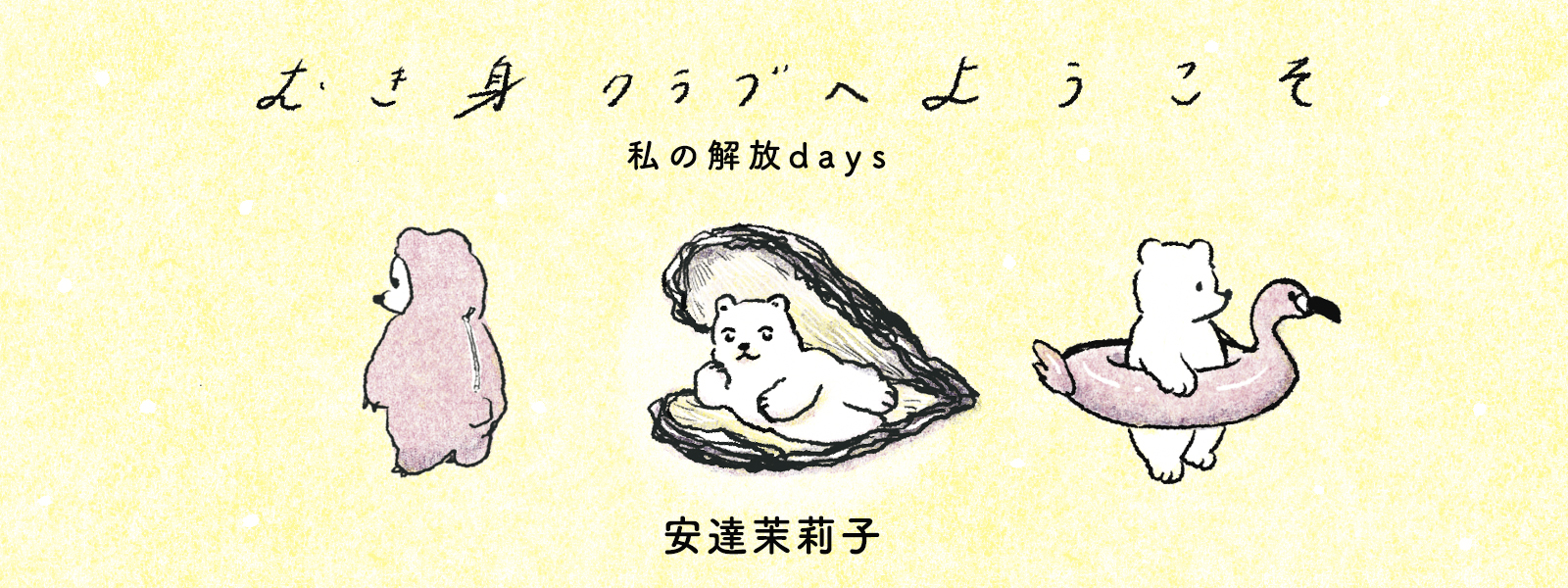むき身とは? 牡蠣をむいた時の中身のように、プルプルの震えている一番無防備な状態のまま、ただ存在している状態。身に纏ってきた不要なものをやさしく洗い流し、脱ぎ、ただ「むき身」になることを目指すクラブ。誰にも頼まれず結社し、むき身クラブと言い続けていたら、いつの間にか連載タイトルにまでなってしまいました。申告不要、出入り自由。それぞれの幸せをただ願い、自分を解(ほど)いて放っていく、日々の手立てを記します。
初めてむき身クラブをオンラインで開催したときのこと〜「あ、帰りの方角一緒ですね」にウッとなる時のワーク
むき身クラブの連載を行う中で、実際に本当に、初めましての方々と一緒にやってみたいという気持ちが日に日に高まっていった。概念としてだけではなく、ちゃんとやってみたら、どんなことが起きるだろう? それを見てみたい。意を決して、ついに実際にオンラインで開催してみたのは2024年2月のこと。完全オンラインで、ZOOMでの開催。20名で告知を開始したところ、すぐに満席となり、急遽追加の回を設定して、2回に分けて行った。
一時間半に設定して、内容としてはこんな感じだ。
・「むき身」とは何か、むき身になるとはどんなことかについてのお話
・ むき身ワーク ―― 自分の「殻」を感じてみよう / むき身になるを試してみるワーク
・ むき身クラブセッション ――感じていること、悩み、困ったこと etc…をただ話してみるお話しセッション
私はこんな実験的なイベントへの申込みをいただけたことが嬉しく、どうか皆で楽しめる時間になるようにと、会の「準備運動」として、参加者の方には事前アンケートをお送りしていた。質問は2つだ。
質問1.この中で、一番ウッとするものは何でしょう?
・職場の人と駅に向かう途中「あ、帰りの方角一緒ですね」
・グイグイいったらちょっと距離を置かれた
・長文メールが来ている
質問2.今のむき身度を表すと・・・?
「ガチガチに防御。触らないで欲しい」を1として、「プルンプルン。一人でいても誰といても別に苦にならない」を5として、1~5のうちどの段階にあるかを任意で回答してもらうようにしていた。
このほか、アンケートには、会の中で特に聞きたいこと、話してみたいこと、相談したいこと、打ち明けてみたいことなどがあればお聞かせくださいとして、自由記入の欄も設けていたが、結果的に本当にこの準備運動のアンケートはお送りしておいてよかったなと後で感じることになった。
一番ウッとするシチュエーション、圧倒的に多かった回答
オンラインむき身クラブでは、顔や名前を画面上に出している人もいるが、こちらから指定することはせず、各自自由に設定してもらうことにした。ROMのような形で参加してもらうのもOK。とにかく、一切気を使ったり、他人と合わせたりするのではなく、自分がしたいようにやってみるという場にしたかった。
面白いことに、アンケートで聞いた最初の「1.この中で、一番ウッとするものは何でしょう?」という質問は、「職場の人と駅に向かう途中『あ、帰りの方角一緒ですね』」を選んだ人が圧倒的に多かった。
2回合わせて、約50パーセントの方が、職場の人と一緒の電車になるのを避けようとしているのだった。「グイグイいったらちょっと距離を置かれた」と「長文メールが来ている」はそれぞれ約25パーセント。私は基本的にどのシチュエーションもそれぞれ平等にウッとなるけれど、実は「電車で帰りの方角が同じ」は一番マシかなと考えていたので、この結果は鮮やかだった。
(ちなみに、「距離を置かれた」や「長文メールが来ている」について、会の中でその回答を選んだ理由を聞くと、傷つきや、過去のトラウマ的な記憶が浮かび上がった。実は、「長文メール」の選択肢は、過去に長文の説教やアドバイスメールが何通も届いて以来、メールの通知を見ると今でも身構えてしまうという、私の個人的なトラウマ反応から作ったものだ。長文メールというだけで、何かネガティブな想像が引き起こされる人もいれば、何にも感じない人もいる。人にはそれぞれ、嫌な記憶がある)。
会の中で、なぜ「電車で帰りの方角が同じ」を一番に選んだのか参加者の方に話していただいた。職場の人との関係性は仕事のもので、電車の中はようやく一人になり解放される時間なのに、それが延長されるのが苦痛だし、何を話していいかわからないし沈黙も気まずいと回答される方が多かった。一言一句、その通りだ。
それを踏まえて、むき身をやってみるワークとして、こんな提案をしてみた。
・帰りの電車が一緒になってしまったとイメージしてみて、自分の体がどんな感じになっているか(強張っている、呼吸が浅いetc…)、あるいは頭の中にはどんな思考が浮かんでいるか、感じてそのまま話してみてください。
・次に、電車の中に職場の人と隣り合わせで座っている自分自身をイメージしながら、こうイメージしてみて下さい。この職場の人とあなたは、十年後、家族ぐるみで付き合うような本物の人生の友人になっていると、謎のネタバレで知ってしまったとします。何でも話せて、どっちかが入院したらお見舞いに行くような。もし10年後そうなってると今わかってしまったら、帰り道、その人に対する気まずさや感覚は変わりますか?
一瞬、「どゆこと?」という空気になったので頑張って説明し、イメージしてもらった。参加者の方に、このワークをやってみて感じ方が変わったか聞いてみる。すると、
「その人に対して、職場の人としての当たり障りのない会話だけじゃなくて、その人自身が最近どんなことを考えているか、どんなふうに感じるのか、その人自身のことを知ろうとして聞いてみると思います」と答えてくださった方がいた。他にも、自分のプライベートなことを話してみるかもしれませんという方もいた。
誰かと話すとき、ほとんどの場合は肩書きや組織が先に来る。職場の誰々さん、誰々のお母さんの誰々さん、みたいに、自分の中で半ば自動的にカテゴライズする。もちろんそうすることで、公私をきっちり分けて、心理的安全性が保たれるということもあるし、職場によってはむしろそれを推奨するところもあるだろう。それ自体は私は全く悪いことだと思わない。だけど、時にそれが殻となって、目の前にいるその人そのものと通じ合うことができなくなってしまう。それでもいいんだけど、時々寂しくなるし、虚しくなる。カテゴリーにとらわれず、その人の出会いが自分の人生の中でも大事な、一生の出会いになったっていいじゃないか。その可能性を最初から諦めたくない。
逆にいうと、職場の人だとカテゴライズした上で自分を作って接するんじゃなくて、最初から自分のむき身の状態で向かってみることで、相手もまた殻を下ろすことがあるかもしれない。ワークを考えたのはそう思ったからだ。まず自分から、出してみる。それを今オンラインで、参加者の方々と一緒にやっているんだという実感があった。
会は1時間半で設定していたが、結局は大幅に時間をオーバーしてしまった。特に盛り上がったのは、事前に募集していた「打ち明けてみたいこと、話してみたいこと」をただ一人一人語ってもらうこと。自分もまた同じように感じていると、誰かの話を受けて語ってくれた人もいたし、ZOOMのチャット欄はコメントを追えないほど盛り上がっていた。
その様子を見ていると、こういう場は、リアルの生活では本当にないのかもしれないと思った。職場やローカルな人間関係の中では、基本的に自分を出さない。自分の心の中を話してみたいけれど、変なことを言って相手にどう思われるか、重たい空気にしてしまわないかと気を遣ってしまう。それはある意味で優しさでもあるし、本当に自分のことを出し合える人がいない孤独がずっと続いていくということでもある。
その点、 「むき身クラブ」なんて集まりにわざわざ申し込んで集まってくれた人たちとの場だから、ある程度の心理的安心感があるのかもしれなかった。素直に自分の中にあるものを誰かに向かって話すことができるのかもしれない。内側にあるものを流し合っていく参加者の方々の姿を見ていると、こういう場がもっとあっていいのだと思った。アドバイスも否定もせず、自分が感じていることを同じように感じている人がいると体感できる場。直接自分が発言しなくても、誰かの話を聞いているだけで、「流れ弾」みたいに自分の中にも響くものがある。
自分自身もむき身になって、ただ話を聞く
私自身、オンラインで開催して気づいたことがある。初回は正直、ものすごく緊張していた。「うまくやらなきゃ」「がっかりさせてはいけない」と思ったのが原因だった。それは後々振り返ると、「参加したことを後悔させたくない」、「損をしたと思わせたくない」という恐れだった。
むき身の体に、恐れは麻痺剤のように染み渡っていく。我ながら最初はぎこちなかったけれど、会の途中でもうしょうがないと諦めた。これもまた、経験だ。「うまくやらなきゃ」と考えると、体が強張ってしまう。そうではなくて、目の前にいる人の話をただちゃんと聞きたいと思うこと。ただ自分の心を話してみたいと思うことにだけ集中する。2回目の開催では、力みが取れて、淡々とその場にいることができたと思う。
私は現在も、幸いなことにいろんなトークイベントや講演会に呼んでもらうことが多い。人前で話をする機会が本当に増えた。そんな時に意識するのは、まさにむき身でいくことだった。人生は一度きりで、出会いは一期一会。トークイベントを成功させるために頑張って武装するのではなく、むしろ解除し、おろしていく。トークイベントという口実があったから、今日ここにいる皆さんと会えて、人生の中で言葉を交わせている。だからその瞬間を楽しもう。そんな気持ちでむき身で行くと、成功も失敗もなく、実りだけがある。心と心、ふるえているもの同士でただ話ができたという実感だけ、毎回残るのだ。
作家・文筆家。東京外国語大学英語専攻卒業、サセックス大学開発学研究所開発学修士課程修了。政府機関、限界集落、留学などを経て、言葉と絵による作品発表・執筆をおこなう。
著書に『毛布 - あなたをくるんでくれるもの』(玄光社)、『私の生活改善運動 THIS IS MY LIFE 』(三輪舎)、『臆病者の自転車生活』(亜紀書房)、『世界に放りこまれた』(ignition gallery)ほか。