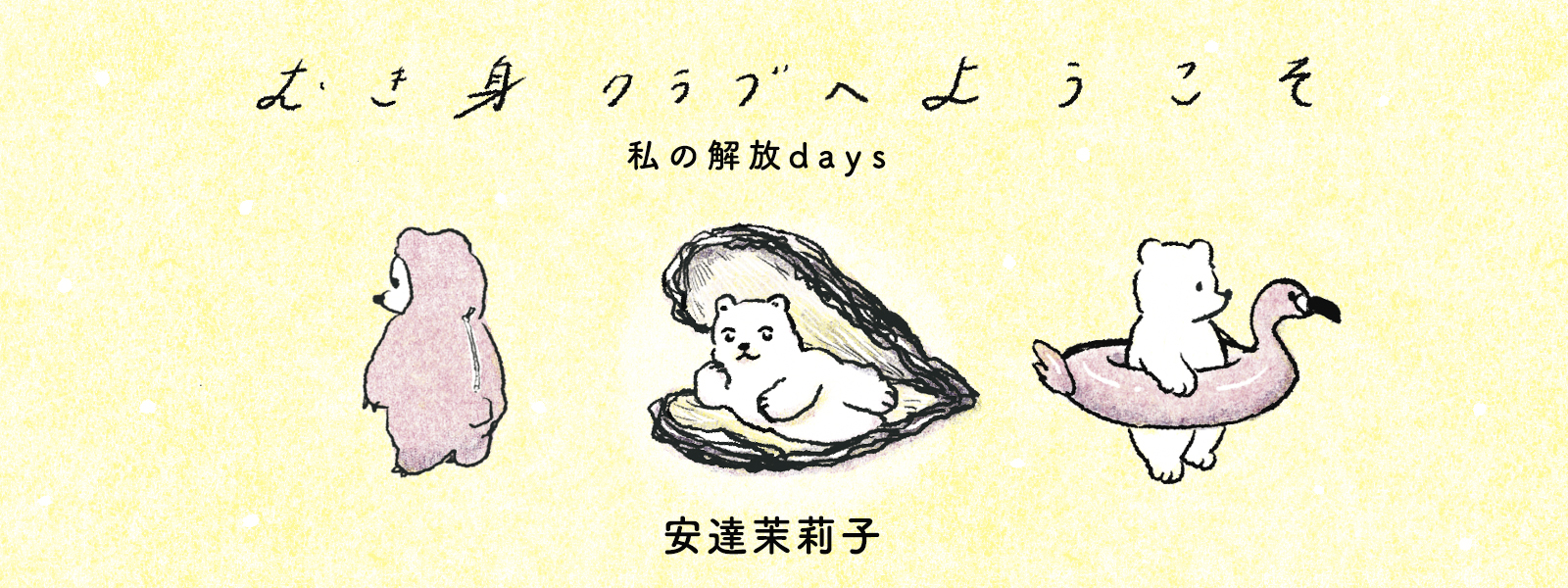むき身とは? 牡蠣をむいた時の中身のように、プルプルの震えている一番無防備な状態のまま、ただ存在している状態。身に纏ってきた不要なものをやさしく洗い流し、脱ぎ、ただ「むき身」になることを目指すクラブ。誰にも頼まれず結社し、むき身クラブと言い続けていたら、いつの間にか連載タイトルにまでなってしまいました。申告不要、出入り自由。それぞれの幸せをただ願い、自分を解(ほど)いて放っていく、日々の手立てを記します。
自分から奴隷にならないための解放闘争:前編
「そんなふうにあなたがたを支配しているその敵には、目が二つ、腕は二本、からだはひとつしかない。」——エティエンヌ・ド・ラ・ボエシ『自発的隷従論』(ちくま学芸文庫)
むき身クラブは、自分を覆う分厚い殻をおろし、その内側にあるやわらかい生身のまま、むき身のままで生きていくことを目指している。殻自体は別に悪いものではない。屋根も壁もない家に住みたい人はいない。だけど、好んで閉じこもっているわけではなく、本当は人を招いたり自分も外に出たりしたいのに、ドアも窓も開けられない状態があるかもしれない。そんな状態があっても、それは自分が悪いわけじゃない。
私は大学生の頃、就職活動をする時期に家を出られなくなった。一人暮らしだったので、買い物や自分の用事のためには外出はできる。だけど人に会うのはできる限り避けるようにしていた。人に会うと就職活動の話になる。ろくに就職活動ができていないし卒業後どうやって生計を立てていけばいいか見当もつかない自分は、義務を果たしていないような後ろめたい気持ちが強くあり、そんな状態で人にあれこれ言われるのが嫌で、誰にも会いたくなかった。かろうじて企業説明会を予約するが、当日朝になると体が強張って準備ができない。そうこうしているうちに家を出なければいけない時間を過ぎ、どう急いでも間に合わなくなってしまう。そんなことが何度も続いた。
就職活動に対してそこまで抵抗感があった理由はまた別の回で書きたいと思うが、基本的に私は人に会うのがずっと苦手だった。人と過ごすのは、気を遣ってどっと疲れる苦役みたいだ。自分の内側に入りこんでもまったく嫌じゃない人以外には、できる限り会いたくない。もっと嫌だったのは、こちらがドアを開けていないのにずけずけと入りこんで、部屋が汚いとかもっとこうしたほうがいいとかアドバイスをしてくる人だった。嫌なのに、そういう人がいざ玄関に来ると、ドアを開けてしまう。そして笑顔でへらへらと、そうだよね、ありがとう、そうしてみる、とアドバイスを受け入れて恭順を示してしまうそんな自分に嫌気がさし、見損なっていた。
「自発的隷従」
冒頭に引用したのは、16世紀のフランスを生き、32歳で夭折した法官が書いた「自発的隷従論」という論文の一節だ。母校の大学で行われたシンポジウムで「自発的隷従」という言葉を聞いて以来、ずっと心に残っていた。
本来、自由を望む性質であるはずの人間が、なぜその自由を放棄してまで、自ら圧政者に隷従してしまうのか? 本来は政治哲学の領域であるその問いは、21世紀を生きる私に、とても個人的で、私の心理的な部分、とても内側の領域に深く刺さった。
人と接するのが苦手だったと書いたが、その中で、何人か特に苦手な人がいた。その人といると、どうしてだか自分らしくいられなくなる。一緒の空間にいると、自動的に、その人の支配下に入ってしまったような感覚になり、その人によく思われないといけない、いうことを聞かなければならないと、勝手に自分が合わせて動いてしまう。だけど体が固まってちぐはぐなことばかりして、余計に焦る。自分をよく見せようとする必要もなく、言いたい放題言っては笑い合えるような、恐怖心のない関係ではない。会う前は気が重い。メールが来るだけでヒュッと体の奥が強張る。今日は何を言われるだろうかと緊張する。会わなければいいのに、避けると何を言われるかわからないので断れない。
その人たちは、私のことを嫌いだったり、憎んでいたわけではない。大事に思ってくれていたと思うし、何ひとつ悪気はなかったと思う。ただ、私にとっては深く傷つけられる言葉が、遠慮なく親しげに発せられた。「また太ったね、やばいよ。痩せないと。」「いつも思ってたけど、あなたの声暗いよ。もうちょっと明るくしたら。」「そんなの無理だって。現実見たら。」
多分それらは全部、アドバイスだった。ただ自分の価値観に照らして、正しいと思うことを言っているだけなのだ。
たとえば電車の中で、隣の席に座った人が、その人の友人と話し込んでいたとする。自分の娘がいかに出来が悪く、いつも暗く、愛想も礼儀もなく、見た目も悪く、将来こんなことじゃ嫁の貰い手なんてないと捲し立てているとする。私は、自分の苦手な人たちといると、そう言われている出来の悪い娘になったような気持ちだった。
今だったら、「ちょっと、さっきから聞いてればなんですか。言い過ぎじゃないですか? 考え方が一方的すぎますよ、押し付けないでください!」と突然割って入って電車内ドラマを繰り広げてしまいそうだが、当時は根本的な自己肯定感がなく、自分で自分を否定していたこともあり、他人に人格否定をされても違和感がなかった。相手は正しく、言われているうちが花で、アドバイスを無駄にせず、自分が受け入れて適応していけばいいのだと無意識に思っていた。
素直だが、危なっかしい。免疫機能が育っていないのに、なんでもかんでも吸収するなんて無理だろう。毒は内側に入っていき、内側から自分をむしばむ。毒は知らず知らずに溜まっていく。そして、恨みつらみでいっぱいになっていく。当たり前だ。何も抵抗できなければ、恨むくらいしかできない。あの人さえいなければ。あの人がああじゃなかったら。ずっとそう思っていたのに、一度も「やめてください」とは言えなかった。ヘラヘラしている自分をより一層深く嫌いになった。固い殻の内側は、泥でいっぱいだった。
ゲームからおりる
だけど、これは本当に、「そんな誰かと私」の間だけの話だったのだろうか?
誰か特定の人の前で強く萎縮してしまい、自分らしくいられなくなる現象は、繰り返し訪れた。社会人になってからの威圧的な上司や厳しい先輩。突然怒りをぶつけてくる人。かつては親しかった人。こちらが答えられないのに論理的に詰めてくる人。そんなとき私は手が震えて言葉が出なくなる。これは、繰り返すパターンなのだと思った。ごく普通の人間関係だったのに、いつしか、支配関係、あるいは上下関係、力関係で成り立つ人間関係のパターンに入っていってしまう。そんな関係まっぴらごめんだとサッと逃げればいいのに、逃げない。見返して認めさせてやるぜという根性のある話ではない。走る車の前に出てしまったタヌキのように、麻痺して動けなくなるのだ。そしてその関係性の中で、相手をどうにか怒らせないように、自分を責めて律し始める。相手を愛せない。ずっと不和が続く。
分厚い殻をおろし、家のドアを開けて人を招き入れることへの潜在的な恐れがあったのは、私にとって人間関係とは、一度気を許すとこの支配と隷属の関係パターンになってしまうとどこかで思っていたからかもしれない。もしかしたら、自分自身もまた支配的な側に回っていたかもしれない。
私の解放daysの人間関係編は、誰か特定の苦手だった人とのドラマについて書くものではない。人間関係のベースが「支配と隷属」モデルではなく、より自分自身を愛し尊重した上で、誰かと対等な状態で向かい合うことは可能だという、「愛と尊重」モデルに移行していった長い取り組みがテーマだ。
とても長い時間がかかった。最初に書いておくと、誰かのことを好きになれなくても、愛をもって接することはできる。その人の支配下に入り、相手の気分をよくしようとしなくても、従属しなくても、愛を送り愛を与えることはできる。支配と隷属の関係性からおりて、ただお互いの幸せを祈る関係性は可能だ。そんな話をこれからしていきたいと思う。
作家・文筆家。東京外国語大学英語専攻卒業、サセックス大学開発学研究所開発学修士課程修了。政府機関、限界集落、留学などを経て、言葉と絵による作品発表・執筆をおこなう。
著書に『毛布 - あなたをくるんでくれるもの』(玄光社)、『私の生活改善運動 THIS IS MY LIFE 』(三輪舎)、『臆病者の自転車生活』(亜紀書房)、『世界に放りこまれた』(ignition gallery)ほか。