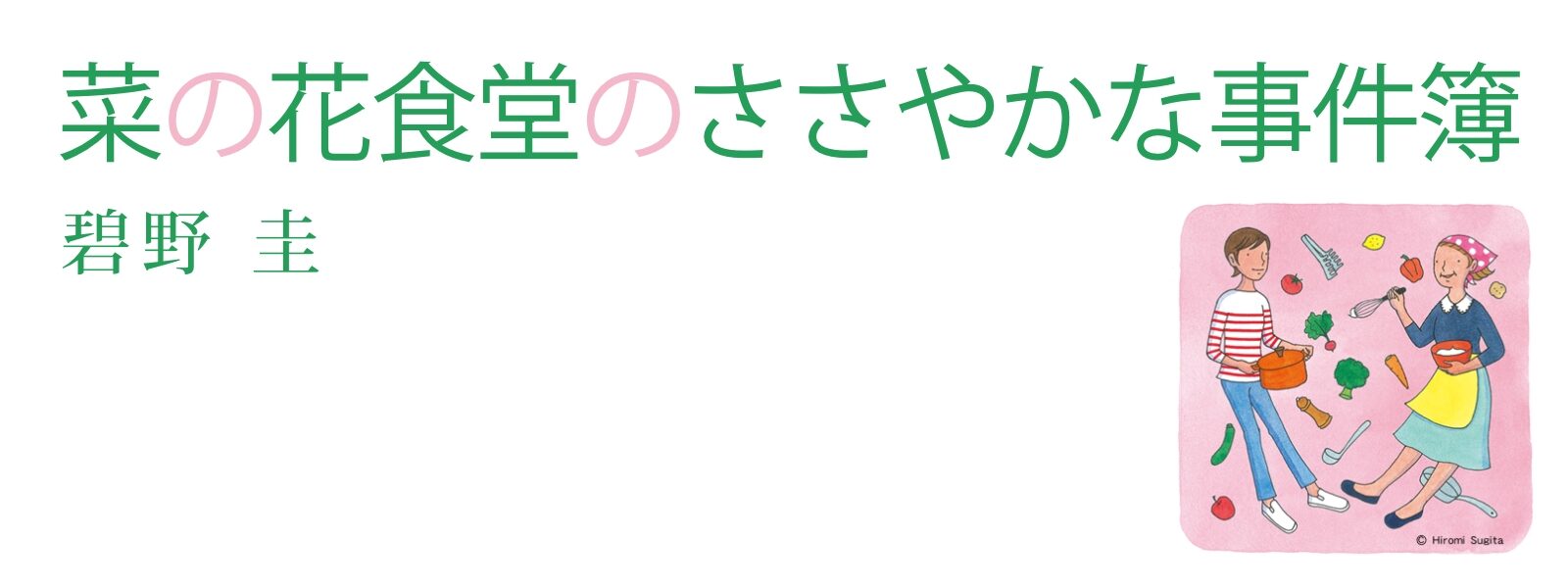蕎麦と思いやり 後編
創作蕎麦のレストランでランチを摂った後、私たちは店から歩いて一〇分ほどのところにある悟朗さんの自宅へと向かった。映画で話題になっている「国宝」の原作本を悟朗さんが持っているというので、貸してもらうことにしたのだ。私は(原作本を)読んでから(映画を)観る派なのだが、近所の本屋では文庫が売り切れていた。それで悟朗さんが貸してくれることになったのだ。農家道と呼ばれる通りを歩いて行くと、道路に面したところに野菜の無人販売がある。その横にあるのが悟朗さんの住むアパートだ。その奥には大家の保田さんの自宅がある。
「あれ、保田さんご夫婦がいる」
野菜の無人販売の辺りで、保田さんと奥さんが何か言い争っているようだ。ふたりとも興奮しているのが遠目でも見て取れる。
「どうしたんだろう。いつも仲良しご夫婦なのに」
私は思わずつぶやく。保田さんは菜の花食堂にいつも野菜を届けてくれるし、夫婦揃って食堂のお得意さまでもある。保田さんは少し口が悪いが、こころの温かい人だ。奥さんも輪を掛けていい人で、私も世話になっている。
そんなふたりがどうして喧嘩なんかしているんだろう。
「だから、そんなの私には関係ないってば」
「そこをまあ、なんとか」
「私だって暇じゃないんですよ。勝手に話を決めて来ないでよ」
そんな会話が聞こえてきた。
「こんにちは、保田さん。どうかしましたか?」
悟朗さんがふたりに声を掛ける。それを聞いて悟朗さんを認めた保田さんの奥さんの顔がぱっと明るくなった。
「聞いてよ、この人ったら、私が知らないうちに武蔵野うどんを一〇人分作るって話を決めてきちゃったんですよ」
「知ってますよ。うどんと蕎麦の頂上決戦をやるっていうんでしょ? 僕らも審査員として呼ばれていますから」
「あら、あんたたちも知ってるの。だったら話が早い」
保田さんの奥さんは、どうやらうどんを作るのが不満らしい。
「私は別に料理人でもなんでもないし、そんな私が作る武蔵野うどんを代表するみたいなこと、できませんよ。それに蕎麦を打つのは、本も出してるような有名な人らしいし」
「相手だって蕎麦打ちは趣味でやってるだけだよ。だからそんな引けをとるはずないよ」
「そうは言っても作ったものを比べられるのは嫌ですよ。一〇人分も作って挙句にそっちの方が美味かったとか言われるなんて、骨折り損じゃないですか」
「だけど、親戚の集まりではそれくらいよく作っていたじゃないか。親戚だってみんな『和子さんの作る武蔵野うどんがいちばんだ』って言ってたし」
「そんなの、身内の贔屓目ですよ。身内が褒めてくれたからって、それが特別美味い保証にはなりませんよ。なのに、靖子さんみたいなプロの料理人に審査されるなんて、私は嫌です。ほかの人を巻き込まず、あなたや守屋さんが自分で作ればいいじゃないですか」
保田さんの奥さんは本気で嫌がっているようだ。
「いや、奥さんのお料理は美味しいって思いますよ。何でも手際よく調理するし、特別な素材を使わなくてもちゃんと上手く調理する。奥さんの作るうどんだったら、僕も食べてみたいな」
保田さん夫妻は世話好きで、独身の悟朗さんがちゃんと栄養を摂れているか心配して、よく自宅に招いて食事を振る舞っている。農家だから野菜を使った料理をいろいろ知っているし、私も保田さんの奥さんにはたまに菜の花食堂のレシピについて、アドバイスを貰ったりしている。
「それは……悟朗ちゃんだったら、いつでも作ってあげるよ」
保田さんの奥さんは、少し表情を緩めた。愛情深い人なので、店子の悟朗さんのことも、実の息子のようにかわいがっているのだ。
「だったらさ、ひとり分作るも一〇人分作るも同じじゃないか。みんなだっておまえの作る武蔵野うどんを楽しみにしてるんだし」
「別に私が作らなくても、武蔵野うどんを専門に作っているお店があるじゃないですか。そっちで食べればいいでしょう?」
奥さんは頑なに拒む。
「そりゃ、まあ、そうだけど……」
「ですが、武蔵野うどんは代々そのご家庭で伝えられてきたものでしょ? それを受け継いでいる奥さんの味には、お店にない味わいがあると思います。私も、奥さんの作るうどんを食べてみたいです」
私も保田さんの味方をする。やっぱり蕎麦とうどんの頂上決戦を、私自身も楽しみにしているのだ。
「優希ちゃんまで。……そりゃ、あなたたちに振る舞うのは、こっちも楽しいことだけど」
和子さんはちょっと軟化してきた。すかさず保田さんが言う。
「ね、だからさ、この際みんなのための作ってよ。俺の顔を立てると思って」
保田さんの言葉を聞いて、たちまち和子さんの態度は硬化する。
「とは言っても、来週の日曜日なんでしょ。私だって予定がいろいろあるんですからね。あなたの勝手にはつきあえませんよ。じゃあ、悟朗さん、優希ちゃん、またね」
そう言って、保田さんの奥さんは奥の自宅の方へと引っ込んだ。その背中を三人で見送ると、保田さんが私たちに弁明する。
「まあ、あんなこと言ってるけど、根は世話好きだし、後でちゃんと説得するから心配しないで。でも、いつもはこういうイベントは好きなのに、どうしてあんなに怒っているんだろうな。今日は機嫌が悪かったのかな」
保田さんはわけがわからない、というように肩を竦めた。私はなんと返したらいいかわからず、あいまいに微笑んだ。
しかし、保田さんの奥さんの機嫌は直らなかった。
「どうしても嫌だって、うちの奥さんは言うんですよ。なんでそんなに意地になっているかわからない。順位を付けられることだって、普段なら面白そうって笑い飛ばすような性格なのに」
今日は保田さんが菜の花食堂に来て、ランチを食べていた。今日のメニューはカレー。甘口か辛口か選べるようになっている。特製サラダとコンソメスープがついている。カレーの時だけつけるスープで、保田さんはこのスープをカレーと同じくらい好き、と言っていた。
「今回はなぜか頑固になって、意地でも参加しない、みたいに言っている。なんでそんなに意地になるかな」
保田さんはそう言って愚痴る。食堂に来たのも、最近その件で夫婦間がぎぐしゃぐしているので、家にいたくなかったらしい。夫婦で農業をしているので、その状態でいると息が詰まる。しばしの逃避だ。
「あー、このコンソメやっぱり美味いわ。おかわりは……もらえないよね」
「えっと、あと五分しても誰も来なかったら、特別におかわりできますよ。ランチタイムも終わりですし、ひとり分くらいは余っていますから」
靖子先生がそう言った途端、カランコロンとドアベルが音を立てて、お客さまが入って来た。
「まだやってる?」
守屋さんだった。
「なんだ、おまえか。まずいところに来やがって」
「えっ、なんかあったのか?」
そう言いながら、守屋さんはカウンターの保田さんの隣に座った。
「ランチですね?」
私が聞くと、もちろん、というように守屋さんはうなずいだ。
「なんでもねえよ。タイミングの悪い奴め」
保田さんは口の中でぶつぶつ言っている。
「カレーは辛口で大丈夫ですよね?」
「もちろん。甘口なんて子どもしか食べないんだろう?」
守屋さんの問いに、先生が答える。
「そうでもないですよ。最近では辛い物を食べると口の中がぴりぴりするとか、痛くなるっていう人もいますからね。一種のアレルギーだと思いますが。男性でも甘口を求められる方もいますよ」
「そうなんだ。辛いものもアレルギーなんだ。なんでもアレルギーって、難しいね。俺らの子どもの頃にはアレルギーなんて子、いなかったのに、今じゃクラスに何人かはいるって言うしさ。日本人の体質が変わったのかね?」
守屋さんが言うと、保田さんも続ける。
「アレルギーで食べられないっていうけど、なかには食べたくないからアレルギーって言ってごまかすやつもいるんじゃないのかな? いまは贅沢になって偏食も増えてる気がするんだ」
「そうでもないですよ。深刻なアレルギーの場合は、命に係わることもありますからね。本人にとっては大きな問題ですよ。おふたりともアレルギーでないことを、親に感謝しなきゃいけませんね」
そう言いながら、靖子先生はランチの載ったお盆を守屋さんの前に出した。
「うわ、うまそう」
「それから、こちら」
靖子先生はスープが半分くらい入ったマグカップを、保田さんに手渡した。
「お、いいの? ありがとう」
「いいなあ。俺もおかわりほしいな」
そう言いながら、守屋さんはカレーの皿にスプーンをつける。
「ところで、頂上決戦の方、蕎麦の先生は大丈夫そう?」
「もちろん。来週の日曜には先約があったそうだけど、そっちをキャンセルしてこちらに来てくれることになっている。先生も気合が入っているよ」
「そうか……」
「そっちの奥さんはどう?」
守屋さんが保田さんに尋ねる。
「それがさ、出るのは嫌だって言い出して、困っているんだ」
「ええ? どうして」
「なんか、勝手に予定決められたとか、そんな偉い先生と比べたくないとか、ぶつぶつ言っててさ。訳がわからないんだ。最近では武蔵野うどんの本物を食べたことがない人も増えているから、そういう人にも食べさせてあげたいね、と言っていたから、てっきり喜んで参加すると思ったのに」
「ほんと、女はよくわからないよな。うちの嫁もせっかくの機会だから立ち合えって言ったんだけど、私なんかよりほかの人の方がいいんじゃないの、とか言うしさ。こっちはせっかく師匠の打ち立ての蕎麦を嫁にも食べてもらいたいと思っているのに」
「こっちもかみさんの腕前をみんなに知ってもらいたいって思ってるんだ。かみさんの武蔵野うどんはどこに出しても恥ずかしくないからね」
「女はこっちの気持ちをわかっていないっていうかさ」
「気分でこっちの言うことに反対してきたりするから」
「まったく女はめんどうだ」
「おやおや、それは聞き捨てなりませんね」
カウンターの中から靖子先生が口を挟む。
「どういうこと?」
保田さんが聞き返す。
「それぞれ嫌だという理由がちゃんとあるのかもしれませんよ。守屋さんの奥さまには、『無理に食べなくてもいい。見に来るだけでもいいから』と言ってみたらいいと思います。『師匠が来るから挨拶だけでもしてやってくれ』って」
「それだけ?」
守屋さんは半信半疑だ。
「それから保田さんの奥さんのことは、私もよく知ってますからね。気分で意見を変えるような人じゃありません」
靖子先生は保田さんの奥さんの和子さんとはママ友だ。長男の勝くんが、保田さんの息子の尚人くんと同級生だったのだ。
「じゃあ、何か理由があるっていうの?」
「そうだと思うわ」
「じゃあ、ちゃんと言えばいいのに。それとも言えない訳でもあるの?」
「言えないというか、保田さんに気づいてほしいんじゃないかしら」
「俺が気づく?」
「たぶん和子さんにとっては大事な事なんですよ」
「だったら、なおのことちゃんと説明すればいいのに」
保田さんは不満げに唇を着き出す。
「大事なことだから、忘れている保田さんに腹を立ててるんですよ」
「大事なことって、何?」
「私よりも保田さんの方が知ってるんじゃないですか?」
「わからない。なんのヒントもないし」
保田さんはふてくされたように言う。
「来週の日曜日は七月一三日ですね。何か覚えはないですか?」
「七月一三日? 覚えなんかないね」
「じゃあ去年のこの日は何をしていました?」
「去年のことなんて覚えてないよ」
「スマホを見れば思い出すんじゃないですか?」
「スマホ? スケジュール帳は使っているけど、去年のことなんて残っているのかな?」
そう言いながら、保田さんはスマホを取り出し、スケジュール表を開いて過去をさかのぼる。
「えっと、五月、三月……ああ、去年のも残っているわ。えっと、七月……一三日、三回忌。えっ、三回忌ってなんだっけ。……そうだ、和子の母親の三回忌だったんだ」
保田さんはやってしまった、と言う顔をした。
「そうか、なんで俺は忘れていたんだろ」
「つまり来週の日曜日は和子さんのおかあさまの命日ということなんですね。本当ならお墓参りに行って静かに過ごそうと和子さんは思っていたんじゃないでしょうか。和子さんにとっては大事な日ですものね」
「その通り。あいつは母親思いだったからな」
保田さんは頭をぼりぼりと掻いた。思い出さなかった自分を恥じているのかもしれない。義理の母だから命日なんてどうでもいいのだろう、と奥さんに責められても仕方ないのだ。
「三回忌といったら、今年はまだ三年目。和子さんにとってはつい最近のこと。なのに保田さんがすっかり忘れて、人の集まるイベントに参加しろなんて言われたら、そりゃ腹も立つでしょうね」
「だったら言えばいいのに。すぐに言ってくれれば日にちも変更できたのに」
「いまさら変更はできないよ。うちの師匠はわざわざ予定を変更して、その日に合わせてくれたんだし」
守屋さんが言う。わかってる、というように保田さんはうなずく。
「どうすればいいんだろ」
途方に暮れたように、保田さんは力ない声で言う。
「まずは忘れていたことを和子さんに謝ること。誠心誠意謝れば、和子さんも許してくれますよ。それからね」
靖子先生は保田さんにいくつかアドバイスを授けた。保田さんは神妙にうん、うん、と聞いていた。
「では、深大寺蕎麦と武蔵野うどんの手打ち試食会を開催します」
守屋さんがみんなにそう宣言した。場所は菜の花食堂の別棟の料理教室の部屋である。結局予定通りイベントは開催されることになった。
「うどんを打ってくれるのは保田和子さん。地元でうどん打ちの腕前は一目置かれる存在です。蕎麦を打ってくれるのは江戸蕎麦愛好会の会長の原浩一さん」
だが「頂上決戦」と銘打つのはやめて、手打ち試食会に変更した。食べ物で順位付けするのはよくない、というのは靖子先生の意見だった。
「おいしいという事に絶対はない。自分のよい記憶と結びついていれば特別美味しく感じるし、その逆もある。自分が好みの味と思わなくても、それを好きな人もいる。だから美味しいに順位をつけるのはおかしいと思うのよ。それぞれが自分の美味しいという想いを大事にすればいい」
靖子先生の意見に、和子さんも賛成したそうだ。
「私が作るものが武蔵野うどんの最上というわけではないし、それで判断されたら武蔵野うどんに申し訳ない」
守屋さんの師匠である蕎麦打ちの原さんもそれに同意を示した。
「蕎麦には蕎麦の良さがあるし、うどんにはうどんの良さがある。双方の良さを伝える会の方がいいでしょう」
というのが原さんの意見だった。原さんは七〇歳くらいの年齢で小柄で目元も優しく、見るからに温厚そうな人だ。競ったり争ったりするのはもともと好きではないのだろう。原さんに言われると、弟子である守屋さんも反対はできない。
その結果、審査は無しにして、多くの人に打ち立ての蕎麦とうどんを食べてもらおうということになった。お店のポスターでそれを告知し、村田さんや杉本さん、八木さんといった常連さんも七、八人集まってくれた。先生のお手伝いをしている小学生の奏太くんも、今日はおかあさんと一緒に参加している。靖子先生、香奈さんと香奈さんの彼氏、私と悟朗さん、それに守屋さんの奥さまも見守っている。
「では始めてください」
司会進行の守屋さんがそう声を掛けると、ふたりは作業を開始する。みんなはそれぞれの周りに立って、作業を見学する。
「まずは蕎麦粉をふるいに掛けて、水回しの作業に掛かります」
原さんは説明しながら慣れた手つきでこね鉢の上でふるいに掛ける。
「この粉は繋ぎはどれくらい入っているのですか?」
「深大寺蕎麦を、という注文でしたが、深大寺蕎麦には作り方に明確な定義はありません。深大寺周辺で採れた蕎麦の実と湧き水を使って作った蕎麦ということ、白っぽくて甘味が感じられるということなので、更科粉を使っていたのかもしれません。いまは深大寺近辺で採れた蕎麦粉を入手するのは難しいので、北海道産の粉を取り寄せて使います。ですが、挽きたてのものを購入しています。繋ぎの割合も現存する深大寺蕎麦のお店ではそれぞれ異なりますが、二八から一〇割が多いようです。一〇割蕎麦となると切れやすいし、ちょっと工夫も必要ですから、今日は二八蕎麦、つまり蕎麦粉八に対して繋ぎ二、つまり小麦粉を二割入れています」
人前で蕎麦を打つことも多いらしく、原さんはよどみなく説明する。一方で和子さんは緊張しているようだ。
「まずは塩水の準備。ボウルに水を入れて塩を溶かします」
「えっと水は何㏄ですか?」
メモを取りながら聞いている八木さんが質問した。
「だいたい四〇〇くらい。湿度にもよるけど、今日はちょっと湿度が高めだからもう少し少なくてもいいかも。えっと、捏ねる時の感触で水の量は変えるので」
「塩の量は?」
「えっと、水が四〇〇ならとりあえず四〇g入れます」
「小麦の種類は?」
「中力粉ですね。国産小麦を使っています」
保田さんは和子さんに謝罪し、昨日ふたりでお墓参りに行って来たそうだ。青梅にお墓があるので半日がかりだったらしいが、それで和子さんも機嫌を直した。今日の試食会にも喜んで参加してくれている。
「輸入ものと違いがあるんですか?」
「うどんの出来には関係ないけど、なるべく国産のものを使うようにしてるんですよ。うちも農家だから、生産者を応援したいからね」
そんな具合に、それぞれ解説しながら麺を作っている。お客さんはそれぞれ好きな方を見ている。原さんの説明にも熱が入る。
「粉に水を加えて捏ねることを水回しといいます。これが蕎麦打ちで要になります。粉に均等に水を分散することで美味しく、照りのある蕎麦に仕上がります。蕎麦打ちの間では木鉢つまり水回し三年、延し三ヶ月、切り三日という言葉があるくらい、上手に水回しができるようになるのは難しい」
そう解説しながら迷いのない手つきで粉に水を加え、両手で混ぜ合わせる。水が混ざると粉はほろほろと小さな粒状になっていく。そうして粉に十分水が行き渡り、細かいほろほろの粒がたくさんできたところで、全体を集めてひとつの塊にまとめる。その繊細な手つきに、思わず見とれてしまう。
「これを捏ねながら空気を抜いていきます。捏ねるとコシが生まれますが、捏ねすぎるとまとまりにくくなるので注意が必要です」
かたや、和子さんはもっとダイナミックだ。小麦粉を大きなボウルに入れ、二回に分けて塩水を入れる。
「専用の鉢があるといいんだけど、たまにしか出番がないし、家にあるボウルで十分。粉と塩水が混ざったかどうかは、捏ねた時の感触でわかります。塩水が足りないと思ったら、少しづつ加えます。うん、これくらい。……確認したい人がいれば、触ってみてください」
和子さんがそう言って薄いビニールの手袋を差し出す。何人かがそれを着けて塊を触る。私も触ってみた。弾力があり、思ったより硬い。
「うどん作りのコツと言ったら、この塩水の量と捏ね。これをビニールで挟んで、上から足で踏みます」
「えっ、足で?」
誰かが驚きの声をあげる。私もびっくりした。そういえば、葡萄酒を作る時も、葡萄を足で踏んでいたと聞いたことがある。原始的だけど、確実なやり方なのかもしれない。
「ええ。絶対に足に触れないように、厚手のビニールを使います。米を入れてる袋を取っておいて、その両端を切って作ると便利ですよ」
そう言いながら和子さんは下にビニールを敷き、うどんの生地を置いてその上からまたビニールを置く。厚手のビニールで生地を挟んだ形になる。
「これで生地が外に出ることはないので、上から足で踏みます」
和子さんはスリッパを脱ぐとビニールの上から踏みつける。
「ここでしっかり踏むことが大事です。どなたかやってみますか?」
なるほど、和子さんの方は見るだけでなく参加型だ。原さんのような巧みな解説ではないけど、これはこれで面白い。
「僕、やってみたい」
奏太くんが手を挙げる。
「はい。では交替」
奏太くんは身長が一四〇センチくらい。小柄で痩せているからちゃんと捏ねられるだろうか、と思ったが、和子さんは奏太くんの好奇心を大事にしたいのだろう。
奏太くんはスリッパを脱ぎ、ビニールの上で足をその場でランニングするように素早く上下する。
「あら上手」
和子さんはにこにことその様子を見守っている。
「うちの息子も昔はよくそうやって手伝ってくれました。最近はあまりやってくれないけど」
奏太くんはしばらく足を踏みしめていたが、すぐに「疲れた」と足を止めた。
「お疲れさま。では、ほかにやってみたい方はいますか?」
「じゃあ、私が」
守屋さんの奥さまが手を挙げて、奏太くんと交替した。
そうしている間にも、原さんは蕎麦の作業を進めている。
「こうして丸くまとめた生地を、麺棒を使って伸ばします。地方では丸のしと言うやり方です。このまま薄く丸く伸ばします。大きな円に伸ばした生地を、端から麺棒に巻き、四〇~五〇㎝ずつ巻き伸ばして薄くしていくやり方をします。そうして薄い大きな円形の生地にするのです。これは広い場所が必要なので座位で行います」
原さんのすぐ前には杉本さんが立ち、原さんの言葉を一生懸命メモに取っている。やはり杉本さんも男性だから蕎麦に興味があるのだろうか。
「一方江戸時代に確立された江戸打ちは、一度丸くまとめた生地を麺棒で薄く伸ばし、正方形になるように形を整えます。これを四つ出しと言います。その一方の辺を伸ばし、さらに薄くしていきます。こちらの方が場所を取りませんし、深大寺蕎麦も江戸打ちだったと思うので、今日はそれでやってみます」
こういう蘊蓄が蕎麦好きの男性にハマるのだろう。杉本さんだけでなく保田さん、香奈さんの彼氏の浩史さん、それに悟朗さんといった男性陣が原さんの話に耳を傾けている。もっとも保田さんは自分の妻が教えているのを見るのが気恥ずかしくて、蕎麦の方にいるのかもしれない。
一方で伊勢うどん作りの観客は女性が多く、楽し気な笑い声が聞こえる。交替で生地を踏んでいるのだ。
「はい、その辺で大丈夫です。で、これを一時間くらい寝かせます。いつもはその間につけ汁を作るのですが、今日は時間がないので事前に寝かせたものを用意しました」
そうして和子さんは、棚の中から寝かせていた生地を取り出す。
「そうしてこれを伸ばします。あまり難しく考えることはありません。こうして均等になるように端から少しづつ伸ばします」
そう言いながら、和子さんは器用に麺棒を動かす。
「こちらは終わりましたが、茹でるのはそちらに合わせますか?」
原さんが靖子先生に尋ねる。もう蕎麦を切る作業は終わっている。
しまった、和子さんの方に見惚れて、切るところを見損ねてしまった、と私は内心思う。両方を全部見るのは難しい。
「そうですね。茹でるのもこちらの方が時間が掛かりますから、少し待ってもらえますか? こちらが茹で上がる頃に、そちらを茹で始めるくらいでちょうどいいと思います」
「わかりました。では待ってる間に、江戸で蕎麦が庶民の間に広がって行った理由について、少しお話ししましょうか」
そうして蕎麦の方では座学が始まる。その間に和子さんは生地を伸ばしてじゃばらに折り、端から細く切って行く。
「さて、これをたっぷりのお湯で茹でます。茹でるのは一二分くらい。その間につけ汁を作ります。豚バラ肉とネギとを大きく切り、炒めてから出汁、醤油、砂糖、みりん、酒で味付けします」
「分量はどれくらい?」
「あ、一応レシピを書いて用意しましたので、それをお配りしますね」
私は蕎麦の方をちらりと見た。原さんの熱のこもった話に、男性陣が聞きほれているようだ。
そうしてうどんが茹で上がり、水で締める頃に蕎麦の方も茹で始めた。こちらの茹で時間は一,二分だろうか。あっという間に茹で上がった。
「では、完成しましたので、試食を始めます」
靖子先生がそう言って、蕎麦の方に靖子先生と私、うどんの方には香奈さんと常連の村田さんがサポートについて料理を器に盛り、お客さまにお分けする。二種類食してもらうので、普通より少なめに盛っている。
「うどんと蕎麦、皆さんに試食していただける量は十分にありますので、順番にとってくださいね」
一通り行き渡ると、それぞれ食べ始める。原さんも和子さんもそれに加わる。私もまず蕎麦を食べてみた。蕎麦は紙皿に小盛りになっており、蕎麦つゆは紙コップに少量入っている。
「できれば最初は何もつけずに召し上がってください。それから、岩塩を用意しましたのでまずはそちらで。それから蕎麦つゆを試してみてください」
「綺麗ですね」
私は皿に盛られた蕎麦を見て思わず言った。艶やかな薄いグレーの麺はまるで機械で切ったように細く、太さも均一だ。これが包丁で切ったものとは信じられない。
「ありがとうございます」
原さんははにかんだように微笑む。
蕎麦を口に含む。ほのかな香りと舌触り。いままで食べてきた蕎麦とは明らかに違う。丁寧に作られた蕎麦特有の歯ごたえと微かな蕎麦の香り。べたっとしない、一本一本の存在が立っている。甘いとか辛いとか舌で味わうというより、口の中で蕎麦の存在感を楽しむ感じだ。
ああ、確かにこれは打ち立てだからこそ味わえるものだ。
私は感動していた。蕎麦にこだわる人たちの気持ちが少しわかる気がした。
みんなは蕎麦とうどん、好きな方に集まって、和気あいあいと談笑しながら食べている。原さんや和子さんに質問している人もいる。蕎麦を食べ終わるとうどん、というように、順番に両方を楽しんでいる。「美味しい」という声があちこちから聞こえる。
大盛況だ。このイベントは成功だ、と私は思う。
蕎麦を食べ終わったので、今度は武蔵野うどんの方を味わってみる。こちらは腰の強いしっかりしたうどんを水で締めているのでうどん自体は冷たい。それを温かい汁で味わう。豚バラ肉を使った濃厚な旨味の汁に、シンプルで腰のあるうどんがよく似合う。普通のうどんだったら、つけ汁の濃厚さに負けてしまうかもしれない。素朴で、食べると力が湧くようなうどんだ。蕎麦とどちらがなどと比べる必要はない。これはこれで美味しいのだから。
「僕も手伝ったおうどん、美味しいねー」
奏太くんが得意げにおかあさんに言っている。おかあさんは「そうね」といいながらにこにこ笑っている。
「君もこっちで食べたら?」
守屋さんが奥さんを蕎麦のテーブルの方に誘う。
「じゃあ、この大盛りのやつを」
奥さんに差し出そうとした皿を、靖子先生が止める。
「ダメですよ、無理強いは。本人が食べられる量にしておかないと」
「でも」
守屋さんは不満そうだ。そもそもこのイベントを開いた目的のひとつが、自分の奥さんに師匠の手打ち蕎麦を食べさせたい、それでもっと蕎麦を好きになってほしい、というものだったから。
「これくらいにしておいた方がいいんじゃないですか?」
靖子先生はほんの少しの量の蕎麦の皿を、守屋さんの奥さんに差し出す。
「ありがとうございます」
奥さんがそれを受け取るのを、守屋さんは不満げに見ている。
「せっかく師匠が打ってくださったのに」
「そうは言っても、体質がありますからね。ね、奥さん」
靖子先生は彼女の方に優しい目を向ける。
「え、ええ」
奥さんは五〇代半ばらしいが、大きな目が印象的なかわいらしい感じの女性だ。
「蕎麦を食べると、何か身体に不調が現れるんでしょ?」
靖子先生がふいに奥さんに聞く。
「えっ、どうしてそれを」
「どういうことだ?」
守屋さんが奥さんに尋ねる。
「不調というほどのものではないけど、実は蕎麦を食べると口の中が痒くなるんです。それであまり蕎麦を食べることに気が進まなくて」
「それって?」
守屋さんが靖子先生に尋ねる。靖子先生は重々しい口調で言う。
「軽度の蕎麦アレルギーです」
「えっ、そうだったんですか?」
言い出した守屋さんの奥さんの方が、守屋さんよりびっくりしている。
「これもアレルギーの一種だったんですね。知らなかった」
「重度の蕎麦アレルギーは呼吸困難やアナフィラキーショックを起こすことが知られています。だから、はっきり蕎麦アレルギーと診断される人は気を付けているけど、軽度の場合は気が付かないこともあります。口の中がぴりぴりしたり、くしゃみが出たり」
「ああ、そうです。そんな感じ」
うんうん、と奥さんはうなずく。
「なんでいままで黙ってたんだ」
「だってあなたは蕎麦が大好きなのに、私が蕎麦を食べると具合悪くなるなんて言えないじゃない」
「そんなこと」
守屋さんは困ったような、戸惑ったような表情をしている。
「それにさほど大した症状じゃないし、少し我慢すれば食べられないことはないから」
奥さんは弁明するように言う。
「そういうことだと思いましたよ。守屋さんと奥さんは仲が良いし、お互い楽しみを共有したいタイプ。なのに奥さんがたまにしか蕎麦を食べないというのは、旦那さんに気を遣って我慢しているんだろうと思いました」
靖子先生が言うと、守屋さんの奥さまは感心したように言う。
「噂通り下河辺さんはミス・マープルみたいですね。そんなふうに言い当てられるとは思いませんでした。蕎麦の味自体は嫌いじゃないんですよ。だから、この人が強く勧める時には食べるようにしているんですけどね」
「アレルギーは気を付けた方がいいですよ。無理強いもいけない」
口を挟んだのは原さんだ。
「私の知り合いの蕎麦好きにもアレルギーがいましてね。でも、蕎麦好きだし軽度だからと我々と一緒になって食べたり、蕎麦打ちにも参加していたんです。そうしたら蕎麦打ちの会場で突然呼吸困難になり、救急車で運ばれる騒ぎになった。あとでわかったのは、蕎麦アレルギーはそれまで軽度でも突然重症化することがあるってことです。昨日まで平気でも今日はダメかもしれない。だから、蕎麦を食べることより身体を大事にしてほしい」
「原さん……」
守屋さんは絶句している。奥さんは持っていた蕎麦の皿をそっとテーブルに戻した。
「すみません、せっかくのイベントに水を差すようなことになって」
奥さんは原さんに頭を下げる。
「いえ、いいんですよ。逆にこれがきっかけで奥さんのアレルギーのことを旦那さんにもわかってもらえたんだから、よかったと思います」
原さんは鷹揚に言う。やはり師匠と慕われるだけあって、懐深い人なんだな、と私は思った。
守屋さんは師匠の言葉を噛み締めるように、何度もうなずいていた。
その翌週、また守屋さんが菜の花食堂に姿を現した。今日はもうランチタイムが終わってティータイムの時間だ。珈琲を注文すると、守屋さんは神妙な顔で言う。
「イベントの時にはお世話になりました」
「いえいえ、みんな喜んでましたし、打ち立てのうどんも蕎麦も両方美味しかったです。実演を見せていただけたのも興味深かったですよ」
靖子先生に続いて香奈さんも言う。
「イベントとしては大成功だったんじゃないですか? あれを見て浩史も蕎麦打ちやってみようかな、って言ってましたよ。もし原さんが蕎麦打ちの教室をやっているなら、参加したいと言ってました」
「そうか、それは嬉しいな。蕎麦好きを増やすことができたなら、師匠もここでイベントをやった甲斐がある」
安堵したように守屋さんの眉尻が下がる。
「私も武蔵野うどんを作ってみたくなりました。蕎麦よりも簡単にできそうな気がするし」
私もちょっとその気になっている。やっぱり打ち立ては美味しいし、友だちや家族に振る舞ったら楽しいだろう。
「実はうちの妻もそう言ってるんですよ。蕎麦は無理だけど、うどんなら大丈夫。打ち立てをみんなに食べさせたいって」
「そういう反響が多かったので、和子さんは武蔵野うどん作りの教室を始めるそうですね。武蔵野うどんを広めたいという想いがあるので、喜んでいるそうですよ」
それは楽しそうだ。和子さんが先生なら私も参加したい。地元の名物を作れるようになったら、私もこの地により溶け込んだ、と思えるかもしれない。
「それはよかった。でもちょっと気持ちは複雑ですよ。ほんとは蕎麦を嫁に食べさせたかったのに、まさか蕎麦がダメだとは。それに長いこと気づかなかった自分も情けない」
守屋さんはしおたれている。イベントをやった目的にも、奥さんに師匠の作った蕎麦を食べさせたい、という想いがあったはずだ。
「まあ、それは仕方ないですよ。奥さまも守屋さんには知られないように、と思っていたのでしょうから。お互いよかれ、と思ってやってたことが行き違っていたんですね」
「俺も蕎麦を食べるのをやめた方がいいのかな」
守屋さんは真面目な顔で言う。愛妻家なので、妻の為に自分も何かしなければと思ったのだろう。
「そこまですることはないと思いますよ」
「でも、嫁が食べられないものを、俺だけ楽しむというのもね、どうかと思うんだ」
「いえ、それは奥さんが喜ばないと思いますよ」
靖子先生はきっぱり言った。
「そうかな」
「江戸蕎麦のお仲間とのおつきあいは守屋さんにとって大事なものだったんでしょう? 守屋さんがそうやって楽しんでいることを、奥さまも喜んでいると思います。だからこそ蕎麦が苦手だと言い出さなかったんですよ。守屋さんの楽しみに水を差したくなかったから」
「そうか。じゃあ、いままで通り蕎麦仲間とつきあってもいいのかな」
「いいですとも。奥さまだって武蔵野うどん作りに参加して、新しいお友だちができるかもしれませんからね。それぞれ楽しめばいいんですよ」
それを聞いて守屋さんはようやくほっとしたように微笑んだ。
「珈琲のおかわりはいかがですか?」
私は守屋さんに聞いた。守屋さんのカップがいつの間にか空になっていた。
「いただきます」
私は守屋さんのカップに珈琲を注いだ。
守屋さんはカップを持つと、味わうようにゆっくりと口に含んだ。
愛知県生まれ。東京学芸大学教育学部卒業。フリーライター、出版社勤務を経て、2006年『辞めない理由』で作家としてデビュー。
『菜の花食堂のささやかな事件簿』シリーズのほか、ベストセラーとなりドラマ化された『書店ガール』シリーズ、『凛として弓を引く』シリーズ、『スケートボーイズ』『駒子さんは出世なんてしたくなかった』『書店員と二つの罪』『レイアウトは期日までに』等、多数の著書がある。
伝統的な日本の食文化への興味から、江戸東京野菜コンシェルジュと江戸ソバリエの資格を取得。