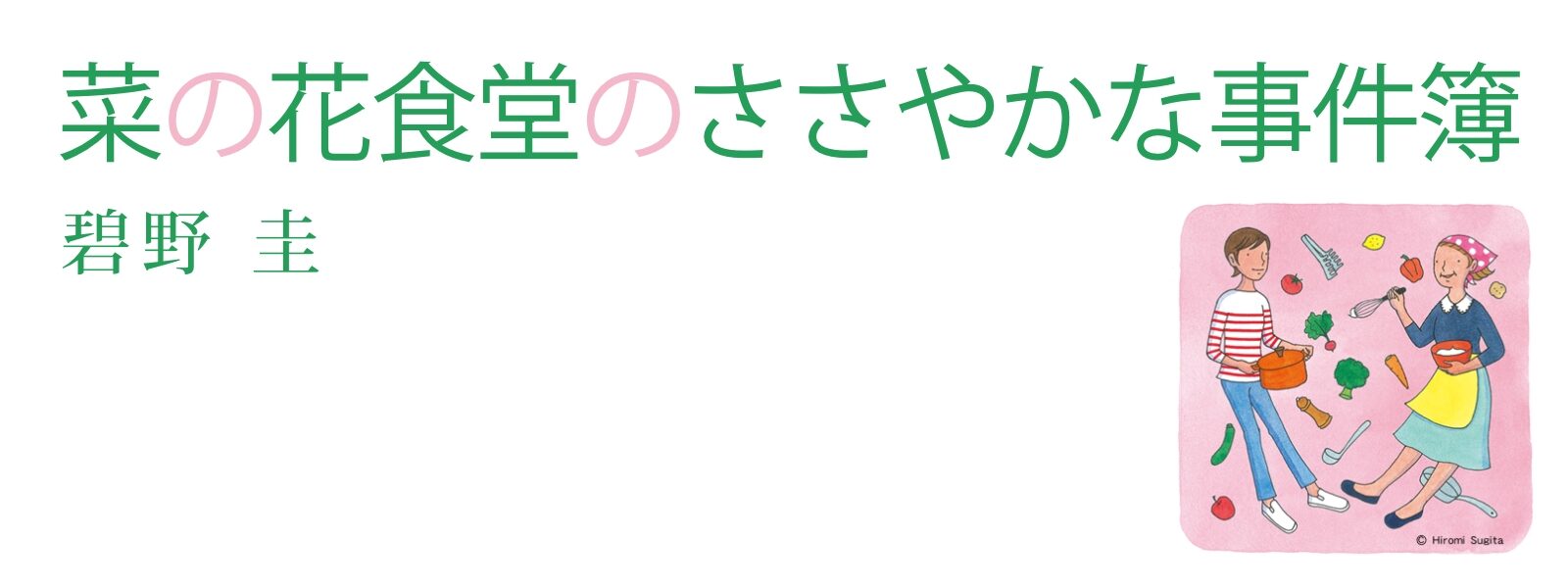栗は告発する 前編
檀上に審査員三人が立った。
「では、審査員の皆さまをご紹介しましょう。右から、上田和弘さん。上田さんは地元では知らない人はいない名店スイーツ上田のオーナーシェフであり、製菓学校の講師もされています。今日の審査にはぴったりの人物と言えましょう」
司会を務める商工会議所の守屋正一さんが紹介すると、上田さんは満足げな顔をしながら軽くお辞儀した。ちょっと神経質そうな目元をしている初老の男性だ。
「次は、長く地元の小学校で調理師を務め、定年退職後は食育の活動をされている川上真悠子さん。半世紀近く子どもの食事に関わってこられた方です。家族の食という視点から審査に加わってもらうことにしました」
やさしそうな白髪のふっくらした女性が、にこにこしながら軽く頭を下げる。
今日は商工会主催のイベントで、栗を使ったオリジナルレシピの審査会だ。栗はかつてこの地の名物だった。江戸時代に幕府に献上する栗を植える御栗林があり、数千本の栗の木が植えられていたそうだ。いまはもう農地も少ないので栗の木もほとんどみられないが、栗が名産品だった歴史を大事にしていこうということで、こういうイベントが開かれている。
「三人目は菜の花食堂で働いている館林優希さん。菜の花食堂は野川近くで三〇年以上続く人気店。館林さんはそこで瓶詰の商品開発を手掛けられました。その瓶詰は近年市内の新しい名物になっていますので、ご存じの方も多いでしょう。館林さんは料理のプロ。プロの立場からのご意見を伺えればと思います」
こんな紹介をされるとこそばゆい気がするが、私のことを精一杯権威付けしようという守田さんの思いやりだ。間違ってはいない。私はなるべく口角を上げてお辞儀をしたが、困惑した顔をしていたと思う。観客席にいる悟朗さんが私の方を見ながら「がんばれ」と言うように、小さく右手を握るガッツポーズをした。
「みなさん、栗は馴染みのある食材だと思います。そのまま食べても料理に使っても美味しいし、甘味があるので和菓子でも洋菓子でも人気があります。ポテンシャルの高い食材ですから、まだまだ可能性はあると思うのです。なので今回はオリジナリティに重きを置き、新しい栗のレシピを市民の皆さんと考案していきたいと思います」
会場からぱちぱちとまばらな拍手が起こる。会場には三〇人くらいいるだろうか。場所は市の中心地にある商工会議所の小ホールだ。会議室として使われることもある。
「既に発表されているように、今回優勝したレシピは市報で紹介されることになっています。それだけでなくこれをもっとたくさんの人に味わってもらおうということで、市内の小学校の学校給食で提供しよう、という事が決まりました!」
そうだったんだ、と私はびっくりした。商工会の小さなイベントだと思っていたけど、意外と広がりのあるものになっている。
「市長も大変このイベントに乗り気で、いまは仕事で遅れていますが、表彰式までにはこちらにみえることになっています。優勝者は市長の方からトロフィーを手渡してもらうことになります」
守屋さんは得意げだ。市長といっても住人が十二万程度の小さな市だから、そんなに遠い人ではない。料理教室の生徒さんのひとりは、子どもの保育園のパパ友だと言っていた。実際子どもを自転車に乗せて野川の土手を走っている姿を、私も見た事がある。市民と近い関係にあるから、こういう集まりにもよく顔を出すのだ。
「そんなわけなので、審査員の皆さまも、子どもたちにも食べさせたいと思うような素敵なレシピをしっかり選んでください」
私とほかのふたりの審査員も、守屋さんに軽く頭を下げた。
思ったよりちゃんとしたコンテストなんだな。キャリアのあるほかのふたりの審査員に比べて自分は若く、未熟だ。自分なんかが審査してもいいのだろうか、と思う。
本当はここにいるのは私ではなかった。靖子先生が審査員をするはずだった。私は靖子先生の代理だ。しかし、先生に急用ができてしまったのだ。
それは一昨日のこと。先生はスマホに届いたメールを見ると、沈んだ声で言う。
「母の従妹が亡くなったわ」
「それは……ご愁傷さまです」
母の従妹というのは、関係性として近いのだろうか、と思いながら私は言う。
「もう九二歳だから、大往生ではあるのだけど、母が大変お世話になった方だから、葬儀には参加しなきゃ」
ちょうどランチタイムが終わり、後片付けをしているところだった。
「それはぜひ行ってください。お店は私たちでなんとかしますから」
「ありがとう。ただ、場所がね」
「どちらなんですか?」
「京都。明日お通夜で明後日がお葬式」
京都は先生の出身地だ。親戚はそちらの方に多いのだろう。
「では、今晩出発して、戻りは明後日の夜になりますか?」
私が尋ねると、先生は言う。
「できればそうしたいのだけど」
「明日のランチなら、私と優希さんのふたりで大丈夫です。メニューも決まっているし。明後日は定休日ですし」
香奈さんが言う。先生が病気で休まれた時も、ふたりで乗り切った。一日くらいならなんとかなると思う。
「ありがとう。だけど、明後日の予定がね」
先生は浮かぬ顔だ。それで私は思い出した。
「明後日っていうと、レシピコンテストですか?」
先生がその日審査員をすることは、私たちも知っていた。常連である商工会議所の守屋さんに頼まれたのだ。
「そうなの。困ったわ」
「仕方ないですよ。葬儀の日にちはこちらで選べるものではありませんし」
「そうね。守屋さんに連絡して、欠席にさせてもらうしかないわね」
先生が電話するとしばらく揉めているようだった。それで電話では埒が明かないと思ったのか、守屋さんは直接お店にやってきた。
「靖子さん、本当にダメなの? なんとかならない?」
「私もできれば審査員をやりたいのですが、こればかりはどうしようもなくて。本当に申し訳ありません」
靖子先生は頭を下げると、守屋さんは困ったように頭を掻いた。
「いや、靖子さんが抜けると痛手だ。どうしようかなあ」
「私のほかにも立派な審査員がふたりいるじゃないですか」
「そのふたりがね、問題なんだ」
「どういうことですか?」
「実は審査員をお願いしてからわかったんだけど、ほかのふたり、上田さんと川上さんはあまり仲が良くないらしい。数年前、川上さんが食育の講演会で『子どもにはケーキはなるべく食べさせない方がいい。市販のケーキは砂糖と油脂が多すぎる』と発言したんだよ。おやつもなるべく手作りをと提唱されている方なので、つい口が滑ったんだと思う。でも、それを聞きつけた上田さんが『営業妨害だ』と怒って抗議をしたんだ」
「まあ、そんなことが」
靖子先生は目を丸くする。先生は噂話には疎いので、知らなかったのだろう。
「結局川上さんが『言い過ぎました。誕生日やクリスマスなど特別な時に市販のケーキを食べるのは悪いことじゃないし、私も楽しみにしています』と謝ったんだけど、上田さんは意固地な職人気質だし、根に持つタイプだからね。謝罪も上から目線だ、と不満に思ったらしい。でも、そういう事情を俺は知らなくてね。食育は商工会とはあまり関係ないからねえ。それでふたりをセッティングしてしまった」
「それはちょっと面倒ですね」
人間関係は計算通りにはいかない。それぞれのスペシャリストと思って選んだふたりがそういう関係性とは、守屋さんも思ってもみなかっただろう。
「靖子さんが入ってくれれば緩衝材になったくれると思ったんだ。ふたりともおとなだから、さすがに第三者がいるところでは喧嘩したりしないと思うし、靖子さんならうまくあのふたりも扱ってくれるだろうしね」
「そんな重責があったんですね」
靖子先生は困ったような顔をしている。でも、守屋さんが言うのもわかる。靖子先生なら、ふたりが対立しないようにうまく誘導してくれるだろう。
「ほんとに、出席するのは難しい?」
守屋さんがすがるような目で先生を見る。
「ごめんなさい。今回ばかりはどうしても」
「困ったな。明後日のことだから、代理を立てるのも難しいし。……あ、そうだ。靖子さんがダメなら、優希ちゃんか香奈ちゃんが出られないかな?」
「えーっ。そんな無茶な」
私は思わず言う。靖子先生の代理なんて務まるわけがない。まして、そんな難しい関係のふたりの間に割って入るなんて無理だ。
「私は無理です」
香奈さんはきっぱりと言い切る。
「日曜日、私は予定があるので」
「予定?」
「婚約者の両親との顔合わせがあるんです」
これには文句のつけようもない。
「ああ、そうか。それは仕方ないね。じゃあ優希ちゃん」
「無理ですよ、私にはそんな大役務まりません」
私は顔の前で右手を左右に全力で振った。思わぬとばっちりだ。
「大丈夫だよ、優希ちゃんなら。めんどくさい客の対応にも慣れているし、彼らもうんと年下の優希ちゃんの前では、みっともないことはしないだろう」
「そうは言っても、審査員なんて無理ですよ」
「いやいや、大丈夫。そんな難しいものじゃない。プロは参加禁止だし、ローカルなコンテストだから応募もそんなにないんだよ。少なくて困ってたくらい。市が協賛に入っているので広報誌やポスターを公共施設に貼って募集を掛けたけど、応募数は全部で二五件。それも知り合いにも参加してもらうよう頼んで、やっとこの数なんだ。まあ、賞品も大したことないからなあ」
参加者全員に市のマスコットキャラの印刷されたクリアファイルが贈呈される。一次通過者は市内の加盟店で使える三千円の商品券、優勝者は一万円の商品券が貰え、レシピが市の広報に掲載される。食品メーカー主催のレシピコンテストに比べると、確かに地味かもしれない。
「明後日は予選通過者に自分で作った料理を持って来てもらい、レシピの説明とそれを思ついたきっかけなんかを説明してもらう。コンテストと言っても、権威があるわけじゃない。栗という名産品を市民に知ってもらうことが目的だし、みんなに栗のレシピを楽しんでもらえればいいんだ」
「でも、私は料理を作る仕事ではないですし」
「料理は作らなくても、レシピを考えたり、盛り付けしたりするのが仕事だよね?」
「ええ、まあ」
靖子先生に言われて最近ではランチのメニューを考えたり、新しいレシピの提案もする。ほかのレストランでみつけたメニューをうちでもやれないか考えたり、この食材でこんな料理ができないかと提案したりする。実際に制作するのは靖子先生と香奈さんだが、経費と手間を考えてランチのメニューを組み立てるのは、最近では私の仕事になりつつある。
「だったら、優希ちゃんにも十分資格がある。ほかのふたりは味とか手順についての意見を言ってもらうけど、優希ちゃんは盛り付けやコスパの点から意見を出してもらいたい。それに、実際のところ採点を決めるのは、レシピ考案者のプレゼンなんだよ」
「プレゼン?」
「今までも同じような企画をやったんだけど、素人が作るものだから、レシピに大差があるわけではない。なので、どうしてこのメニューを思いついたかとか、誰に食べさせたいかといった話が印象に残る。採点でも、プレゼンがうまい人のものが高得点になる傾向がある」
「ああ、なるほど」
「順位は二の次。審査もそんなに難しくない。すごいレシピなんてまず出て来ないし、みんながいいと思うようなものはそんなに多くない。せいぜいひとつかふたつだから、あとのふたりの意見を聞いて、自分なりの考えをまとめてくれればいい」
「それでも、私より適任がいるんじゃないでしょうか」
「そうかもしれないけど、あと二日でそういう人をみつけるのは難しい。頼むよ、俺を助けると思って」
「でも、靖子先生。私は審査員の器じゃないですよね」
私は先生に助けを求めた。先生ならきっと私の味方をしてくれるだろうと思ったのだ。しかし、期待に反して先生は逆の意見だった。
「そうねえ。優希さんなら人との調整もちゃんとやれると思う。物事をよく見ているし、公平な考え方ができる人だから」
「でも、私が審査員なんて、みんなが納得するでしょうか?」
「大丈夫。知名度は関係ない。川上さんだって知る人ぞ知るくらいの人だし、スイーツ上田は知っていても、オーナーが誰かなんてみんな気にしていない。優希ちゃんと知名度にそんなに差があるわけじゃないんだよ」
守屋さんにはそう言って押し切られた。
結局私が承諾したのは、靖子先生に頼まれたからだ。
「面倒を押し付けて申し訳ないけど、私の代わりを頼めるのは優希さんしかいない。どうかお願い」
私は先生にたくさん助けられているけど、私が先生の力になれることは少ない。何か頼まれごとをすることもない。滅多にないことだから、引き受けることにしたのだ。
ただ、条件をひとつあげた。万一なにかあった時には先生のアドバイスが受けられるよう、審査中の時間にはいつでも先生と連絡が取れるようにしてほしい、とお願いしたのだ。お葬式は午前中だそうで、審査の時間には終わっているはずだ。だからそれはなんとかなりそうだ。
こういう経緯で私は審査員をすることになったのだ。
「では、これからコンテスト参加者に入場していただきます」
誘導係のスタッフの杉野さんに案内され、隣室に待機していた応募者が自分の作った料理を持って入場してくる。候補者の六番目の人を見て思わず声をあげそうになった。奏太くんだった。奏太くんと目が合うと、驚いた様子もなくにやっと笑った。どうやら奏太くんは私が審査員であることを知っていたらしい。私は驚きを顔に出さないよう懸命に抑える。奏太くん以外は全員おとな。しかもみんな女性だ。
会場は商工会議所の中にある小ホール兼会議室。よくイベントにも使われる。正面には教卓のような台が置かれ、応募者は順番にそこに立って説明する。我々審査員はその脇に座っている。会場にはパイプ椅子が五〇ほど置かれていて、希望者は誰でも無料で観覧できる。三分の二ほど座席が埋まっているが、ほとんどが応募者の身内か友人のようだ。
「では、エントリーナンバー一番の方から、説明をお願いします」
指名されて、一と書かれたバッジを付けた女性が台のところに着く。「ママ、頑張れー」と小さな子の声がして、会場に笑い声が起こる。
一番の女性の顔にも照れたような笑みが浮かぶ。
「では、まずは自己紹介からお願いします」
守屋さんに促されて、女性が口を開く。
「一番谷垣です。東町に住んでいます。えっと、主婦です。私のレシピは栗と豚バラ肉とインゲンの煮ものです」
女性が料理を盛った大皿を卓に置く。よく煮えた豚バラに焼き目をつけた栗とインゲンの煮ものだ。
「レシピを作られたきっかけは?」
「以前JAで栗が安く、大量に売っていたんです。それで思わず買ったんですけど、よく考えると、家族は栗きんとんはあまり好きじゃない。焼き栗なら売ってるものの方が美味しい。それで、いっそ料理に使ってみようと思って考えました」
家で考えてきたらしい。すらすらと暗唱するように語ってみせる。少し緊張した面持ちだ。
「セールスポイントは?」
「えっと……」
女性は口ごもった。考えていなかったのか、言おうと思った事柄を忘れてしまったのだろうか。
「煮物の煮汁を辛めにしてるので、栗を食べた時の甘味がいいアクセントになっていると思います」
「ご家庭の夕食で出されるのですね?」
「はい、みんな喜んで食べてくれます」
その答えの後、会場から「だーい好き」という声がして、みんなの笑い声が響く。最初から和やかな雰囲気だ。レシピもオリジナリティという点では少し疑問が残るが、決して悪いものではない。
私は審査員席で、それぞれの発言をメモしている。審査の参考になるかもしれない、と思うからだ。ほかのふたりはメモは取らず、にこにこしながらプレゼンを聞いている。
次の候補者は栗のロールケーキ。通常はクリームに入れる栗を、小さく削ってパウンド生地の方にも混ぜ込んでいる。クリームは栗をつぶしてつくったマロンクリーム。なかなか手間が掛かった一品だ。
「私はお菓子作りが趣味なので、栗の風味を活かしたケーキを作ってみました」
候補者の女性は若く、まだ大学生くらいだろうか。パウンドの生地もふんわりと焼けており、なかなか美味しそうだ。
その次はベテラン主婦の作った栗を使った寒天のお菓子。寒天の色が透明と黒の二色になっている。
「最初に黒蜜で味付けした寒天を作り、固めてからその上に栗を載せ、上から砂糖だけを入れた寒天を流し込みました」
見た目も美しく、売っている和菓子と変わらないレベルだ。アマチュアでもこれだけできるのは素晴らしいと思う。
「私はお茶を習っているので、お茶菓子も自分で作れないか、と思っていろいろ試してみたりしているんです」
その人は落ち着いた感じの中年女性で、お茶を習っているというと、なるほど、と思う。そんな風に、目的があって作るレシピは何よりだと思う。
さらにお菓子が続く。チョコレートに小さなマシュマロと栗の欠片を混ぜてでこぼこした形に丸めたもの。目新しい感じはしないが、プレゼンがよかった。四〇前後くらいの主婦が考案者なのだが、子どものために考えたレシピだという。
「息子はピーナッツ・アレルギーなんです。ピーナッツのチョコレートが食べられない。それでちょっとでもそれっぽいお菓子ができないかと考えました。それで、栗の歯ざわりがちょっと近いかな、と思って作ったんです。これなら安心して食べさせられますから」
そんな感じでレシピの紹介が進み、いよいよ奏太くんの番だ。奏太くんはトーストのようなものが載った皿を持っている。発表するのが嬉しくてたまらない、というように、勢いよく壇に上がる。
「六番、山内奏太。第一小学校四年二組です」
大きな声で言うと、奏太くんは会場を見回した。端の方に座っているおかあさんをみつけると、にっこり笑った。おかあさんも座席から、目立たないように小さく手を振り返す。奏太くんはトーストの皿を目の前に持ち上げて、はっきりした声で言う。
「これは栗きんとんを挟んだバタートーストです」
ほお、と会場から声が漏れる。
「正月のおせち料理の栗きんとんが余ったので、それを使って何か作ろうと思って、やってみました。あんバタートーストがあるので、栗きんとんでもできるんじゃないかと思っいました。そうしたら大成功」
ここで奏太くんがにっこり笑う。つられて会場の人達も微笑む。
「栗きんとんの甘さとバターの塩味がベストマッチ! 簡単で美味しいおやつになりました。ママ、いえおかあさんも喜んでくれました」
奏太くんのおかあさんは少し恥ずかしそうに、だが嬉しそうに微笑んでいる。
「以上です!」
それだけ言うと、奏太くんはぴょんと壇を降りた。その背中に拍手が贈られる。
簡単で、料理というほどではないけど、気軽に作れるレシピという点では奏太くんのものがいちばんだ。子どもらしくて、いいレシピだと思う。
そして次はキャリアウーマンかな、と思うようなきびきびした感じの女性だ。女性は西町の近藤と名乗ると、すぐに自分のレシピの説明をする。
「私が作ったのは、リゾットです。チーズと海老、塩鮭、インゲンに栗を混ぜました。塩気のあるチーズや塩鮭の中で、栗の甘みがいいアクセントになっています」
ほお、と感心したような声が会場に漏れる。お菓子が続いたなかで食事系のレシピは目立つし、リゾットに栗を使うという発想が新鮮だ。
「レシピを思いついたのは偶然です。仕事で忙しくて、ご飯を炊いておかずを作ってというのが面倒だった時、一品で済むリゾットを作ろうと思ったんです。それで、その時冷蔵庫にあった食材を適当に炊飯器に入れてみたら、意外に美味しかった。家族にも好評でした。それで、コンテストに出してみようと思ったんです」
リゾットは彩りも美しい。リゾットを盛った細長いオーバルプレートもセンスがいい。
「セールスポイントとしては栄養があるし、栗の存在感が活かされているってことです」
ほかの候補者よりこういう説明に慣れているのか、緊張した様子もなくはきはきと説明をした。
最後に出て来たのは少しおどおどした感じの四〇代くらいの女性だ。
「八番 田辺です。私はその、栗のドリンクを作ってみました」
女性は黒っぽい信楽焼のコーヒーカップをテーブルに置いた。遠目には、中身は見えない。
「栗のペーストを、ジャスミンティーとミルクで割りました。アクセントにクコの実を飾っています」
「レシピはどうやって思いついたのですか?」
守屋さんの質問に、女性は「えっと」と、一瞬口ごもるが、すぐに続ける。
「あの……栗のドリンクは珍しいので、あったらいいな、と思ったんです」
「いいですね。あったらいいなという考えこそ新しいものを作り出す時に大事なことだと思います。栗のドリンク、香りもいいですね」
守屋さんが褒める。確かに栗のドリンクは珍しい。ジャスミンティーで割る、というのも新鮮だ。ほかのレシピはなんとなく味の想像もつくが、これは新鮮だ。試食が楽しみだ。
発表の後、審査員は試食をする。やはり味が決め手になるからだ。審査員特権で私は全部試食できる。これはラッキーなことだと思う。
「これで一次審査通過者の発表は終わりです。発表者はご退場ください」
発表者は自分の作ったものを持って、隣の控室に移動する。
「この後審査に移ります。審査員の方たちには別室で審査を行ってもらいます、発表と表彰式は一時間後の三時を予定しています。このままここでお待ちいただいても大丈夫ですし、いったん退出されてまたその頃戻っていただいても結構です。もちろんこのままお帰りになってもかまいません。発表まで、もう少しお待ちください」
そう言われて、観客は立ち、ぞろぞろと出入口の方に向かう。審査員の私たちも、
「では、控室へ」
と守屋さんに言われて立ち上がるが、観客もいっしょの出入口を使うので少しもたついた。出入口の混雑を抜けると、お客さまたちの進行方向とは逆方向にある控室に行く。ほかのふたりの審査員も一緒だ。
廊下の端にある部屋の扉には「関係者控室」と張り紙がされている。扉を開けると一〇畳くらいの小部屋で、真ん中に大きなテーブルがあり、その上に審査する食品が載っている。小皿とフォークも傍に置かれている。審査に際しては、当然試食もするからだ。
「それぞれ応募者からのレシピをお渡しします」
アシスタントの女性が審査員に何枚かの紙を渡してくれる。そこには材料の分量と、作り方の手順が書かれている。
「では、この後は皆さまにおまかせします」
そう言って、守屋さんは壁際に下がった。ほかにふたりの女性スタッフが室内で待機している。
「どうしましょうか。各自それぞれで試食して、講評に移りますか? それともひとつづつ講評しますか?」
上田さんが口火を切った。
「そうですね。先に全部試食すると印象が薄れてしまいますから、試食しながら一点ずつ講評して、最終的に優勝を決めるというのでどうでしょうか?」
川上さんの提案に上田さんも私も反対する理由がなかったので、それで進めることになった。
「では、最初から」
栗と豚バラといんげんの煮込みだ。それぞれ小皿の上に肉と栗とインゲンを載せる。
「うーん、ちょっと甘味が強すぎますね。栗を引き立たせるためにはもうちょっと醤油を増やした方がいい」
と、上田さん。川上さんも言う。
「オリジナリティという点から言っても、ちょっとありきたりというか。鶏手羽を使った栗の煮物はわりとよくありますしね。豚バラよりも手羽の方が味も馴染むと思うし」
のっけからふたりは辛口だ。
「館林さんは?」
「そ、そうですね。確かに、これを鶏肉に置き替えたら、わりとポピュラーかもしれません。ただ、味のバランスは悪くないと思います。見た目もきれいですし」
「まあ、それはそうだけど」
私は内心ハラハラする。実は事前の打ち合わせでも、ふたりはあまりいい関係ではなかった。
「基準はどうしましょう。味、見た目、オリジナリティの三項目になりますか?」
前日の打ち合わせで私が提案すると、川上さんが反対する。
「やはりレシピですから栄養という面での評価もいるんじゃないでしょうか。最終的に小学校で提供されるわけですし」
すると上田さんが不愉快そうに言う。
「それを言ったら料理が有利で、お菓子系は全部評価が下がるじゃないですか。栄養は関係ないでしょう」
「でも味と見た目だけで評価されるというのもどうかと思います。小学校で提供されるということを考えれば、食育的な意義も大事だということですから」
「食育だと?」
上田さんは声を荒げた。
「あなたねえ、食育食育って実利的なことばかり言っていたら、いいレシピなんて思いつかない。食べるというのは文化だ。栄養とかそういう事だけじゃなく、美しさとか味とかそうした面も大事なんだ。食育は毎日の家庭料理で追及すればいい。こういうコンテストは文化としての料理の側面こそ大事にされるべきだ」
さっそく意見が対立する。ふたりとも自分自身の仕事の根幹にも関わることなので、譲れないのだろう。
困った。私自身はこの会話にどう参加すればいいのだろうか。頭を抱えていると、守屋さんがふたりをなだめるように言う。
「まあまあ、おふたりともそんなに熱くならずに」
「別に熱くなんかなってませんよ」
「そうですとも」
こういう点では意見が一致している。
「では、館林さんはどうお考えですか」
いきなり話を振られて、私はどぎまぎする。ふたりの視線が私に突き刺さる。
「そうですね。その、栄養ということに限定すると、お菓子系の出品が不利になるのは確かだと思います」
そこまで言うと、川上さんが冷たい視線で私を見る。つい臆してしまうが、言葉を続ける。
「でも、学校給食で出されるということを考慮するというのも大事なことだと思います。それを採点に反映させるというのも大事かと」
「では、何かご提案はありますか}
守屋さんが興味深そうに私に尋ねる。
「栄養という事に押し込めず、もうちょっと広い考えで評価をしたらどうでしょうか?」
「というと?}
「たとえば……そうですね。小学生に薦めたいかどうか、とか」
「それは、漠然としてますね」
「ええ。だからいいんだと思います。ひとつくらいはそれぞれの自由裁量で採点する項目があってもいいんじゃないかと」
私が提案すると、聞いていたふたりが「なるほど」と声をそろえた。
「どういう点で小学生に薦めたいかというのは、それぞれの判断でいい、ということですね」
守屋さんが確認する。
「はい、そういうことです。それぞれ得意分野が違いますし、それぞれの基準で評価をすればいいんじゃないかと思います」
「ふむ、それならいいかもしれない」
上田さんが言うと、川上さんが私に尋ねる。
「私は栄養で評価してもいいということですね」
「もちろんです」
「では、小学生に薦めたいかどうか、ということも項目に加えるということで」
守屋さんがそう発言すると、ふたりは同意というようにうなずいた。提案が聞き入られたことよりも、ふたりの喧嘩を回避できて私はほっとした。
「では、味、見た目、オリジナリティ、小学生に薦めたいかの四項目で採点する、ということでいいでしょうか?」
「四つというのはバランスが悪いな。もうひとつくらい何かないかな」
「だったら、作る手間とか?」
私が言うと上田さんが聞き返す。
「手間?」
「すごく手間が掛かってしまうと、そのレシピを再現しようという人は少なくなると思うんです。せっかく公開するんですから、同じものが簡単に作れるというのも大事じゃないかと思うんです」
「再現する必要はありますかねえ」
上田さんは不満に口を尖らせる。
「あの、これは小学校で作るという点からも大事だと思ったんです。小学校の給食に加えるのに手間が掛かり過ぎてはいけないだろうと思いますし」
「それはその通りですね。給食作りの現場を困らせるのは本意ではないですし」
川上さんが同意すると、上田さんもしぶしぶ言う。
「まあ、いまどきの若い人はタイパとか言うし、手間が掛かるかも大事かもしれないな」
「では、味、見た目、オリジナリティ、手間、小学生に薦めたいかの五項目で採点するということでいいですね?」
「はい」
「じゃあ、それを書き入れた審査シートを、明日までに用意しておきます」
そう言って、守屋さんは再び後ろに下がる。
「じゃあ、ひとつひとつ講評しながら、各自点数を付ければいいな。五段階評価でいいかな」
「いいんじゃないですかね」
上田さんの提案に、川上さんも同意した。
「では、一番については、俺は味二、見た目三、オリジナリティ二、小学生に薦めたいかは三、手間は四。合計だと……一四点」
「点数で出しておくと、比較がしやすいですね。私は味三、見た目二、オリジナリティ二、小学生に薦めたいか四、手間三、合計一四点」
ふたりとも少し辛口だ。素人が作るものだから、もう少し点数高くてもいいのに、と思う。
「えっと、私は味三、見た目四、オリジナリティ三、小学生に薦めたいか四、手間三で合計一七点」
「えっと三つ合計すると……四五点か」
「では、これが基準になりますね」
「次に行きましょう」
そうして講評しながら順番に採点していく。評価が高いのは、二色の寒天を使った和菓子。見た目と味で五点が並び、それぞれ二〇点超えと高評価だ。
意外と奏太くんのサンドイッチも評判がよく、三人とも手間の項目には五点を付ける。小学生らしい考案ということで小学生に薦めたい、という点では満点だ。それでかなりの高得点になった。
「では、最後の栗のドリンク」
八番めの応募作は飲み物なので信楽焼のコーヒーカップの中に入っている。その中を覗き込んだ上田さんが驚いた声を出した。
「あれ? 中身がない!」
「えっ、ほんとですか?」
私も近寄ってコーヒーカップをのぞきこんだ。中身は空っぽだった。
*後編に続く
愛知県生まれ。東京学芸大学教育学部卒業。フリーライター、出版社勤務を経て、2006年『辞めない理由』で作家としてデビュー。
『菜の花食堂のささやかな事件簿』シリーズのほか、ベストセラーとなりドラマ化された『書店ガール』シリーズ、『凛として弓を引く』シリーズ、『スケートボーイズ』『駒子さんは出世なんてしたくなかった』『書店員と二つの罪』『レイアウトは期日までに』等、多数の著書がある。
伝統的な日本の食文化への興味から、江戸東京野菜コンシェルジュと江戸ソバリエの資格を取得。