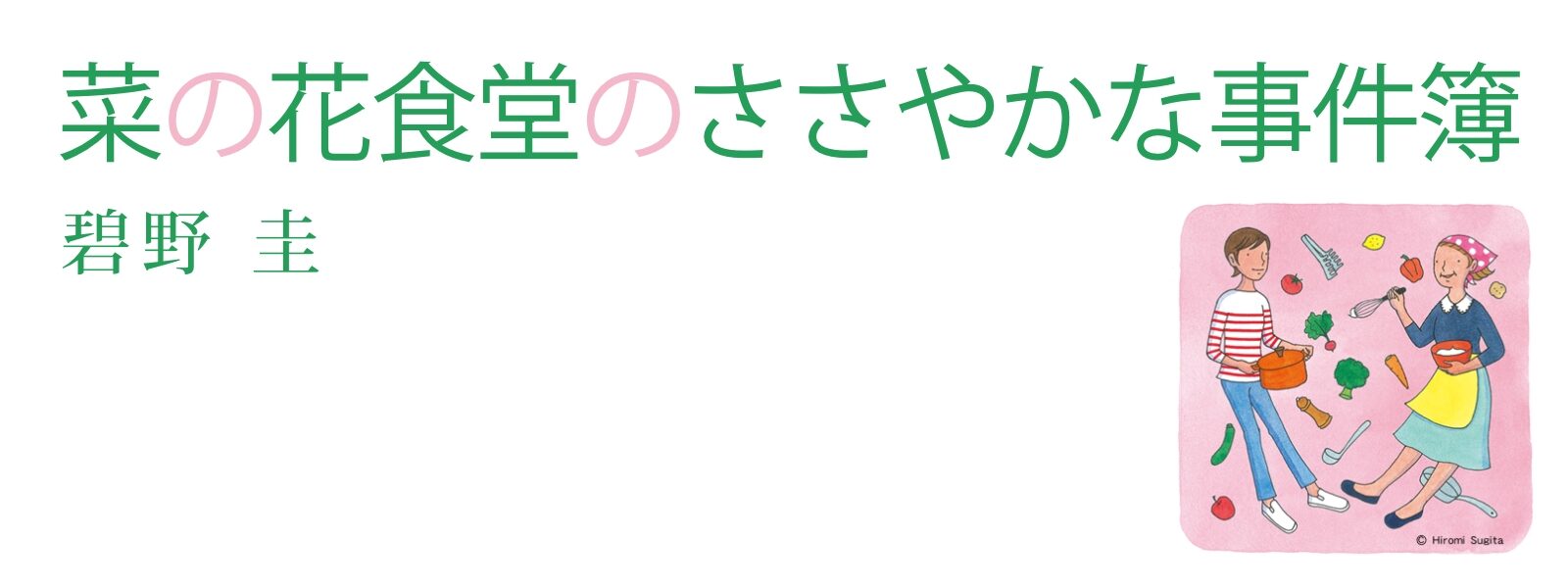トマトは嘘を吐く 前編
汗が額から耳の方に流れ落ちた。頬だけではない、首も腕も足も汗が浮んでいる。床についた背中もべっとりと濡れている。前にこんなに汗をかいたのはいつだろう。高校時代に強制参加させられた校内マラソン以来じゃないだろうか。
「しっかり水を摂ってくださいね。水を摂ると代謝が上がります」
インストラクターに言われて目を開け、上半身を起こして頭の所に置いてあったペットボトルを手に取った。汗を流しているから喉も乾く。一リットルのボトルももう空になりそうだ。
飲み終わると再び横になり、天井を見る。真っ白い天井には丸い小さな照明が点在しているが、光量が絞られていて部屋は薄暗い。もわっと湿度の高い部屋の中で寝そべっているのは私だけじゃない。隣に寝ている香奈さん以外は見ず知らずで、年代もばらばらな二十人以上の女性たちが、薄着で汗まみれになって寝そべっている。一通りレッスンが終わって、いまはクールダウンの時間なのだ。
第三者が見たら異様な光景かもしれないな。
そう思いながら再び目を瞑った。
「はい、そろそろ意識を戻します」
インストラクターはそう言って、照明の光量を上げた。
「たくさん汗を流すことで、余計な水分や老廃物が排出されます。身体のめぐりをよくすることはとても大切。ダイエットや体質改善に繋がります。レッスンのない日でも、毎日二リットルの水分を摂ることで代謝を高める効果があります。なので、お水をちゃんと摂ってくださいね」
一日二リットルか。思ったより多いんだな。そんなに飲めるのかしら。
「じゃあ、皆さん起き上がってください。挨拶をして終わりましょう」
その声を合図に、レッスン室に寝ていた女性たちはゆっくりと起き上がった。
今日、私、館林優希は同僚の和泉香奈さんとホットヨガの体験教室に来ていた。駅前に女性専用のスタジオができたから行ってみないか、と香奈さんに誘われたのだ。
香奈さんは結婚が決まったので、式までにもう二キロ落としたいらしい。私はまだそんな予定はないが、最近少し体重が増えてきた。食堂で働いているので新しいメニューの試食をしたり、余った料理を貰ったり、休憩時間に靖子先生のお手製の焼き菓子を食べているのだから無理もない。運動でもしなきゃ、と思っていたところだった。
「気持ちよかったね」
「うん、こんなに汗をかいたのは久しぶり」
シャワーで汗を流して洋服に着替えると、受付に更衣室の鍵を返却する。
「いかがでしたか?」
受付の女性が明るい声で尋ねる。
「気持ちよかったです。運動して汗をたくさんかくとスッキリしますね」
香奈さんが答える。ホットヨガは三十五度以上、湿度六十パーセントくらいに設定された環境の中でヨガのレッスンを行う。ダイエットや美肌効果、冷えやむくみの体質改善にもなるという。香奈さんはヨガの経験もあり身体も柔らかいので、ヨガのポーズも楽々こなしていた。私は初めてだったので、うまく形をとれないポーズもいくつかあった。
「一度だけでも効果はありますが、やはり続けることで健康効果に繋がります。今日入会すると入会金無料の特典がありますが、どうなさいますか?」
「はい。入会します」
香奈さんははっきり言い切る。
「私は、もうちょっと検討します」
汗をかくのは気持ちよかったが、会費が思ったより高い。これだけの設備を提供するのだから当然だが、一人暮らしの自分には痛い出費だ。
「一名様ご入会ですね。では、こちらの用紙にご記入お願いします。
香奈さんが入会手続きをするのを、ソファに座って待つ。
同じ給料だが、香奈さんは実家住まいだ。家に少しお金を入れているそうだが、生活費は掛からない。だからゆとりがある。
駅の北側に二十四時間使えるジムができたらしい。安いそうなので、そっちに行ってみようかな。でも女性一人で通うのは不安だな。
ぼんやり考えていると、香奈さんの入会手続きが終わった。
「お待たせ」
そう言われて、私はソファから立ち上がった。
「ホットヨガ? いろんなジムがあるのねえ」
靖子先生は感嘆したようだ。次の料理教室の準備をしながら、私たちは雑談をしている。
「結局入会したのは香奈さんだけですけど」
料理教室の打ち合わせなので、香奈さんは参加していない。香奈さんは当日お手伝いするだけだ。
「優希さんはスポーツジムには興味がないの?」
「いえ、わざわざジムに通わなくっても、動画サイトにはいろんなトレーニング法が出ているので、それをやればいいかなって」
「動画サイト? スマホを見ながらやるってこと?」
「そうです。若い女性向けのものもいろいろ上がっているから、好きなものを選べますし、お金も掛からない」
「なるほどね。いろんなやり方があるのね」
「実際に本職のインストラクターや整体師が動画サイトを運営している場合もあるし、たいていは本人も見本を見せるから、画面の中の人と一緒に運動をしている気になるんです」
気に入った動画の運動を毎日寝る前に三十分、それから水を一日に二リットル飲むことを日課にしている。ホットヨガの先生にも言われたし、後から動画サイトで調べたら、水を二リットル飲むことで肌がきれいになったとか、痩せたという体験者の報告がいくつも出ていた。最近は肌荒れにも悩まされているので、薬ではなく水でよくなるなら何よりだと思ったのだ。
「ところで、次の料理教室は何にしましょうか」
靖子先生に聞かれる。
「生徒さんからのリクエストでは、薬膳料理をやってほしい、という意見があるんですけど」
「薬膳料理?」
「はい、橋口さん、橋口小夜子さんに言われました。疲れやすくて食欲もあまりないから、体調を改善するような食事を教えて欲しいって」
橋口さんは二年くらい前から熱心に料理教室に通っている女性で、去年の秋に出産したばかりだ。月に一度、赤ん坊をベビーシッターに預けて教室に参加している。結婚と同時にこちらに引っ越してきたので、近くにあまり友人もいない。料理教室は月に一度のストレス解消だ、と言っていた。
「薬膳料理ねえ。それは難しいかな」
「そうなんですか? 先生は東洋医学的な事にもお詳しいから、薬膳の知識もあるんだと思ってました」
以前小豆の茹で汁が便秘に効くことを指摘した靖子先生だ。薬膳料理も教えられるのではないかと思う。
「うーん、少しは知識はあるけど。……年を取った叔母に元気になってほしくて、一時期集中的に勉強したことがある。だけど、知識があることと教えられることは別物だから」
「そうなんですか?」
「中医学で生まれた薬食同源という考え方がある。つまり食事も薬も元は同じ。バランスの取れた食事をすることで健康を維持し、病気を予防するというもの。それに基づいて作られたのが薬膳料理。ちゃんとやろうとしたら、それぞれの体質に合った料理を作ることになるから難しい」
「体質に合った料理って、どういう事ですか?」
「不調にはそれぞれ原因があって、たとえば疲れやすいといっても、ストレスで気の巡りが悪くなっている人もいれば、腎臓が疲れていてそれが身体に現れる場合もある。体質によって違う。何が原因か見極めて、その人に合ったものを作るのが本来の薬膳料理」
「なるほど。そういうものなんですね」
確かに、ちゃんとした薬膳料理の店は、まずお客の状態を見てから料理を決めると聞いたことがある。素人判断では難しいかもしれない。
「そこまで細かく追及せず、薬膳の知識を活かして、季節ごとの変化に誰もが対応できるようにするというカジュアルな方法もある。たとえば寒い時には身体を温める生姜を料理に取り入れたり、生姜湯を飲んだりするのも、薬膳の一種ではある。そういう事はみんななんとなく知ってるし、実行してる人も多い」
「たぶんそういうカジュアルなやり方を橋口さんは望んでいるんでしょうね」
本格的な薬膳料理を学ぼうとしたら、たまに参加する料理教室ではとても無理だろう。だが、薬膳料理のニュアンスを活かした料理を知りたい、それくらいの気持ちなんだろうと思う。
「カジュアルな方法を教えるにしても、まずは薬膳の基本的な考え方をちゃんと教えなきゃいけない。ある程度の座学が必要だと思う。片手間でできるものではないし、うちの料理教室のやり方とは違う。野菜のいろんな料理法を知ってもらうというのが目的の教室だから」
毎回ひとつの野菜をテーマに決め、その野菜のいろんな調理法を紹介していく、というのが菜の花食堂の料理教室のやり方だ。確かに、薬膳料理をちょっと教えるというわけにはいかない。先生は話を続ける。
「ただ、季節の旬のものは、その季節に身体が必要とする栄養素を含んでいる、という考え方があるの。たとえば春は身体に貯め込んだ老廃物を排出する、つまりデトックス効果のある山菜やヨモギ、筍などが旬だし、それを摂ることで花粉症の予防にもなる。夏が旬のきゅうりやナス、トマトなどは身体の熱を冷ます効果がある。なので、あまり考え過ぎず、旬のものをたくさん摂っているだけでも、身体を整える効果はあるのよ」
「そうだったんですね。知らなかった」
「食材には何かしらの効能がある、というのが薬膳の考え方ですしね」
「じゃあ、そのことを料理教室で説明したらどうでしょうか?」
「えっ? どういうこと?」
「トマトにはリコピンとかビタミンが含まれているっていうことは、みんな知っていると思うんですよ。だから美肌にいい、とは栄養学的によく言われることですから。だけど、薬膳的な効能についてはあまり知られていない。なんで旬のものがいいのか、どんな効能があるかを知れば、作る方もモチベーションが上がると思うんですよ」
「ああ、そうかもしれない。いまは年中売ってる野菜も多いし、旬の概念が薄れてきていますしね。薬膳をきちんと教えるのは難しいけど、効能について少し触れるのはありかもしれませんね。次回からその説明もすることにしましょう」
「では、次は何の野菜を扱いましょうか?」
「そうねえ。いま話に出たトマトはどうかしら? 旬を問わない食材だけど、旬の今はいろんな種類のトマトが安く出ているから、作りやすいと思うし」
「いいですね。じゃあ、トマトにしましょう。ちなみにトマトにはどんな効能があるんですか?」
私はメモを取りながら靖子先生の話を聞いている。
「トマトは身体の熱を取る、と言われているの。それに水分を補って渇きを止める働きがある。さらに、食欲を増進させて消化を助けると言われている」
「じゃあ、まさに夏にぴったりですね」
「そう。だけど気を付けなければならないのは、身体の熱を取るのはつまり冷やすということ。なので冷え性の人は取り過ぎに気を付けなければならないのよ。それに、きゅうりやかぼちゃとの食べ合わせはよくない、とも言われている」
「えっ、きゅうりとの相性は悪いんですか?」
私は思わず聞き返した。トマトときゅうりはサラダの食材としては定番だ。何もない時にはそのふたつを副菜にしたりする。
「酢が加わればその働きが弱くなるので、ドレッシングを掛けてあれば大丈夫。それに熱が加われば生の時ほど身体を冷やすことはないし」
「ああ、よかった」
「じゃあ、メニューを考えましょう。サラダはよくあるから、それ以外のもので」
そうして考えたのが、次のメニューだ。
ガスパッチョ、トマトと卵の炒め物、ラタトゥイユ、トマトとナスと豚肉の炒め物、トマトカップのひき肉詰め、たことプチトマトの炊き込みご飯。
メニューを考えた後は、実際に一度作ってみる。それを元にレシピを私が作成し、当日生徒さんたちに配る。当日生徒さんにどういう手順で作ってもらうかも、ここで検討する。同時にいくつもの調理をするので、効率よく作るには順番も大事なのだ。
びん詰めの作業場で料理教室をやるようになってから、一度に教えられる生徒の数は増えた。設備が整っているので以前の倍くらい、一度に二四人までは教えることができる。だが、最近はびん詰めの仕事もあるので、料理教室の回数は前より減らしている。それもあってすぐに満席になってしまう。申し訳ない気持ちになるが、今回薬膳料理のリクエストをくれた橋口さんは無事に参加してもらうことができた。前方の黒板のすぐ前の席に着いている。色白で茶髪、ピンクの小花柄のエプロンが似合うかわいらしい人だ。
「トマトは皆さん、よく使う食材だと思います。いまは年中手に入りますが、旬は夏、いまの季節です。自然の恵みはよくできていて、旬の野菜は人間がその季節に適応しやすいような効能を持っていることが多いのです。これは薬膳の考え方ですが、トマトは身体の熱を取る、という働きがあると言われています。それに胃の働きを活発にするので、食欲のない時に食べると消化を助けます。栄養学的にはビタミンやミネラルや食物繊維が含まれているし、リコピンの働きで抗酸化作用があると言われていますね。なのでアンチエイジングの代表的な食材でもありますね」
先生の言ったことを、熱心にメモしている人もいる。橋口さんもそのひとりだ。
先生は簡単に食材の働きを説明すると、すぐに調理を始める。五人か六人で一グループになっており、同時にいくつもの料理を作るので、手分けして作業をする。先生と私、香奈さんでそれぞれのグループの作業をチェックする。
作業場には水を流す音、じゅうじゅう焼き付ける音、食器のぶつかる音や何かを説明する声、たのしそうな笑い声などの音があふれている。その時間が私は好きだ。みんなで料理を作り上げようと気持ちをひとつにしている。雑談しながらもどこか緊張感がある。
「トマトをくり抜いて出る種や実は捨てないで。ガスパチョの方で使えますから」
テーブルを回って気づいたことを私も注意する。トマトカップ作りがやりにくそうにしている班には、実際にやってみせたりもする。前の席に行くと、橋口さんがラタトゥイユのための野菜を刻んでいる。
「どうですか?」
「はい。楽しいです」
そう語る橋口さんの手元はゆっくりで、野菜は大きさがまちまちだ。こういう作業に慣れていないのがひと目でわかる。
橋口さんは料理が苦手だ。結婚するまで料理はしたことがなく、一人暮らしをしていた夫の方が料理は上手だという。共働きなので外食で済ますことも多かったが、子どもができて「このままではいけない」と思って料理教室に通い始めたのだそうだ。素直で一生懸命、料理教室で習った料理は家で何回も作るのだという。
「おかげで少しレパートリーが増えました」
と、笑って語る。その笑顔はあどけない子どものようにかわいらしく、乳児の母とは思えないくらいほっそりとしている。ちょっと頼りないようにも見える。料理を作り終わった後、それぞれ班ごとに試食するのだが、明るい橋口さんは話題の中心にいる。
教室が終わった後、橋口さんが先生の方に近づいて来た。
「質問があるんですが」
「はい、なんでしょうか?」
「あの、トマトの効能についてなんですが」
橋口さんが言ってる後ろを「ありがとうございましたー」と生徒さんたちは帰って行く。生徒で残っているのは橋口さんだけだ。
「トマトが身体を冷やすって、本当ですか?」
「薬膳ではそういう考え方をしてますね」
靖子先生が説明する。
「きゅうりとかナスとか、夏の野菜にはそういう性質があると言われています。ゴーヤなんかもそうね」
「だとしたら、冷え性の人間はあまり食べない方がいいということでしょうか?」
「そうね。暑がりで身体に熱がこもるタイプの人にはお勧めだけど、冷え性の人にはあまり勧められないですね」
「血の巡りがよくなるから、食べた方がいいんだと思っていました」
橋口さんは納得できないのか、ちょっと首を傾げる。
「血の巡り?」
「はい。私は瘀血(おけつ)というタイプなんだそうで、血の巡りをよくする生野菜をたくさん食べた方がいいと言われていたんですけど。それに、水もたくさん飲んだ方がいいって」
橋口さんの言葉を聞いて、先生は微かに眉をひそめた。
「それは誰が言ったの?」
「友人です。料理がすごく上手で、薬膳の知識もあるんです。その人にアドバイスされたんですけど」
「失礼ですけど、その方、薬膳の知識があるっていうのは本当なのかしら?」
「本当だと思います。私が頭痛持ちだとか、生理が重いことも言い当てていました。それに、会ったことないのに夫の足がつりやすいんじゃないかと指摘して、乳製品や海藻や大豆を勧めてくれたんです。それで毎日湯舟に浸かるようにって。それを実行したら、夫の足がつることは減りました。それで、彼女の言うことは確かだって思ったんです」.
「その方は、ほかにどんな食を勧めているんですか?」
「私は脂っこいものを避けろ、と言われています。できれば牛肉よりも鶏肉や白身の魚の方がいい。さっぱりした食事がいい、と。おかげで少し体重が減りました」
「ふーむ」
先生は複雑な顔をしている。
「それで、最近の体調はどうなんですか? 毎日元気で過ごせていますか?」
「それが……。やっぱり赤ん坊がいるので毎日バタバタしていますし、夜も熟睡できませんから、どうしても身体がだるいです。それで永瀬さん、いえ、友だちが気に掛けてくれて、よく食事を持って来てくれたりするんです。作り過ぎたからおすそ分けって。私はあんまり料理が得意じゃないので、ほんと、ありがたくて」
橋口さんはその「友だち」のことを、とても大事に想っているのだろう。嬉しそうに話すその表情から察せられる。
「その方とは、いつからのおつきあいなんですか?」
「半年くらい前だったかな。子どもが生まれてすぐくらいです。彼女は同じマンションの住人で、エントランスや近くのスーパーで偶然会う事が多くて、それで会話するようになったんです。うちも結婚してからこちらに引っ越して来たので、近くに友人はいないんです。彼女の方は子どもはいないけどすごくいい人だし、年も近いからすぐ仲良くなって」
「その方、薬膳はどちらで勉強されたんでしょう?」
「もともと食品会社に勤めていたそうです。いまは結婚して会社を辞めたので、もとから興味があった薬膳調整師の資格を通信教育で取った、と言ってました」
「そう、じゃあちゃんと勉強した人なのね」
「ええ」
「でも、ひとつだけ忠告しておくと、冷え性なら生野菜よりも温野菜を食べた方がいいわ。冷たいものも避ける。薬膳は昔にできたものだから、クーラーのある生活を想定していない。だから、薬膳どおりのやり方そのままがいいとは言えないのよ」
「ああ、言われてみれば確かに」
「いまはアイスとか冷たいドリンクも手軽に手に入る。クーラーも効いているし、むしろ夏は冷たいものの取り過ぎで不調を訴える人が多い。冷え性なら夏でも生姜とかシナモンとか身体を温めるものを摂った方がいい」
「そうなんですね」
横で聞いていた私も、そういうことか、と思った。確かに薬膳が成立した時代には夏に氷を手に入れるのも難しかっただろう。
「それにいま授乳中ですよね」
「はい。まだ断乳はできてなくて」
橋口さんのお子さんはまだ一歳にもなっていなかったはずだ。離乳食を少しずつ始めている、と言っていた。
「だとしたらもまず肝臓をいたわるような食材を取り入れた方がいいわ」
「肝臓をいたわる食材というのは?」
「やっぱりレバー。薬膳の考えでは何か臓器が弱った時は、同じ臓器を食べるといい、という考えがあるの」
「じゃあ豚でも鶏でもレバーならいいんですね」
「もちろん。それに牛肉」
「牛肉も?」
橋口さんは驚いたように目を見開く。確か、牛肉は食べない方がいい、と友だちに言われていた食材だったはずだ。
「あとはカツオとかブリ、鮭。ウナギももちろんいいですし」
「ウナギは脂っこいから駄目かと思っていました」
「お友だち、永瀬さんでしたっけ? 聞いたら気を悪くされるかもしれませんが、母乳は赤ん坊を育てるものだし、白い血液と言われています。その分、授乳期間は栄養補給をする必要がある。野菜なら人参とか小松菜、ほうれん草、小松菜、黒豆もいい。瘀血の問題よりも、まずはお子さんをしっかり育てる方が大事ですから」
「そうですね」
「私が食材リストを作りますから、試しに一週間それでやってみてください。それで調子がよかったら、私のやり方の方が橋口さんには合っていたということになると思います。薬膳はひとりひとりの体質や状況で変わるもの。私も永瀬さんも専門家ではないから、もしかするとどちらかが間違っているかもしれません。でも、レバーを食べて悪いことはありません。とにかく試してみてください」
橋口さんは先生の言葉に戸惑ったようだ。永瀬というお友だちのことを信頼しているので、全然違う食材を勧める靖子先生の言葉を、すぐに受け入れられなかったのだろう。だが、最終的には靖子先生への信頼が勝ったようだ。橋口さんは妊娠前からこの教室に通っていたし、子どもを預けてまで通うほど教室や先生のことを気に入っている。
「わかりました。永瀬さんは確かに授乳のことについては何も言ってなかったから、授乳期はやり方が違うのかもしれませんね。しばらく先生のやり方で試してみます」
「そう、よかったわ。じゃあ、お勧めの食材のリストや避けた方がいい食材のリストを書きますね。一週間後にこの食事を続けた感想を聞かせてください」
先生はメモ帳を取り出すと、さらさらと書き始めた。
「あ、でもせっかく今日トマトの料理を習ったのに、トマトも食べない方がいいんでしょうか?」
「いえ、トマトも生ではなく火を通したものであればそんなに気にしなくて大丈夫ですよ。野菜を摂ることは悪いことではありませんからね」
「ああ、よかった。今日習ったトマトと卵の炒め物、今晩の食事で出そうと思うんです。簡単だし、美味しかったので」
橋口さんはそう語ると、一児の母とは思えないあどけない笑みを浮かべた。
橋口さんが帰ると、先生はほおっと大きな溜め息を吐いた。
「橋口さんが納得してくれてよかった」
「やっぱり、お友だちから聞いたやり方は間違っているんでしょうか?」
私は先生に尋ねた。
「間違いも間違い。冷え性なのに生野菜を食べたら、かえって身体を冷やすだけ。薬膳を知らなくてもそれは常識。瘀血と言ってたけど、それもどうなのかしら。そもそもそうであれば妊娠はしにくいでしょうし」
先生は吐き捨てるように言う。
「えっ、そうなんですか?」
「瘀血というのは確かに中医学で使われる言葉だけど、生野菜が血の巡りをよくする、というのは言われない。ナスにはそういう効能もあるとは言うけど、ナスは生で食べることはあまりないし。むしろ血の巡りをよくするなら、身体を温める食材を勧めるはず」
「じゃあ、全然でたらめを言われていたってことでしょうか?」
「でたらめというより、わざと嘘を教えたようにも思えるわ」
先生は強い口調だ。かなり怒っているようだ。
「わざと? 何のために?」
「わからない。でも、瘀血とか薬膳調整師って言葉を知ってるってことは、薬膳関係について知らない訳ではないと思う。でも、言ってることはおかしい。冷えがある人に真逆のことを勧めている。まして授乳中の女性に必要な栄養を教えない。その人に言われた通りの食事をしていたら、栄養不足になると思う」
「だったら、なぜ橋口さんにはっきりそれを言わなかったんですか?」
「言っても信じてもらえるか、わからなかったから。橋口さんはずいぶん永瀬という人のことを信用しているみたいだし。いきなり私が批判したら、そんな酷いことをするはずないって反発すると思ったから」
「ああ、そうですね」
橋口さんはその友人のことを「とてもいい人」だと言っていた。嬉しそうに語る口ぶりから、信頼しきっているのだろう、と察せられた。
「なので、とにかく食事を変えてもらって、私の言うことが正しいとわかってもらうしかない。でも、本当に言ったことを実践してくれるかわからないし、一週間続けてくれるかもわからない。続けたとしても一週間で効果が出なかったら、私の言う事を信じてもらえないでしょうから」
「そうすると、賭けみたいなものですね」
私が言うと、先生ははっとしたようだ。
「そう、賭け。彼女の体調が今後どうなるか。彼女自身が頑張らないとどうようもない。できればこの賭けに勝ちたい。自分のためでなく、彼女のために」
先生はつぶやくように言う。その気持ちが橋口さんに届きますように、と私も願わずにはいられなかった。
*後編に続く
愛知県生まれ。東京学芸大学教育学部卒業。フリーライター、出版社勤務を経て、2006年『辞めない理由』で作家としてデビュー。
『菜の花食堂のささやかな事件簿』シリーズのほか、ベストセラーとなりドラマ化された『書店ガール』シリーズ、『凛として弓を引く』シリーズ、『スケートボーイズ』『駒子さんは出世なんてしたくなかった』『書店員と二つの罪』『レイアウトは期日までに』等、多数の著書がある。
伝統的な日本の食文化への興味から、江戸東京野菜コンシェルジュと江戸ソバリエの資格を取得。