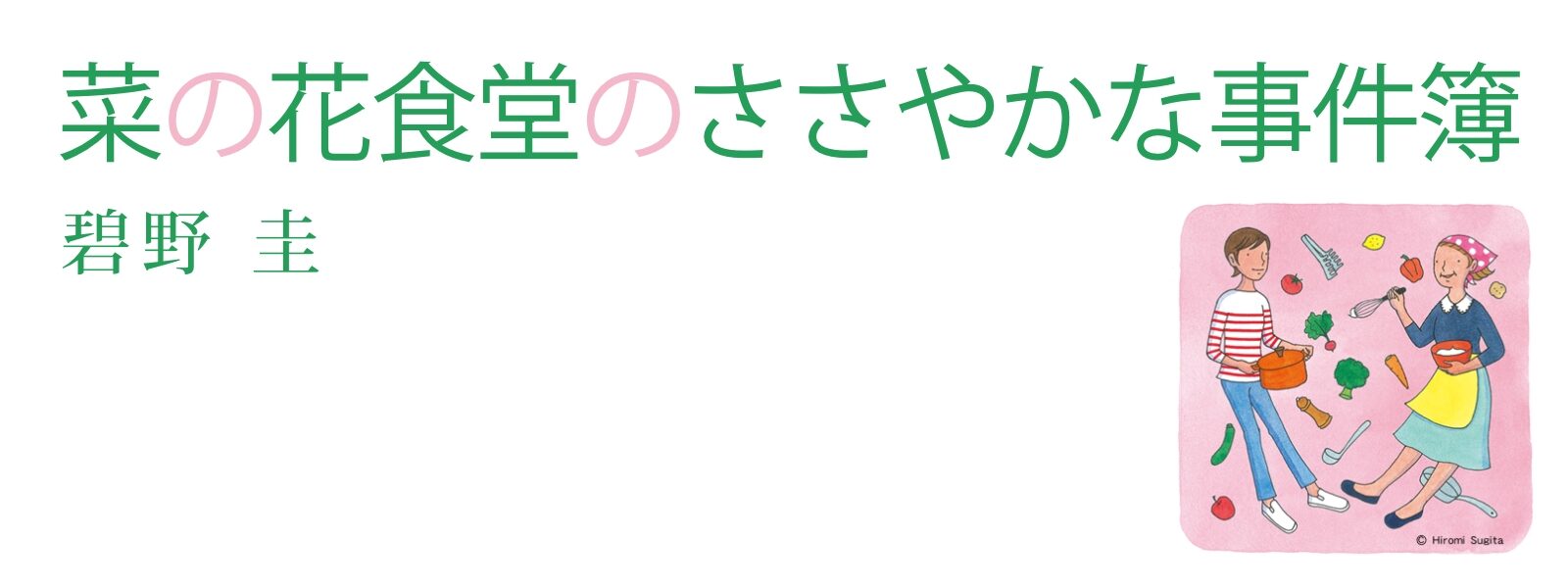トマトは嘘を吐く 後編
一週間後、ランチタイムの終わる頃に橋口さんはベビーカーに子どもを載せて菜の花食堂にやってきた。今日も変わらずにこやかだ。
「子どもはベビーカーに載せたままでも大丈夫でしょうか?」
ベビーカーの中の赤ん坊はよく太り、ご機嫌で足をバタバタさせている。
「もちろん。そちらの席の横なら、邪魔になりませんし。ベビーカーのお客さまにはいつもそこに座ってもらうんですよ」
私は端の方の四人掛けの席に案内した。一時半を過ぎているので、店はそれほど混んでいない。うちの店はお子様歓迎なので、子連れのお客さまもよく来店される。
「では、ランチセットをひとつお願いします」
今日のメニューは鮭のホイル焼き、ピーマンとみょうがの煮びたし、なすと玉ねぎの味噌汁だ。デザートにレモンパウンドケーキがつく。
「食後は珈琲か紅茶、どちらになさいますか?」
「紅茶をお願いします」
「かしこまりました」
私がオーダーを取ってカウンターの中にいる香奈さんに伝える。すると、靖子先生が言う。
「デザートのレモンパウンドケーキが切れてしまったの。代わりにプリンでもいいか、橋口さんに聞いてくれない?」
それを聞いた香奈さんは「えっ?」という顔をした。香奈さんの視線はオーブンの横の方を向いている。そこにはレモンパウンドケーキがまだ数切れ皿に載っている。
「優希さん、お願い」
靖子先生に促されて、私は橋口さんの方に行く。先生には何か考えがあるのだろう、と思ったのだ。
「プリンで大丈夫です」
橋口さんは答えた。隣にいる赤ちゃんは手にガラガラを持って、機嫌よく遊んでいる。
「赤ちゃん、可愛いですね。名前は?」
「樹里です。夫が付けたんです」
「そうですか。可愛い名前ですね。樹里ちゃん、ぴったりですね」
お世辞ではなく、本当に思った。赤ん坊だけど、目鼻だちがはっきりして、睫毛の長い可愛らしい子だ。大きくなったらおかあさんに似た美人になりそうだ。
そうして赤ちゃんの様子を見ながら橋口さんは食事をする。時々赤ちゃんがぐずると、私が傍に行ってあやすのを手伝う。そうしているうちほかのお客さまが食事を終え、店を出て行った。お客さまが橋口さんだけになると、先生はカウンターを出て、橋口さんの席に来る。橋口さんは食事を終え、デザートのプリンを食べている。樹里ちゃんが手を伸ばしておかあさんの腕を掴もうとする。
「これ、ほしいの? ちょっとだけよ」
そう言って橋口さんは樹里ちゃんに一口、プリンを与えた。
微笑ましい光景だ。もしかして、先生は樹里ちゃんが食べたがるのを見越してプリンにしたのかな、と私は思った。
「ちょっといいですか?」
先生は橋口さんの前に座る。
「その後、体調はどうですか?」
聞かれた橋口さんは嬉しそうに答える。
「先生に言われた通りにやってみたら、体調がよくなりました。ここのところ身体がだるくて全然やる気が出なかったんですけど、それが無くなって、嘘みたいに身体が軽いんです」
「そう、それはよかったわ。レバーを調理するのは面倒だと思うけど、大丈夫でした?」
先生は安堵したような顔をしている。
「テイクアウトの焼き鳥のレバーを買って食べました。それからイタリアンのお惣菜を売ってるお店でレバーペーストとキャロットラペを買って、パンに載せて毎朝食べていました。美味しいので、ちっとも苦になりませんでした。黒豆も調理したものがスーパーに売ってるし」
「なるほど、既製品を上手に取り入れたのね」
「はい。黒豆を煮るなんてこと、料理が苦手な私には面倒でなかなかできないし」
橋口さんはちょっと恥ずかしそうだ。
「そりゃそうよ。赤ちゃんを抱えていたらそのお世話で大変だから、黒豆煮るまではなかなか手が回らない。既製品に助けてもらうのも大事なことよ」
先生は励ますように言う。先生は主婦の大変さがわかっているので、決して手作りを押し付けたりしない。
「牛肉とかウナギとかこってりした食材を出したら、夫も喜ぶんです。夏バテ解消になるって。最近は鶏肉のさっぱりしたものばかりだったから、ちょっと飽きてたみたい。普段は私が作ったものに文句を言ったりはしないので、そんな風に思っていたとは知らなかった。ちょっと反省しました」
「飲み物はどうしていたの?」
「教えていただいたように水をがぶがぶ飲むのはやめて、温かいお茶やハーブティーを飲むようにしていました。紅茶にジンジャーシロップを入れたりして」
「それはいいわ。紅茶はそれ自体身体を温める作用があるけど、生姜を加えるとさらに効果がありますからね」
先生は満足そうにうなずく。ジンジャーシロップはうちの店に売っている。以前橋口さんが購入されていたから、それを使ったのだろう。
「あの、水をたくさん飲むのはよくないんですか? 代謝が上がると言われていますけど」
私は気になって聞いてみた。ホットヨガではたくさん水を飲むといいと言われたし、ネットにも美容や健康効果があると書かれている。
「それは体質や運動量次第。真夏でも外にいて働いてたくさん汗をかいている人は、普通の人より多く水を摂らなきゃもたない。身体が火照りやすい人も水をある程度摂ることが必要でしょうね。だけど、身体に水をため込むような体質の人、いつもクーラーの利いた部屋にいるような人は水分の摂り過ぎは害になる。薬膳では水毒と言って、水がうまく代謝されないことも不調の原因だとされているのよ」
それを聞いて私はどきっとした。私は汗っかきでもないし、いつもクーラーの利いた部屋にいる。水分がうまく代謝されているだろうか。
「じゃあ、私は?」
橋口さんが無邪気に尋ねる。
「橋口さんは無理に水を摂らない方がいいと思います。そもそも冷え性ってことは身体を冷やさない方がいいし、身体に水をため込まない方がいい」
「でも、私、瘀血だそうだし」
「ほんとうに瘀血だとしたら、よけい冷えには気をつけなきゃダメ。冷えによって瘀血は悪化するから。だけど、いままでやっていたことはそれに反することばかり。瘀血対策とは思えない」
「それは……」
橋口さんは戸惑っている。友人を悪く思いたくないけど、実際に先生のやり方とは真逆なことを教えられてきたし、実行してきたが、それでよくはならなかったのも事実だ。
「それに橋口さん、本当に瘀血なのかしら?」
「えっ?」
「本などによく体質の分類が載っているけど、典型的な例に当てはまるのは案外少ないものよ。実際ふたつくらいの症状が重なっていることもある。素人が勝手に判断するのは間違いやすいし、避けた方がいい」
「じゃあ、私が永瀬さんに聞いていたことは、間違いだったんでしょうか?」
「言いにくいことだけど、間違いというより、故意に嘘の情報を教えられていたように思う」
「嘘?」
橋口さんは目を大きく見開いた。そんなことは考えたことなかった、というように。
「永瀬さんという人はどこまで信用できるんですか?」
「信用って……。最近ではいちばん親しくしているし、お互いの家も行き来しているし……。いつも笑顔を絶やさない、親切でとてもいい人なんですよ」
「家族ぐるみのおつきあいなんですか?」
「いえ、夫は会ったことはありません」
「じゃあ、永瀬さんの存在は知らないの?」
「私がよく話をするので、どういう人かは知っています。でも、直接会ったことはないです。いつもお互いの夫がいない時に、遊びに行ったりしてますから」
「永瀬さんのご主人のことは?」
「出張が多くて、あまり家にいない、と言っていました。なので会ったことはありません」
「写真でも見た事ない?」
「そういえばないですね」
「橋口さんの方は見せたことあるの?」
「ええ。リビングには結婚式や新婚旅行の時、娘が生まれた時の写真などいろいろ飾ってありますし、頼まれてスマホの写真を見せたことがあります」
橋口さんらしい。きっとリビングのいちばんいい場所に、写真立てに入れた家族写真をいろいろ飾ってあるのだろう。自分の幸せを隠すことはしない。年賀状にも家族写真を使うタイプだと思う。
「永瀬さんとはどれくらいの頻度で会っているんですか?」
「そうですね。週に一度はおかずとかお菓子を持って遊びに来てくれます。私も娘が小さいのでなかなか外出できないし、いい気晴らしになっているんです。先生は、永瀬さんが悪い人だと思ってるんですか?」
「そうね、疑ってはいます。もし、本当に薬膳の知識があるなら、わざとあなたに真逆のことを教えているし、もし本気でいいことだと思って教えているなら、ろくに知らないのにいい加減なことを教えている」
「そんな……」
橋口さんは涙目になっている。それだけ永瀬さんのことを信じていたのだろう。
「お友だちのことを知らない私が、こんなことを言ってごめんなさい。でも、その人があなたにしたことは酷い。授乳期間という大事な時期に真逆な食事をしていたら、あなたの体調を悪くする。それこそ本当にあなたが瘀血になってもおかしくない。薬膳というのは医食同源。間違った食事は身体を壊す事になるのよ」
「でもなんでそんな酷いことを? 私に何か恨みでもあるのかな?」
橋口さんは涙目になっている。
「心貧しい人は、何を恨みに思うかはわかりません。それこそ家族がいて幸せそうにしているだけでも妬まれる原因になる。子どもがいなかったら、子どものいる人がうらやましかったり」
「それはないと思います。永瀬さんは子どもが苦手で子どもは欲しくないと言ってます。うちの子にもあまりかまったりはしないですし」
「そうなんですね。だとしたら、旦那さんと知り合いという可能性はありませんか?」
「それはないと思います。名前を聞いても、特に反応はないですし」
「彼女の写真を見せたことは?」
「……ないです。そういえば写真を撮ったことはないですね」
橋口さんは信じたくない、というように、頭を横に振った。樹里ちゃんが何かを察したのか「ふえー」と声をあげる。
「きっと薬膳のこと、ほんとはあまり知らないんだと思います。だから、私に間違ったことを言っただけで、悪気はないと思います」
それでも橋口さんは相手を庇う。おそらく人を憎んだり、悪く思うのが苦手なのだろう。だから事実を認めたくないのだ。
「そうかもしれない。だけど知ってるふりして誰かにこうしろ、というのもおかしいと思うのよ。どっちにしてもよくないことだと思う」
先生がここまできっぱり言うのは珍しい。
「私は……どうすればいいのかしら」
橋口さんは心底困惑しているようだ。
「難しいですね。間違ったことを教えただけで、犯罪というわけでもない。いままで親しくしていたのに、急に距離を置くのもどうかと思うし」
「食事の事は聞き流せばいいのかな。それ以外はこれといっておかしいことはないし」
「逆に、私に言われたことを話してみればいいんじゃないかしら」
「先生に言われたこと?」
「授乳中はレバーを摂るといいってこと。通っている料理教室の先生に言われて実行したら、とても体調がよくなったって」
「それで?」
「相手がどう反応するかを見るのよ。もし他意がなければ『よかったね』で終わると思うけど、そうでなかった場合、なんて言うのかな。それで彼女の本当の気持ちがわかると思います」
「そうですね。それくらいならやってみてもいいかも」
橋口さんはほっとしている。温和な性格なので、誰かを問い詰めたり、糾弾したりするのはやりたくなかったのだろう。
「あなたの身体に関わることですからね。相手の気持ちをちゃんと見極めた方がいい。あなたが体調不良で倒れたりしたら、お子さんのためにもよくないですから」
「はい、わかりました」
橋口さんはこっくりうなずいた。その顔が幼くて、本当に大丈夫かな、と私は少し心配になった。
次に橋口さんが訪ねて来たのは、その三日後だった。樹里ちゃんを抱っこしているが、樹里ちゃんは母親の胸で眠っているようだ。橋口さんは手には紙袋を持っている。
「どうしたんですか?」
私は思わず尋ねた。橋口さんの顔色が悪い。ランチタイムが終わって、ティータイムに切り替わった直後の時間だった。お客は誰もいない。
「あの、先生にお話を聞いてもらいたくて」
思いつめた表情だ。カウンターの中にいた先生がフロアに出て来た。
「そこに座って。赤ちゃんはそのままでいいのかしら」
先生に言われて、橋口さんは端の席に座る。抱っこベルトの中に樹里ちゃんが眠っている。
「大丈夫です。椅子に置くと起こしてしまうので」
「何か飲み物を召し上がりますか?」
「え、ええあの、ミルクティーをお願いします。ホットで」
ダージリンの葉を入れたポットに、牛乳をピッチャーに入れて持って行く。うちの店ではクリームは出さない。クリームは紅茶の風味を消す、と靖子先生は言うのだ。
「それで、どうしましたか?」
「あの、今日の午前中、永瀬さんが尋ねて来たんです。『最近体調はどう?』って聞かれたので、『まあまあ』と言ったら『生野菜、ちゃんと摂ってる?』と聞くんです。『あなたの体質には、生野菜が大事だからね』って。それでランチに食べようって、豆腐とチキンのおかずサラダを持って来るんです。それに、お手製のレモネードも。それ自体は美味しいかったけれど、やっぱり身体を冷やすものだし、私が食べるのを見張っている感じなんです。レモネードもホットにしようとしたら、『暑いから冷やした方がいいわ』って、氷をたくさん入れるし」
「意図的に身体を冷やすように仕向けている感じね」
「それで、思い切って言ってみたんです。『そういえば、料理教室の先生に言われてレバーを摂るようにしている。授乳期にはレバーを摂った方がいいんですって』って」
「それで、どうだった?」
「一瞬、凄い目で睨まれたんです。いままで見たことないくらい怖い目だった。それまでずっと微笑んでいたので、別人かと思うくらい」
「何か、感想は言われた?」
「特に何も。すぐに元の表情に戻り、私の話が聞こえなかったようにスルーして、別の話を始めるんです。近所に新しいスーパーが出来たとか、そんな話。それで私、怖くなって」
ずっといい人を装って仮面を付けていたのが、一瞬剥がれた、という事なのだろう。それがその人の素なのではないだろうか。
「子どもを寝かせるので、と言って、食事が終わったら帰ってもらいました。でも、しばらくしたら戻って来て、これを渡されたんです」
橋口さんは持っていた紙箱をテーブルに置いた。そして、中を開いてみせる。
中身はカップケーキが四つ入っていた。クリームか何かでデコレーションされていて、上には小さくカットされたフルーツが載っている。ラッピングも可愛く、まるでプロが作ったような上手な出来栄えだ。
「これ、樹里ちゃんに食べさせてねって。上のクリームは水切りヨーグルトを使っているし、そろそろこういうものも食べられるでしょって言われました。いままで樹里の食べ物には無関心だったのに、急に言われてなんか変な気がしたんです」
「四つは多いわね」
「余ったら、私が食べればいいって。それで、樹里が食べるところが見たいって言われたんですけど、ちょうど寝ていたので、後で食べさせるって追い返したんです。それですぐにこちらへ」
「ちょっと食べてもいいかしら?」
靖子先生が聞くと、橋口さんは黙ってうなずいた。
靖子先生はお皿とフォークを出してきて、カップケーキを載せた。カップケーキをフォークでカットすると、口の中に入れてゆっくり咀嚼する。
「やっぱりそうね」
「というと?」
「これ、ハチミツで味付けしている。ケーキ本体も、デコレーションのクリームも」
橋口さんの顔色が変わった。
「どういうことですか?」
事情がわからなくて、私が聞いてみた。
「一歳まではハチミツを食べさせてはいけないの。乳児は腸内環境が未熟で、ハチミツに含まれるボツリヌス菌によって乳児ボツリヌス症を発症する危険性があるから。乳児ボツリヌス症は嘔吐や下痢だけでなく神経麻痺を引き起こすし、呼吸困難で亡くなった例もある。怖いものなのよ。加熱してもボツリヌス菌は死なないから、注意しないといけないのよ」
そういうことだったのか。私は知らなかったけど、橋口さんの顔が強張っているのは、子どもを持つおかあさんには常識だからなのだろう。
「うちでは、乳児を連れたお客さまにはハチミツを使った料理を出さないように気を付けているの。赤ちゃんはなんでも口に入れたがるから、お菓子などは特に」
先生に言われてはっとした。以前レモンパウンドケーキが残っているのに、橋口さんにはプリンをお出しした。レモンパウンドケーキはハチミツを使っている。だからだったのか。
「樹里ちゃんに、と言って持って来たものにハチミツが入っているのは、悪意があるとしか思えないわね」
「ほんと、酷い。なんでこんなことを」
橋口さんの声は震えている。先生に指摘される前だったら、すっかり信用して樹里ちゃんにカップケーキを与えていただろう。
「子どもにまで手を出してくるのは穏やかじゃないわね。サイコパスでもなければ無意味に赤ん坊に手を出したりはしないけど。橋口さん、本当に永瀬さんのこと、知らないのね? 過去に自分か親が因縁のあった相手とかではないのね?」
「はい。私大学まではずっと仙台でしたし、家族は今もそちらにいます。あの人は港区育ちのお嬢さまだから、接点はありません」
「だったら、旦那さまの知り合いとか?」
「名前を言っても知らないみたいでしたけど。あ、結婚して苗字が変わったのかもしれませんね」
「名前は変えられますからね。その人、マンションのポストや表札にも永瀬って名前を出しているんですか?」
「えっと、特に出してはいなかったと思います。でも、防犯のために表札出してない家もあるので、そんなに珍しいことじゃないと思いますが」
「ところで橋口さん、住んでるのはファミリーマンションですよね?」
「はい。駅の近くのファミリーマンションです」
橋口さんはマンションの名前を出した。最近できたばかりの高級マンションだ。
「だったら管理人さんはいるのね」
「はい、います」
「管理人さんとは親しいですか?」
「関係は悪くはないと思います。年配の男性ですが、会えば挨拶するし、子ども好きで樹里を見ると『可愛いね』とか『今日はご機嫌だね』って、いつも声を掛けてくれるんです」
「では、ちょっと管理人さんに会いに行きましょう」
「いま、ですか?」
「相手は樹里ちゃんにまで手を出してきましたからね。何をするかわからない。急いだ方がいいでしょう」
そう言って、先生と橋口さんは出て行った。私と香奈さんはお店の仕事があるので残ったが、先生がなぜ管理人さんにこだわっているのか、気になっていた。
一時間後、先生は戻って来た。浮かない顔をしている。
「どうでしたか?」
「やはり確認してよかった。永瀬と名乗る人が住む部屋は別の名前の人が契約しているし、一人暮らしだった。しっかりしたマンションでは管理人が住居ごとの住人の名前も人数も把握してますからね。永瀬という夫婦ものはいないそうよ。あの部屋は女性のひとり暮らしでした」
「それはつまり……」
「おそらく橋口家を狙ったストーカーね」
私は背筋がぞっとした。ストーカーという非現実的な言葉が身近にあるとは、とうてい受け入れられなかった。
それから数日後、店が終わる頃に橋口夫妻が樹里ちゃんも連れてやって来た。以前何度か家族でこの店に来ているので、橋口さんの旦那さんとも初対面ではない。
「このたびはたいへんお世話になりました。アドバイスいただいた通りにしたら、彼女は自宅に戻りました」
「そう、それはよかった」
「でもまさか、うちの家族を狙うなんて。彼女とはもう四年も会ってなかったのに」
旦那さんは困惑している。橋口さんの旦那さんは背が高く、顔立ちも整っている。住んでるマンションから察するに、それなりの企業にお勤めなのだろう。
先生は橋口さんに永瀬さんの写真を撮って、旦那さんに見せるように指示した。それで彼女が昔つきあっていた女性だという事がわかった。真柴麗奈というのが本名だそうだ。
「同じ大学のサークル仲間で、卒業してからつきあうようになったけど、すぐに別れたんです。彼女は代々麻布に住むようなお金持ちの家庭で、地方公務員の息子である自分とは金銭感覚が違うんです。誕生日やクリスマスは高級レストランで一人一万円以上するフルコースが当たり前。プレゼントもそれなりなものを期待されるし、旅行で選ぶホテルも社会人一年生には分不相応としか思えなかった」
東京には金持ちが多いけど、代々麻布に住むのであれば本物のお金持ちだ。賃貸でも麻布は家賃が高くて、なかなか住めない。
「でも、それだけではなくて、彼女のレストランやホテルの人を見下すような態度が嫌だったんです。サークルにいた頃は高嶺の花と憧れていたので、つきあった当初は僕も舞い上がっていた。でも、その期間が過ぎるとだんだんあらが見えてきた。話題も噛み合わないし、一年経たずに僕から別れを切り出しました。いまの奥さんと出会ったのはその後。誰とでも親しくなれるし、人を和ますような穏やかな人柄に惹かれました。なので麗奈のことはすっかり過去になっていたんですけど」
「自分が振られたことに納得がいかなかったのでしょうね。いいうちのお嬢さまで、おそらく学歴もあり容姿にも恵まれている。だからプライドが高く、振られたことがショックだったのかもしれません。それに、まだ橋口さんに未練があったのでしょう」
「そうなんでしょうね。サークルでは美人でお嬢さまってことでとても人気がありました。なので、俺と別れてもすぐに別の男性が現れると思っていたのですが」
旦那さんは溜め息を吐く。男女のことは本人にしかわからないが、四年も経って、昔の彼女にストーカーされるのは悪夢のようなものだろう。
「でも、先生に気づいていただいて本当によかった。あの時指摘していただかなかったら、私の体調も悪くなっていただろうし、何より樹里が」
そう言って橋口さんの奥さんは娘をぎゅっと抱きしめた。樹里ちゃんは急に身体を締め付けられて、不満そうに「うう」と言っている。
「ですが、警察沙汰になるほどではないし、証拠は何もない。ハチミツの事だって、知らなかったと言われればそれまでですから。未然に防げて本当によかったです。ありがとうございました」
そう言って、橋口さんは夫妻で頭を下げた。
「いいんですよ。たまたまですから。頭を上げてください」
先生はなんでもない、というように言う。だが、先生でなければきっと麗奈という女性の悪だくみに気づくことはなかっただろう。
「それで、相手のご家族はなんて」
先生は橋口さんの旦那さんに、本人ではなくそのご家族に話をするといい、とアドバイスしたそうだ。本人はたぶん憎しみで頭がおかしくなっているので、話してもらちがあかないだろう。それより家族に対処させる方がいい、と。
「麗奈の連絡先はとっくに消去していたんですが、サークル仲間から麗奈の自宅の連絡先を聞いて電話したんです。そうしたらすぐに母親が飛んできて、娘を連れて帰りました。それなりの名家なので、外聞が悪いと思ったのでしょうね。『この件はご内密に』と、お金を渡そうとしてきましたが、断りました。『娘さんを二度と僕や僕の家族に近づけないでください』と言ったら、了解してくれました」
「部屋も引き払ったみたいです。なので、もううちに訪ねてくることもないと思います」
橋口夫妻の報告を聞いて、靖子先生は安堵したように微笑んだ。
「仕事もしていないのにあのマンションに住んでいるってことは、親が家賃を払っていると思ったんです。親に説明して家賃を止める方が手っ取り早い。それに名家であればあるほど醜聞を嫌いますからね。昔の彼氏と同じマンションに住むというだけで十分ストーカーですし、偽名を使っているとなったらなおのこと。なのですぐに対処してくれるだろうと思ったんです」
「ありがとうございます。ほんと、なんでこんなことになるのか、わからないんです。別れる時も『あなたがそう言うなら、そうしましょう』と、修羅場もなくあっさり別れたんです。こっちが拍子抜けするくらいだった。だから、俺のこと、たいして好きじゃなかったんだと思って、逆にこっちがへこんだくらいなのに」
橋口さんはぼやく。きれいに別れた相手からストーカーされるなんて、本人にとっては災難でしかないだろう。
「ひとのこころは複雑ですからね。プライドが高いから、別れ際では精一杯彼女も虚勢を張ったんでしょう。でも、未練はあったし、もしかしたらその後別の男性とつきあってみて、改めて橋口さんの良さに気づいたのかもしれない。どちらにしても、自分は新しい相手と進めないのに、橋口さんが幸せな結婚をし、子どもが生まれていることに怒りを感じたんでしょう。その家庭を壊してやりたい、奥さんや子どもを傷つけたいって感情が湧いてきたんでしょうね」
「そうかもしれませんね」
「なんか、可哀そう」
そう言ったのは橋口さんの奥さんだ。
「きっといまが幸せではないんですね。だから、ひとの幸せが妬ましい。麗奈さんにも新しい出会いがあって、昔のことなんか早く忘れるといいな、と思う」
それを聞いて橋口さんの旦那さんが愛おしそうに微笑んで、ぽんぽんと彼女の頭に触れた。嫌な目にあわされたのに、恨みもせず、相手の幸せを願う。
ああ、きっと旦那さんは彼女のこういう優しさが好きで結婚したんだろうと私は思った。
ふたりが帰った後、先生が私に言った。
「最近、優希さん、お水を多く摂っているわね。何か理由があるの?」
「あ、あれですか。健康にいいと聞いてちょっと試してみたけど、自分には合わないと思ってもうやめました」
先生にも気づかれていたのか、と私は冷や汗が出る思いだ。
「それがいいわ。世間にはいろんな健康法があるけど、人によって体質が違うから、合う合わないは必ずある。何事も極端なのはよくないわ」
「そうですね」
「確かに、体質によってこれを食べた方がいいとか、やめた方がいいという食材はある。薬膳の知識はそれを助けてくれる。だけど、とりたてて病気とか不調でなければ、旬のものをバランスよく食べて、適度な運動をすればいい。それが身体を整えることになると思うのよ。優希さんはまだ若いし、これといった不調もないんだから、それを守っていればいいの」
「そうですね。そうします」
私の返事を聞いて、先生はにっこり笑った。先生に見守られていれば、私は大丈夫だと思う。
「じゃあ、お茶でもしましょうか。橋口さんのお話を伺って、ちょっと気疲れしたわ」
「いいですね。じゃあ私、お茶の支度をします」
そう言って私は紅茶の置かれている棚の所に行き、ダージリンにしようか、オレンジペコにしようか、と考えた。はらはらするような事があったけど、そこはいつもと変わらない菜の花食堂の午後だった。
愛知県生まれ。東京学芸大学教育学部卒業。フリーライター、出版社勤務を経て、2006年『辞めない理由』で作家としてデビュー。
『菜の花食堂のささやかな事件簿』シリーズのほか、ベストセラーとなりドラマ化された『書店ガール』シリーズ、『凛として弓を引く』シリーズ、『スケートボーイズ』『駒子さんは出世なんてしたくなかった』『書店員と二つの罪』『レイアウトは期日までに』等、多数の著書がある。
伝統的な日本の食文化への興味から、江戸東京野菜コンシェルジュと江戸ソバリエの資格を取得。