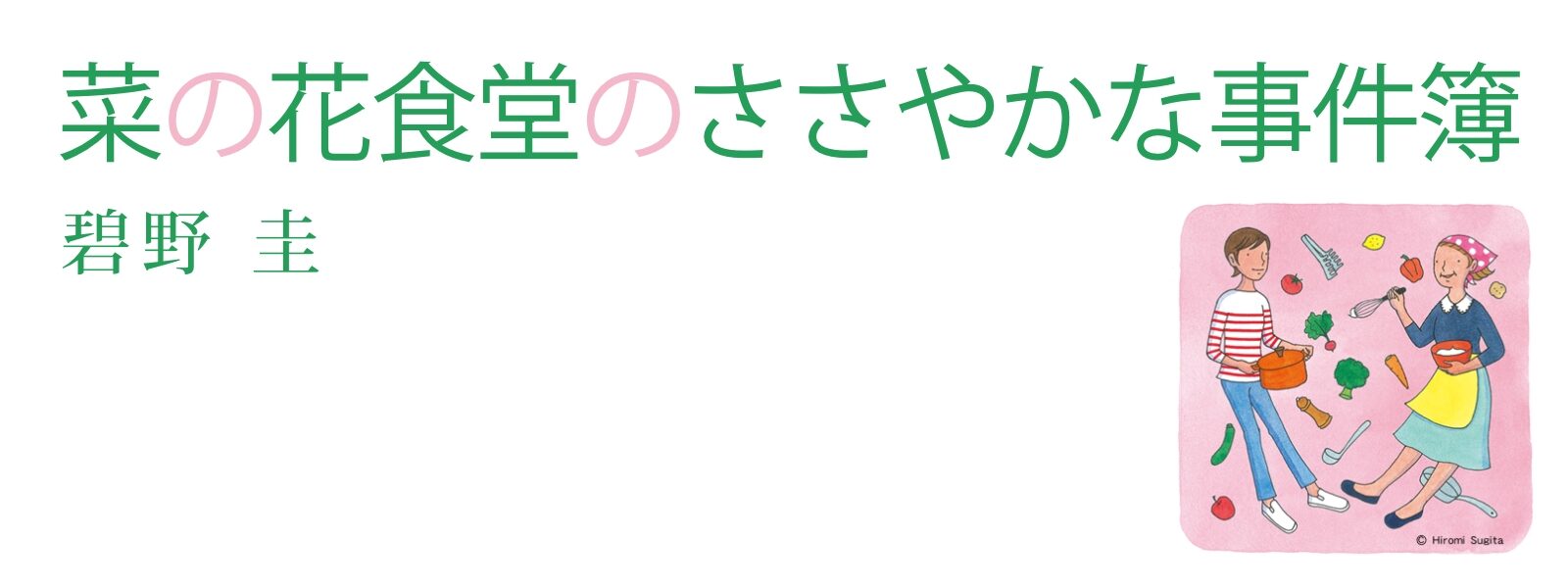栗は告発する 後編
『それでどうなったの?』
私は電話で靖子先生に経緯を報告している。
「そのカップは使われた様子がなかったから、間違ってドリンク入りのコップがどこかに置かれていないか、部屋の中を探しました。それから応募者が呼ばれて、どこに置いていたか確認しました。彼女はちゃんとテーブルの上に置いたと証言しました」
『応募作が控室に置かれた時、控室に誰か人がいたの?』
「いえ、誰も。応募者は自分の作品を置くとすぐに部屋を出たそうです。その二分後くらいには私たちが控室に入りました。なので、その二分の間に誰か入り込んで中身を処分しようと思えばできたかもしれません」
『そう、ではその可能性がある人は?』
「えっと、関係者の中にはいません。公共施設なので入り込もうとすれば誰でも入れたので、それ以外の人にはいくらでも可能性があります。ですが、応募者たちも怪しい人間は見ていないし、私たちより先に部屋に着いたスタッフも怪しい人間が出入りするところは見なかった、と言っています」
『そう。それで審査はどうなったの?』
「いま、どうするか揉めています。味見しないで選考するわけにはいきませんし」
オリジナリティという点ではこれが一番だったと思う。どんな味かも見当がつかない。味見しないで正しい評価はできない。
私は部屋の隅で目立たないように気を付けながら靖子先生と電話している。いまは審査員の控室ではなく、応募者の控室に移動している。部屋の真ん中では上田さんと川上さんが応募者たちの前に立って質問している。
「じゃあ、誰も怪しい人は見てないってことだね?」
「はい。誘導係のスタッフの杉野さんに案内されて、私たち八人が部屋に入りました。私たちが出た時には、廊下には誰もいませんでした。そうだよね」
応募者のひとりがほかの人たちに問い掛ける。リゾットで応募した近藤さんという女性だ。
「うん。誰も見てない。部屋に入ったのも僕たちだけだった」
奏太くんがはきはきと発言する。
「で、この部屋を最後に出たのは誰?」
「えっと、順番に料理を並べて、最後に私と八番の方がほぼ同時に出たと思います。それでスタッフの方に参加者控室に通されました」
審査する部屋とは別に参加者の控室が用意されていた。審査の内容を応募者に聞かせるわけにはいかないからだ。案内したのは守屋さんの部下の杉野惇太さんという若い男性だ。応募者だけでなく審査員の誘導係もしている。
「その後、誰もこの部屋には入ってないんだね」
「うん。スタッフの人にこっちに連れて来られた時、ちゃんと八人いた。その後もずっとみんなで一緒だったから、そっちには行けなかったよ」
そこまで聞いて、私は電話の会話に戻る。
「こんな感じで、誰も出入りした形跡はなく、犯人はわからないままなんです」
今日こそ靖子先生にいてほしかった、と私は痛切に思う。先生がここにいれば、誰が栗ドリンクのカップを持ち出したか、すぐに突き止めただろう。
『審査は中止になるの?』
「いえ、守屋さんはできればちゃんと審査してほしい、と言っています。やり直すわけにもいかないし、中止するわけにもいかないからって。守屋さんは、誰かこのイベントを気に入らない人間がこういう妨害を仕掛けたのだろう、と思っています。だから意地でも中断しない、と言っています」
『じゃあ無くなったものを除いた七品で審査するってこと?』
「そうなります」
守屋さんは八番の女性に、レシピを作り直せないか、と尋ねた。しかし、女性はもう材料も使い切ったし、作れないと言った。
「こうなったのは私の不注意です。なので、どうぞ私におかまいなく審査を続けてください。私は辞退します」
と、言ったのだ。
「だけど、そうですか、とあっさり承諾して、八番抜きに進めるのもどうかと思うんです」
『いいんじゃない、それでも』
あっさり先生が言うので、私は少し驚いた。
「でも、それじゃ八番の人が気の毒だと思いますが」
『と言っても作り直すこともできない訳だし、本人もそれでいいと言うなら、そうするしかないと思う』
「それはそうですけど」
先生のアドバイスが聞きたくて電話したが、こういう答えは想定外だ。先生なら遠方にいても犯人を言い当てて、ドリンクの在り処をみつけてくれると思っていたのだ。
『どちらにしても、時間がないわ。発表は遅らせられないんでしょ?』
「ええまあ」
あと一〇分で予定していた発表の時間だ。いったん外に出た観客が戻ってくるし、そろそろ市長が到着する、という連絡も来ている。受賞者への賞状授与は市長が執り行うのだ。
『とにかく発表はちゃんとやらないと』
「はあ」
腑に落ちないという感じで返事すると、靖子先生は話を打ち切るようにきっぱりと言った。
『今日の夜八時頃には帰るから、その時また話をしましょう』
そう言って先生は電話を切った。
「どうだった?」
守屋さんが心配そうに尋ねた。実は守屋さんに頼まれて私は電話を掛けたのだ。守屋さんも靖子先生がいままでいろんな謎を解いてきたことを知っている。今回も靖子先生なら、と期待したのだ。
「残った七つで審査をして発表したら、と言われました」
「それで、栗のドリンクを持ち去った犯人については?」
「何も言ってませんでした」
「そうか。さすがの靖子さんでも見ていない現場の犯人のことはわからないか」
「私の説明が悪かったのかもしれません」
私はメモを見ながら気づいたことを話した。でも、この場にいない人にはわかりにくい説明だったかもしれない。
「どうしましょうか?」
スタッフの杉野さんが心配そうに聞く。杉野さんは守屋さんの部下で、たまにうちの食堂にも来るので顔なじみだ。
「それは審査員の先生方に伺わないと」
そう言って守屋さんは審査員三人を連れて審査員控室の方に戻った。応募者に聞かせにくい話をあるからだ。
「誰がドリンクを持ち去ったのかはわかりませんが、審査については時間通り進めないといけません。それを待っている人もいるし、市長もそろそろ到着しますから」
守屋さんが言うと、上田さんが答える。
「こういう事になったら『該当者なし』にすべきじゃないかな。公平な審査ができないんだから、順位は決められないよ」
「そうねえ。あのドリンクは結構よさそうだったから、もしあれば優勝だったかもしれない。それなしで一位を決めるというのは審査員として納得できない」
川上さんも同意する。しかし、守屋さんが困ったように言う。
「それはそうなんですが、該当者なしというのは困ります。これは商工会としては新しい試みですし、市を巻き込んだイベントですからなんとか成立させたいんです。正直お金も掛かっていますし……」
確かに、商工会にとっては滅多にないイベントだし予算も使っている。市からもバックアップも受けている。ちゃんと結果を出して形にしないと次回に続かない。商工会にとっては切実な問題だ。
「ああ、確かに。学校給食でも採用するという話でしたから、そちらの関係者も期待しているでしょうし」
川上さんは同意を示すが、上田さんは困惑顔だ。
「それはそうですが、いまの中で優勝者を決めるというのもねえ」
「だったら」
私が言うと三人の視線が私に集まる。
「あの、優勝という形でひとりを選ぶのではなく、敢闘賞とか奨励賞といった別の名前にして、ふたりか三人選んだらどうでしょうか」
私の提案に、一瞬ふたりは戸惑った顔をしたが、すぐに同意してくれた。
「ああ、そうだねえ。それならいいかもしれないなあ」
「そうですね。全部の中の一位と順位づけするのではなくて、いまある中でのよいものを選ぶのであれば、私も納得できます」
「ありがとうございます。そうしていただけると助かります」
守屋さんが安堵した顔をしている。たとえ優勝という名前ができなくても、該当者なしに比べればましだということだろう。
「じゃあ、審査に戻りましょうか」
川上さんが言って、私たち三人は話し合いを続行した。
「お待たせしました。審査結果を発表します」
市長がそう言いながら、持っていた封筒を開く。授賞式っぽい演出をしたいということで、わざわざ結果を書いた紙を封筒に入れたのだ。観客は朝の時の半分くらい。一〇数名が結果を待ってくれていた。さらに応募者も壇の近くに並んで結果発表を待っている。
「まず最初に、今回はどれも素晴らしいレシピが揃っており、一名だけ優勝という形にすることができませんでした」
応募作がひとつ失われたことは、観客には内緒にされている。市長も知らされていない。八番目の応募者が大ごとにはしたくない、と望んだし、商工会もせっかくのイベントに水を差すようなことはしたくない。それでドリンク紛失事件は発表しないことになったのだ。
「代わりに、優れたレシピを三つ選ばせていただきました。まずは優秀賞、三番の今井さん!」
今井さんは驚いた顔で口に手を当てる。上田さんが選考理由を述べる。
「寒天の二色使いの美しさと栗と黒砂糖のマッチングがよかったです。このままお店で出してもいいのでは、と思うほど完成度の高いお菓子でした」
「続いて敢闘賞。四番、水野さん」
水野さんはチョコレートのお菓子を作った人だ。名前が発表されると、会場から「ママ、やった!」と子どもが叫んだ。水野さんは信じられない、という顔をしている。
私がマイクの所に進み出て講評を述べる。
「水野さんのレシピはアレルギーのお子さんにもいろいろ食べさせたい、という想いが素晴らしいと思います。アレルギーの家族がいるといろいろ工夫が必要になりますが、そこから新しいレシピに繋げたのが素晴らしいです」
アレルギーの家族の食事作りはこれからも続く。毎日手を抜けない。これからも頑張ってほしい、そういう意味での敢闘賞だ。
「もう一人、奨励賞に選ばれたのは、六番、山内奏太くん!」
「やったー!」
ほかの応募者と並んで立っていた奏太くんが、跳び上がって喜んでいる。取り囲むおとなたちは笑顔で拍手している。
「この若さでレシピコンテストに応募しようという気概が素晴らしいです。それに、余ったおせち料理で作ろうという発想もいい。レシピのためのレシピではなく食材を余らせず使い切る、それは料理作りでとても大事なことです。誰でも簡単にできるのもいいですね。それでこのレシピを選ばせてもらいました」
川上さんもにこにこしながら奏太くんを見ている。
実は優勝以外の賞を選ぶにあたっては、審査員がそれぞれ与えたい賞を、自分の気に入った応募者に与えようということになった。だから奏太くんの授賞に、私は関わっていない。奏太くんを選ぶと身びいきのように思えるので自粛したのだ。だから、川上さんが奏太くんのレシピを選んでくれたのは、私も嬉しかった。
入賞者三人には賞状と、商工会から五千円の商品券が贈られた。三人とも嬉しそうだ。
「では、受賞者の皆さまに拍手を!」
受賞者三人は檀上に立ち、会場の人たちからの大きな拍手を受けている。私は横の方を見る。入賞を逃した応募者が並んでいる。彼女たちもにこやかな表情で拍手している。その中に、応募作が紛失した八番の田辺という女性もいた。そんなアクシデントがあったのに、嫌な顔せずほかの人達を祝福できるのはえらいな、と私は思っていた。
その夜八時頃、靖子先生から電話があった。
『今日はいろいろありがとう。いま東京に戻ってきたところ』
「お疲れさまです」
『それでさっそくだけど、守屋さんと話をしたの。守屋さんとしたら、例の失われたドリンクのことをちゃんと知りたい、と言われた。優希さんも関わったことなので、もし話が聞きたいというのであれば商工会議所の方に来てもらえないかしら』
私はその時、見逃したドラマを配信で観ていた。ドラマは後からでも観られる。
「はい、すぐ行きます。二〇分あれば着くと思います」
そうして素早く部屋着からデニムとシャツに着替え、自転車を飛ばして駅近くにある商工会議所の建物まで行った。
表通り沿いにある商工会議所は、夜八時のいまは就業時間が終わっており、ビルの一、二階は真っ暗になっている。だが、三階だけは電気が点いている。イベントホールがあるフロアだ。玄関も空いていたので、エレベーターで三階まで上がる。
「ああ、優希ちゃん、夜にわざわざ来てもらってすまないね」
守屋さんが出迎えてくれる。後ろには靖子先生がいる。
「いえ、私も気になってましたから」
「急に呼び出してごめんなさいね」
靖子先生はそう言うが、先生こそ外出着のスーツを着たままだ。もしかすると家に寄らずに駅からここに直行したのだろう。
部屋の隅にはスーツケースと紙袋が置かれている。
さらにもう一人男性がその場にいた。守屋さんの部下で、案内係をしていた杉野さんだ。杉野さんは二〇代半ばくらい。おそらく独身だろう。でなければ夜八時に呼び出されて簡単に外出できるとは思えない。
「じゃあ、関係者が集まったところで現場を見せてもらいましょうか」
靖子先生は言う。
「あの、これはどういう事で集まったのでしょう?」
杉野さんはまだ状況を把握していないようだ。
「今日の昼のレシピコンテストで、応募作がひとつ無くなっただろ? それについて下河辺さんの意見を聞こうと思うんだ」
「それはなぜ? コンテストは無事に終わったんだし、もういいんじゃないですか?」
杉野さんは不満そうだ。いくら独身でも、急に上司に呼び出されたらおもしろくないだろう。
「そうは言っても、あれは事件だ。紛失はうちの責任だ。田辺さんがいい人だからよかったけど、そうでなければ大騒ぎになったところだ」
「田辺さんはお知り合いですか?」
先生が守屋さんに尋ねる。
「はい。実はうちと付き合いのある業者の方で、レシピコンテストの応募数が少ないという事を杉野から聞いて参加してくれたんです。だからすんなり納得してくれたけど、普通じゃそうはいかない」
なるほど、それで田辺さんはおとなの態度だったのか、と私は納得した。純粋にコンテストの結果に期待していたら、泣きたくなるような出来事だ。
「ほかに、商工会議所の人がお願いして参加してくれた方はいますか?」
靖子先生の問いに、守屋さんはばつの悪そうな顔をする。
「何人かいるけど、二次審査に残ったなかでは田辺さんともうひとり、奏太くんだけだ」
「奏太くんも?」
私はびっくりした。奏太くんが参加したのは、守屋さんに頼まれたからなのか。
「あ、だとしても不正とかは関係ないよ。たまたま奏太くんに会った時、コンテストのチラシを持っていたから『興味ありそうな人に渡して』と頼んだんだ。奏太くんがそれを見て『僕が参加してもいいの?』と聞いたんで『年齢制限はないし、ぜひ参加して』とお願いした。だけど、一次の書類審査はうちの職員全員が無記名のレシピを見て、よいと思うものにチェックを入れた。チェックの数の多い八名が今回の出場者だ。二次審査だって、審査員に自由に選んでもらっている。声は掛けたけど、それで審査を加減するようなことはしていない」
「それは事実です。私たち審査員だけで選びました」
私は付け加える。主催者側からのプレッシャーは一切なかった。それははっきりさせておきたい。
「つまり、コンテスト参加を呼び掛けたけど、審査自体は公平だったということですね。それなら問題はないと思います」
靖子先生に言われて、守屋さんは安堵したようだ。
「なのでせっかく参加してくれた人に遺恨が残るようなことになったのは、残念で仕方ない。田辺さんにも申し訳なくてね」
「ええ。でも立ち話もなんですから、会議室の方に行ってみましょう」
それで四人は会議室に入る。昼間に来たばかりの場所だが、パイプ椅子があったところに長机がいくつも並んでいる。全然別の部屋のようだ。ホワイトボードも置かれており、イベントホールというより大会議室の趣の方が強い。
「ここで発表を行って、発表が終わった時点で候補者は審査員の控室まで行ったんですね。この時、案内したのは杉野さん?」
「はい、そうです」
「候補者は全員一緒に行ったんですか?」
「はい。出入口に近い一番の人から順番に退出しました。全員を審査員の控室の方に案内しました。それから中央のテーブルの、番号が書いてあるところに自分の応募作を置くように指示しました。置いたらすぐに隣の応募者控室に行ってもらいました」
淡々と杉野さんは語る。
「では、応募作を持って行った部屋に連れて行って下さい」
靖子先生に言われて、四人はぞろぞろと審査員控室として使っていた隣の小会議室へと移動する。
こちらもテーブルの位置が変わっている。審査の時は真ん中にまとめられていたが、いまは縦四列、縦二列に並べ替えられている。部屋の隅に観葉植物がひとつ置かれているが、壁には何もなく殺風景な印象を与える部屋だ。
「では、全員が置いたところを杉野さんは見ていたのですね。間違いなく八番のドリンクも置かれていたのですね?」
「はい」
「その後、部屋を出たのはどういう順番だったんですか?」
「どういう順番と言われましても、そこまでは」
「応募者の人たちが最初ですか?」
「はい、そうでした」
「杉野さんの後に出た人はいなかったんですね?」
「そうだったと思います」
「最後に部屋を出た時、ここに鍵を掛けましたか?」
「いいえ。すぐに審査員の先生方がいらっしゃるのはわかっていましたから」
「だけど、実際は出入口が混雑して来るのに手間取った。それで二分くらいの空白が生まれた。この間に誰かがドリンクの中身を持ち去ったのは確かですね」
「いや、器ごと持ち去って、新しい器を替わりに用意したとも考えられる」
守屋さんが指摘する。
「それはそうですね。ただ、中身を持ち去る必要があったでしょうか?」
「というと?」
「この紛失の目的は、八番のドリンクを審査から外すことだったと思うんです。なので、中身を無くせばそれでよかったんだと思う」
「それは……どうやって」
「飲んでしまう、という事もできますが、いつ部屋に人が入ってくるかわからないし、カップ一杯のドリンクを飲むのは数十秒は掛かってしまう。それより捨ててしまえば一瞬で無くなる」
「捨てる? どうやって」
「最初は窓から捨てたのか、とも思いました。でも、窓を開けたり閉めたりする時間がいるし、その間に誰かが入って来たら言い訳できない。だから、それ以外の方法だと思います」
そう言って先生は、部屋の隅の観葉植物のところに行った。
「やはりここですね。証拠が残っている」
私たちも植物の方に行った。植物の根元をよく見ると、クコの実の小さな粒がふたつみっつ土や落ち葉の間に見えていた。
「つまりここに捨てたってことですか?」
守屋さんが驚いたような声を出す。
「そうですよね、杉野さん」
杉野さんはびっくりして目を丸くした。
「えっ、僕ですか?」
「証言を付け合わせれば、物理的に犯行が可能なのは杉野さんだけ。最後に部屋を出るふりをして、ドリンクを捨てるのは一瞬。さらに杉野さんは持っていたティッシュでコップの中を拭く。そうしてコップをもとに戻しても一分掛からず可能だと思います」
「それは、ほんとうか?」
信じられないという顔で守屋さんが杉野さんに詰め寄る。杉野さんは黙ったままだ。
つまり、靖子先生の言ったことは事実だったのだろう。
「なんでそんなことを」
守屋さんが怒った顔で杉野さんに掴みかかる。先生がふたりの間に割って入った。
「やめてください、守屋さん。杉野さんは商工会の名誉を守ろうとしたんですよ」
「商工会の名誉?」
「田辺さんのレシピは別の栗を使ったレシピコンテストのものを、ほぼそのまま流用したもの。もしこれが優勝して市報に載ったりすれば、誰かがそれに気づくかもしれない。それで破棄したんですね?」
「は、はい、その通りです。なんでわかったんですか?」
杉野さんは驚きを隠せない。私や守屋さんもあっけにとられた。
「冷静に考えればわかることよ。それより杉野さんはいつ盗作だと知ったのですか?」
「今朝です。会場の準備をしていたら、田辺さんが来て話したいことがある、と言われて、ここでその話を聞いたんです」
杉野さんは汗をぬぐった。
「田辺さんは、まさか予選通過するなんて思わなかった。申し訳ないので辞退したいと言うのだけど、今日の今日だし、いきなりそんな話をしてイベントが盛り下がるのも困る。どうしたらいいのか、と思っているうちにイベントがどんどん進んでしまう。ドリンクは目新しいから、どうやら審査員の先生方も興味を持っておられる。これが優勝したらどうしよう、と思って、ひとりきりでこの部屋に残された時、発作的に捨ててしまったんです」
「杉野……」
守屋さんが握っていた杉野さんのシャツの首元を放した。やったことは悪いことだけど、そういう事情なら責められない。
「小さなコンテストだけど、市長が立ち会ったり、学校給食のレシピに載せるというように話が大きくなったから、杉野さんはよけいつらくなったのね」
先生が言うと、杉野さんは黙ったまま深くうなずいた。
「先生、よく気づきましたね」
私が先生に言う。
「レシピコンテストでも権威のあるものであればプロの料理人も応募するし、賞金もそれなり。だから競争も激しくなる。だけど、優勝しても一万円程度のコンテストだし、権威もない。だから、ライバルの出品作を隠してまで蹴落とそうとする人はいない。そこまでのメリットがない。だから、八番の出品作を無くしたかったのはほかの人ではなく、出品者自身じゃないか、と思ったのよ」
「なるほどね」
守屋さんが感心したように言う。
「でもね、ほんとは八番が盗作だっていうことは、優希さんから電話で説明を聞いた時に、すぐに気が付いたの」
「それはどうして?」
「審査員を頼まれた時、栗のレシピコンテストがいままであるか、調べてみたの。そうしたら、すぐに検索で出て来た。やはり町おこしのために栗を使ったレシピを募集しているところがあってね。その入賞作のひとつが栗のドリンクだった」
「ああ、そうなんですね」
事前に似たようなレシピがないか探す、それもコンテストの審査員としては必要な作業だ。急遽の代役だったし、私はそこまでは頭が回らなかった。
「そういうことなら、田辺さんから聞いた時、すぐに俺に言ってくれればよかったのに」
守屋さんが言うと、杉野さんが弁明する。
「守屋さんは忙しそうでしたし、人目もあるから相談できなくて。田辺さんは辞退するって言ったんですが、俺が無理に頼んだのに田辺さんを悪者にするのも心苦しい。それでどうしようか、と迷っているうちにコンテストが始まってしまったんです。ほんと、申し訳ありません」
「出品作という以前に、食べ物を捨てるのはよくないことだけど、それだけ追い詰められていたのね」
靖子先生が優しく問い掛ける。
「はあ、頭に血が上っていて、気が付いたらやってしまっていた……」
杉野さんはうなだれる。
「そういうことですから、守屋さんもあまり杉野さんを責めないでくださいね」
靖子先生が頼むと、守屋さんはすっとぼけた顔をする。
「は? なんのことかな? コンテストは無事に終わったし、審査員は立派な結果を出してくれた。来た人たちも喜んでいたし、市長にも『よいイベントだった』と褒められた。イベントとしては大成功だったよ」
つまり、守屋さんは杉野さんのしたことをなかったことにしようとしているのだろう。
「守屋さん……」
杉野さんは驚いて守屋さんの顔を見る。守屋さんは続ける。
「まあ、次回への教訓としては、応募作品がほかの盗作じゃないかを事前にきちんと調べないとな。それは主催者側の責任だから」
「ほんとうに、すみませんでした」
杉野さんは泣きそうな顔をしている。守屋さんはまあまあ、というようにその肩をやさしく叩いた。
私もほっとした。杉野さんのやったことはいいことではないけど、誰も傷つけずにことを終わらせたかったのだろう。同情の余地はある。
「ところで、市の給食に出す件はどうなったの?」
靖子先生が尋ねる。それは私も気になっている。本来は優勝者の作品を使う予定だったが、三つの場合はどうするのだろう、と思っていたのだ。
「三つあるし、これから学校給食の関係者と相談する。もしかしたら、奏太くんのレシピを実際に生徒たちで作ってみよう、ということになるかもしれない。川上さんがそういうやり方が今回のコンテストの趣旨に合うと思うし、関係者にも勧めてみると言っていた」
守屋さんが言う。素敵な話だ。そうなったら奏太くんも鼻高々だろう。結局はコンテストはいい形に終わりそうだ。審査員として私は安堵した。
「そうそう、三人にお渡ししたいものがあるの」
そう言って、靖子先生は部屋の隅に置いてあった紙袋を持って来た。中から包みをみっつ取り出す。
「わらび餅。京都で今日買ったもの。賞味期限が短いので、明後日までに食べてね。今晩話をしようと思ったのは、一刻も早くこれをお渡ししたかったからなの」
「おお、それは嬉しいね。ありがとう。靖子さんが選んだものだから、さぞ美味いんだろうな」
守屋さんが嬉しそうに声をあげる。
「お店は小さくてマスコミにはあまり取り上げられないけど、昔ながらの本わらび粉を使っていて味も抜群。だから私はわらび餅ならここ、と決めているの」
先生は守屋さんに包みを渡すと、私にも包みを差し出した。
「いいんですか?」
「優希さんは私の代役をしっかり務めて下さったから」
「優希ちゃんには助けられましたよ。ほかのふたりが険悪になりそうな時もうまくなだめてくれたし、入賞者を三人にするっていうアイデアも出してくれたし」
「それは……役目だと思ったので」
「ほんと、今回は助かりました。私が思っていた以上に立派に役目を果たしてくれたようね。わらび餅くらいのお礼で申し訳ないくらい」
「そんなことないです。わらび餅、嬉しいです。ありがとうございます」
守屋さんにも靖子先生にも褒められるのは嬉しい。それにわらび餅も嬉しい。私は先生から包みを受け取った。もうひとつの包みを、靖子先生は杉野さんに差し出す。
「あの、私までいいんですか?」
「もちろんよ。お疲れさまでした。今日はいろいろ大変だったでしょ? 甘いものでも食べて、ゆっくり休んでください」
「……ありがとうございます」
杉野さんは消え入りそうな声でお礼を言った。
「ああ、早く帰ってこれをいただきたいな。家内も喜ぶと思うし。それにいつまでもここにいると電気代がもったいない」
「そうね、もう帰りましょう」
「じゃあ、電気を消して。戸締りは大丈夫かな?」
「は、はい。俺、見てきます」
杉野さんが小走りで廊下を走りだした。
私もほっとした。いろいろ気を揉んだけど、終わりよければすべてよし。家に帰ってわらび餅をいただくのが楽しみだった。
愛知県生まれ。東京学芸大学教育学部卒業。フリーライター、出版社勤務を経て、2006年『辞めない理由』で作家としてデビュー。
『菜の花食堂のささやかな事件簿』シリーズのほか、ベストセラーとなりドラマ化された『書店ガール』シリーズ、『凛として弓を引く』シリーズ、『スケートボーイズ』『駒子さんは出世なんてしたくなかった』『書店員と二つの罪』『レイアウトは期日までに』等、多数の著書がある。
伝統的な日本の食文化への興味から、江戸東京野菜コンシェルジュと江戸ソバリエの資格を取得。