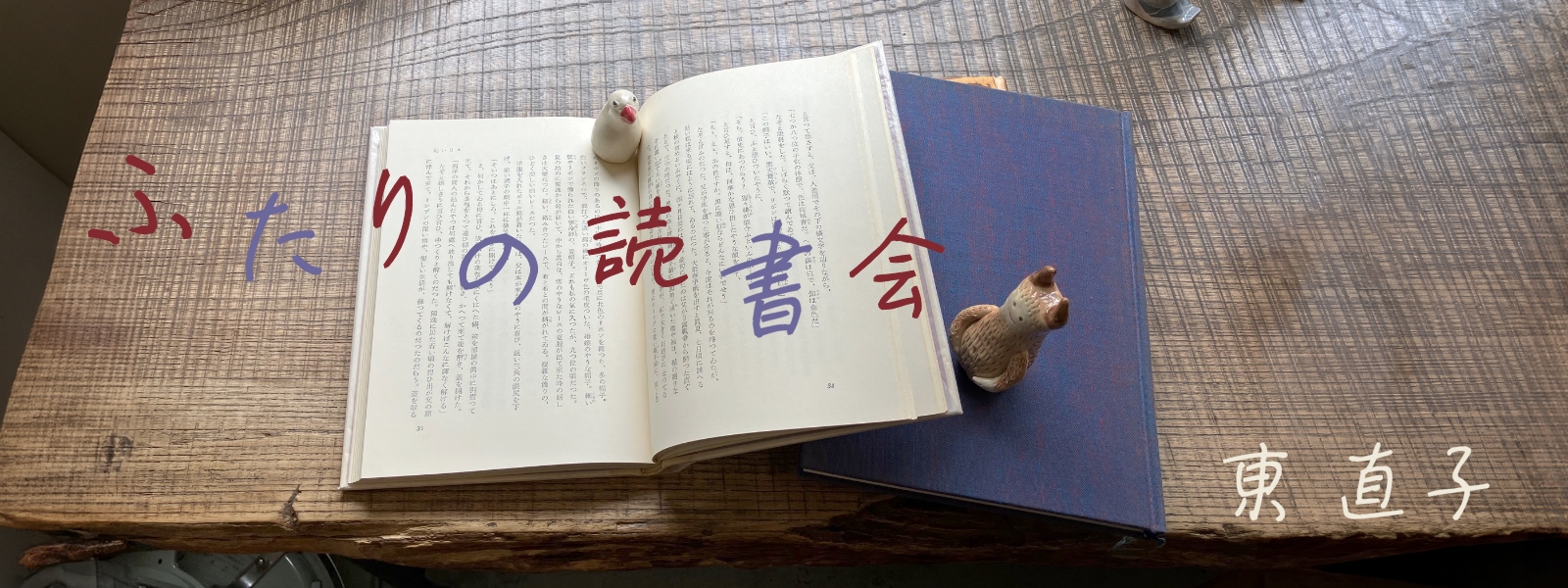書評家のワコさんと大学生のリリ。三〇歳も年の離れた、二人きりの家族。
親子のようで、親友のようで、そのどちらでもない。
二人は、いくつもの本を通して日々揺れ動く気持ちを伝えあう。
白い蝋燭に火をともしたら、二人きりの読書会が始まる。
ゆっくりと心が満ちていく読書の時間へ──。
桃と野焼き 後編
夕食後、リリはすっかりきれいに片付けた食卓の上で白い蝋燭に火を灯した。これは、二人の間でいつのまにか習慣化した「お話をしましょう」の合図である。あるときから気になった本について、一緒に語りあう時間になることが多くなった。本好きが高じて書評家になったワコさんと、もともと本が好きだったリリは、三〇歳も年が離れているが、一冊の本の前ではそんなことはすっかり忘れてしまう。
蝋燭を運ぶリリの後ろからワコさんがココアを運んできた。
「ワコさん、『有夫恋』、すごくよかった。めっちゃエモかった」
「でしょ」
「最初の方から読んでいっていい? 『しあわせを話すと友の瞳が光る』。〝瞳が光る〟って、真逆の意味合いがあると思うんだ。生き生きした気持ちになってきらきらした気分のときの『瞳が光る』っていうのと、何かを警戒したり、意地悪な気持ちでいるときに『それ本気で言ってる?』って思うときのと」
「なるほど。で、これはどっちだと思う?」
「一瞬キラキラに見せかけて、実は意地悪」
「どうしてそう思う?」
「なんとなく。この句のふたつ前に『倖せを言われ言訳せずにおき』があって、なんか心にもやもやしたものがあるのに言えないでいるのかなって思ったのもあるし。なんにもなかったら、今しあわせだよって話してるときに、友達の目が光っているようには感じないんじゃないかな。友達の目の変化なんて気にしないんだよ。思ってもいないこと言ってるから、あ、わかっちゃったかな、って気にしてるから、そう感じるんだと思う。明日学校に行って、彼氏とどう? なんて友達に訊かれて、言い出しにくくて、まあ、いいかんじだよとかごまかしたら、友達の目、ぜったい光ると思う」
ワコさんは思わずあはは、と笑ってしまい、失恋がからんでるのに笑ってしまったことを即座に申し訳なく思って、あ、ごめんと小さく謝った。
「ワコさん、いいよ、あやまらないで。そこは流して」
「あ、はい」
「それで、自分もそうやって友達の話に目を光らせてきたことに気づかされたんだ。インスタのキラキラ生活に目を光らせる感じとか。これ、何年前の句?」
「章題に作った年代が書いてあるね。〝一九五五〜六〇〟の最初の方の句だから、約七〇年前だね」
「わあ、そんなに経ってるのに……」
「普遍性あるよね」
「ワコさんは、どの句が好き?」
ワコさんの顔をのぞきこむリリのつやつやした頬に蝋燭の炎の影がゆれている。ふっくらした唇が少し開いていて、つやっぽい表情だなとワコさんは思う。
「いろいろあるよ、そうねえ……『手が好きでやがてすべてが好きになる』、これ、かわいいよね」
「うん、胸キュンだ。わかる」
「〝神は細部に宿る〟という格言があるけど、最初は小さな〝好き〟がだんだん集合してて〝大好き〟になっていくんだよね。そのきっかけが〝手〟ってところがね。この頃は、フェティシズムなんて認識は浸透してなかったと思うけど」
リリは頷きながら「認識なくても気づいてたんだね」とつぶやいて、本をめくった。
「私はねえ、これ、『ポケットの手を出しなさいお別れです』が気になった。ちゃんとしなきゃいけない場面でちゃんとできない人を諭してる、のかな。かっこいい。〝お別れです〟は、自分自身にも言ってるんだと思う」
「そうだね。心にピリオドをきっちり打つ感じだね」
「あー、私の方からこう言ってやりたかった」
「キツネセーターさんに?」
「うん。よく考えれば、ずっと別に好きじゃなかった」
「じゃあ、今、これ、声に出して読んでみれば。すっきりするよ」
リリは、はっとしたように大きく目を開いた。軽い深呼吸を一つして、背筋をのばした。
「ポケットの手を出しなさいお別れです」
一語一語しっかりと発した声に反応するように、蝋燭の火がやわらかく揺れた。かすかに微笑んだとたん、じわっと目から涙がにじんだ。
「あ、やだ」指先でその涙をごしごしとこすった。
「どんなお別れも、切なくはあるよね」とワコさんは穏やかに言って、本を手に取ってめくった。
「『わたくしの野焼き始まる夕焼けよ』なんて壮絶だね」
「うん。自分で自分を野焼きみたいに葬り去ろうとしている」
「長く生きてると、そうしたい気持ちにもなるんだろうね」
「ワコさんも、そう?」
「そうねえ、まあまあ長く生きてはいるから、うわああって急に自分のしたことが恥ずかしくなることはあるね」
「私、まだ一九年しか生きてないけど、うわああって、恥ずかしくなること、もうなんべんもあるよ。野焼きできるもんなら、私もしたい」
「夕焼けをひたすら見つめていたら、この句みたいに心の野焼きができるのかもしれない」
「じゃあこんど、夕焼けを浴びてみようか、ワコさんと二人で」
「そうねえ、どこで見る夕焼けが一番有効かしらね」
「……ジャングルジムの上?」
「ジャングルジム! なるほど、若さ、というか、青春を感じるな。私は、商店街のアーケードの切れたあたりで立ってる図を想像してた」
「わびしい……」
「余計なお世話です」
言いながら、ワコが笑い、リリも笑った。リリが笑いながらココアを含んだので、むせてせきこんだ。それを見て、ワコさんは、さらに笑った。そうしてひとしきり笑ったあと、ふいにしずまった。
にぎやかに笑ったあとにふいに訪れる沈黙は、宇宙の上にとつぜん放り出されたような静けさがある。外は暗く、空気には冬の終わりの冷たさを含んでいる。でも家の中はあたたかく、蝋燭の灯りはやわらかい。三〇歳も年の離れた女が二人住む、小さな部屋。血縁関係はない、二人きりの家族。親子のようで、親友のようで、そのどちらでもない、と二人とも思っている。この二人にしかない、二人だけの関係なのである。
今目の前にいるリリが、お母さんいってらっしゃい、と無邪気に母親を送り出した日のことをワコさんにふいに思い出させる。
「ワコさんがこの世にいてくれて、よかった」
リリがしみじみと言った。
「え、なんで、急に?」
「これ」
リリが、句集の終わりの方にある一句を指さした。
入っています入っていますこの世です
「この句、トイレが急に〝この世〟に広がったみたいでおもしろい。で、ワコさんも私も、この世に確かに入ってるんだなあって、今思った。私のお母さんは、この世のドアの外にいて、ノックしてるのかな」
「うん、そうだね、きっと、思い出してるときは、その人がノックしてるんだよ」
「じゃあ、お母さんに川柳で返事しよ。えっとね……『ふられてもワコさんがいて元気です』」
「杏子さん、安心できるね」
「でも、川柳というより文章になっちゃった」
「私も返事を考えてみよう。そうだなあ。『残されてこの世の言葉あたためる』」
「ワコさん、さすが。すてきだ」
「いやいや」
「川柳って、新聞にときどき載ってるサラリーマン川柳みたいな、世相を皮肉ったものだと思ってたけど、こんなに情感豊かな作品もあるんだね。びっくりした」
「そうなんだよ。俳句は季語が大事で、あんまり個人の感情を込めたりしない文学なんだけど、季語を使う必要のない川柳はもっと自由で、新子さんみたいに、喜怒哀楽を率直に表現することもあるみたい」
「自分の気持ちをうまく言葉にできて、それが他の人にもばっちり伝わったら、気持ちいいだろうなあ」
「気持ちを伝えるなら、五七五七七の短歌は向いてると思うし、詩の形でたっぷり書くというものいいかもね」
「そういうのができたらいいな。でも今は、誰かが書き残してくれた言葉を読み解くのが楽しい。自分と同じだって思うのも、そんなふうに自分も思うのかなって想像をふくらませるのも。ねえこの『象を見ている静かで寒い時間だな』の「寒い時間」って、淋しいけど、それもいいなって思っているような気がする。なんともいえない気持ちになる」
「ああこれ、私はリリの年の頃には良さがわかんなかったけど、今はすごくいいなって思う。リリはあの頃の私より、大人なのかもしれない」
ワコさんの言葉に、リリは目を見開いて一瞬きょとんとした表情になったあと、すぐに少し淋しそうな顔になった。リリが経験したことで何かを決めつけてしまったことへの悲しみなのではないかとワコさんはとっさに思い、リリにすぐに謝りたくなった。が、さっき謝らないでと言われたばかりなので、言葉にするのはやめた。代わりにテーブルの上の『有夫恋』をなでた。
「こういう短い言葉でできた文学って、ときどき読み返すと響きかたが以前とは違ったりするから、面白いよ」
「うん、きっとまた読み返す。一年後、二年後、一〇年後、一〇〇年後」
「じゃあ、一一九歳で?」
「うん、一一九歳で」
リリはほんのり微笑みながら蝋燭に息を吹きかけて火を消した。
<引用文献>
時実新子『有夫恋』(朝日新聞社)1987年刊
掲載ページ P.6、P.113、P.141、P.166、P.173
広島県生まれ。歌人、作家。
1996年、「草かんむりの訪問者」で第七回歌壇賞受賞。2016年、『いとの森の家』で第三一回坪田譲治文学賞を受賞。
2006年に初の小説『長崎くんの指』を出版。
歌集『春原さんのリコーダー』『青卵』『十階』、小説作品『とりつくしま』『さようなら窓』『薬屋のタバサ』『晴れ女の耳』『階段にパレット』『ひとっこひとり』『フランネルの紐』、エッセイ集『一緒に生きる 親子の風景』『レモン石鹼泡立てる』『魚を抱いて 私の中の映画とドラマ』、歌書『愛のうた』、『短歌の詰め合わせ』、『短歌の時間』『現代短歌版百人一首 花々は色あせるのね』、穂村弘との共著『短歌遠足帖』、くどうれいんとの共著『水歌通信』、詩集『朝、空が見えます』、絵本『あめ ぽぽぽ』(絵・木内達朗)、『わたしのマントはぼうしつき』(絵・町田尚子)、『シマちゃん モモちゃん もりのなか』(絵・松田奈那子)など著書多数。