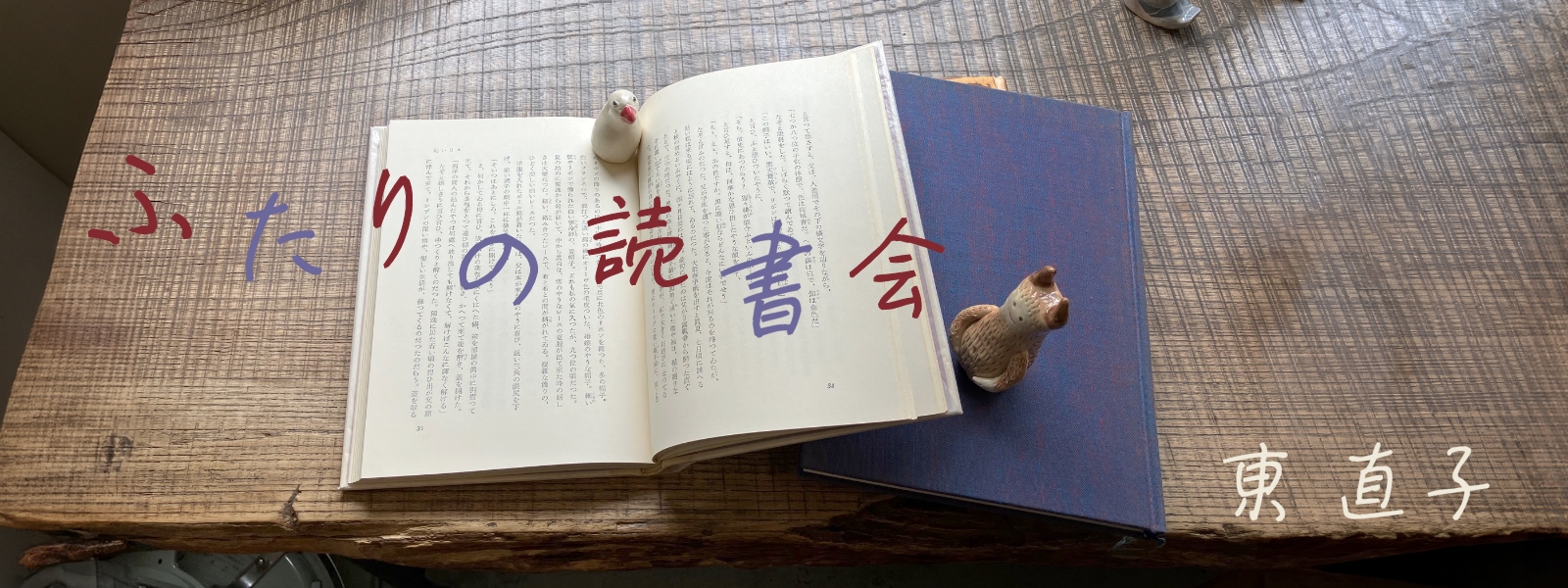書評家のワコさんと大学生のリリ。三〇歳も年の離れた、二人きりの家族。
親子のようで、親友のようで、そのどちらでもない。
二人は、いくつもの本を通して日々揺れ動く気持ちを伝えあう。
白い蝋燭に火をともしたら、二人きりの読書会が始まる。
ゆっくりと心が満ちていく読書の時間へ──。
青いテント、無数の言葉 前編
リリは、大学内にあるパン屋で購入したサンドイッチを持って芝生の上をさくさくと早足で歩いていった。二限が終わったあとの昼時の食堂はとても混むので、いつもテイクアウトできる物を買って校内のどこかでさっさと済ませるようにしていた。
大学は郊外にあるためか敷地が広く、公園のように広々とした芝生がある。そこを横切ってさらに奥に進んでいくと、森のように大木が茂っている場所がある。ところどころに腰をかけられるように置かれた平たい大きな石があり、リリはそこに座って一人で昼ご飯を食べるのが好きだった。
この日も、その大きな石の表面の埃をてのひらでさっと払って腰かけた。持参している水筒には、家で淹れたあたたかい紅茶が入っている。九月なかば、大学の秋期が始まったばかりである。草木はまだ青々としていて、少し歩くとたちまち汗ばむ。しかし木漏れ日を揺らす風は、秋の気配を含んでいて、心地よい。
ハムサンドをぱくぱくと平らげ、フルーツサンドをひと齧りしたところで、背後でガサリと音がして、リリは肩をすくませた。振り返ると、森の奥の方に人影が見えた。だぼっとした衣服とボサボサの髪の人影が、森の奥の方へと逃げるように去っていった。
一瞬のできごとだったが、リリはそのまましばらくかたまってしまった。
今の人、まるで森に住んでいるような雰囲気だった、とリリは思う。そのまま昼食を中断して次の教室に向かっていると、同じ授業を受けている里村さんに会った。森で会った人のことを伝えると、里村さんは、ああそれ、と、思い当たることがあるようだった。
「夏休みの間に、学校にホームレスの人が一人住みついちゃったって、うわさを聞いたよ」
「え、じゃあ、あの人……」
ほぼシルエットだけを見た状態だが、そのような風貌に確かに見えた気がする。
「やっぱり本当だったんだ。でもそのうちにその人、追い出されちゃうんだろうね」
ささやくように言う里村さんに、リリは「うん……」とひとことだけこたえた。
あんなに暑かった夏の間、この大学の中にひそんで暮らしていたのかな。森になっているから少しは涼しいかもしれないけど、この異常に暑い夏はだいぶ厳しかったんじゃないかな。今になって追い出されても、その人はどこに行くんだろう。
リリの頭の中で、ボサボサの髪の人がふらりふらりと都市をさまよう姿が浮かび上がる。ゆっくりと顔をあげ、髪をかき上げて見えてきた顔は、鏡の中にいつもいる自分の顔だった。
「わ」
自分の想像に自分で驚いて、思わず声が出てしまった。
街の中で、ふいに見かける道で眠っている人のことが、リリは子どもの頃から気になっていた。
「しっかり生きないとね」
リリが釘付けになっている視線の先にいる人を見ながら母親がそう言ったことを、まだ覚えている。
リリの家族はずっと、母親の杏子一人だった。杏子は結婚せずに一人でリリを産んだのである。生まれたときから二人きりの家族だったので、それがあたり前のことだとリリは思っていた。二人きりの母子家庭のことを、さびしいでしょう、とか、不安だよね、などと言う人がときどきいて、そういうふうに感じる人もいるのかと驚いた。
しかし、ふいに耳に入ってきた母親の「しっかり生きないとね」の一言は、つんとした痛みと共にリリの胸に焼き付いたのだった。
しっかり生きていかないと、こんなふうに道で寝るような事態になってしまうよ、という意味だとそのときも理解したのだが、「しっかり生きる」ということがどういうことなのか、なにをすればいいのか全くわからず、ふっと身体がつめたくなっていくような感覚を覚えた。そして、もしもたった一人の母親がいなくなってしまったら、自分も今いる家を追い出されて、どこにも居場所がなくなってしまうのだ、ということを初めて考えたのだった。
どうしようもなく不安になる、という感情にリリはおそわれた。「しっかり生きないとね」の言葉の背後には、茫漠とした不安がはりついていたのだ。ホームレスの人を見かけるたびに、あれは自分かもしれない、という潜在意識が淡く浮上する。
そしてあの日、長く漂っていた漠然とした不安が、現実になってしまったのだ。
リリは十歳。仕事で泊まりがけの出張があるときは、いつも杏子の友人であるワコさんの家に泊まっていた。このときは一泊した次の日の夜に帰宅する予定だったので、ワコさんの家で夕ご飯を食べさせてもらって、出張帰りの杏子が迎えにくるのを待っていた。
午後八時までには着くと言っていたのに、九時になっても、十時になっても、杏子は来なかった。約束した時間はきっちりと守る性格だったので、リリもワコさんもひどく心配になった。ワコさんは、杏子になんども電話したり、メールをしたりしたが、返信がなかった。
その頃のリリは携帯電話をまだ持っていなかった。不安がこみあげてきたものの、ワコさんに遠慮してがまんしていたが、ついにタガが外れたようにはらはらと涙を流しはじめた。泣きながら震える小さなリリの肩を、ワコさんはそっと抱きしめた。
「大丈夫だよ、杏子さんはすぐに帰ってくるよ。きっと、電車がとまったとかで帰れなくて、電波がないとか、電源が切れているとか、そんなところだよ、そうだよ」
「ママしかいないのに……、ママしかいないのに……」
リリは、ワコさんに抱かれたまま、小さな小さな声でなんどもつぶやいた。
あのとき、ママは戻ってこなかった。永遠に。
リリは、今でも胸をつめたく貫くあの日のことをまた思い出す。杏子の電話からの着信を受け取ったワコさんが受話器から聞いた声は、杏子の声ではなかった。出張先での杏子の病死を知らせる、警察官の声だった。
リリは授業後にもういちど大学の森の方に歩いていった。今回は、石の椅子でスマホを触ったり、本を読んだりしている人が三人いた。リリは、人影を見かけた森の奥の方へ、ゆっくりと足を進めた。しばらく歩いてあたりを見渡した。誰もいなかったが、一枚のブルーシートが目に入った。きちんと四角く畳まれた鮮やかな青い色が、ここにいましたよ、と無言で告げているように思えて胸を突かれた。
あの人は、どこに行ったのだろう。もしも私たちの夏休みが永遠に続いていたらずっとここにいることができたのかな。
リリはブルーシートの前にしゃがんで、てのひらでそっとふれた。ほんのりあたたくて、じんわりとしめっていた。
「家を失うかもしれないっていうのは、私もなんども考えたよ」
リリから話を聞いたワコさんが、タマネギの皮を剥きながらしずかな声でこたえた。
「そうなんだ」
リリは隣でじゃがいもの皮をピーラーで剥いている。
「ずっとフリーで仕事をしてるから、いつか全く仕事がなくなるんじゃないかっていう不安は常にあるよ。最初はアルバイトをしながらいろんな頼まれ事をこなしつつ、今は念願の書評の仕事だけでやっていけるようになったのは、ほんとにラッキーなことだったと思う」
ワコさんは、皮を剥いたタマネギの根のところを包丁で切り落とした。
「それは、ワコさんに才能があったから、当然の結果なんじゃないかな」
リリはじゃがいもの芽をピーラーの突起でほじり出しつつ言った。
「仕事が成立してるから、そういう見方もできるかもだけど、私よりずっとよく本を読んでいて、おもしろい評が書ける子は文学部の同級生に何人もいたから、自分は書く場所を与えられた環境にたまたまいられたんだなって思ったりするよ」
「そうなんだ。でも何が得意かはっきりしてたから、環境に近づけたんだよね。私には、何ができるのか、まだぜんぜん見えないな」
リリは手を止めて考え込んだ。
「何ができるかも大事だけど、何がやりたいかの方が大事なんじゃないかなあ」
「それは、そうだね」
「そうそう。でも、それ、そんなに焦って見つけることないからね。私も、学生のときなんて、ただただぼんやり、雑食的に読んでただけだったから……ん、タマネギ、きた」
タマネギが目にしみたワコさんは涙が流れ出した目をぎゅっとつむって、洗面所に走った。
リリは、くすくす笑いながらワコさんの背中を見送って、櫛形に切られてまな板の上に放置されたままのタマネギをさっと集めてボールに入れた。
「でね、リリの話を聞いて、この本のことを思い出した」
夕食のカレーを二人で食べたあと、ワコさんがリリに一冊の本を手渡した。
「『小山さんノート』小山さんノートワークショップ編……」
リリが表紙の文字をゆっくりと読み上げた。
「ホームレスだった女性が残した手書きのノートを、その人が亡くなってから有志が書き起こして纏めたものなんだよ」
「そうなんだ。〝小山さん〟って呼ばれていたんだね」
リリは緑色の木々の真ん中に鮮やかな青いテントが描かれた装画の表紙をめくり、最初の方のページをめくって読んだ。
1991年1月7日
子どもの頃からの性質がぬけない。いつも、女のくせに生意気だとおさえ、おさえ続けられてきた。
そして、現実の自分は何なのかと問われたら、何にもなりきれなかった。
「女のくせにっておさえられて生きて、そして、自分はこれだって言えるものが何もないままできてしまったって思っちゃったんだ。……苦しそう」
眉間に細い皺を寄せてリリが言った。
「この日記には、いろいろな苦しみが書き続けられていて、正直、読んでいてずっと苦しい。でも、小山さんはこれを書かずにはいられなかった。書くことで心を保ち、自分を保ち続けてきたんだと思う。びっしりとノートに文字を刻んで、何冊も、何冊も、しっかり書き込んで、何度も読み返して、書き直して。どんなことがあっても大量の日記を大事に保存し続けたのは、誰かに、知ってほしかったんだろうって、まわりの人も思って、何人もの人が手助けをして、何年もかけて本になったんだよ」
「そうなんだね……。たった一人の思いでも、伝えてもらえるって、すごいことだね。苦しいの覚悟で、読むよ、ワコさん」
*後編につづく
<引用文献>
小山さんノートワークショップ著『小山さんノート』 (エトセトラブックス)2023年刊
p.22 下段5行目~9行目
広島県生まれ。歌人、作家。
1996年、「草かんむりの訪問者」で第七回歌壇賞受賞。2016年、『いとの森の家』で第三一回坪田譲治文学賞を受賞。
2006年に初の小説『長崎くんの指』を出版。
歌集『春原さんのリコーダー』『青卵』『十階』、小説作品『とりつくしま』『さようなら窓』『薬屋のタバサ』『晴れ女の耳』『階段にパレット』『ひとっこひとり』『フランネルの紐』、エッセイ集『一緒に生きる 親子の風景』『レモン石鹼泡立てる』『魚を抱いて 私の中の映画とドラマ』、歌書『愛のうた』、『短歌の詰め合わせ』、『短歌の時間』『現代短歌版百人一首 花々は色あせるのね』、穂村弘との共著『短歌遠足帖』、くどうれいんとの共著『水歌通信』、詩集『朝、空が見えます』、絵本『あめ ぽぽぽ』(絵・木内達朗)、『わたしのマントはぼうしつき』(絵・町田尚子)、『シマちゃん モモちゃん もりのなか』(絵・松田奈那子)など著書多数。