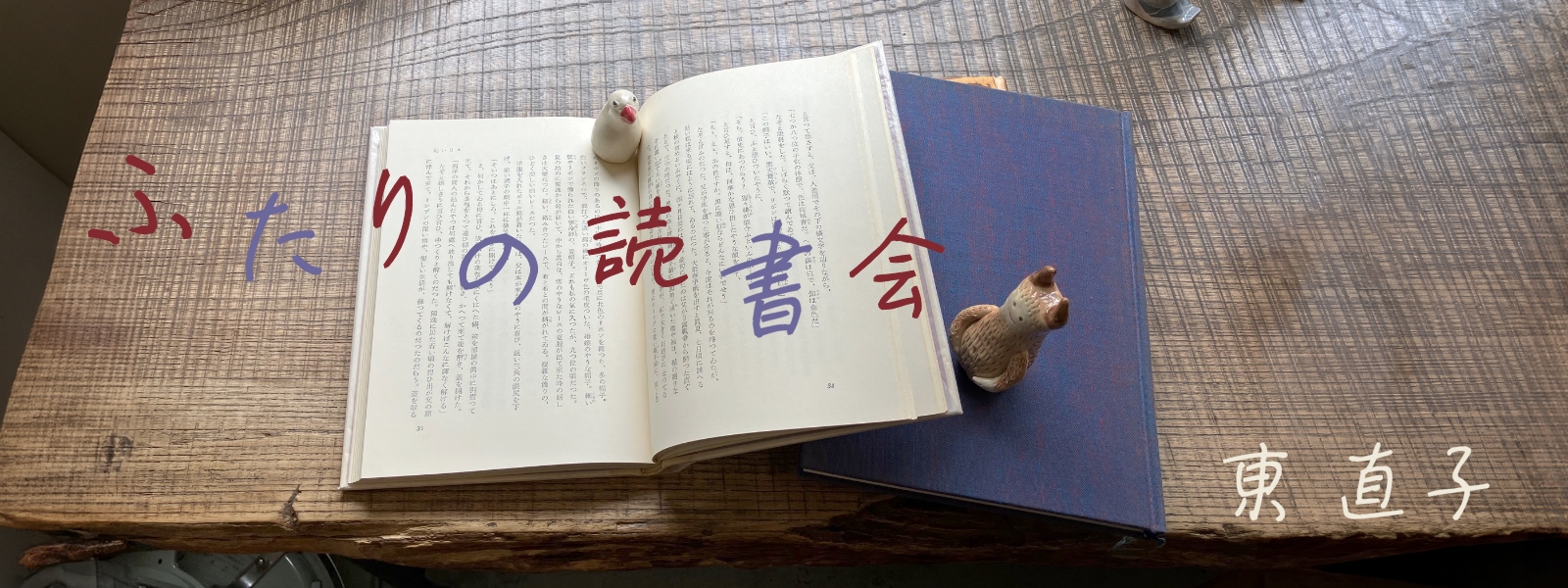書評家のワコさんと大学生のリリ。三〇歳も年の離れた、二人きりの家族。
親子のようで、親友のようで、そのどちらでもない。
二人は、いくつもの本を通して日々揺れ動く気持ちを伝えあう。
白い蝋燭に火をともしたら、二人きりの読書会が始まる。
ゆっくりと心が満ちていく読書の時間へ──。
木の上にのぼる 前編
まず洗面台で軽くうがいをする。顔を洗ってタオルで水分をぬぐい、化粧水と乳液で簡単に肌を整える。それから、リビングルームに入ってすぐのところに吊るしている日めくりカレンダーを一枚めくる。それがワコさんの朝の起き抜けのルーティーンである。この日もいつものようにカレンダーを一枚めくったところで、あ、と小さな声が出た。そこには「ママの生まれた日」と、オレンジ色のペンで書いてあったからだ。
「今日は、杏子さんの誕生日だった」
ワコさんはつぶやいた。オレンジ色の書き込みは、リリが書いたものである。
リリはダイニングテーブルについて、自分で焼いたパンをかじっていた。マグカップにはカフェオレが湯気を立て、目玉焼きが二皿分、置いてある。
「私の分の目玉焼きも作ってくれたんだね」
「うん。ついでだから。パンは焼き立ての方がいいかと思って、まだ焼いてない」
「わかった。ありがと」
ワコさんはキッチンのトースターに食パンをセットした。ティファールで湧かした湯で紅茶を淹れながら「杏子さん、生きてたら今日で四七歳だね」と、リリに声をかけた。
リリは、小さく、そっか、と声を出した。
「ママ、お誕生日おめでとう」
リリは手を合わせた。
「杏子さん、おめでとう」
ワコさんもキッチンで手を合わせた。
「杏子さんの方が、私より一ヶ月だけお姉さんなんだ」
ワコさんは、トーストと紅茶を丸い木のお盆に載せて運び、リリの向かいに座った。
「ママ、今も生きてたら、なにをしてたかなあ」
「そうね。相変わらずバリバリ働いてただろうね」
「うん……」
「杏子さんと初めて会ったときね、杏子さん、木の上にいたんだよ」
「木の上? なんで?」
「わかんない。でも、木の上で暮らす人の話を読んでたから、その気分を味わいたかったんじゃないかな」
ワコさんが楽しそうに言った。
「木の上で暮らす人?」
「そう。その本を木の上から落としたの。私はそのときその木の下に座って本を読んでて。びっくりしちゃった。とつぜん空から本が落ちてきたんだから」
「あぶないじゃん」
「目の前に落ちただけで、身体には当たらなかったんだ。もし当たったとしても軽い文庫本だったから、大したことなかったと思うよ。でも、木の上から『ごめんね』って、声がふってきたの。それが杏子さん。私たちの初めての出会い」
「え、そんな出会いある? なんだか童話みたい」
「ね。私たち、すっかり大人だったけど」
ワコさんは、木の上の人を見上げるように、顔を上げた。
「杏子さんは、大きな公園の、大きな木の太い枝に、パンツスーツですっくと立ってた。逆光で顔はよく見えなかったけど、そのシルエットがすごくかっこよかった。〝正義の味方、ここに参上〟みたいだったよ」
「なんだそれ〜」
頭の中で木の上に立つ「正義の味方」のシルエットを想像して、リリはくすくす笑った。ワコさんもつられて笑った。
ひとしきり笑ったあとで、しんとした時間が訪れた。
「で、それ、なんて本? ママとワコさんを出会わせてくれた本、私も読んでみたい」
「うん。リリにもぜひ読んでほしい。杏子さんが、いちばん好きで心安らぐけれど、いちばん悲しくなる本なんだって、何度も読み返してるって言っていた本だから」
「心安らぐのに、いちばん悲しくなる……?」
「読めば、意味は分かると思う。トルーマン・カポーティの『草の竪琴』っていう本だよ」
「草の竪琴……すてきなタイトルだ。どこの国の人?」
「アメリカだよ。あとで探しとくね」
「うん。ありがと」
リリはマグカップをテーブルに置いて、目を閉じた。幻の「草の竪琴」の音に耳を澄ますように。
ワコさんから手渡された新潮文庫の『草の竪琴』には、白い花がちりばめられた藍染めのブックカバーがかけられていた。
「この本、こういう状態で杏子さんからもらったの。あのとき驚かせたおわびに差し上げますって言って。ブックカバーは読んだらはずして使ってね、という意味だったと思うけど、このままにしておいたんだ」
「本も新しく買ったものなんだね」
「そうみたい。自分で読んでいたのは、大分ぼろぼろだったから」
「きれい」
リリは、小動物をなでるように藍色のブックカバーをなでてから、最初のページを開いた。〝深い愛情の記念として、ミス・スックに捧ぐ〟という一文が目に入る。
「これ、なんていうだっけ、〝〜に捧ぐ〟って書いてるの」ワコさんに尋ねた。
「〝エピグラフ〟だね。本の内容に深く関わった人への謝辞を込めたもの。〝ミス・スック〟は、作者のカポーティの年上の従姉妹で、両親の離婚で親戚をたらい回しにされていた幼いころに一緒に暮らしたことがあって、深く心を寄せていた人みたい」
リリは、へえ、とつぶやいてから、冒頭を黙読した。
《僕がはじめて、草の竪琴のことを聞いたのはいつのことだったろう。あの秋をむかえるずっと前から、僕たちはムクロジの木に住んだことがあったけれど、あれはたしか夏が終ってまもないころだった。もちろん教えてくれたのは、ドリーをおいて他にはいない。誰もその呼び方を知っている者はいなかったのだから。草の竪琴というその名を。》
「ファンタジーのはじまりみたい。ワクワクする」
リリが目を耀かせた。
「そうね、一般的なファンタジーのイメージとはだいぶ違うとは思うけど」
ワコさんが眉を少し上げて言った。
授業が始まる前の教室でリリが『草の竪琴』を読んでいると、同じ授業を取っている里村さんが「なに読んでるの?」と声をかけてきた。
「え、カポーティ! 私すごく好きなんだけど」
「そうなんだ。私は、初めて読むんだ。私のママが好きだったみたいで」
「『ティファニーで朝食を』を書いた人だもんね」
「あ、オードリー・ヘップバーンの映画の?」
「そう」
「そうだったんだ。映画、観たことないけど」
「私はあるよ。親がDVD持ってたから。今は配信で観られるかもね」
「だいぶ前の、アメリカのお洒落映画?」
「まあ、そんなとこだと思うけど、主人公の境遇って案外重いし、いろいろぶっとんでるよ。原作の方がそれが詳しく分かるから、両方味わった方がいいと思う。あ、ママがそういう話はもうしてたか」
「ううん。ママは十年前に亡くなったんだ」
「え、リリって、そうだったんだ」
里村さんが声のトーンを落として言った。
「うん。今はママの友達と住んでで、ママが好きだったことはその友達から聞いて、本を貸してもらったんだ」
「えっと、聞いていいのかな。お父さんは……?」
「お父さんは、最初からいないみたい。会ったことなくて、名前も分からない。詳しいことはなんにも教えてくれなかったし、まわりの人も知らないんだって」
「そっか……。カポーティも小さい頃から……」
里村さんが言いかけて、途中で止めた。リリは、その先の言葉を、なんとなく察した。里村さんは、一瞬目をそらせてから、笑顔をリリに向けた。
「えと、それ、その『草の竪琴』私もすごく好き。泣いた。泣いたっていうか、もやもやした。あ、いい意味でだよ。リリも読み終えたら、ぜひ感想きかせて」
「うん」
そこへちょうど「短詩型文学論」の先生が教室に入ってきたので、二人は会話を止めた。
ワコさんは、ラベンダーとマロウブルーで淹れたハーブティーを白いティーカップに注ぎ、その上から櫛形に切ったレモンを搾って、ぽたぽたと汁を落とした。淡い青紫色のお茶が、みるみるとばら色に変化していった。
「すごい、夜明けの空を見てるみたい」
「いいでしょ。眺めてるだけで和むよね。ドリーさんの作る水腫薬にちなんで、神秘的なハーブティーを淹れてみました。さてリリさん、どうでしたか、『草の竪琴』は」
「ママがこの話を好きだったこと、なんとなくわかった。主人公のコリン少年って、両親を失って、父親の従姉妹にあたるドリーとヴェリーナの姉妹に引き取られるけど、作者の境遇とほとんど同じなんだね。コリンも、コリンと仲良くなる年の離れたドリーも、ドリーの世話を焼くキャサリンも、それから、あとから木の上の住人になる判事やライリーも、幸福な時間が失われたあとの孤独を抱えてて、無意識のうちによりどころを求めてる」
「そうだね、孤独が苦しいというより、すでに受け入れてはいるけど、やっぱり何かのよりどころがほしいと切実に願っている」
「とつぜん家出することになってみんなで住むムクロジの木の上の家が、それになるんだね」
*後編に続く
<引用文献>
トルーマン・カポーティ著 大澤薫訳『草の竪琴』(新潮文庫) 1993年刊
p.4、p.5 1~4行目
広島県生まれ。歌人、作家。
1996年、「草かんむりの訪問者」で第七回歌壇賞受賞。2016年、『いとの森の家』で第三一回坪田譲治文学賞を受賞。
2006年に初の小説『長崎くんの指』を出版。
歌集『春原さんのリコーダー』『青卵』『十階』、小説作品『とりつくしま』『さようなら窓』『薬屋のタバサ』『晴れ女の耳』『階段にパレット』『ひとっこひとり』『フランネルの紐』、エッセイ集『一緒に生きる 親子の風景』『レモン石鹼泡立てる』『魚を抱いて 私の中の映画とドラマ』、歌書『愛のうた』、『短歌の詰め合わせ』、『短歌の時間』『現代短歌版百人一首 花々は色あせるのね』、穂村弘との共著『短歌遠足帖』、くどうれいんとの共著『水歌通信』、詩集『朝、空が見えます』、絵本『あめ ぽぽぽ』(絵・木内達朗)、『わたしのマントはぼうしつき』(絵・町田尚子)、『シマちゃん モモちゃん もりのなか』(絵・松田奈那子)など著書多数。