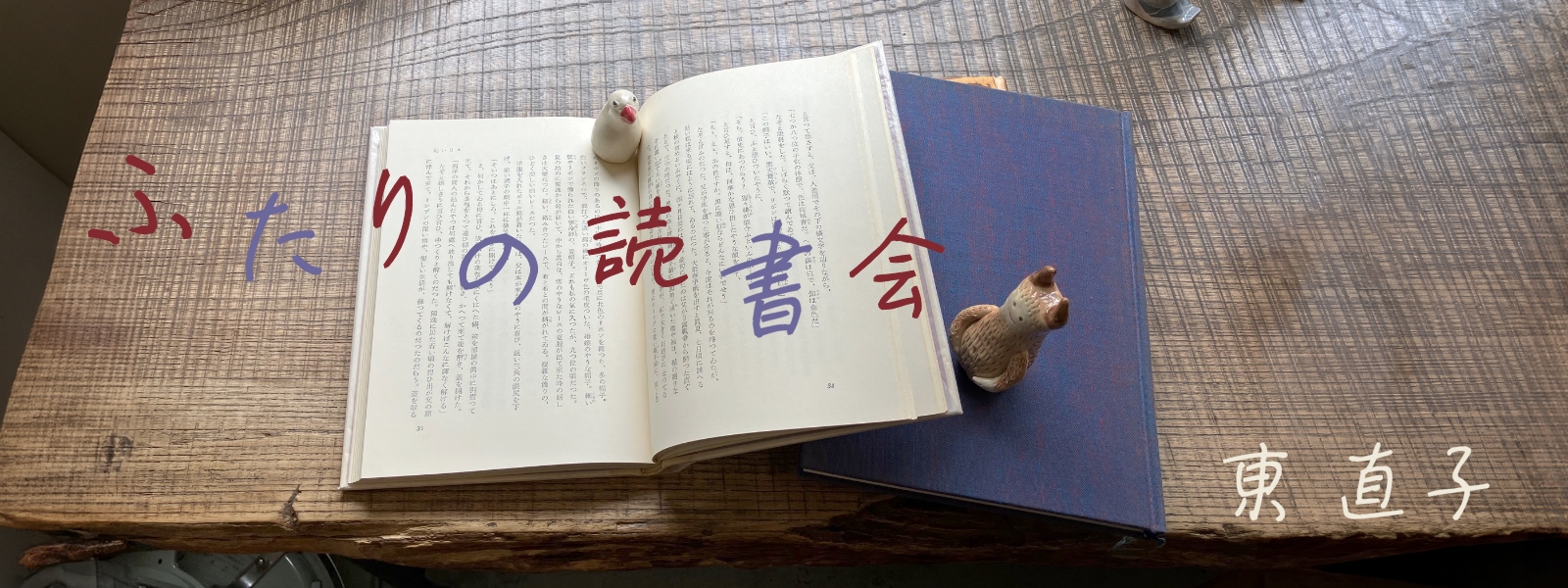書評家のワコさんと大学生のリリ。三〇歳も年の離れた、二人きりの家族。
親子のようで、親友のようで、そのどちらでもない。
二人は、いくつもの本を通して日々揺れ動く気持ちを伝えあう。
白い蝋燭に火をともしたら、二人きりの読書会が始まる。
ゆっくりと心が満ちていく読書の時間へ──。
木の上にのぼる 後編
ワコさんはリリの言葉に頷きながら、このところ読んできた本がみんな孤独感が底を流れているものばかりだったと思う。
「で、出てくる人たちがみんな漫画みたいにキャラが立ってて、一人一人どこか変で、でもいつか会ったことがあるような気がするし、自分にもこういうとこあるよなあ、って思わせてくれる。ママは誰に共感したのかなって、考えながら読んでた」
「杏子さんは有能だから、たくましく事業展開しているヴェリーナっぽいけど」
「でもヴェリーナは、この小説では主人公のコリンや姉のドリーと敵対する相手になってしまったよね。主人公と敵対するような人物に自分を重ねるかなあ」
「そこなんだけどね、すごく久しぶりにこの本を読み返しみて、以前は考えなかったヴェリーナの気持ちが気になったんだよね」
「へえ」
「ヴェリーナは、ドリーが野草から作っていた水腫薬を工業化するためにそのレシピを聞き出そうとしてきっぱり拒否されるわけだけど、ドリーに著作権のある事業を残すことで、自分にもしものことがあったとしてもドリーやコリンに引き継いでふたりが生きていけるように、ということも考えていたのではないかなって、ふと思ったの。いつも自分に従順なドリーが自分の提案を断るなんて夢にも考えていなかっただろうし、すべてよかれと思ってやってたことなんだから」
ワコさんの話を神妙に聞いていたリリは、視線を遠くに飛ばしながらしばらく考えた。
「確かに、〝みんなあなたのためなのよ〟って、本人も言ってる。たった一人の姉のドリーのことを家族として大切に思っていたことは間違いないだろうし、家庭が崩壊したコリンを引き取ることを決意したのもヴェリーナだったし。いろいろキツいところはあるけど、ちゃんと情はあるんだよね。じゃあ、ママがヴェリーナに共感したんじゃないかって、ワコさんは思ってるの?」
「さすがに一番共感したってことはないと思うけど、ヴェリーナの方も理解した上で、物語全体の熱気を愛でていたんじゃないかな」
「なるほど。ママは、少なくともドリーには似てなかった。六十歳にもなってなにかにおびえ続ける少女のように、妹のヴェリーナの庇護のもと、ピンク色に塗りこめた部屋にひきこもっていたドリーには」
「今で言うひきももり状態で、社会の中でうまくやっていくことはできなかったドリーだけど、もっとも魅力的な人物として描かれてるよね」
「そう。誰よりも心やさしくてピュアで、水腫薬を渡す一人一人の相手のことを思って書いてた手紙には感動しちゃった。ただ弱々しいだけじゃなくて、誇り高くて頑固なところもあって。そしてカンが鋭い。なにしろ、ジプシーが口ずさんでいた歌ヒントに薬草を調合して水腫薬というよく効く薬を作っちゃうんだから。妖精っていうより、魔女って感じ」
「魔力があるんだよね。少女時代に身寄りを失ってこの家に引き取られて、お手伝いさんとして暮らしてきたキャサリンはドリーに心酔しているし、コリンも〝彼女の存在を心にとめたそのとき、僕は恋におちてしまったのだ〟って状態だし、判事さんは木の上でドリーの虜になってしまうし、風来坊のライリーもて手なずけてしまうし。で、対照的に、ヴェリーナは誰のことも惹きつけておくことができない」
「うん」
リリが、確認するように頷いた。
「ヴェリーナは、商売上手なのに、人たらしにはなれない。心から好きになった年下の女性は別の人を好きになって遠ざかってしまうし、信頼して水腫薬の事業を任せようとしたドクター・リッツにはひどい裏切り方をされてしまうし」
「あのドクター・リッツのいかがわしさについては、ヴェリーナ以外はみんな気付いてたってところが、悲しいよね。あんなにわかりやすく騙されるなんて、ヴェリーナの寂しさにつけ入ったんじゃないかな」
「ドリーとヴェリーナは対極的な性格だけど、芯に抱えている孤独は同じように深いんだと思う。二人だけじゃなく、孤独のヴァリエーションを、繊細に、絶妙に書き分けてる」
「カポーティって、孤独のエキスパートなんだね」
リリが、ブックカバーをいとおしそうになでた。
「作者の人生と作品とをやたらと結びつけるのっていかがなものかと思ったりもするんだけど、この作品に関しては、やっぱり考えずにはいられない。エピグラフの〝ミス・スック〟はドリーのモデルだって言われているし」
「訳者の大澤薫さんの解説にもそう書いてあったね」
「小説の舞台となったアメリカの南部の町も、カポーティが幼少時代にミス・スックと暮らしていた町と一致する。自分が実際に体験したことを、この不思議な物語に折り込んで書いたことは間違いないと思う」
「子どもの時の強い思いが、その時代を物語として新しく立ち上げたんだね」
リリは、しみじみとした気持ちになり、ティーカップの中の朝焼け色のお茶をしばらく見つめた。そして彼らが見た空のことを考えた。
「木の上から見た朝焼け、格別だっただろうな。ヴェリーナの家を出て、ドリーとコリンとキャサリンは木の上で暮らしはじめて、なかなかハードな環境になってしまったのに、それまでよりずっと生き生きしてる」
「子どもみたいにはしゃいでるよね。自分たちだけの秘密基地みたいなのを作ってわくわくする、あの感じ」
「わかる」
リリの黒い瞳がきらりと光った。
「木の上の世界を思いっきり楽しめるかどうかは、年齢は関係ないんだなって、この世界の人たちを見てて思う」
「そこを楽しみとするか、忌避するべきものとするかが、境界線になっているね」ワコさんが同意するように頷いた。
「ヴェリーナも一緒に楽しめる方の人だったらよかったのに。さびしかっただろうな」
「だけど、ドリーの世界に同化してたら、経済的にたちゆかなくなってたかもしれないけど……」
「そりゃそうだ。ドリーが置き手紙を残して家を出ていったあと、ヴェリーナが保安官に連絡して捜索隊が組まれたときの、内容を伝えるための電報がひどすぎて笑っちゃった」
「私も笑った。〝ドリー・オーガスタ・タルボー。白人、六十歳、卵色がかった灰色の髪、痩せぎす、身長五フィート三、緑色の瞳、やや精神障害の傾向あるも危険性はなきものと推断す。甘味を好む〟だもんね。〝キャサリン・クリーク。黒人。自称インディアン、推定年齢六十歳、歯は無く、言語不明瞭、短躯にして肥満体、強情、凶暴性あり。コリン・タルボー・フェンウィック。白人、十六歳、童顔、五フィート七、金髪、灰色の瞳、痩せぎす、姿勢悪し、口元に傷跡あり、性格無愛想〟。それぞれの体形と習性のみを書いてて、野生動物の探索みたい。だいぶ後になってから発見した文章のようだけど、コリンは〝ドクター・リッツの手になるものと思われた〟って推察してる」
「ドクター・リッツは、三人のことをやっかいな動物くらいに思ってたんだね」
「こんな内容をヴェリーナがOKしたのかって思うと、ヴェリーナの怒りと落胆が感じられて、なんだか……」
「最後の方のヴェリーナ、すっかり人が変わったようになって、胸が痛かった。あれ、私たち、どんどんヴェリーナに気持ちを寄せてるね」
「ドリーとは違う魅力があるんだよ。説得されていくっていうか。リリが最初に漫画みたいにキャラが立ってるって言ったけど、それぞれの言動から目が放せない」
「一人一人、やさしかったり、勇敢だったりはもちろん、欲深かったり、おろかだったり、セコかったりするところも全部、人間的な愛嬌というか、魅力に変わっていくよね。最後の方に出てきた、シスター・アイダって人も、すごいインパクトがあった。十五人も子どもがいて。十五人って、ありえないよね」
「まあ、少し前の世代は日本でも一人の女の人がたくさん子どもを産んでたけど、十五人は多いわね」
「で、十五人も連れてシスターとして独自の布教活動の旅をするまでの過程が滔々と語られていくけど、講談でも聞いているかのようなおもしろさで。お姉さんの結婚相手のダン・レイニーの子どもを産んで、その子を姉夫婦に預けて旅に出たの、確か十六歳だった」
「そうそう、その後ダンの面影を求めて何人もの男の人と関係を持って、次々に子どもを産んで! たくましく生き抜いていく様子は、あっぱれって思った」
「ドリーたちができなかったことを、全部やって豪快に生きてる。ドリーにはまぶしかっただろうなあ。実際〝妹かキャサリンに、赤ちゃんがあったらと思いますわ〟って、アイダに言ってる」
「切ないね。突然現れて木の上の家にも上がって、ヴェリーナをはじめたくさんの町の人を巻き込んで大騒ぎを起こしたあと、みんないっぺんに去っていく。台風みたいな一家だった」
「ドリーと判事に一緒に行こうって言う子どもたちがいて、それ見ていたコリンが〝僕を連れていきたいと思う者は誰もいないようだった〟って思うところで、あ、これはコリンが見ていた世界だった、って思い出した。そういえば、コリンを唯一無二の人として思ってくれる人はいなかったのでは、って」
「コリン……そうかも」
ワコさんは、はっとしたように顔を上げた。
「個性的な人たちがにぎやかに活躍する中、一人称のコリンは、それほど特徴はなくて、誰とも強く衝突はせず、深くは愛されず、わりあい透明な存在で。そして最後の最後まで孤独は癒やされない。最終的に、癒やされないことを嘆くんではなくて、噛みしめている。根深い。なんて根深い小説なんだろう。……ママ、コリンだったのかもしれない」
「杏子さんが、小さい頃から孤独なまま生きてきたって思うの? 子どもの頃のこと、聞いたことある?」
「ううん。ぜんぜん話してくれなかった。でも、おばあちゃんはどこかで生きてるかもしれないけど、二度と会うつもりはないって言ってたから、子どもの頃からうまくいってなかったのかなって、なんとなく思ってた」
「杏子さんのお母さんとは私も連絡がついてないんだよね。お兄さんの貴文さんにはなんとか連絡できてよかった。リリとこうして暮らすことを認めてもらえて」
「うん」
「杏子さんがリリを産むまでのこと、知りたい?」
リリが大きく開いた目の、瞳が揺らいだ。
「それは、知りたい……けど、怖い。今は、まだ、考えたくないかな。自分が本当はどういふうに産まれてきたのかってことは……。何者でもないまま、ここに、ワコさんのところにいさせてほしい。私は居候だって、ワコさんの人生を侵食してるって、気付いてはいるんだけど」
「え、どうしてそんなこと言うの? 侵食なんて、言わないでよ。こんなに、一緒にいると楽しいのに」
「ほんと……?」
リリのゆらゆら揺れる瞳がみるみる潤っきて、涙があふれた。ティッシュを手渡しながら、コリンが、カポーティが流したであろう涙のことを、ワコさんは考えずにいられなかった。
ワコさんの胸の中で、コリンが覚えていたドリーの言葉が蘇る。
《聞える? あれは草の竪琴よ。いつもお話を聞かせているの。丘に眠るすべての人たち、この世に生きたすべての人たちの物語をみんな知っているのよ。わたしたちが死んだら、やっぱり同じようにわたしたちのことを話してくれるのよ、あの草の竪琴は》
<引用文献>
トルーマン・カポーティ著 大澤薫訳『草の竪琴』(新潮文庫) 1993年刊
p.32 2~3行目、p.8 15行目、p.45 17行目~p.46 6行目、p.45 16~17行目、p.141 4行目、p.150 1行目、p.6 1~4行目
広島県生まれ。歌人、作家。
1996年、「草かんむりの訪問者」で第七回歌壇賞受賞。2016年、『いとの森の家』で第三一回坪田譲治文学賞を受賞。
2006年に初の小説『長崎くんの指』を出版。
歌集『春原さんのリコーダー』『青卵』『十階』、小説作品『とりつくしま』『さようなら窓』『薬屋のタバサ』『晴れ女の耳』『階段にパレット』『ひとっこひとり』『フランネルの紐』、エッセイ集『一緒に生きる 親子の風景』『レモン石鹼泡立てる』『魚を抱いて 私の中の映画とドラマ』、歌書『愛のうた』、『短歌の詰め合わせ』、『短歌の時間』『現代短歌版百人一首 花々は色あせるのね』、穂村弘との共著『短歌遠足帖』、くどうれいんとの共著『水歌通信』、詩集『朝、空が見えます』、絵本『あめ ぽぽぽ』(絵・木内達朗)、『わたしのマントはぼうしつき』(絵・町田尚子)、『シマちゃん モモちゃん もりのなか』(絵・松田奈那子)など著書多数。