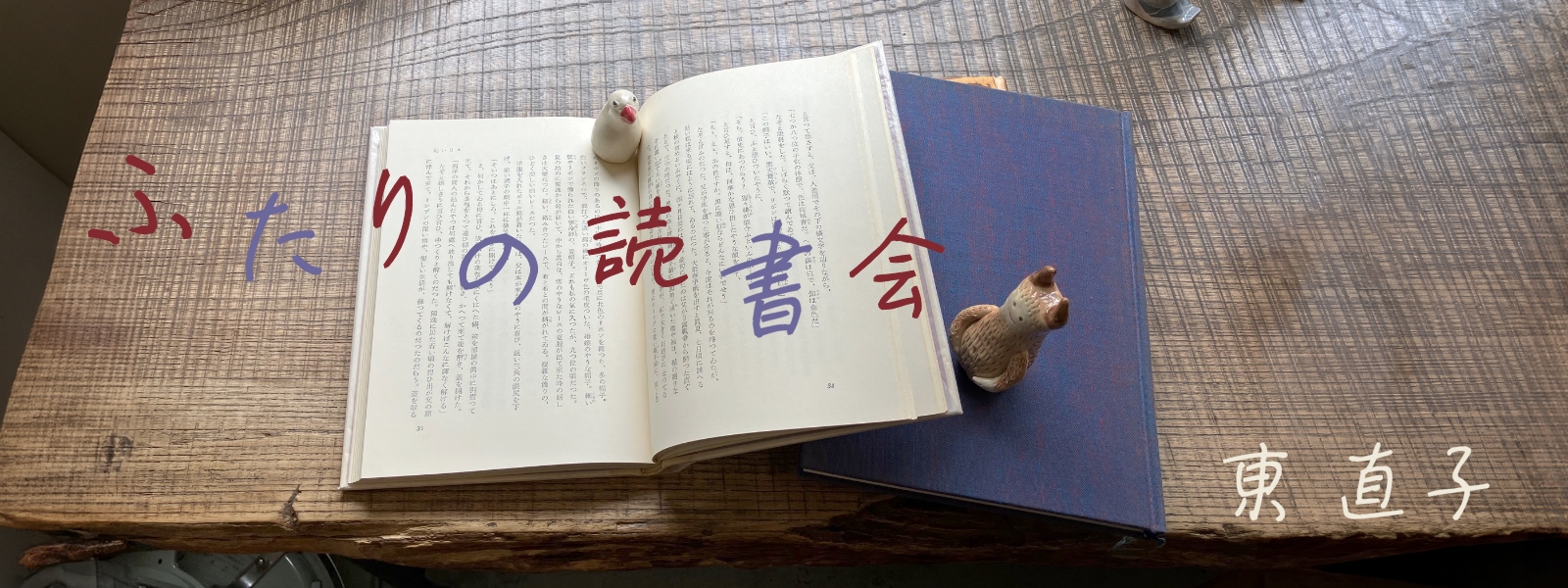書評家のワコさんと大学生のリリ。三〇歳も年の離れた、二人きりの家族。
親子のようで、親友のようで、そのどちらでもない。
二人は、いくつもの本を通して日々揺れ動く気持ちを伝えあう。
白い蝋燭に火をともしたら、二人きりの読書会が始まる。
ゆっくりと心が満ちていく読書の時間へ──。
永遠のはっさく 前編
「二時三五分」
ワコさんはデジタル時計を眺めた。午前二時三五分。外は暗い。二九度設定のクーラーをかけっぱなしの部屋はどんよりと蒸し暑く、目が覚めてしまったのだ。ぼんやりとした頭でベッドに仰向けに寝たまま足の裏を合わせ、両手をばんざいのように上げた。外から見ると、とっても姿勢の悪い人のように見えるが、こうすると股関節や腰、脇の下が伸びて気持ちがいいのだ。そのうちにまた自然に眠ってしまうことが多いのだが、この夜は違った。
「弱者」
何度も思考の水平線上に浮上しては沈むを繰り返していた言葉を、小さくつぶやいた。昼間に急に電話をかけてきた編集者が、何度も口にした言葉だった。
(あのですね、たいへん申し訳ないのですが、タイトルに使っている「弱者」という言葉が違和感があるので変えてほしいと、先生に言われまして……)
「先生」と呼ばれているのは、ワコさんが書評をした本の著者のことである。身体の小さないじめれっ子、働き口が見つからず居場所のない人、持病を抱えている人など、弱い立場にいる人々を見守るような描写が多かったため、書評のタイトルを「弱者を見守る視点」としたのだ。その「弱者」に強い違和感があるというのだ。
(その、つまり、先生の中では人間を「弱者」「強者」に分類するのはナンセンスだとおっしゃっていて、「弱者」という言葉は自分の世界にはない、ということなんです)
そう言われて、ワコさんは戸惑った。「先生」の世界の中にはなくても、日本の辞書には「弱者」という言葉が確かにある。
(もちろん書評が作者の意向を汲まなくてはいけないってことはない、作者が口出しすべきではないとは思っているけれども、出版元の雑誌にこういうふうにタイトルで使われるれるのは困る、ということだそうで)
ワコさんは話を聞きながら「弱者」という言葉を電子辞書で確認した。
《弱い者。力のない者。社会的に弱い立場にある者》
まさに、この作者が背中を押そうとしたのはこうした人たちのことではなかったの?とけげんな気持ちが胸の中でさらに濃くなる。
意味的には間違っていなくても憎んでいる言葉、それが「先生」にとっての「弱者ってことですね、と、ちょっと嫌みな言い方をしているなと思いつつ、編集者に確認した。
ワコさんはその後、少し考えてから、「逸脱する心のゆくえ」というタイトルの変更案をメールで送り、それが採用になった。結果的にその方がよかったような気もしたが、自分の世界にないからといって、他の人の書いた文章で言葉を使用禁止にするのって、どうなんだろうと、もやもやする気持ちがぬぐえなかった。
未明に目覚めた脳が、ふたたびそのことを考えてしまったのだった。
「弱者」と「強者」、そんな分かりやすい分断を意識して書いたわけではない、と思ったのだろう。確かにどちらとも取れない微妙な心理を汲んでいた文章だったし、登場人物も「あなたは弱者」と決めつけられたらむっとしたかもしれない。
親を失った子ども(リリ)とフリーランスの書評家(私)。うちは社会的な弱者二人が暮らす家だな、とワコさんはしみじみと思った。でも「弱者」って言葉で十把一からげにするな、と同じような立場の人たちが抗議するような気もする。「同情するなら金をくれ」というドラマのセリフがだいぶ前に話題になったが、同情というのは、同情される方にとってなんの足しにもならない上にちょっと屈辱的でもあるからやっかいだ。でも本来、他の人の心に寄り添って、悲しみを自分のことのように感じるのは、やさしい気持ちの表れでもあるんだが。
ぐるぐると考えているうちに眠気が押し寄せてきて、ワコさんはふたたび眠りに落ちた。
目が覚めたとき、すっかり陽が高くなっていた。一限の授業があるリリはすでに学校にでかけていて、家の中は静かだった。ダイニングテーブルに、一冊の文庫本が置いてあり、その上に付せんが貼ってあった。付せんには、リリの字で「コレ!」とだけ書かれていた。表紙には額縁のような四角い黄色い線が描かれていて、その内側に「えーえんとくちから 笹井宏之」とある。「えーえんとくちから」ってどういう意味だろうと思いつつページを開くと、行間をあけた二行ずつの言葉が並んでいる。ぱらぱらと目を通して、あ、これは短歌だ、とワコさんは気づいた。
本の上の付箋の「コレ!」は、「これを読んでみて。こんど読書会をしよう」の略だとワコさんは理解した。
えーえんとくちからえーえんとくちから永遠解く力を下さい
冒頭の一首をワコさんはじっと見つめた。これがタイトルになったんだ、と思う。ひらがなの「えーえんとくちから」は、えーんえーんと泣き声を口からこぼしている赤ん坊の姿がぼんやりと浮かぶ。それが繰り返されているから、ずっと赤ん坊が泣き続けているようなやるせない印象があるが、最後の漢字表記でそれが覆される。なるほど、永遠を解く力を下さいって言ってたんだ、と一瞬納得したが、新しい疑問が湧き上がる。
「永遠解く力」って何? さらに「下さい」って、どういう状況?
分からないけど、なんか分かるような。なんだろうこれ。まったく初めて味わう感覚だ。そう思いながら次のページを開いた。
二十日まえ茜野原を吹いていた風の兄さん 風の母さん
こんどは随分とファンタジックな世界、とワコさんは思う。風を擬人化していて、景色は見える。安房直子の童話『北風が忘れたハンカチ』で、風の親子が登場したことを思い出す。ひとりぼっちのくまの家を、北風の父親と母親と娘が別々に訪ねる話だった。大人の親二人は冷酷で、まだ少女だった娘は清らかでやさしかった。
「茜野原」に吹いていた「風の兄さん」と「風の母さん」はどんな性格で、どんな関係だったのだろう。「二十日まえ」に二人は一緒にいたのかもしれないけど、間に一字あいてるから、「風の母さん」はもっと遠い日にいたのかもしれない。歌の主人公は二十日前に「茜野原」で風に吹かれていたことを思い出している。あのときの風は、風の兄さんが吹いていた風。あの兄さんにはきっと「風の母さん」がいるだろう。主人公にとっての「母さん」も、風のような存在なのかもしれない。なんだか切ないけれど、どこか爽やか。たったこれだけの言葉でできているのに、なんて広がるんだろう。いや、たったこれだけの言葉だから広がるんだな、きっと。
最初の二首ですでに胸がいっぱいになり、ワコさんは目を閉じた。暗闇の中で、遠い誰かが泣いている。こころもとなく、不安で、淋しくて、泣くしかなくて泣いている。泣き声のまわりからぼんやりと明るくなって、茜色の野原が見えてくる。野原には、風が吹いている。なにか大きな力を秘めた泣き声だと思う。
目を開いて、次の歌に目を移した。
この森で軍手を売って暮らしたい まちがえて図書館を建てたい
…………どいうこと……? とワコさんは思った。
「永遠のはっさく」後編に続く
<引用文献>
笹井宏之『えーえんとくちから』(ちくま文庫)2019年刊
掲載ページ p.5、p.6・1行目、p.6・2行目
広島県生まれ。歌人、作家。
1996年、「草かんむりの訪問者」で第七回歌壇賞受賞。2016年、『いとの森の家』で第三一回坪田譲治文学賞を受賞。
2006年に初の小説『長崎くんの指』を出版。
歌集『春原さんのリコーダー』『青卵』『十階』、小説作品『とりつくしま』『さようなら窓』『薬屋のタバサ』『晴れ女の耳』『階段にパレット』『ひとっこひとり』『フランネルの紐』、エッセイ集『一緒に生きる 親子の風景』『レモン石鹼泡立てる』『魚を抱いて 私の中の映画とドラマ』、歌書『愛のうた』、『短歌の詰め合わせ』、『短歌の時間』『現代短歌版百人一首 花々は色あせるのね』、穂村弘との共著『短歌遠足帖』、くどうれいんとの共著『水歌通信』、詩集『朝、空が見えます』、絵本『あめ ぽぽぽ』(絵・木内達朗)、『わたしのマントはぼうしつき』(絵・町田尚子)、『シマちゃん モモちゃん もりのなか』(絵・松田奈那子)など著書多数。