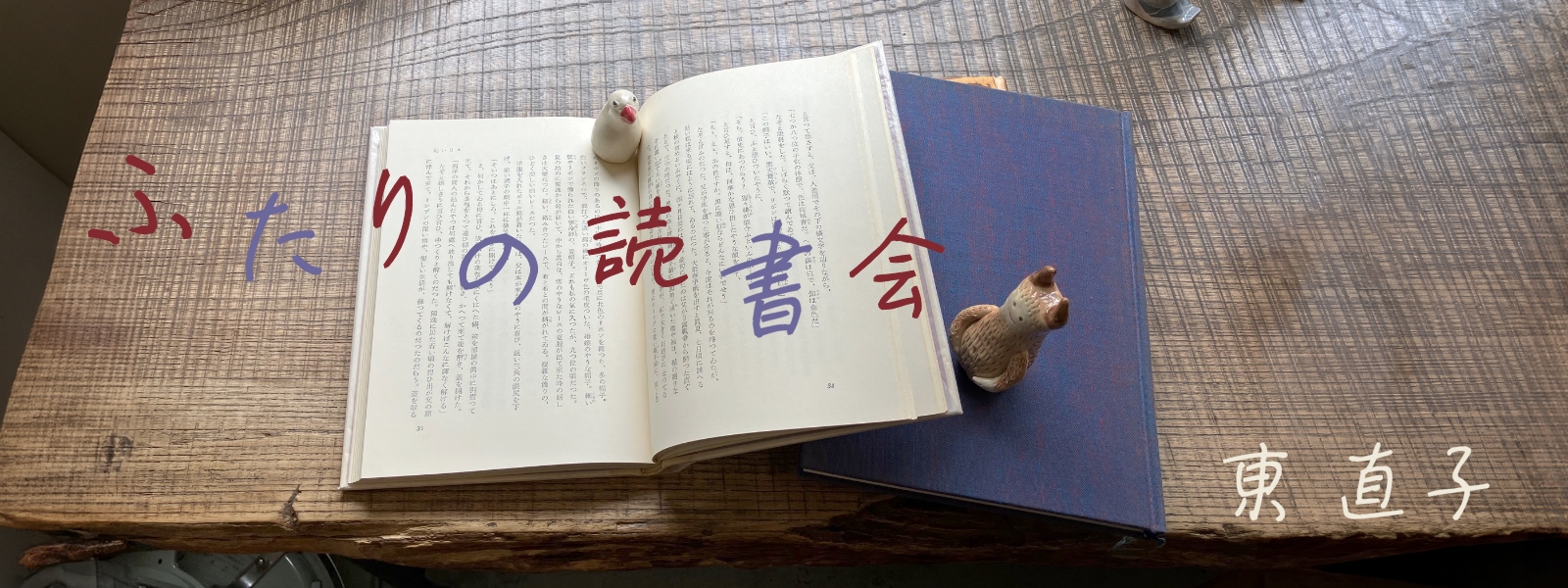書評家のワコさんと大学生のリリ。三〇歳も年の離れた、二人きりの家族。
親子のようで、親友のようで、そのどちらでもない。
二人は、いくつもの本を通して日々揺れ動く気持ちを伝えあう。
白い蝋燭に火をともしたら、二人きりの読書会が始まる。
ゆっくりと心が満ちていく読書の時間へ──。
青いテント、無数の言葉 後編
ワコさんは、湯飲みにほうじ茶を注いだ。ほっとする香りだね、とリリが言う。
「暑さも一段落してきたから、そろそろあたたかくて胃にやさしい飲み物を飲むといいかな、と思ってね。ほうじ茶の中ではこの加賀の棒ほうじ茶が好きなんだよね」
「あ、それ、自販機で売ってた」
「なんだ、すっかり有名なんだね。ほうじ茶って、カフェインが入っていないから、緑茶や紅茶と違って赤ちゃんが飲んでもいいんだよ」
「へえ。小山さんは、テントの中でお茶を飲んだりもしてたのかな。お酒を飲んだことはよく書いてあるけど」
「お酒とタバコが好きで、喫茶店に行くことが至福だったみたいだね。太陽の席とか月の席とか、お気に入りのお店の座席に自分で名前をつけたりして。喫茶店では何を飲んでたのかな」
ワコさんは『小山さんノート』を手に取って、パラパラとめくった。
「喫茶店での具体的な飲み物のことはほとんど書いてないね。身体をあたためたとか、体感的なことは書いてあっても。普通にコーヒーを飲んでたんだろうね。長居させてもらってありがたいとかも書いてたね」
「うん。〝喫茶〟はあこがれの場所で、心のよりどころで。2001年2月3日の日記に、家の中だと〝生活のしがらみから離れられないため、精神が開放されない〟って書いてて、喫茶店の時間を〝一番貴重だ〟って」
「本が読めて、文章を書くことがゆるされている。その空間が貴重だったんだね。本とノートが、小山さんにとっては生き甲斐そのものだった」
「だけど、お金がなくて喫茶店に行けないことを嘆く場面が多くて、悲しくなる。じゃあ無料で利用できる図書館に通えばいいのにって思ってたら〝図書館はげんしゅくすぎて、かたく息苦しい〟って書いててちょっとびっくりした。2001年4月24日分だ」
「そうだったね、図書館については一行だけそう書いてあって、それ以上の理由はわかんないよね。公共施設だから、しずかにしなきゃいけないとか、あまり長い時間いすわっちゃいけないとか、いろいろ細かいことを言われちゃったのかもしれないね」
「このあとに書かれてる夢が、楽しそう」
リリが、その文章を声に出して読んだ。
人間の自由な館を作ることが夢であった。芸術的な感覚で、読み、語り、食べ、飲み、普段の規制の時間、職務を離れ、自分を養い成長できる、自由な空間……。自由なファッションをして、その時ばかりは人間として、知的な精神をみがき、普段のしがらみより開放される。音楽や絵、衣装もあり、踊り、雪、雨、嵐の時でもしのぎ、休養できる。極端な思考をやわらげ、視野を広め、自己を高めていく、自由な精神を養うオアシスがほしかった。
「すてきな夢だね。〝自由な精神を養うオアシス〟、ほんとうにそんな場所があれば、……」
リリの脳裏に、大学の森の奥で見かけた人影が浮かんだ。あの人も、そんな場所を見つけたいと思っているのではないだろうか。
「〝オアシス〟を夢想してるから、みんなとわいわいいろんなことをするのが好きなのかなあって思ったんだけど、このすぐあとの日記には〝私は集団生活ができない〟って書いてる」
リリはページを捲りながらその先を読み上げる。
「〝福祉があれど、なりくりがかみあわない。話を聞いただけであきらめなければならない〟って続いてて、福祉制度を利用するために役所で話をきいたけど、自分には無理だと判断したってことだよね」
「このときどんな会話がなされたのかはわからないけど、以前の日記に、警察を通じて兄に連絡をしたけれど、冷たくどなられて助けてもらえなかったことが書いてあったから、親族とか性格的なこととか、福祉制度を利用するには困難な状態だったのかもしれない」
「本のはじめに、同じテント村で生活していたアーティストのいちむらみさこさんが、小山さんの最後を看取ったことを書いていて、他の人とはあまり交流はなく、病院も頑として行かなかったって」
「小山さんのことを直接知っている人は、この本に関わった人の中では、いちむらさんと吉田さんという人だけ。でも、ノートを書き起こすワークショップを通じて人々がたくさん集まって、小山さんがどんな人だったのか、どのように生きたのか、想像の輪がどんどん広がって、本になって、こうして縁もゆかりもなかった私たちも届いて、いろんなことを考えさせてくれる」
「こんなことになるなんて、小山さんは想像もしてなかったと思うけど、小山さんの言葉が、小山さんの夢見た心のオアシスを産んだんだと思う。でも、亡くなってからこんなに注目されてしまうなんて、なんか、切ない。生きてるうちに、もっと幸せになってほしかった」
「そうだよね。意外だったのが、テントの中で一人で暮らしていたわけでなはかったことで、〝共の人〟などと書かれる男性のパートナーがいたこと。どこかで食べ物やお金を手に入れて、生活を支えている面もあったようだけど、小山さんへの日々の暴力や暴言がほんとうにひどい」
「そう、ほんっとにひどくて、苦しくて、〝共の人〟が憎くてしょうがなかった! お気に入りの紫色のドレスを理由なく引き裂いたり、理不尽すぎて、なんでこんな人とずっと一緒にいるのか、ぜんぜんわかんなくて、むかついた」
リリが睨むような目をして、こぶしを硬くにぎった。
「そうだよね。ほんとに信じられないくらい理不尽だって、私も思った。ホームレスの人たちが暮らすテント村は男性がほとんどで、数少ない女性は力が弱くて、こんなに理不尽な相手だけど、男ということで、小山さんを守っている面もあったみたいね。暴力や暴言は、常にではなくて泥酔しているときなどで、普段は几帳面だし、やさしい面もあるから、小山さんは混乱している」
「その飴とムチみたいなの、DV男の典型的なやり口だからね」
ワコさんは頷きながら、『小山さんノート』を開いて朗読した。
春風が強く、噴水が涙のようになだれ飛んでいる。人影の少ない午後の光に身をさらし、冷酷なつながりを早く離れられるよう、気迫と孤高の精神をふるい起こす。
「2001年3月26日、〝共の人″の暴言から逃れて雨上がりの公園の広場をめぐったときの描写なんだけど、表現が魅力的だな、と思って」
「たしかに、いいね。〝噴水が涙のようになだれ飛んでる〟って、噴水と自分を重ねているみたい。とめどない悲しみでもあるし、思いっきり悲しみのエネルギーを噴出してもいるみたい」
「この日喫茶店の〝いつもの席〟に行けたんだね。〝すっかり外界を離れ、わずかな時間、フランスに行ったつもりで自己の世界に入れる時、笑い飛ばすだけの意識がよみがえる時がある。ジメジメとした感情はきらいだ。まして戦いは最もいやだ〟って語気強く書いてる。小山さんは本来、からっとした楽天的な面もあったんだろうね。でも〝まるで煮ても焼いても殺しにもならないコンニャクのようなバカ者だと何百回も言われながら過ぎた月日は長すぎてうんざりだ〟って続いてて、暴言によって心がどんどん侵されていったんだって、想像できる」
「私、不思議なんだけど」リリが目を伏せたままゆっくりと言った。
「何が?」
「こんなに酷いことばっかりしてた〝共の人〟とは一緒に暮らせないってなってたのに、彼が突然死したあとは〝金真〟って呼んで、大切に供養して、毎日のように偲んだりしてることが」
「複雑ながらも、パートナーとして愛情があったってことじゃないかな。亡くなったら仏様になるという概念が染み込んでいるのかも……。といっても私も疑問には思ったよ。このあたりは小山さん本人にしかわからない感情の動きがあるんだろうね」
「本人にしかわからないっていうのは、誰でもそうかもしれないけど」
「私は、この本でホームレスの人の暮らしのリアルな一面をいろんな人が知ることができた功績は大きいと思う。ほんとうのところは理解できなくても、わかりたいって思うこと事態が、貴重なことだもん」
「貴重っていえば、ワークショップに関わった人の文章も添えられていて、小山さんやホームレスのことを考える切り口が様々に開いているのが、よかった」
「そうだね、小山さんとの生身での対話はもう叶わないけど、残された言葉は無限の対話を望むことができる。小山さんの言葉は、強いね」
「うん。小山さん、最後の方は〝ルーラ〟っていう幻の人と日記の中で対話してるね。大好きなフランスを時々夢想するように、ルーラは夢の理想世界を生きている。イマジナリーフレンドみたい。私もそういう存在を作って、対話してみようかな」
「心の中に逃げ場所があるって、精神衛生上とても有効だと思うよ」
「なんて名前がいいかなあ。私の梨々っていう名前の響きががなんだかイマジナリーフレンドっぽいから、逆に地味な名前をつけたい」
「『アンネの日記』では「親愛なるキティーへ」っていう書き出しで、架空の友達に向けて日記を書く、という形を取ってるんだよ」
「そうなんだ。キティーは、もう一人の自分でもあり、理想の友達でもありって感じで、客観的になれるんだろうね。実は、この本読みながら、ワコさんとのことも考えた。ワコさんと二人で、テントで暮らすこととか」
「そこまで!」
「だって、ありえなくもないよ、普通の家よりは」
「まあ、そうかもだけど」
「ぎりぎりなんだって、思ってる。みんなのんきに暮らしているようで、実はみんな、境界線ぎりぎりを生きているんだって、気づいた気がする。一寸先は闇、ってやつで」
「よくそんな言葉知ってるね」
「ワコさんの家で本に囲まれてれば、そのくらい」
ワコさんは、笑顔をうかべて蝋燭の火を見つめた。
「今のところ、蝋燭の火は消えてない。これぽっちの火でも、灯っているかぎり、闇はあたたかい」
「ありがたいね、火って」
蝋燭を見つめるリリの笑顔が、その火の光でかすかにゆれるのを、ワコさんはしばらく見つめた。
<引用文献>
小山さんノートワークショップ著『小山さんノート』 (エトセトラブックス)2023年刊
p.35 上段4~5行目、同9~10行目、p.57下段 5行目、同6~14行目、p.58 上段1~4行目、p.49 下段4~7行目、同15~18行目、同18行目~p.50上段3行目
広島県生まれ。歌人、作家。
1996年、「草かんむりの訪問者」で第七回歌壇賞受賞。2016年、『いとの森の家』で第三一回坪田譲治文学賞を受賞。
2006年に初の小説『長崎くんの指』を出版。
歌集『春原さんのリコーダー』『青卵』『十階』、小説作品『とりつくしま』『さようなら窓』『薬屋のタバサ』『晴れ女の耳』『階段にパレット』『ひとっこひとり』『フランネルの紐』、エッセイ集『一緒に生きる 親子の風景』『レモン石鹼泡立てる』『魚を抱いて 私の中の映画とドラマ』、歌書『愛のうた』、『短歌の詰め合わせ』、『短歌の時間』『現代短歌版百人一首 花々は色あせるのね』、穂村弘との共著『短歌遠足帖』、くどうれいんとの共著『水歌通信』、詩集『朝、空が見えます』、絵本『あめ ぽぽぽ』(絵・木内達朗)、『わたしのマントはぼうしつき』(絵・町田尚子)、『シマちゃん モモちゃん もりのなか』(絵・松田奈那子)など著書多数。