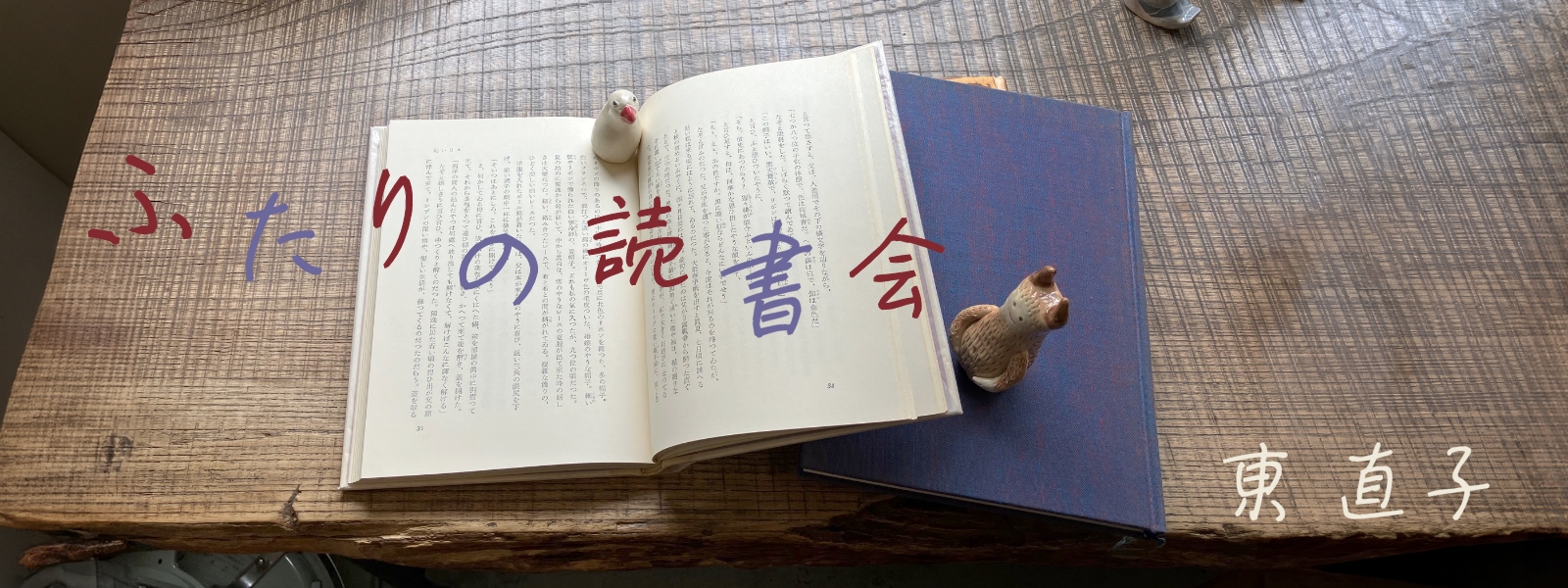書評家のワコさんと大学生のリリ。三〇歳も年の離れた、二人きりの家族。
親子のようで、親友のようで、そのどちらでもない。
二人は、いくつもの本を通して日々揺れ動く気持ちを伝えあう。
白い蝋燭に火をともしたら、二人きりの読書会が始まる。
ゆっくりと心が満ちていく読書の時間へ──。
夕闇にすいか 後編
朝から雨が降り続いた日の夜、食卓に蝋燭が灯された。それぞれのマグカップに、ばら色のお茶が湯気をたてている。ワコさんが淹れたローズヒップティーである。甘酸っぱい香りがほのかに漂う。
テーブルに『すいかの匂い』の白い本が置かれた。白といっても少し黄身を帯びた色の表紙が、やさしいたたずまいだとリリは思う。
「主人公の子供がみんなどこか偏屈で、冷徹で、かわいげはないんだけど、そこがよかった」
リリが読書会の口火を切った。
「全部、気持ちの解像度が高くて、びっくりした」
「解像度……たしかに」
「それで、大人に容赦ない」
「ないね」
「大人って、子供のことをまだ何もわかってないからちょっと舐めてたりするけど、そういうところもふくめて、子供の方が見通している感じが鋭いなって思った。たとえば〝蕗子さん〟に、すごく困った状況に陥っているのに、大人に見つかりたくないって思う場面があって『大人は、どんな場合も事をややこしくするだけだ』ってある。〝海辺の町〟では、『おばさんには二種類ある』って言ってて『子供を見ると叱るおばさん(怖いおばさん)と、子供を見るとにこにこして頭をなでたりするおばさん(気持ちのわるいおばさん)だ』って断言してる。叱るおばさんは怖いってみんなが思うだろうけど、頭をなでる方は普通はやさしいおばさんってことになってたりするから、目から鱗で、そうだった、ほんとは自分もそんなふうに感じてたんじゃないかって、思った。言葉にできてなかっただけで。読みながら記憶の解像度も上がっていくみたいだった」
「そうだね。私も、久しぶりに読み返して、細かいところを、ああそうだったと思い返しながら、自分の眠っていた感覚を刺激される感じだった。リリは、どの話が好きだった?」
リリは、目をぱちぱちとしばたいた。
「えっと、どれも好きだったなあ。最初の〝すいかの匂い〟は、ちょっと恐い昔話を読んだみたいな後味だったし、弟とお葬式ごっこする〝弟〟の、妙なことにとりつかれている感じとか、すごい迫力だった」
「〝弟〟は、現在も含めて所在なくしている時間と、葬式ごっこに熱中しているときのメリハリが、すばらしいよね」
ワコさんがリリの顔を見ながら言うと、リリはゆっくりとうなずいた。
「きょうだいがいるって、どんなだろうってよく思う」
「私も一人っ子だから、こればっかりは想像するしかないんだよね。でもこの小説を読むと、どこにも嘘がないように思えてきて、弟がいる世界を疑似体験してきた気がする」
「小説だから、嘘を書いてるのに」
「嘘だけど、嘘であることを忘れさせてくれるんだね」
「嘘っていえば、毎日自分を生きているわけだけど、自分自身の言動でも、何がほんとで何が嘘か、わかんなくなることがある」
リリは、人さし指で頭をくるくるとさわった。考えがまとまらないときにする無意識の癖である。
「なにかしら演じてる部分があるってこと?」
「そう。例えば、私は、シングルマザーの子供を演じさせられてきたっていうとちょっと大げさだけど、そいういう子供らしく控えめにしとかなきゃなって思ってたところはあると思う。さらにはシングルマザーの母親が死んじゃって、ひとりぼっちになった”かわいそうな子供”っていうのも、あった」
リリが核心的なことを言おうとしていると思い、ワコさんは背筋を伸ばした。
「でもさ、ワコさんと暮らすことになって、だいぶイレギュラーになったから、私は個別案件として振る舞うことがゆるされるようになって、楽になったよ」
ふわっと身体の力が抜けるのをワコさんは感じた。
「そう、そうはよかった。なんか、光栄です」
「そこでワコさんが光栄です、っていうのは、ちょっと違うかな」
「あ、そう? ごめん」
「そこで謝られるのも、もっと違う、かも」
「そうなんだ、ご……、あ、えっと、ま、いっか」
二人で目を合わせてあはは、と笑い、お茶を同時に口に含んだ。
「で、好きな短編なんだけど」と、リリが話を戻した。「新幹線に乗ってる話が好きだった。〝あげは蝶〟だ」
「あげは蝶のタトゥーシールを貼ってもらう女の子の話だね」
「そう。いきなり『私は新幹線が嫌いだ』ってはじまるんだけど、とにかくいろんなものを嫌ってて、不機嫌なんだよね。両親の帰省につきあってて、その両親のことも嫌ってる。でも、なぜか新幹線でいちゃついていたカップルの、蠱惑的で下品な感じの女に惹かれる。で、女の方も女の子が気に入ったのか、いきなり一緒に逃げようって誘う。どちらも理由なんてわからない。わけのわからない感情が一瞬にして生まれて、ふっと持っていかれそうになる。得体の知れない魅力に巻き込まれてぎりぎりのところでせめぎあう感じで、ドキドキした」
「女の子が一一歳だってわかったとき、女は『じゃあもう働けるね』って言うんだよね。そんな馬鹿な、って思うけど、そういう常識がある世界もあるのだろうって、説得もされるから不思議よね」
「うん。子供でも一一歳ではまだ働けないというのは分かってるけど、この強烈なお姉さんとなら、もう働いて生きていける場所を知っていて、『あなたには華族さんの血が流れてるのよ』なんてことを言ってくるうっとうしい両親から離れて未知の世界に行けるんなら、と魅力的に感じちゃったんじゃないかな」
「『華族』と『蠱惑的で下品』が対極として書かれてて、でも根底では似てるんじゃないかって言っている気がする。といっても、過剰なドラマチックさはなくて、客観的でクールなんだよね」
「そういえば、短篇ごとに主人公は変わるけど、共通してクールだよね。主人公が惹かれる人もだいたいクール」
「だね。熱血教師との熱い交流とか憎んでそう」
「うんうん」
「〝ジャミパン〟のお母さんもクールで好きだった。私のママともちょっと似てるかも。ノーパンで町を歩いたりはしなかったと思うけど」
「あはは、杏子さんは、それはしないね。ジャミパン、つまりジャムパンの中身があんずジャムってところも時代を感じるね。駄菓子屋さんでもあんずを使ったお菓子がいくつかあったような。そういえば杏子さんの杏は、あんずだね」
「あ、そうか。ジャミパン扱いされたら、ママ、怒りそうだけど」
「自分の心の絶対的な拠り所だった弟をお嫁さんにもっていかれた悔しさと、そんなことを認めたくないプライドがせめぎあった結果が、ジャミパンを食べること、なんだろうね」
「うん。お葬式ごっこをする弟と、このお母さんの弟、それから〝すいかの匂い〟にも兄弟が出てくるね」
「弟は、一番気持ちが近くて、どこか庇護すべきところがある存在として描かれているよね。特に、葬式ごっこの弟はいじめられていて、その恨みを姉として晴らしたい一心で、いじめっこの葬式を夢想して、心の中で殺していく」
「それが姉としての愛情表現なんだけど、当の弟が『かわいそう』と言って泣きながら、姉の命令に従ってお葬式ごっこをやり遂げるところが、泣けた。結局、姉より先に煙になってしまう」
「その白い煙を、姉が讃えているとこもいいよね。そこまで見届けるのも姉の本望だったと思えてくる。現実のお葬式はだるくても」
「他の話でもいじめが書かれてるね。〝蕗子さん〟では落とし穴に落とされることが分かってて落ちる場面が痛切だったし、〝薔薇のアーチ〟では、いじめられていることを隠して、美化した東京の小学校生活を、海辺の田舎町の子に話してた。自分の理想を嘘に込めてて切なかった」
「『いじめ、絶対ダメ』とかのメッセージを伝えるんじゃなくて、そう簡単には解決できないものとして書かれてたね」
「そう、その投げ出したままな感じがリアルだった。あと、〝水の輪〟と〝はるかちゃん〟と〝影〟は、マイノリティー側にいる子供が描かれていて、心の底にある残酷さが浮き彫りになっていて、考えさせられちゃったな。最初は、大人をディスってる小説だなあって思ったけど、よく読むと、主人公も含め、子供たちの残忍さやずるさなんかもちゃんと書いてる」
「性的な部分にも踏み込んでるよね」
「そうそう、びっくりした。今だとタブーになりそうな。とにかく、正直だなって思った。説教しようとしてるんじゃなくて、あるがままを書こうとしてるんだなと思えて、ぐいぐい読める。それで最後の〝影〟に出てくるMってなんだろうってずっと考えてる」
「残響担当みたいな話だね」
「親友ってわけでもないのに、要所要所に現れて貴重なアドバイスをくれるM……。ワコさんは、Mってどういう人だと思う?」
「うーん、単純かもしれないけど、〝影〟ってタイトルが暗示するように、もう一人の自分なんじゃないかな」
「心の中にいる、架空の人ってこと?」
「そんなところ。実在の人物として書かれてはいるけど、なんだか謎めいているし、実は実在しないんじゃないかな。ときどき電話をかけてくるのも、ときどき自問してるってことだと思う」
「なるほど……。一人の人間にも多面性があるもんね。もしかしたら、いじめられっこだった輝子ちゃんのことを見捨てたうしろめたさで、後から作り上げた人物だったのかも」
「後から?」
「記憶って、後から塗り替わったり、するんでしょ」
リリの真剣な目がまっすぐに入ってくる。
「そういうことも、まあ、あるだろうね」
「問題は、塗り替わってしまったことに、気づかないことだよね」
リリはそう言って視線をそらした。答える言葉が出てこず、ワコさんはしばらくその横顔を見つめ続けた。
<引用文献>
江國香織『すいかの匂い』(新潮社)1998年刊
掲載ページ P.35・5~6行目、P.65・3~5行目、P.89・13行目、P.97・1行目、P.109・11~12行目、P.101・7~8行目
広島県生まれ。歌人、作家。
1996年、「草かんむりの訪問者」で第七回歌壇賞受賞。2016年、『いとの森の家』で第三一回坪田譲治文学賞を受賞。
2006年に初の小説『長崎くんの指』を出版。
歌集『春原さんのリコーダー』『青卵』『十階』、小説作品『とりつくしま』『さようなら窓』『薬屋のタバサ』『晴れ女の耳』『階段にパレット』『ひとっこひとり』『フランネルの紐』、エッセイ集『一緒に生きる 親子の風景』『レモン石鹼泡立てる』『魚を抱いて 私の中の映画とドラマ』、歌書『愛のうた』、『短歌の詰め合わせ』、『短歌の時間』『現代短歌版百人一首 花々は色あせるのね』、穂村弘との共著『短歌遠足帖』、くどうれいんとの共著『水歌通信』、詩集『朝、空が見えます』、絵本『あめ ぽぽぽ』(絵・木内達朗)、『わたしのマントはぼうしつき』(絵・町田尚子)、『シマちゃん モモちゃん もりのなか』(絵・松田奈那子)など著書多数。