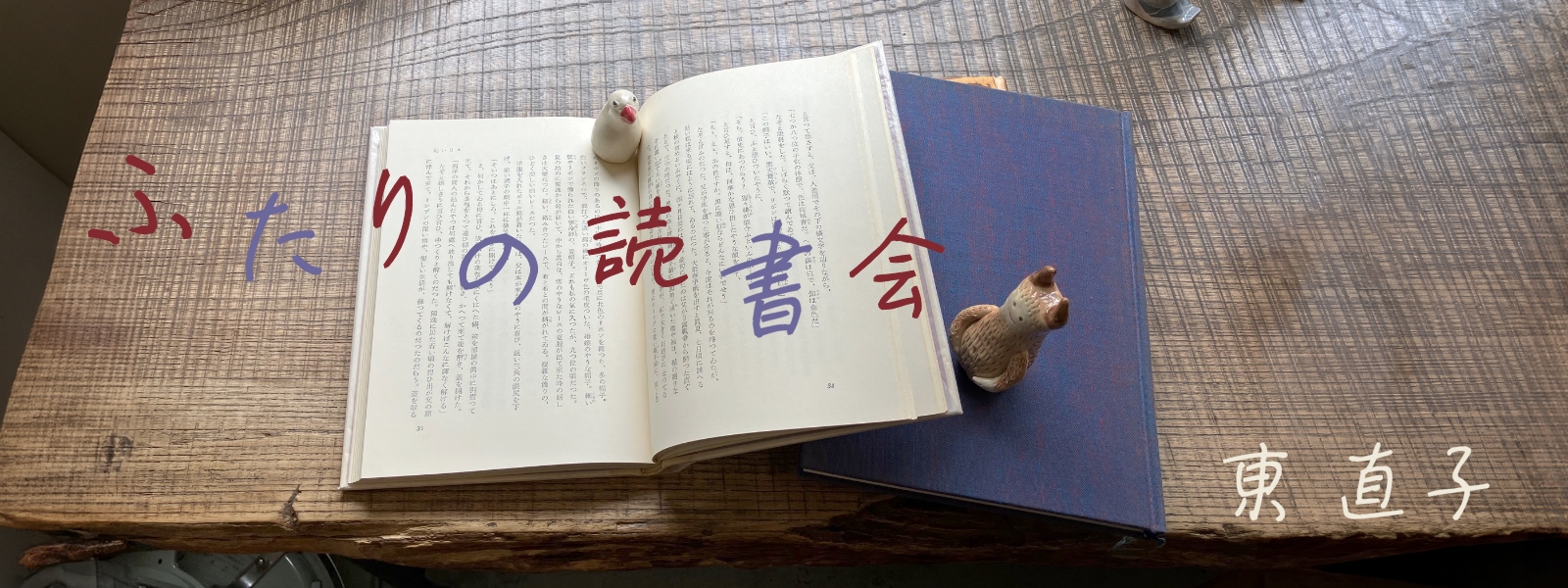書評家のワコさんと大学生のリリ。三〇歳も年の離れた、二人きりの家族。
親子のようで、親友のようで、そのどちらでもない。
二人は、いくつもの本を通して日々揺れ動く気持ちを伝えあう。
白い蝋燭に火をともしたら、二人きりの読書会が始まる。
ゆっくりと心が満ちていく読書の時間へ──。
永遠のはっさく 後編
蝋燭に火を灯した。今日は暑いので、グラスにぎっしり詰めた氷の上に、ポットで淹れたレモンバームのお茶を注いだ。さわやかな香りの冷茶が、昼間の熱を浴びてほてった身体をやさしく冷やしてくれる。
『えーえんとくちから』は、リリが推薦した本なので、リリから話し始めるのを待っているが、少しもじもじしている。
「なんで、この本を読もうと思ったの?」
ワコさんが口火を切った。
「こないだ、大学の近くの本屋さんに友達と一緒に行ったんだよね。前に読んだ『有夫恋』がおもしろかったから、そういうのを置いてそうな棚を探してたら、短歌フェアをやっていて」
「このごろそういうのよくやってるよね。〝短歌ブーム〟だってテレビでも」
「そう、友達も、歌集を買ったことあるってその時言ってた。表紙がおしゃれでかわいいのばかりで、わあいいなあと思って、ジャケ買いしそうになってた」
「で、この『えーえんとくちから』を……?」
「うん。ジャケ買いってわけじゃないけど、カラフルな本の間で、小さくてシンプルで、ひらがなばっかりのタイトルが妙な耀き方をしてて、ここにいるよ、って声にならない声で呼んでいるように感じたんだよね」
「なるほど。この不思議なタイトル、確かに惹かれるよね」
「それでページを開いたら最初の謎かけみたいに、このタイトルの歌が置いてあって」
えーえんとくちからえーえんとくちから永遠解く力を下さい
「歌の最後でそういうことかあ、って思いながら、じゃあ〝永遠解く〟ってどういうことだろう、とも考え初めて、その場から動けなくなった」
「文庫の後ろの方にある穂村弘さんの解説で、〝永遠〟が、病気で寝たきり状態だった作者自身のことを示していて、〝〈私〉は〈私〉自身を「解く力」を求めていたのでは。〟って書いてるね」
「たしかにそういう自分自身の状況に対する強い願いを込めているのは間違いないと思う。永遠に続くような長く苦しい時間から早く逃れたいって。でも私、それだけじゃないような気がしてる」
「それだけじゃない?」
「うん……なんていったらいいのかな」
リリは長い睫毛を伏せ、眉間にかすかに皺を寄せ、グラスを手に取り、アイスレモンバームを一口ゆっくりと飲んだ。
「永遠って言葉、誰でも使うけど、実際には摑んだりはできないよね。だから永遠というとんでもない謎を解くための力を自分に下さい、という神様みたいな存在への願いなんじゃないかなって」
「永遠という謎を……。そう思うと、文芸に対する決意みたいにも思えてくるね」
「そう! だから冒頭に置かれてるんだと思う」
「この不思議な歌集の冒頭に、よく似合う一首だよね。ただこの歌集、本人が亡くなってから編集されたものみたいよ」
「あ、そうだった、遺族のお父さんが〝あとがき〟でそんな経緯を書かれてた」
「本人が唯一編集した第一歌集『ひとさらい』を調べてみたんだけど、この〝えーえんとくちから〟の歌は二番目に置かれてるんだよね。『えーえんとくちから』では二番目に置かれてる「二十日まえ茜野原を吹いていた風の兄さん 風の母さん」が冒頭に来ている」
「本の最初の歌の順番を入れ替えたんだ。先にこっちで読んだせいか、〝えーえんとくちから〟が最初にある方がぐっとくる気がする」
「二番目に置いてあるから本人の思い入れが強かったのは間違いないだろうね。思い入れが強いあまり最初に持ってくるのは、本人だからこそためらったのかも」
「うん。置かれた場所でイメージが変わるって、おもしろいね。とにかく他にもいろいろ気になる作品ばっかりだった。正直、なんだこれ、って思っちゃったのもある。なんだこれ、って思うけど、すごく気になるんだよね」
「どんな作品が?」
「えっとね、例えばこれ」
「スライスチーズ、スライスチーズになる前の話をぼくにきかせておくれ」
「なぜか全体が「」で括られてるね。スライスチーズになる前ってつまり、チーズの塊だったころってことで、これは全体が何かの暗喩なのかなって思うけど、本気でスライスチーズそのもののこれまでの物語を知りたがっているようにも思えてきて。どっちにしてもスライスチーズって残酷な食べ物かもって初めて思った」
「私は〝スライスチーズ〟の響きって、楽しいんだなって初めて思った」
「そうそう、響きの楽しさで強引に説得される感があるよね。隣の歌も」
「雨だねぇ こんでんえいねんしざいほう何年だったか思い出せそう?」
「墾田永年私財法って、日本史で習った覚えがあるけど、音だけ取り出すと、妙にリズムがいいっていうか、ラップにうまくはまりそうだなって」
「何年だったか分かる? じゃなくて〝思い出せそう?〟ってところがミソだね」
「そうそう、その一言でシチュエーションが特別になるね。〝魂がいつかかたちを成すとして あなたははっさくになりなさい〟も、なんで〝はっさく〟?って思っちゃうんだけど、どこか気が抜けたようなひょうひょうとした〝はっさく〟という言葉の響きが〝魂〟の重さをポップにしてくれて、なんだかおもしろいぞ、ってなる」
「この〝魂〟と〝はっさく〟みたいに何かが何かに生まれ変わる話が多いよね」
「そうなんだよね。〝ねむらないただ一本の樹となってあなたのワンピースに実を落とす〟とか、〝さあここであなたは海になりなさい 鞄は持っていてあげるから〟とか」
「どちらも語りかけている相手のことを見守っているやさしさがありつつ、深いところで支配しているような怖さも感じる」
「〝生涯をかけて砂場の砂になる練習をしている子どもたち〟なんて、砂場で遊ぶ子どもに遠い死をはっきりと見据えてる」
「転生ものがどこかユーモラスだったりして、死は特別であるけど身近なもの、あるいは一種のあこがれみたいなものとして描かれている気がする。砂場の砂って、子どもにとってどんなものにも形を変えられる自由なものだもん。〝永遠解く力〟の一つの回答ともいえるんじゃない?」
「そのリリの感じ方、リリらしくて、そして作者の魂と通じ合ってる部分だと思う」
「笹井さんの短歌は、いろんな感じ方ができる分、いろんな人がいろんな形で魂と通じあう体験ができるんじゃないかな」
「そうかもしれない。感受性が尖っている時期は特に」
「尖りと尖りが共鳴するってあるよね。全体的にやさしい印象だけど、〝よかったら絶望をしてくださいね きちんとあとを追いますからね〟みたいにシニカルな歌もある。で、私は、その隣にある歌が好きだった」
火から火がうまれるときの静かさであなたにわたす小さなコップ
「今、目の前に小さな蝋燭の火が揺れてるからなおさらだけど、気持ちが連鎖していくことを、目に見えるものにしてくれたって感じた。そっと、大事に伝えたいなにかを、伝えるときの動作だけで、見せてくれたようで」
「いいね、この歌」
「うん。火から火が生まれるのが〝静かさ〟だっていう把握、なにげないようで、なにげなくなくて、しびれる」
「火は下手すると何もかもを焼き尽くす大きな力になってしまうけど、静かさとしてそっと伝えられたら、美しいよね」
「ワコさんはどの歌が好きだった?」
「うーん、いろいろあるけど、しいて一首をあげるとするなら、これかな」
一生に一度ひらくという窓のむこう あなたは靴をそろえる
「窓の前に靴をそろえてある場面って、自殺の場面も浮かんでしまうんだけど、私はそうではなくて、きちんと最後まで生きようとする意志を込めたんだと思う。〝一生に一度ひらくという窓〟は死を暗示しているけど、窓は自分で開けるのではなく、寿命がきて自然にひらくんだと描いている。ひらいた窓を受け入れて、必要がなくなった靴を脱いで、きちんとそろえて窓のこちら側へとやって来ようとしている。やるだけのことはやって満足している〝あなた〟が見える」
「じゃあワコさんの考える短歌の主体は、窓のこっち側から〝あなた〟を見てるんだ」
「そういうふうに思ったけど」
「私は、これから生まれるんだと思った」
「え?」
「〝一生に一度ひらく窓〟は、これから現世に向かうツールで、これからそこへむかうための靴を一度しっかり揃えてから一歩を踏み出そうとしているんだって」
「そうか、そうだね、そんなふうにも読めるね。すごい」
「死も再生も、両方感じてもらってもいいって、作ったんじゃないかな。死を想うことって、今生きてるってことを強く思うことだもん」
リリがほのかに笑顔を浮かべる。
ふいに沈黙が訪れ、レモンバームのグラスのとけかけの氷が動いて涼しい音が響いた。
<引用文献>
笹井宏之『えーえんとくちから』(ちくま文庫)2019年刊
掲載ページ p.5、p.193・16行目、p.16・1行目、p.16・2行目、p.41・1行目、p.10、p.66・2行目、p.117・2行目、p.103・2行目、p.103・1行目、p.150
笹井宏之『ひとさらい』(書肆侃侃房)2011年刊
掲載ページ p.6・1行目、p.6・2行目
広島県生まれ。歌人、作家。
1996年、「草かんむりの訪問者」で第七回歌壇賞受賞。2016年、『いとの森の家』で第三一回坪田譲治文学賞を受賞。
2006年に初の小説『長崎くんの指』を出版。
歌集『春原さんのリコーダー』『青卵』『十階』、小説作品『とりつくしま』『さようなら窓』『薬屋のタバサ』『晴れ女の耳』『階段にパレット』『ひとっこひとり』『フランネルの紐』、エッセイ集『一緒に生きる 親子の風景』『レモン石鹼泡立てる』『魚を抱いて 私の中の映画とドラマ』、歌書『愛のうた』、『短歌の詰め合わせ』、『短歌の時間』『現代短歌版百人一首 花々は色あせるのね』、穂村弘との共著『短歌遠足帖』、くどうれいんとの共著『水歌通信』、詩集『朝、空が見えます』、絵本『あめ ぽぽぽ』(絵・木内達朗)、『わたしのマントはぼうしつき』(絵・町田尚子)、『シマちゃん モモちゃん もりのなか』(絵・松田奈那子)など著書多数。