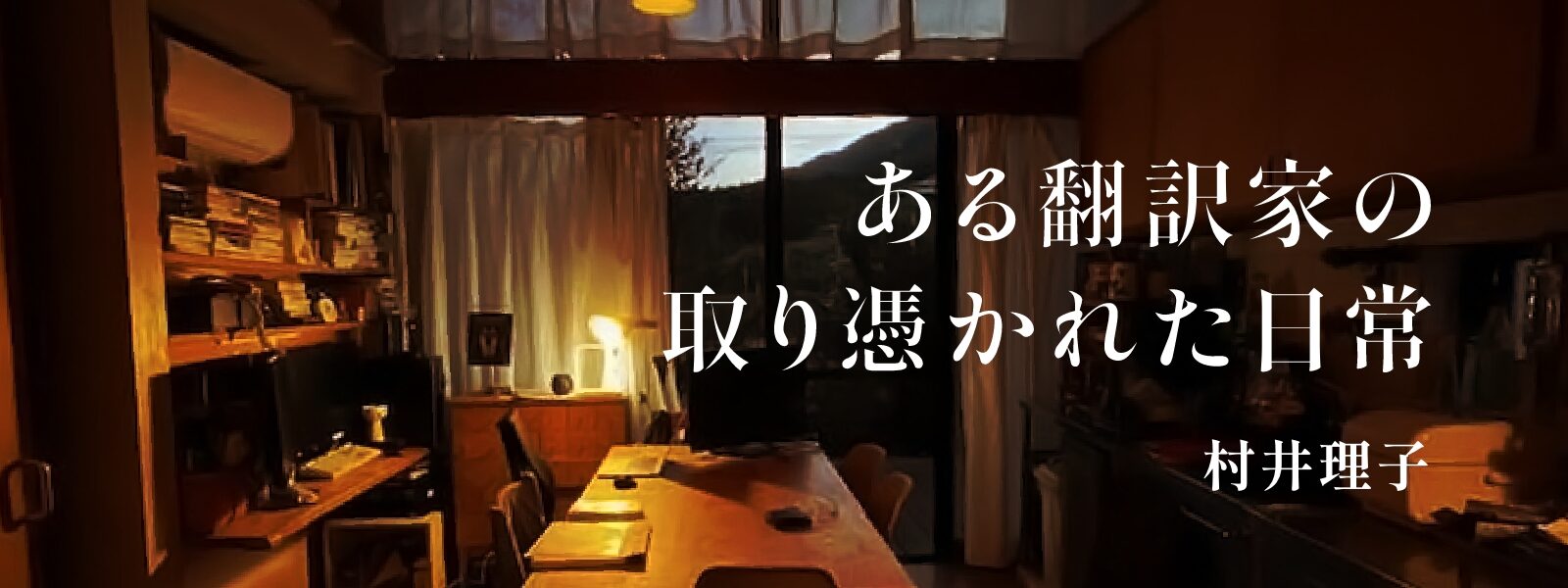2025/05/16-2025/05/31
2025/05/16 金曜日
まるで19歳の頃の自分を自分で助けるように、19歳になった二人の息子に対して「できるだけのことをやってあげよう」という気持ちになっている。これは子どもに甘いということになるのだろうか。
19歳。私にとっては特別な年齢だ。自分が19歳のとき、人生が激変したという自覚があるからだ。19歳の頃を思い出すと、一気に暗い場所に引きずり込まれるような感覚がある。当時、私のような学生は珍しくもなんともなかったけれど、19歳から23歳あたりまで、とても生活が苦しかった。
西京極の灰色の街並み。過酷なアルバイト。慣れない大学の授業。19歳の私には親の助けが必要で、だけどシングルマザーになった母にはその余力がなかった。私はたった一人、京都で孤独に生きていた。一人なんて慣れっこだったはずなのに、京都の孤独は耐えがたいものだった。あの頃の暗黒であれば、いくらでも書ける気がする。
夏の夕暮れ時、バイト終わりで疲れ果て、葛野大路花屋町のガードレールに座っていたら、道路挟んで向かい側のガソリンスタンドから(今はセブンイレブン)大音量で田原俊彦の『ごめんよ 涙』が流れていた。
2025/05/17 土曜日
「あなたたちは恵まれているとか、そうじゃないとか、そういうシンプルな話をしているんじゃないんです。昔話は退屈だと言われてもかまわない。ただ、今日だけは聞いてほしい」と言って、息子たちに話をしていた(しつこい)。
何を話したかというと、困ったら遠慮なく親に言いなさいということ。何か迷ったら、必ず助けを求めて下さいと言った。「親に相談するわけないやろ」と思うこともあるでしょうが、それでも何か困ったのなら言いなさいと繰り返して、私自身の19歳を成仏させようと必死になった。
私は19歳で一人暮らしをはじめた。京都の小さなマンションだった。そこに荷物を運び入れてくれたのは兄で、荷物を運び入れると「じゃあな」と彼は出て行き、狭くて暗い部屋のテレビからは『東京砂漠』が流れ、その日以来、『東京砂漠』は私のトラウマ楽曲となった。後に田原俊彦の『ごめんよ 涙』が加わる。
2025/05/18 日曜日
昨日、義父を訪ねて、元同僚の方が実家にやってきたらしい。食べ物、飲み物をたっぷり頂いたようで、義父は喜んでいた。義父によってスローに語られる二人の男性のこれまでのドラマチックな人生を白目で聞き、タイミングをずらさぬよう相槌を打つことに神経をすり減らし、へえ、すごいですねえと反応した。私も年を取ったら過去の武勇伝とも呼べない普通の話を繰り返すのだろうか。そんな人間になったら注意してほしい(関係者の皆様へ)。
すると気を良くした義父が、今からその方に電話して、「父がお世話になって感謝しております。お仕事のことも聞きました。感動しました」と伝えなさいと言い出した。感動はしてねえよ。
調子乗ってんだろ? と心の中で思いつつなにもせずに帰ってきたのだが、車中で腹が立つったらない。この、「どこかへ電話してお礼を伝える」という行為を、いままでどれだけ義父母に強制されてきたかわからない。まったく知らない人に電話をするよう言われ、義父母に優しくしてくださって嫁からお礼を申し上げますと言えということなのだが、これは嫁を思うがままに操ることが出来るという力の誇示だったのかと思ったら、アクセルを踏む勢いが若干上がったような気がした。
私の友だちは、実親からこれを強制されて、本当に嫌だったと言っていた。自分で言わずに子世代に言わせることで、何を誇示したいのか。親孝行な娘を持つと幸せだわみたいなこと?? 自分の幸せは自分で表現したらいいのに。コンテンポラリーダンスみたいにさ。その方が素敵じゃん。
2025/05/19 月曜日
週末、いつもだったら家でゆったりしているのに、先週末は犬のイベントに出たりして忙しかったので、今日は休み。
休みと言っても完全に休むわけではなく、今日みたいな日は読書にあてることにしている。意識して時間を作らないとできないのが読書だが、時間を作ることが出来たとしても、ブランクがあるとスムーズに読み進めることができない。そういう部分はスポーツと同じだといつも思う。読書の場合、ページが進まないなと思ったら、私はジャンルを変えて別の本を読んでみて、スピードが上がってきたら、そこから元の本に戻ったり、まったく違う資料の読み込みなどに路線を変えたりする。コミックも大好きだ。
読書も、読むというよりは、流し込むような感覚になってきている。特に英語だと、頭のなかでの音声再生なしで注ぎ込む感じだな。日本語も最近は音声再生なしで両目から直接脳に入るような気がしてきた。
それにしても、本はいつ何時でも私を裏切らない。子どもの頃から慣れ親しんだ私だけの空間が、本を開けば必ず与えられる。本さえあれば、どこにでも私だけの空間を作ることができる。電車内であっても、喫茶店であっても。それは私を守るバリアでもある。
2025/05/20 火曜日
私は甘い親なのだろうか。今まで学校の先生や様々な人から「お母さん、甘いなあ〜」と言われたのだが、私は普通の母親をやっているような気がしている。というか、私は自分の母がそうだったように行動しているだけなのだ。母は私に対して優しくしてくれたし、なんでもかんでも、母に相談すれば常にポジティブな答えをくれた。困ったときには、絶対に母が助けてくれるという安心感があった。万が一私がお勤め(懲役)に行って戻っても、彼女は100%出迎えてくれるという自信があった。
途中からちょっと怪しくなってしまったが(私が年齢を重ね、母が老いることでそうなった)、それでも全体的に見て、母が過保護だとか、甘い母親だったかといえば、そうでもなく、ただただ、優しい人だったという印象だ。母が育てたのは私と兄。彼女にとって子育ては成功だったのか、それとも。母にとっては時代が悪かったのではないか。それでも精一杯やっていたよね。
2025/05/21 水曜日
水曜日はテオがドッグスクールに戻る日。私にささやかな平安が与えられる日。
とはいえ、テオがやんちゃで手に負えない大型犬であるかといえば、その逆だ。テオはぬいぐるみである。本当に優秀な子だ。見た目よし、性格よし、帽子が似合う。明るくて朗らかで、人に優しくて、ゴールデン・レトリバーの鑑のような犬だ。
それでもやっぱり水曜日にスクールに行ってくれると、私は楽である。スクールのみなさんに感謝しかない。
2025/05/22 木曜日
尾崎英子『母の旅立ち』を読んだ。お母様が亡くなるまでの20日間の記録だが、お母さんのこれまでの人生が破天荒過ぎて驚いた。ただ、お母さんの人生を深読みしていくと、時代、家父長制など、その生き方に大きな影響を与えた要素が思い浮かび、その破天荒さはサバイバル術に直結していたのだという思いがした。
誰の人生にも、当人にしか語ることが出来ない物語がある。どれだけ近しい場所にいた人間でも、配偶者でも、子どもであっても、その人の心のなかの全てを覗くことはできない。それでも諦めずに、最期の日々を一緒に過ごした家族の気持ちは何より尊いのだと思う一冊だった。あっぱれ。姉妹っていいな。
2025/05/23 金曜日
7月から日経新聞で半年間の連載がスタートする。週一回締め切りがやってくる生活を半年続けるのだが、大丈夫だろうか。編集者さんにも若干心配されているが、たぶん大丈夫だろうと思う。文字数がそこまで多くないしね。できるぜ、俺なら。何を書こうか。それが課題。
2025/05/24 土曜日
義父からの電話が鳴り止まず、どうしても孫に会いたいと言われたので、息子たちを無理矢理集めて夫の実家に連れて行った。義父母は午後だというのにまだ寝ていて、寝室に行くと、悪臭が鼻についた。窓を開け放つ。義母は目を覚ましていたが、私が誰かはわかっていない。
義父は窓を開けられ、ようやく目を覚まし、双子を確認すると、声にならない声をあげながら起き上がってきた。ベッドに腰をかけたが、梅雨なのに冬用のパジャマを着ている。声を出しているが声にならない。すると、震える右手で引き出しを指して、そこを開けてくれと頼んだ。息子たちの表情が、多少場違いな感じで少しだけ明るくなった。わかる。おこづかいをもらえると思ったのだろう。しかし話はこれからだ。
明るい性格の次男が(そして簡単には希望を失わない)、「ここの引き出しやんな♪」と言いつつ、さっと引き出しを開けると、出てきたのは義父がいままで受け取ってきた表彰状やメダルだった。義父はそれを取り出すよう次男に言い、一枚、一枚、説明しはじめた。
自分がどこで何をしたことで表彰されたか、その表彰式には誰がいたか……まあ正直、19歳にとってはどうでもいいことです。50過ぎのおばさんにとっても、本気でどうでもいいことでした。
自己肯定感が高いのか、それとも低いのか? はっきりしてくれと思う。ヘルパーさんに聞くと、このような行動は、認知症あるあるなんだそうです……
2025/05/25 日曜日
翻訳。日曜日の午前中に難しい英文を読んでいると、ちょっと気分があがってくる。今日はいつもは苦手な細かい作業をやろうという気持ちになったので、参考資料を二冊並べて(両方ともページ数がすごいので、私の狭いデスクの上で広げるのは一苦労だが)、読み比べたりしている。難しい本を訳していると徐々に嬉しくなってくるのは、熱が上がり始めるとウキウキしてくるのに似ている。
夕方、突然思い立って車を飛ばして道の駅に行った。一人で外出するのが年々好きになってくる。
2025/05/26 月曜日
大修館書店の教科書『言語文化』改訂版に、「文字が見せてくれる唯一無二の瞬間」(集英社刊『本を読んだら散歩に行こう』の一篇)が掲載されました。ということは、大修館書店のこの教科書を採用している高校の生徒のみなさんが、私の文章を読んでくれる可能性が非常に高いということです! だからなにというわけではないのだが、発言に気をつけて生きていこうと思いました。
2025/05/27 火曜日
3100人が納骨できるという「前方後円墳」型墓地に応募殺到という新聞記事を読んだ。ええっ! と驚いて記事を見たら、本当に前方後円墳の形の共同墓地で、その周辺には埴輪(ハニワ)がたくさん置かれていた。ちょっと待って、埴輪までついてるの? イングリッシュ・ガーデンみたいになってない!? それも価格が一人28万円、それと永久管理費が7万7千円と、なかなか安いではないですか。6月4日発売『ある翻訳家の取り憑かれた日常2』のオマケに書いた「メモリアル三姉妹」(小さな葬儀屋を営む三姉妹のお話)で、新しいスタイルの葬儀について書いたが、墓も提案したかった! でも、この前方後円墳スタイル以上のアイデアが出るとは思えないけど。
2025/05/28 水曜日
資料として『華麗なるギャツビー』を読んでいる。私の記憶が正しかったら、ギャツビーは19歳のとき、大学の授業で一度読んだ。イギリス人の先生の授業だったはずだ。夏の終わりまでに感想を聞かせてと課題として出され、私はその先生がとても好きだったので夏休み明けを楽しみにしていたら、授業がいきなり休講になっていた。休講なんて、学生にとっては「ヤッター!」のはずなのだけれど、肝臓に病気があると言っていた先生の言葉を思い出して、ちょっと嫌な予感がした。翌週、先生が急逝されたことが大学掲示板に張り出されていた。あの時はショックだった。
もう三十年以上も前の話だが、先生のお墓はどこにあるのだろうか。私は先生の授業が好きでしたよと、伝えに行きたい。
2025/05/29 木曜日
「痛いおばさんが履いているスニーカートップ10」みたいな動画がある。この痛い〇〇シリーズは「痛いおばさん」だけではなく「痛いおじさん」、「痛いおばあさん」、「痛いおじいさん」、「痛いOL」などなど、とにかく誰かの行動を痛いと表現するランキングが大人気らしい。誰に人気なのかはわからない。しかしそこにも救いはあって、それが動物に波及していないところだ。例えば、痛いおばさんが飼う犬ランキングとか出てきたら、それはそれでとても気の毒だ(生き物が)。
それで、痛いおばさんが履いているスニーカーランキングを見ていたのだが、実際のところそれは痛いスニーカーのランキングではなくて、「スニーカーを履くおばさん全員が痛い」と言いたいのだということがよくわかった。ニューバランス履いても、ナイキ履いても、オニツカ履いても、コンバース履いても、とにかくおばさんはやることなすこと全て痛い、全員痛い! ということでした。病院に行ったらいいでしょうか。
2025/05/30 金曜日
忙しく働いているためにお買い物ウィークがスタートしている。今回最も高価なお買い物は、なんといってもホットクック。自動調理器と呼んでいいのだろうか。レシピもいろいろと出版されていたが、私がまず手に入れたのは沖合菜緒さんによる『頑張らないホットクックレシピ』(kindle)だ。すごく簡単な作り方なのに、確かに美味しくできる! 感動してしまった。簡潔に書かれた短いレシピが、気の短い私にぴったり。
2025/05/31 火曜日
あと数日で『ある翻訳家の取り憑かれた日常2』の出版だ。この日記もあっという間に三年目に突入した。私の特技はただひとつ、淡々と続けることなんだけれど、そういう意味でこの日記は私の特技が反映されているのかもしれない。
翻訳だってそうだ。淡々と、心に波風立てないように注意しながら、こつこつとやっていくことで、最終的には必ずゴールが向こうからやってくる。それもなんだか性格の良いやつ(ゴール)が、ニコニコしながらやってくるような気がする。出会った瞬間、握手したくなるような、いいやつがやってくる。
諦めずに淡々と、冷静に作業を続けるだけだ。たまにはさぼっていい。
私ができるのだから、きっと誰にだってできる。
翻訳家、エッセイスト。1970年静岡県生まれ。琵琶湖畔に、夫、双子の息子、ラブラドール・レトリーバーのハリーとともに暮らしながら、雑誌、ウェブ、新聞などに寄稿。
主な著書に『ある翻訳家の取り憑かれた日常』(2巻まで刊行、大和書房)、『兄の終い』『全員悪人』『いらねえけどありがとう いつも何かに追われ、誰かのためにへとへとの私たちが救われる技術
』(CCCメディアハウス)、『犬ニモマケズ』『犬(きみ)がいるから』『ハリー、大きな幸せ』『家族』(亜紀書房)、『村井さんちの生活』(新潮社)、 『村井さんちのぎゅうぎゅう焼き』(KADOKAWA)、『ブッシュ妄言録』(二見書房)、『更年期障害だと思ってたら重病だった話』(中央公論新社)など。
主な訳書に『ダメ女たちの人生を変えた奇跡の料理教室』『ゼロからトースターを作ってみた結果』『黄金州の殺人鬼』『メイドの手帖 最低賃金でトイレを掃除し「書くこと」で自らを救ったシングルマザーの物語』『エデュケーション 大学は私の人生を変えた』『捕食者 全米を震撼させた、待ち伏せする連続殺人鬼』など。