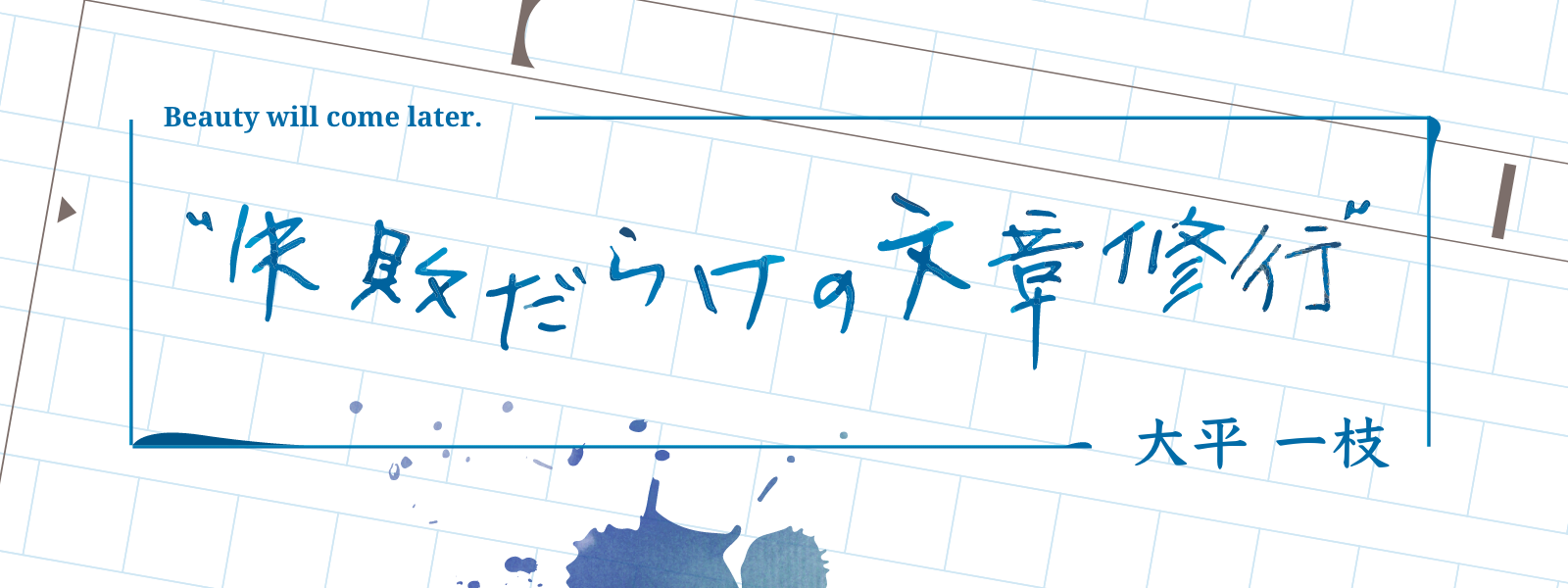文筆生活30年余。失敗からひとつひとつ記事やエッセイの書き方を学んでいった大平さんの七転び八起き。「人柄は穏やか、仕事は鬼」な編集プロダクションのボスの教えから始まる文章修行の日々には、普遍的で誰にも役に立つヒントが満載です。
「偏り」と「独りよがり」
2004年の自分のブログを整理していたら、「苦言」というタイトルでこんな文章があった。
<ある書籍の草稿を編集者にメールで送信。
即座に「偏りもいいが、独りよがりにならないように」「キレイとか可愛いは、情報ではない」と、一刀両断の返信あり。
むむむ、と二の句が出ない。きついけれど,当たっている。
ふと、こんなふうにキビシイことをぴしゃりと言ってくれる編集の人が、自分の周りに少なくなったなあと思った。言ってもしょうがないとあきらめられているのか、もはや言いづらい年齢になりはててしまったのか…。
だから今日は、基本的なことを指摘されて恥ずかしかったが、少し嬉しくもあった。
もっともっと精進せねば。>
このとき40歳。もうすでに、あまり注意してくれる人がいなくなったと綴っている。
20年を経た今はなおさらだ。だからこそ指摘のひとつひとつが、心底ありがたくてしょうがない。若い頃は、イラッときたこともあったのに、皮肉なものだ。苦言を金言と受け止められるようになった頃には、周囲から遠慮され、裸の王様になりかねない状態に陥っている。
さて、偏りと独りよがりについて、である。
情報記事に偏りがあってはならないが、自分の名でエッセイやわたくしごとを書くときには、あっていいと思っている。偏りが、書き手の個性や視点になる。いっぽう、あたりさわりのない、”あたりまえ”のことだけが書かれたものは読まれない。
たとえば、自然は大切にしなければならないというあたりまえの主題を伝える際、できるだけ自分の身に引き寄せて、足元から書く。「電動キックボードに乗ったらこんなことがあった」という偏った視点から始めてもいいし、「急いでいるときに飛び乗った自転車の空気が抜けていた」も読みたくなる。
冒頭のブログで私が編集者から指摘された“独りよがり”がどんなものだったか、具体的に思い出せないが、今でもその病気が文章に出てしまい、推敲で大直しをすることはしばしばだ。
独りよがりな文章とは、編集プロダクション時代のボスによく注意されたもので、「自分だけわかった気になって書いてしまう」こと。
とくに好きな分野、専門分野、今自分が夢中になっているテーマほど危ない。
4カ月前、ガールズオーディション企画「ノーノーガールズ」について、講談社のウエブサイトに短期連載をした。
こういうとき、最終審査会場や配信で、どれほど心を動かされたかだけを書いても伝わらない。
初見の人にもわかるように、それがどういう内容の企画か、どこの誰がどんな目的で主催していて、どんな規模のものか。今、どれくらい注目されているかを、簡潔に説明することが大前提だ。概要がわからない人には、ただの、興奮した観客席のいちファンの独りよがりな文章に見えてしまう。
連載では、その部分は「前文」として、編集部が書き、イントロダクション的役割を担った。
前文でも、「注目されている企画」では独りよがりになる。主観しかなく、意地悪な見かたをすれば、書き手や編集部だけが注目さているだけじゃないの?と言いたくなる。
編集部は、「最終審査一般チケット2万席に5万の申し込み」というタイトルを付けた。とたんに、主観が排除され、「注目」という事実も客観的な補強ができる。
説明は必要、そんなの当然だと思われる向きもいるかもしれない。
しかし、世の中には、説明のない、自分だけがわかっている独りよがりな文章のなんと多いことか。かくいう私も、エッセイを書くとき終始陥る。
指先の文字に集中するあまり、「木」だけで「森」が見えなくなってしまうのだ。
だから私は、窓のあるところで書く。
仕事机の正面には小さな窓があり、通りの向こうまで見える。書いている途中で、パソコン画面からふっと視線を外して、遠くを見る。なにかアイデアが生まれるわけでも、とたんに文章が素敵になるわけでもないが、視線をずらす心地よさを感じる。
狭いところで物事を考えていないか、読み手を置き去りにして自分だけ突っ走っていないか顧みるささやかな足がかりになる。
失敗からの教え
読者を置き去りにする独りよがりな文章に気をつけよ
-
第1話結婚式前夜の鬼特訓
-
第2話人は長文が嫌い
-
第3話自慢禁止
-
第4話五感を表す言葉と、固有名詞にコツあり
-
第5話美文は邪魔になる
-
第6話校閲に学ぶ
-
第7話推敲のヒントーー‟書き立て”の熱は勘違いしやすい
-
第8話「偏り」と「独りよがり」
-
第9話きれいや可愛いは、情報ではない
-
第10話宇野千代さんの料理エッセイとツレヅレハナコさんのインスタ
-
第11話事実確認作業は、書き手の生命線
-
第12話仕事の場面での、手紙の効用について
-
第13話「で、結局何言いたいの」と自分に問う
-
第14話なにをどんなふうに読めば、自分の肥やしになるのか
-
第15話齟齬(そご)を生まない仕事スタイル
-
第16話推敲の大前提に据える最も重要なオキテ
-
第17話文章が散漫になりがちなときの道標(みちしるべ)
作家、エッセイスト。1964年、長野県生まれ。編集プロダクション宮下徳延事務所を経て、1995年、出産を機に独立。『天然生活』『別冊太陽』『チルチンびと』『暮しの手帖』などライターとして雑誌を中心に文筆業をスタート。市井の生活者を描くルポルタージュ、失くしたくないもの・コト・価値観をテーマにした著書を毎年上梓。2003年の、古い暮らしの道具を愛する人々のライフスタイルと価値観を綴った『ジャンク・スタイル』(平凡社)で注目される。
主な著書に『東京の台所』『ジャンク・スタイル』『それでも食べて生きてゆく 東京の台所』、『注文に時間がかかるカフェ』『人生フルーツサンド』『正解のない雑談』『こんなふうに、暮らしと人を書いてきた』『そこに定食屋があるかぎり』「台所が教えてくれたこと』など30冊余。「東京の台所」(朝日新聞デジタルマガジン&w)、「ある日、逗子へアジフライを食べに〜おとなのこたび」(幻冬舎PLUS)、「遠回りの読書」(『サンデー毎日』)他連載多数。