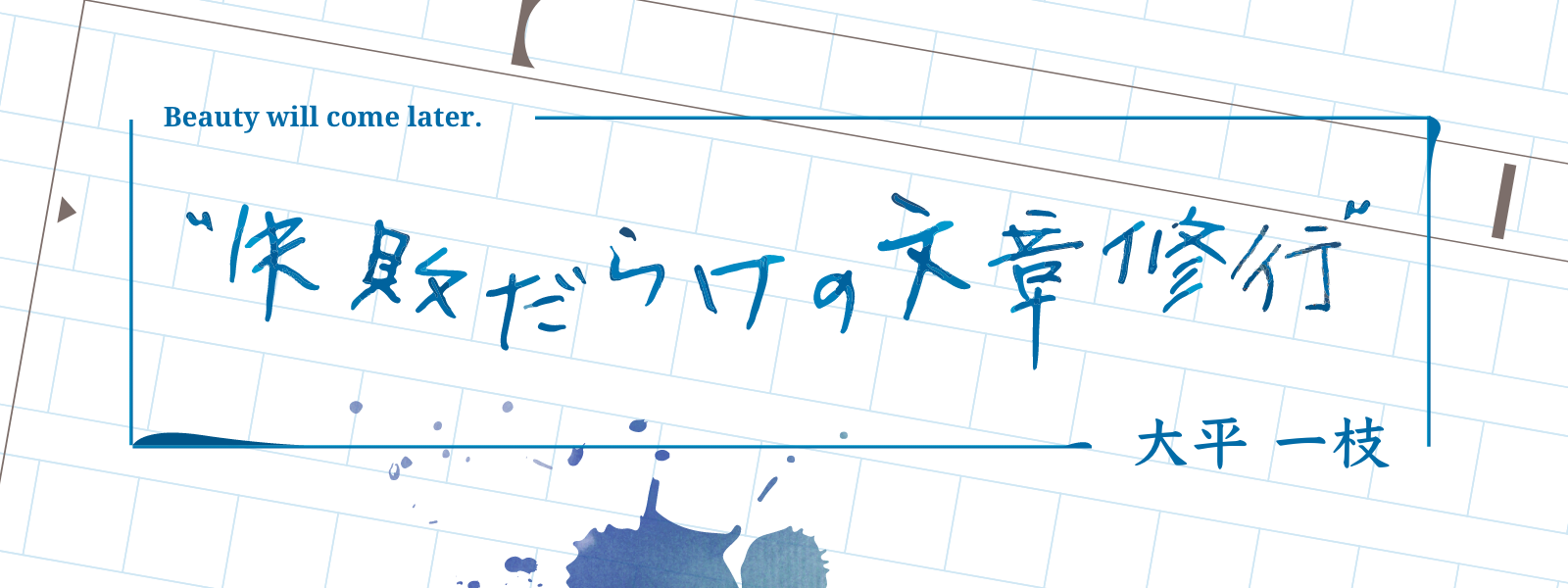文筆生活30年余。失敗からひとつひとつ記事やエッセイの書き方を学んでいった大平さんの七転び八起き。「人柄は穏やか、仕事は鬼」な編集プロダクションのボスの教えから始まる文章修行の日々には、普遍的で誰にも役に立つヒントが満載です。
「で、結局何言いたいの」と自分に問う
「でさ、大平さんはこの文章で何が言いたいわけ?」
「ですからオリンピック選手を育てた母親が、娘の中学時代、心折れそうになった彼女に、◯◯といって、〜〜が、」
編集プロダクションのボスは、火を付けたばかりの煙草をもみ消し、私の言葉を遮った。
「主題は、ひとことで言えなきゃだめなんだよ。だらだらと誰がなにして、ああなってこうなってって書き手が長く説明しなきゃわからないようなもの、読者に伝わるわけないでしょう」
漫画のごとく、頭の中で「がーん」という音が鳴った。それくらいぐうの音も出ない、端的で正しい説教だった。
30年経た今も、しばしばその言葉が頭をもたげる。夢中になるあまり文章が脱線し、あちこちいきかけるたび、あのもみ消された灰皿の光景とともに。
原稿だけではなく、何事もテーマはつねにひとことで言えるようにせよ、という教えはあらゆる場面で言われた。
たとえば雑誌の特集企画、書籍企画、依頼を受けて制作する広告記事。その言葉どおりに原稿に書くことはないが、「これは古い家具を愛する人達の価値観とライフスタイルを紹介するインテリア特集です」とひとことで言語化できれば、自分の羅針盤になる。文章が反れたり、よけいな道に進みかけたり、迷ったりしても、戻ることができる。
また、主旨を他者にひとことで説明できることは、出版の世界で大変重要である。
新たな書籍を執筆するとき、企画意図をひとことで書き手が言えなければ、担当の編集者は企画会議で説得力をもって提案することができない。
「それ、どんな本なの?」と、会議で別の編集者から聞かれたとする。
「失敗や試行錯誤の末、歳を重ねてやっと見えてきた料理のいろはを綴ったエッセイです」
へえ、面白そうだねと言われれば議論は一歩前に進むが、「あんまり新味がないね」と言われることもあろう。「でもですね、お母さんや妻になれば、だれもが自動的に最初から料理がうまくなるわけではないと思うんです。そこに自己嫌悪を抱いている人もいる」などと、反論もできる。
これはたまたま私の新刊『台所が教えてくれたこと』の例で、その場に参加していない私の想像でしかないが、もしも担当編集者が、長々とテーマを説明していたら、「ああはいはい、もういいよ」と、周りはなるかもしれない。これでは会議の俎上にものぼらない。
なにしろ、とにかく編集者は忙しいので。そう教えてくれたのも、ボスだった。
編集者だけではない。読み手のだれもかれもが忙しい。今は、手のひらで、ショートドラマやダンス動画やお笑いコンテンツを見て、つまらなかったら次々クリックして新しい画面にとぶ時代である。
いや、今も昔も読者のありようは変わるまい。
あのときもボスは、読む側の立場になって原稿を書け、といろんな方法で教えてくれたのだと思う。主題が自分にしかわからないような、あるいは長々と言葉を足さないとわからないような自分本位のものは、伝わらない。それは読者に対して不誠実である、と。ただし、私にとって門外漢の小説については、この範疇ではないと記しておく。
文章を書いている途中、「何言いたいかわらなくなってきちゃったな」と思うときがあるかもしれない。そんなときは、主旨を口に出して反芻するといい。うまくひとことで言えなかったら、それは勇気を出して一旦捨て、最初から書き直すことをおすすめする。
私はつい2週間前も、編集者にこう言われたばかりだ。
「この作品で、大平さんがいちばん書きたいことってなんですか」
たったひとりの人間にさえ伝わっていないようじゃ、一から書き直しだなと直感的に悟った。万人にわかるはずもない。
なんとも進歩のない話である。愛煙家の相手がどうしたのか電話だったのでわからないけれど、やっぱりこのときも、くしゃっと押しつぶされた吸い殻の光景が浮かんだ。吸い殻は、私の文章が回りくどくて人をイライラさせてしまった未熟な思い出の象徴なのである。
ボスの教え
主題はつねにひとことで言えるようにせよ
-
第1話結婚式前夜の鬼特訓
-
第2話人は長文が嫌い
-
第3話自慢禁止
-
第4話五感を表す言葉と、固有名詞にコツあり
-
第5話美文は邪魔になる
-
第6話校閲に学ぶ
-
第7話推敲のヒントーー‟書き立て”の熱は勘違いしやすい
-
第8話「偏り」と「独りよがり」
-
第9話きれいや可愛いは、情報ではない
-
第10話宇野千代さんの料理エッセイとツレヅレハナコさんのインスタ
-
第11話事実確認作業は、書き手の生命線
-
第12話仕事の場面での、手紙の効用について
-
第13話「で、結局何言いたいの」と自分に問う
-
第14話なにをどんなふうに読めば、自分の肥やしになるのか
-
第15話齟齬(そご)を生まない仕事スタイル
-
第16話推敲の大前提に据える最も重要なオキテ
-
第17話文章が散漫になりがちなときの道標(みちしるべ)
-
第18話忘れられないあの本棚
作家、エッセイスト。1964年、長野県生まれ。編集プロダクション宮下徳延事務所を経て、1995年、出産を機に独立。『天然生活』『別冊太陽』『チルチンびと』『暮しの手帖』などライターとして雑誌を中心に文筆業をスタート。市井の生活者を描くルポルタージュ、失くしたくないもの・コト・価値観をテーマにした著書を毎年上梓。2003年の、古い暮らしの道具を愛する人々のライフスタイルと価値観を綴った『ジャンク・スタイル』(平凡社)で注目される。
主な著書に『東京の台所』『ジャンク・スタイル』『それでも食べて生きてゆく 東京の台所』、『注文に時間がかかるカフェ』『人生フルーツサンド』『正解のない雑談』『こんなふうに、暮らしと人を書いてきた』『そこに定食屋があるかぎり』「台所が教えてくれたこと』など30冊余。「東京の台所」(朝日新聞デジタルマガジン&w)、「ある日、逗子へアジフライを食べに〜おとなのこたび」(幻冬舎PLUS)、「遠回りの読書」(『サンデー毎日』)他連載多数。