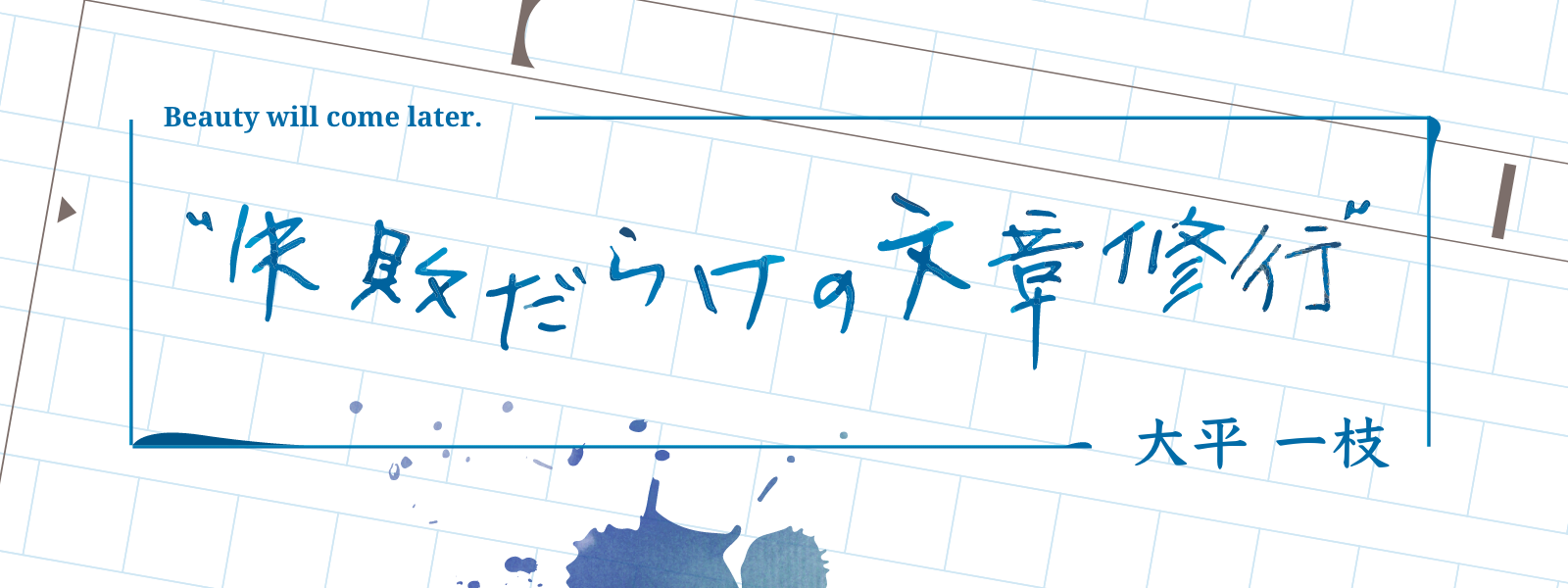文筆生活30年余。失敗からひとつひとつ記事やエッセイの書き方を学んでいった大平さんの七転び八起き。「人柄は穏やか、仕事は鬼」な編集プロダクションのボスの教えから始まる文章修行の日々には、普遍的で誰にも役に立つヒントが満載です。
仕事の場面での、手紙の効用について
紙の手触りやインクの滲み、書き文字が好きだ。だから、手紙も人より書くことがいくらか多いほうだと思う。
紙には、デジタルには映らない書き手(送り手)の情報がたくさん宿る。
編集者には、資料や校正用紙を書き手に送る際、一筆箋やメモ書きをちょっと添える人が多い。そのひと言があるだけで、私は少しほっとするし、楽しい気持ちになる。あの人はこういう紙を使うんだなと思ったり、わ、万年筆だかっこいいと感心したり。相手を知る材料が増えるようで嬉しい。
仮に、ボールペンのなぐり書きでも、あるいは添え書き状はなくて、封筒の差出人のところに「よろしくお願いいたします!」と書かれただけだったとしても、人の手の痕跡はあたたかいものだ。
自分の文章修行を振り返るとき──もちろんそれは死ぬまで続く──、様々な岐路に手紙があった。さし上げる便りは人生が大きく変わるほどではなくとも、出会いやその後の仕事に深みをもたらす、大切な種になった。
たとえば、仕事で長期間タッグを組むお相手、とくにカメラマンやデザイナーなど、編集者ほど頻繁には会わないが互いの理解が良い結果を生むであろう立場の人には、何かを送る用件がある際によく封書を添えた。
あとから「縦書きの便箋をもらったのは数年ぶりです」とか、「あのお手紙は大平さんを知る大きな手助けになりました」と言われたことがある。
最近は、御礼葉書が多い。お相手に合った葉書の柄を選び、季節に合わせた切手を貼る。万年筆のインクも替えたり、ちょんとハンコを押したりすることも。これがまた、葉書に洋服を着せるようで楽しい。半分、趣味のようなものでもある。
新米ライターの頃は、もっと手紙を出していた。ひとつのプロジェクトの終わったときや、ごちそうになったとき。貴重な学びをいただいた先輩や編集者等々に。
切手代がべらぼうに上がり、年賀状の習慣は減少の一途をたどり、便利で早いメールが主の今だからこそ、手書きの手紙は有効だと私は思う。
まず、印象に残る。あとあとまで形として残る。もし、自分が売り込み中の新人ライターだったら、仕事をくださった編集者、組んだお相手に、片っ端から御礼の葉書を出すかもしれない。
仮に、仕事のできが普通だったとしても、余韻が変わる。「あの人は手書きの葉書をくれた人だ」と記憶される。昔は誰もしていたことだが、今はそれがかえって目立つ。丁寧だとみなされ、深く印象に刻まれるのではあるまいか。
家人は映画製作業を生業としているが、駆け出しの制作担当だったころ、ここぞという大事な場面は、手紙を書いたという。
依頼、ねぎらい、交渉事、お詫び。大事な要件は、いろいろある。
「不思議と、手紙だとお願いことが通るんだよな。半分無理だと思っていたようなことでも」
なにやら打算的に見えたら、それはひとえに私の筆の未熟である。
思いを伝えたい一心で紙と真摯に対峙していたのだろうし、同じ文字でも、手紙は相手に文字以上の何かが伝わるからだろう。また、身内がいうのもあれだが、彼の字はなぜだか私の百倍整っている。義父も達筆だったので血筋かもしれない。
話がそれた。
どんな仕事にも、「ていねいな気持ち」が形になって伝わる手紙は有効、と伝えたい。
ごくたまに、「出版の世界に何のつてもないけれど、本を出すにはどうしたらいいですか」と相談を受ける。
以前は自分が書きたいテーマに近い類書の出版社や編集者に、原稿を持ち込む人が多かったと聞く。今は残念ながら、各出版社に対応する人的余裕がない。様々な理由からきっぱりお断りを掲げているところもある。それでもという強い気持ちがあるときは、手紙を書くのはどうだろう。原稿の書き出しだけ付けて。
書きたい内容や主旨はできるだけ短く、わかりやすく。
迷惑だな、とは思うだろうが、面倒だから読まずに捨てようという編集者は、どれくらいいるだろう。
出版社の食指が動くかどうかは、企画と筆力次第。ただし、編集者は忙しいので、いきなり全文送りつけるのはやめよう。
つい最近も、ベテラン編集者が「酔っ払っていても、タイトルや最初の四行読んだら、企画としていけるかどうかわかる」と話していた。
四という数字に妙にリアリティがある。とはいえ半分訝しく思い、聞き返した。
「酔っててもですか? シラフに戻って冷静に読んだら、あれれ面白くなかったって、なりませんか?」
「酔っ払っている状態でさえ面白いと感じたら、それは間違いがないんです。そんな作品は翌朝読んだって絶対に面白い」
編集者によって違うかもしれないが、私はその直感力にひどく納得がいった。
書いたものがすでにあり、伝えたい強いテーマがある、または未完でも自信があり、これを伝えなければ死ぬくらいの熱い思いがあったら、試すのも一考。
類書がなかったら好きな出版社でいい。好きな本のあとがきには、たいてい編集者の名が書かれている。その人宛てに、丁寧に書いた短めの手紙とともに、書き出しと書籍概要を一枚程度つけて送ってみては。
私が駆け出しで、知り合いがひとりもいないまったく別の業界で働いていて、すでに書籍にしたい作品を書きあげていたら、たぶん試している。「やめてくれよ」と渋々封を切った編集者を、絶対に後悔させないという自信があればきっと。
先達の教え
仕事の場面で、形に残る手書き文字をもらって嫌な人はいない
-
第1話結婚式前夜の鬼特訓
-
第2話人は長文が嫌い
-
第3話自慢禁止
-
第4話五感を表す言葉と、固有名詞にコツあり
-
第5話美文は邪魔になる
-
第6話校閲に学ぶ
-
第7話推敲のヒントーー‟書き立て”の熱は勘違いしやすい
-
第8話「偏り」と「独りよがり」
-
第9話きれいや可愛いは、情報ではない
-
第10話宇野千代さんの料理エッセイとツレヅレハナコさんのインスタ
-
第11話事実確認作業は、書き手の生命線
-
第12話仕事の場面での、手紙の効用について
-
第13話「で、結局何言いたいの」と自分に問う
-
第14話なにをどんなふうに読めば、自分の肥やしになるのか
-
第15話齟齬(そご)を生まない仕事スタイル
-
第16話推敲の大前提に据える最も重要なオキテ
-
第17話文章が散漫になりがちなときの道標(みちしるべ)
作家、エッセイスト。1964年、長野県生まれ。編集プロダクション宮下徳延事務所を経て、1995年、出産を機に独立。『天然生活』『別冊太陽』『チルチンびと』『暮しの手帖』などライターとして雑誌を中心に文筆業をスタート。市井の生活者を描くルポルタージュ、失くしたくないもの・コト・価値観をテーマにした著書を毎年上梓。2003年の、古い暮らしの道具を愛する人々のライフスタイルと価値観を綴った『ジャンク・スタイル』(平凡社)で注目される。
主な著書に『東京の台所』『ジャンク・スタイル』『それでも食べて生きてゆく 東京の台所』、『注文に時間がかかるカフェ』『人生フルーツサンド』『正解のない雑談』『こんなふうに、暮らしと人を書いてきた』『そこに定食屋があるかぎり』「台所が教えてくれたこと』など30冊余。「東京の台所」(朝日新聞デジタルマガジン&w)、「ある日、逗子へアジフライを食べに〜おとなのこたび」(幻冬舎PLUS)、「遠回りの読書」(『サンデー毎日』)他連載多数。