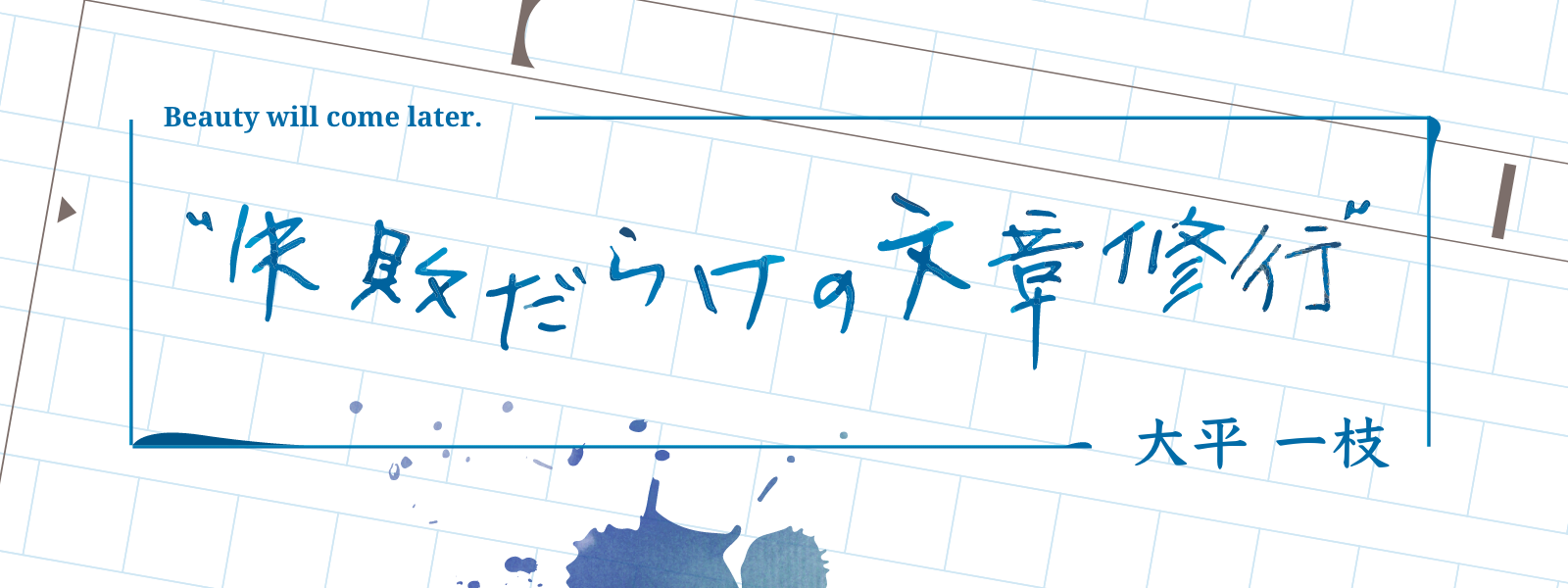文筆生活30年余。失敗からひとつひとつ記事やエッセイの書き方を学んでいった大平さんの七転び八起き。「人柄は穏やか、仕事は鬼」な編集プロダクションのボスの教えから始まる文章修行の日々には、普遍的で誰にも役に立つヒントが満載です。
なにをどんなふうに読めば、自分の肥やしになるのか
文章上達をテーマにした読み物やお悩み相談欄には、たいてい”うまくなりたければ本を読みなさい”と書かれている。
正直なところ、その一文を読むたび、「うん、そりゃそうなんだけどさ」と、肩透かしを食らった気分になった。
それができていれば苦労はしないよね、と。
けれども、編集プロダクション(以下編プロ)から独立して30年、どうにか売文業で住宅ローンを払い、子どもふたりの学費を払ってきた私は──収入の不安定な映画製作業の夫とともに──、一周回ってしみじみと痛感するのである。うまくなるには、やっぱり良い文章を読むしかない。
それが究極の近道であると、身を持って実感したのは、恥ずかしながらここ10年ほどのことだ。
どんなにテクニックを学んでも、それだけでは装備として決定的に足りない。
山登りで、体力がないのに、素晴らしい靴や服や道具や指導者をつけるようなものだ。それでも軽い山は登れるかもしれないが、そのうち必ず、登れない高さの山があることに気づく。
若い頃は、わからなかった。だが、多少小器用で、表面的な装備でなんとかなる登山なぞ、早々に限界が来る。
その限界を、誰も指摘してくれない。ただ仕事が来ない、読者が離れるだけなのである。だから自分で気づくしかない。
私は『東京の台所』(朝日新聞デジタルマガジン)というウェブ連載を続けて13年になる。当初2年間は毎週更新した。その後、自分のスケジュールの都合から隔週にさせていただいている。
この最初の2年間100回余のうちの後半が、思い出すのも苦しい、もがきの連続だった。
圧倒的に自分に語彙がないからだ。構成力もない。時間もない。アポイントを取って、取材して、写真の加工をして(当時は撮影も担っていた)、原稿を書く。そのサイクルが毎週あるため、時間もない。なんでもむしゃらに仕事を受けていた時期とも重なり、実力不足を時間のせいにしていた。
たとえば〆の言い回しが「あれ、これいつかも書いたぞ」と思ったり、タイトルが似通っていたり。十人十色のはずの台所についても「コクピットのような」「清々しい」「あたたかい」「自分流の」というような形容が、頻出する。
けれどもそれに代わる表現が瞬時に思いつかないので、締切間際にえいやっと送ってしまう。
初代編集者はとくに原稿に厳しい人で、瞬時に見抜き、赤字を入れすぐ突き返された。「ここは重複なので差し替えたほうがいい」「この段落はまるっと削除しても伝わるのでは」。そこで鍛えられるわけだが、なにしろ第一稿アップから修正アップまでひと晩しかないことも多く、熟考の足りぬまま毎回なけなしの力を絞り出した。OKが出ても、その場しのぎでなんとか逃げきったような感覚が残り、忸怩たる思いが堆積していくばかりだった。
そうした情けない理由もあって、連載ペースをゆるめてもらうことになる。
このとき、はたと考え込んだ。
台所連載に限らず、つねに締切が迫ったなかで書いている。隔週更新にしてもらったところで、その時間軸はこれからも変わらないだろう。
ということは、短時間で多様な引き出しから言葉を取り出したり、構成のアイデアを考案したりする基礎体力がないと、自分の仕事は続かなくなるだろう。早晩発注が途絶えるのは目に見えている。
さて、どうすべきか。
考えた末たどりついたのは「たくさん、他者の作品を読むこと」という王道だった。
ではなにを、どんなふうに読めば、自分の肥やしになるだろうか。
ふと、編プロのボスとのやりとりが浮かんだ。
女性月刊誌の編集をしていた社員時代、初めて「この記事は自分にも書かせてほしい」とお願いしたときのこと。
書き上がった原稿は使い物にならず、ボスはそっくりボツにして、アンカーという外部のベテランの男性ライターに「大至急あさってまでに」と入稿直前に依頼。記事に穴が開くという惨事を防いだ(ボスはその可能性も織り込み済みで、私の原稿の締切を前倒ししていた)。
この一件は、第5話「美文は邪魔になる」に詳しい。じつは続きがあり、私は数日後、ボスに呼び出された。
書き直しの機会も与えられず、別の書き手にすげ替えられた。”こいつは教えても良くならない”と見限られたショックをまだを引きずっていた。
ボスは、入稿したライターの原稿と、私の手書き原稿(この後ワープロが出始める)を机上に並べ、静かに言った。
「同じ文字数なので、最適な比較になります。読み比べて、どこがどう違うか。自分の原稿のどこがまずかったか考えてください」
ベテランライターは、私の取材メモと元原稿をベースに書いている。つまり取材をしていない。
文字数・テーマ・取材データという同じ制限、同じ材料で、書き出し、構成、結びの表現、なにからなにまで月とスッポン、雲泥の差だった。何を削り、どこをふくらませているか。とりわけ限られた文字数で、‟何を書かないか”は大きな学びになった。
私は、ひたすら取材対象者がいかにすごいかを熱く描き、「感動」「努力」「根性」のオンパレード。ライターさんは感動の押し売りは一切なく、取材対象者から距離をおき、淡々と事実だけを積み上げる。乾いたトーンとクライマックスの熱さの対比によって、胸に迫るものがより深くなる。
私は最初から熱いだけの”お涙頂戴式”、無駄にウエットだった。
あのとき学んだ、同じ文字数のものを読み比べる利点を思い出したのだ。
お勧めの連載文庫化4冊
ウェブ連載でも、文字数はだいたい決まっている。今週3千字で、来週は盛り上がったから1万字はない。雑誌や新聞など紙媒体はもっと厳密に文字数が確定しており、1字でもはみ出したら訂正しなけばならない。
そこで長期連載を続けている人の優れた作品をひたすら読んだ。同じ文字数で、どう起承転結の構成を変え、表現に工夫をこらし、読者の目を引きつけているか。
東海林さだおさんの『まるかじり』シリーズ、平松洋子さんの『この味』(週刊文春)。向田邦子の随筆家デビュー作にして代表作『父の詫び状』は、PR誌『銀座百点』の連載をまとめたものである。開高健の『ずばり東京』は、『週刊朝日』のルポルタージュ連載で1963年、東京五輪を前に急速に変わりゆく東京の暗部を描いた。本作の白眉は文体で、ほぼ会話文だけの作品もあれば、「馬走る頃であります。」と始まる講談風、ポエム風、日記形式もある。同じ連載で、文体を変えていいんだと目から鱗が落ちる思いであった。
どんなに優れた作家でも、読まれなければ連載は打ち切られる。読み続けられるように、先週より今週、今週より来週、みなそれぞれに創意工夫を続ける。その惜しみない努力の跡を発見すると胸が震える。
ここに挙げたものはありがたいことに今はすべて、文庫化されている。安くて小さい。ハードカバーだと気の引ける赤線も、惜しみなくどんどん引けるし、付箋も書き込みも自在だ。
どれも買ったのははるか昔だが、今も仕事場のすぐ手の届くところにおいて紐解く。先人たちの足跡が、今日も、実力の足らない私の水先案内人になっている。
読み比べで、もっと手っ取り早いのは『天声人語』(朝日新聞)である。読売新聞なら『編集手帳』、毎日新聞なら『余録』。新聞社の顔でもある一面コラムの、あれだ。
これぞ同じ文字数の、究極の長期連載。しかもその新聞社で、おそらくいちばん‟文章の上手い記者”が書いている。
日々の読み比べもいいのだけれど、おすすめしたいのは天変地異や、新聞社としてどうしても避けられないテーマのある日の読み比べだ。たとえば終戦の日、8月6日や9日、社会を揺るがす大きなできごとがあった日、国政選挙期間など。平和の尊さ、戦争の愚かさ、一票の重さという普遍的なテーマを、どんな書き出し、どんな起承転結、どんな変化球で書いているか読み比べる。各社しのぎをけずり、文章のトップランナーが、あの手この手の工夫をこらし、「平和は大切ですね」と書かず、別の表現、形容、比喩、展開を用いて伝える。最適な文章上達の教科書だ。
デジタル版含め、新聞購読が減少している時代ゆえ、各紙読み比べは図書館にでも行かないと難しいだろう。一紙でもいい。予想されるテーマがある日、自分ならどんな書き出しでどう展開するかシミュレーションしてから、読んでみては。
ちなみに私は国民的大スターが逝去された日は、できるだけ複数の新聞コラムを読むようにしている。偉業の説明のしかた、悼む気持ちをどんな切り口で書いているか。とくに書き出しが気になる。あれだけ短い文字数の中で、必ず入れなければいけない情報を盛り込みながら、いかに惹きつけ、他紙コラムと差のつく書き出しをしているかを占っている。
いまさらあえて、”たくさん読むこと”のススメを書いた。あらためて考えると、読むだけで上達するなんて、こんなお手軽な方法はない。
失敗からの教え
人気の長期連載読み比べから、構成や書き出しの工夫を学ぶ
-
第1話結婚式前夜の鬼特訓
-
第2話人は長文が嫌い
-
第3話自慢禁止
-
第4話五感を表す言葉と、固有名詞にコツあり
-
第5話美文は邪魔になる
-
第6話校閲に学ぶ
-
第7話推敲のヒントーー‟書き立て”の熱は勘違いしやすい
-
第8話「偏り」と「独りよがり」
-
第9話きれいや可愛いは、情報ではない
-
第10話宇野千代さんの料理エッセイとツレヅレハナコさんのインスタ
-
第11話事実確認作業は、書き手の生命線
-
第12話仕事の場面での、手紙の効用について
-
第13話「で、結局何言いたいの」と自分に問う
-
第14話なにをどんなふうに読めば、自分の肥やしになるのか
-
第15話齟齬(そご)を生まない仕事スタイル
-
第16話推敲の大前提に据える最も重要なオキテ
-
第17話文章が散漫になりがちなときの道標(みちしるべ)
作家、エッセイスト。1964年、長野県生まれ。編集プロダクション宮下徳延事務所を経て、1995年、出産を機に独立。『天然生活』『別冊太陽』『チルチンびと』『暮しの手帖』などライターとして雑誌を中心に文筆業をスタート。市井の生活者を描くルポルタージュ、失くしたくないもの・コト・価値観をテーマにした著書を毎年上梓。2003年の、古い暮らしの道具を愛する人々のライフスタイルと価値観を綴った『ジャンク・スタイル』(平凡社)で注目される。
主な著書に『東京の台所』『ジャンク・スタイル』『それでも食べて生きてゆく 東京の台所』、『注文に時間がかかるカフェ』『人生フルーツサンド』『正解のない雑談』『こんなふうに、暮らしと人を書いてきた』『そこに定食屋があるかぎり』「台所が教えてくれたこと』など30冊余。「東京の台所」(朝日新聞デジタルマガジン&w)、「ある日、逗子へアジフライを食べに〜おとなのこたび」(幻冬舎PLUS)、「遠回りの読書」(『サンデー毎日』)他連載多数。