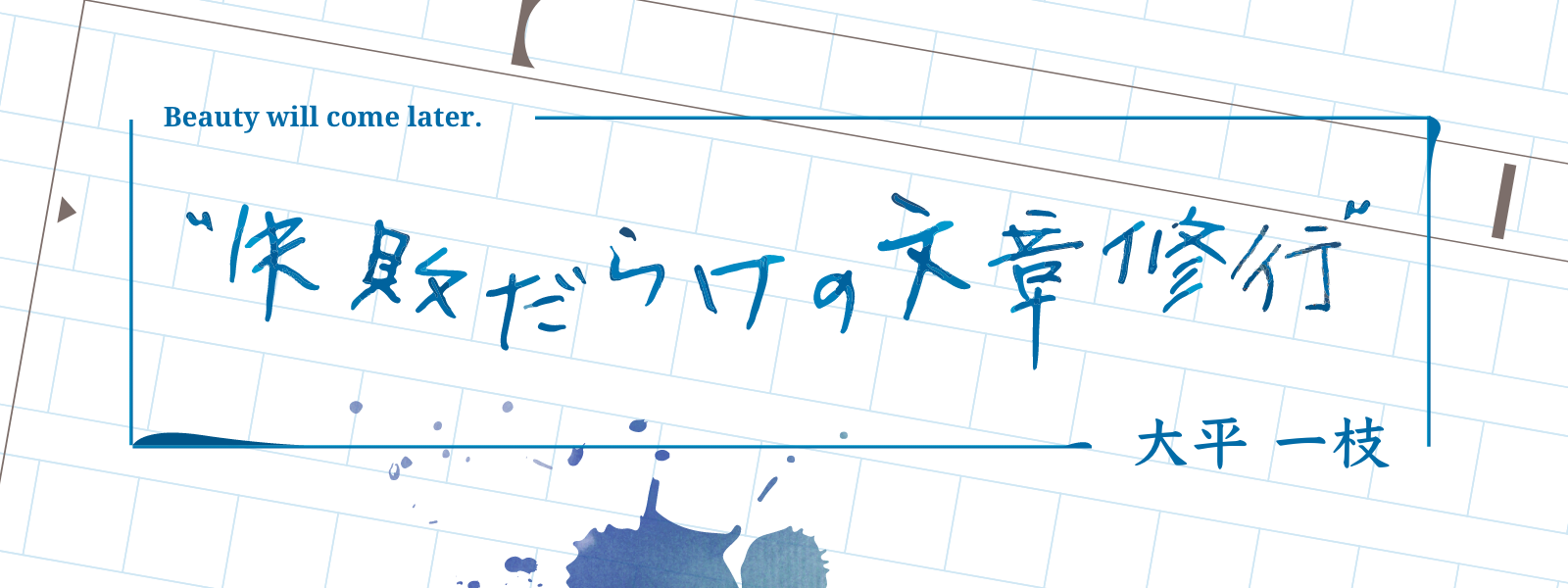文筆生活30年余。失敗からひとつひとつ記事やエッセイの書き方を学んでいった大平さんの七転び八起き。「人柄は穏やか、仕事は鬼」な編集プロダクションのボスの教えから始まる文章修行の日々には、普遍的で誰にも役に立つヒントが満載です。
事実確認作業は、書き手の生命線
少しずつ、このコラムの感想やご意見をいただくようになった。広報誌や専門誌に書いている、あるいは職場で文章を書く機会がある、という方も少なくない。文章の技術を磨きたいという人が全員エッセイを書いたり、なにかのメディアに発表したり、発信したいわけではないのだなと、いまさらながら思い至る。
そこで今回は、エッセイ以外の話もしたい。
個人的な「想い」を書くときと、他者について書く、「情報」を伝えるというときは、注意すべきことが異なる。
30余年前、女性誌の編集プロダクション(以下編プロ)に勤めていた頃、ボスから配られた手書きの冊子がある。「編集の心得」「記者の心得」という簡易なハンドブックで、こんな言葉が書かれていた。
<事実の確認は記者・編集者の生命線>
当時は月刊誌を作っていたので、文字どおり記者編集者向けの助言ではあるが、私はこのいっけん普通に見える言葉の重さを忘れ、足もとをすくわれそうになることが今も時々ある。「正しいはず」と安易に思い込み、後に誤りだとわかり、冷や汗をかくようなことが。
たとえば、ある90代の女性を取材したときのこと。その方は、地元の県で初の女性の警察学校卒業生であり、初の婦人警官だったと語った。
私はそのまま原稿に書いた。すると編集者から、これは事実かと聞かれた。
「ご本人がおっしゃっていますので」
「ご本人以外に、公式の機関や文書などで確認を取りましたか」
え。言葉に詰まった。70年あまりも前のことを、どうやって調べるのか。ご本人は卒業生名簿を持っていない。
警察学校に問い合わせたところで、個人情報を教えてはくれまい。
「こんな大事なこと、御本人は嘘は言わないと思うんです」
編集者は、次のような自身の体験を明かした。
かつて、やはり高齢の方の戦争体験を記事にする仕事があった。原稿にまとめると、上司にすべての裏付けをとれと言われた。細かいところまでは無理だと思ったが、どんな小さな誤りでもひとつあったら記者失格だと言われ、それも当然と納得し、確認作業にとりかかった。
短い記事なのに、ひとつひとつの検証に案外手間ひまがかかる。結果、当時の年齢と出来事のつじつまが合わず本人が「4歳」と言ったのはじつは「7歳」だったり、「◯◯町」が「××町」だったり、誤りが見つかった。
そこで編集者は気づいたのだという。
──お相手が嘘を付くつもりはまったくないけれど、自分のことであっても勘違いや思い違いをしている人はとても多い。高齢者ほどそうで、人の記憶はあてにならないものだ。
「だから大平さんも、必ず裏付けを取ってください。それができなかったら残念ですが、女性初の警察学校卒業生と初の婦人警官のくだりは削ってください」と、言われた。
該当の県の警察学校に電話し、事情を話す。本来ならそちらに伺うべきだが、遠方でそれもできないことを詫びた。
対象者の名前を告げたが、もちろん「個人情報なのでお伝えはできない」との返事だった。だが、なんとか知りたというこちらの想いを汲み、「女性の一期生の卒業年と人数を調べることはできます」とのこと。
さっそく取材相手に卒業年、同期の女性と男性の人数を確認。卒業生名簿と一致し、当時の状況の話も「そういう記録があります」とのことで無事掲載になった。
ただし、婦人警官第一号は、時間内に裏付けが取れず、削除した。
「たとえ自分のことでも、人の記憶はあてにならない」という編集者の言葉は、今も戒めになっている。
いい意味で疑って書くこと。インタビューは、相手によりかかりすぎず、フラットな目線で事実正誤を意識しながら、行うこと。それが、ものを伝える書き手の基本姿勢であると。
前述のボスのハンドブックには、こんな解説が付け加えられている。
<事実についての間違いは絶対に許されない。
思い込みを避け、
時間に追われていても、疲れていても、本能的に事実を確認する習慣を身につけよ。
念には念を入れよ。>
時間に追われていても、疲れていても、という言葉にぎくりとする。
わかっているよそんなことと思っていても、忙しいと、人は自分に甘くなる。人の弱さを見越した言葉が、ボスらしいと思った。
また、案外自分についての記憶違いは多いというのは、エッセイを書く際も戒めになる。未熟をさらすようだが、今もけっこうな頻度で、編集者や校閲者から指摘が入る。自分をいちばん知らないのは自分、と思った方がよい。
ボスの教え
どんなに忙しくても、疲れていても、本能的に事実を確認する習慣を身につけよ
-
第1話結婚式前夜の鬼特訓
-
第2話人は長文が嫌い
-
第3話自慢禁止
-
第4話五感を表す言葉と、固有名詞にコツあり
-
第5話美文は邪魔になる
-
第6話校閲に学ぶ
-
第7話推敲のヒントーー‟書き立て”の熱は勘違いしやすい
-
第8話「偏り」と「独りよがり」
-
第9話きれいや可愛いは、情報ではない
-
第10話宇野千代さんの料理エッセイとツレヅレハナコさんのインスタ
-
第11話事実確認作業は、書き手の生命線
-
第12話仕事の場面での、手紙の効用について
-
第13話「で、結局何言いたいの」と自分に問う
-
第14話なにをどんなふうに読めば、自分の肥やしになるのか
-
第15話齟齬(そご)を生まない仕事スタイル
-
第16話推敲の大前提に据える最も重要なオキテ
-
第17話文章が散漫になりがちなときの道標(みちしるべ)
作家、エッセイスト。1964年、長野県生まれ。編集プロダクション宮下徳延事務所を経て、1995年、出産を機に独立。『天然生活』『別冊太陽』『チルチンびと』『暮しの手帖』などライターとして雑誌を中心に文筆業をスタート。市井の生活者を描くルポルタージュ、失くしたくないもの・コト・価値観をテーマにした著書を毎年上梓。2003年の、古い暮らしの道具を愛する人々のライフスタイルと価値観を綴った『ジャンク・スタイル』(平凡社)で注目される。
主な著書に『東京の台所』『ジャンク・スタイル』『それでも食べて生きてゆく 東京の台所』、『注文に時間がかかるカフェ』『人生フルーツサンド』『正解のない雑談』『こんなふうに、暮らしと人を書いてきた』『そこに定食屋があるかぎり』「台所が教えてくれたこと』など30冊余。「東京の台所」(朝日新聞デジタルマガジン&w)、「ある日、逗子へアジフライを食べに〜おとなのこたび」(幻冬舎PLUS)、「遠回りの読書」(『サンデー毎日』)他連載多数。