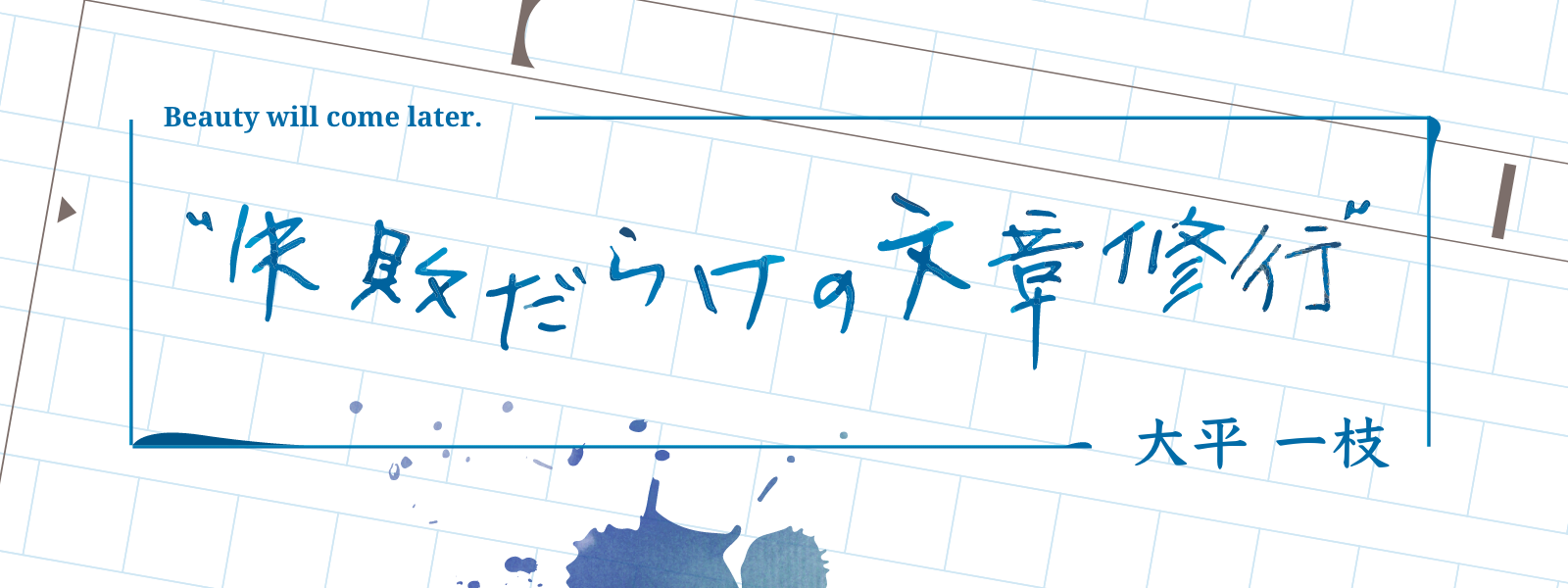文筆生活30年余。失敗からひとつひとつ記事やエッセイの書き方を学んでいった大平さんの七転び八起き。「人柄は穏やか、仕事は鬼」な編集プロダクションのボスの教えから始まる文章修行の日々には、普遍的で誰にも役に立つヒントが満載です。
きれいや可愛いは、情報ではない
前回、 編集者から「きれいとか可愛いは、情報ではない」と指摘されたことを書いた。
このひとことには、いろんな示唆が含まれている。
だれもが使う形容詞を安易に使うなという意味でもあるし、「情報」を伝えようとする時、書き手の主観に依拠した形容は、「感想」でしかないという指摘でもある。きれいや可愛いは、わかりそうでわからない。じつは意味が広すぎて何の意味も持たない説明なのである。
大変有名な、その人の価値観や美意識が特別に注目されている書き手なら許されるかもしれないが、そうでない場合は、どう美しいのか、あるいは可愛らしく見えるのか具体的に書きたい。
ある若手のフリーライター、つまり同業者に相談されたことがある。
「インテリアの取材記事で、“居心地が良い”と書いたら、編集者に怒られました。あなたの居心地の良さなんて、読者はどうでもいい。個人的な主観で書かないでくださいって。どう思いますか」
今にも泣き出しそうな表情だった。
私もやりがちなミスなので、彼女の気持ちが痛いほど伝わった。書き手として、深くブライドを傷つけられたのである。
しかし、やはりその指摘は正しいと言わざるを得ない。エッセイならよいが、取材記事はいけない。取材者が感じたことであって、情報ではないからだ。
<多くの人の滞在時間が長い。一度行けば誰もが、時を忘れていつまでもそこにいたくなるような、居心地の良さを感じるだろう>であれば、まだいいかもしれない。
ただし、厳密に言うと「居心地がいい」もまた常套句なので、できればひと工夫したい。
<閉められているはずの窓から、五月の爽風を肌に感じた。いつまでもそこにいたくなる空間であった>はどうだろう。たとえば“居心地の良さ”を、自分流に書き換えるには、自分の心に耳を澄ますような感覚が大切になってくる。
開高健、向田邦子、小川洋子。
私が好きな作家には、もっと読みたいと思わせる技術があちこちにちりばめられている。もちろん才能であることはまちがいないが、一言一言これでいいか、手垢のついた表現ではないか点検を重ね、精密に言葉を紡ぎ出す“企み”と、言い換えることもできる。
書いても書いてもこれはどっかで聞いたような言葉だなと、自信をなくして前に進めなくなるとき、私はすがるように好きな作家の作品を読み返す。と、これらの表現は極めて高度な、文学的企みであると気づく。計算され尽くした、言葉の結晶だ。けっして思いつきでスラスラ書いたものではない。だから、才能というより、才能に裏付けされた技術とあえていいたくなる。
うっすら、そういうことに気づくようになったのは、ここ最近のことだ。自分の文章を疑うようになった。若い頃は、推敲も足りず、書いたらやりきったような気になって、疑うことをしなかった。
案外、人は長い文章を書いたとき、自分に満足しがちだ。無意識のうちにどこかから借りてきた言葉が表出していても、気付きにくい。それは、自分を疑わないからだ。
私は編プロから数えると34年、独立して30年の今のほうが、自分の文章を疑っている。山の険しさ、高さにおそれおののいている。
そんなときはきっと、好きな作家の作品が、処方箋になる。唯一無二の技術を、一つでも多く心の救急箱に溜めておきたい。
失敗からの教え
自分の文章を疑ってかかる
-
第1話結婚式前夜の鬼特訓
-
第2話人は長文が嫌い
-
第3話自慢禁止
-
第4話五感を表す言葉と、固有名詞にコツあり
-
第5話美文は邪魔になる
-
第6話校閲に学ぶ
-
第7話推敲のヒントーー‟書き立て”の熱は勘違いしやすい
-
第8話「偏り」と「独りよがり」
-
第9話きれいや可愛いは、情報ではない
-
第10話宇野千代さんの料理エッセイとツレヅレハナコさんのインスタ
-
第11話事実確認作業は、書き手の生命線
-
第12話仕事の場面での、手紙の効用について
-
第13話「で、結局何言いたいの」と自分に問う
-
第14話なにをどんなふうに読めば、自分の肥やしになるのか
-
第15話齟齬(そご)を生まない仕事スタイル
-
第16話推敲の大前提に据える最も重要なオキテ
-
第17話文章が散漫になりがちなときの道標(みちしるべ)
-
第18話忘れられないあの本棚
作家、エッセイスト。1964年、長野県生まれ。編集プロダクション宮下徳延事務所を経て、1995年、出産を機に独立。『天然生活』『別冊太陽』『チルチンびと』『暮しの手帖』などライターとして雑誌を中心に文筆業をスタート。市井の生活者を描くルポルタージュ、失くしたくないもの・コト・価値観をテーマにした著書を毎年上梓。2003年の、古い暮らしの道具を愛する人々のライフスタイルと価値観を綴った『ジャンク・スタイル』(平凡社)で注目される。
主な著書に『東京の台所』『ジャンク・スタイル』『それでも食べて生きてゆく 東京の台所』、『注文に時間がかかるカフェ』『人生フルーツサンド』『正解のない雑談』『こんなふうに、暮らしと人を書いてきた』『そこに定食屋があるかぎり』「台所が教えてくれたこと』など30冊余。「東京の台所」(朝日新聞デジタルマガジン&w)、「ある日、逗子へアジフライを食べに〜おとなのこたび」(幻冬舎PLUS)、「遠回りの読書」(『サンデー毎日』)他連載多数。