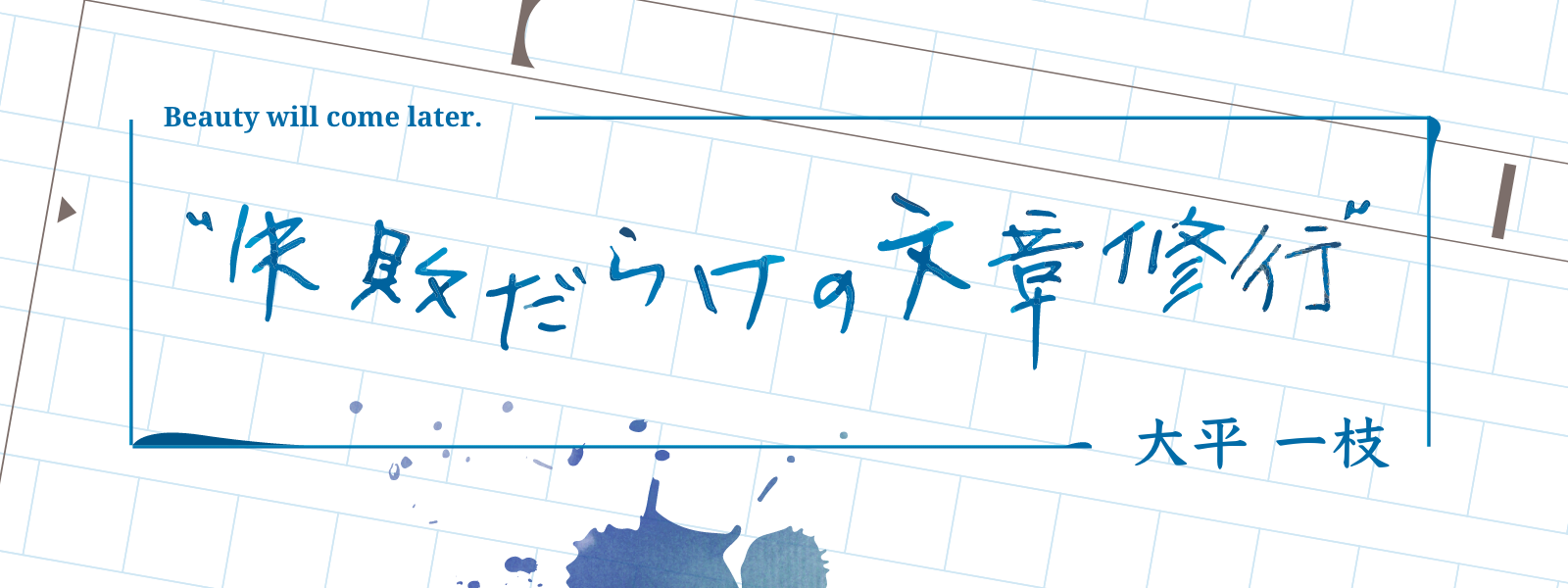文筆生活30年余。失敗からひとつひとつ記事やエッセイの書き方を学んでいった大平さんの七転び八起き。「人柄は穏やか、仕事は鬼」な編集プロダクションのボスの教えから始まる文章修行の日々には、普遍的で誰にも役に立つヒントが満載です。
自慢禁止
あるブログを読んだ。エッセイの練習に書いているとのことだった。
文法も語彙も起承転結も素晴らしい。エピソードもドラマチックだ。だが、決定的な弱点があった。
さりげなく、「こんなすごい人と付き合いのある私」が主語で、行間からにじむ自慢が、読み手の目をかすませていた。惜しいなと思った。
人は、他人の自慢を読むのが嫌いだ。SNSの発達とともに、その傾向はとみに強まっていると感じる。
匂わせ投稿というあまり耳あたりの良くない言葉がある。Aという事象について書いた投稿写真に、さり気なく高級な家具が映り込んでいたり、皆が憧れるAとは関係ないなにかが映り込んでいたりするときにも使われる。
度量の狭い私は、そのブログから、「こんなすごい人を知り合いに持っている私」という自慢の匂いを嗅ぎ取ってしまったのである。
ブログの主は、匂わせているつもりはないかもしれない。純粋にすごい人の良さを伝えたいだけだったかも。こういうとき、私はつい編集プロダクション(以下編プロ)のボスの言葉を思い出してしまう。
「誰もあなたの文章など読まないと思って、書きなさい」
そうすれば、読んでもらうよう工夫をする。読みづらさ、時系列のぶれ、重複表現、ボリューム等々について、読み手の目で点検できる。
自慢になっていやしないか、鼻につかないか、は大きなチェックポイントのひとつである。だれもお金を払って人の自慢など読みたくないし、たとえ無料のウェブだとしてもそんなものに時間を割きたくないからだ。
いっぽう世の中には、いつも上質なおいしいものを食べている人、素敵なものを持っている人、客観的に見るとずいぶん裕福な暮らしをしている人の文章があまたある。自慢になりかねないのに、まったく鼻につかないいどころか、もっと読みたいと思わせる人気の書き手の文章を読むと、私は脱帽したくなる。
さりげないインスタ数行だけでも、じつは細心の注意を払い、鼻につかないよう塩梅を図りながら書いている。じつは高い技術が必要で、どれだけ読んでも飽きさせない工夫が施されている。
へりくだれと言いたいのではない。「◯◯を食べさせていただき、お代を払わせていただいた」なんてわけのわからないニセ謙譲語を使いましょうと勧めているわけでもない。
読み手の立場で考えよう。こう書いたら、「はいはいそれはよかったね」で終わらないか、読んだ時間に相応する価値が宿っているか慮ろう。それだけである。
私も、始終失敗している。不甲斐ない話だが、最近でさえ「忙しい」「連載が月◯本」と書いて印刷されてしまったものがいくつかある。
書くことに夢中になっていると、冷静な視点を失いやすい。日常会話でも「忙しい」と言われすぎたら、「へえ、それで?」と内心冷める。同じことを文章でしているのである。
ネット上で見かける「やさしい息子が」「母は誰からも好かれる人で」「いつも行く紀ノ国屋に、大好きなオーガニックチョコがなくて」なんぞも少々危うい。悪気なく書いていても、世間の目は自分が思っている以上に自慢に過敏で、意地悪なんである。
つまり、「モンブランの万年筆を愛用している」と「一本八〇円の名もなきボールペンを愛用している」という文章と、どちらの書き手の文章を読みたいですか、という話である。
前者は、「へえすごい、よかったね」。後者は「なぜ?」「いまどきそんな安いのがあるの。どんなペン?」「いつから愛用しているのか」「愛用というからにはなにか物語があるんだろう」と次々疑問が生まれ、興味が育つ。
モンブランを書くこと自体は何も悪くない。「父から譲り受けた古いモンブランを直しながら使っている」ならそれだけで物語が始まりそうな予感にワクワクするし、「勇気を出して買ったモンブランを持っている」なら深い共感があり、書き手への親近感が一気に高まるだろう。
人はみな、その書き手にしか書けないオリジナルのモンブランエッセイを読みたいのだ。
さて、冒頭のブログの話に戻る。
もしもブログ主が知り合いで、感想を求められたら私はなんと言うだろうと考えた。
「自慢が鼻につくので、読者が離れてしまいますよ」とは、たぶん言えまい。適当に「おもしろかったです」とお茶を濁すかもしれない。
おとなになると、仕事で文章を扱うケース以外に、文章について注意や率直なダメ出しをされる機会がほぼなくなる。SNSやブログやnoteなど、好きで書いているものならなおさら、心のなかで思っても口にはしない。だから、自分で気づくしかない。
このとき「人は誰もあなたの文章を読まない」という前提が、有用なセンサーにきっとなるはず。
失敗からの教え その3
人は自慢の文章を読むのが嫌い。
-
第1話結婚式前夜の鬼特訓
-
第2話人は長文が嫌い
-
第3話自慢禁止
-
第4話五感を表す言葉と、固有名詞にコツあり
-
第5話美文は邪魔になる
-
第6話校閲に学ぶ
-
第7話推敲のヒントーー‟書き立て”の熱は勘違いしやすい
-
第8話「偏り」と「独りよがり」
-
第9話きれいや可愛いは、情報ではない
-
第10話宇野千代さんの料理エッセイとツレヅレハナコさんのインスタ
-
第11話事実確認作業は、書き手の生命線
-
第12話仕事の場面での、手紙の効用について
-
第13話「で、結局何言いたいの」と自分に問う
-
第14話なにをどんなふうに読めば、自分の肥やしになるのか
-
第15話齟齬(そご)を生まない仕事スタイル
-
第16話推敲の大前提に据える最も重要なオキテ
-
第17話文章が散漫になりがちなときの道標(みちしるべ)
-
第18話忘れられないあの本棚
-
第19話本の正しい読みかた
作家、エッセイスト。1964年、長野県生まれ。編集プロダクション宮下徳延事務所を経て、1995年、出産を機に独立。『天然生活』『別冊太陽』『チルチンびと』『暮しの手帖』などライターとして雑誌を中心に文筆業をスタート。市井の生活者を描くルポルタージュ、失くしたくないもの・コト・価値観をテーマにした著書を毎年上梓。2003年の、古い暮らしの道具を愛する人々のライフスタイルと価値観を綴った『ジャンク・スタイル』(平凡社)で注目される。
主な著書に『東京の台所』『ジャンク・スタイル』『それでも食べて生きてゆく 東京の台所』、『注文に時間がかかるカフェ』『人生フルーツサンド』『正解のない雑談』『こんなふうに、暮らしと人を書いてきた』『そこに定食屋があるかぎり』「台所が教えてくれたこと』など30冊余。「東京の台所」(朝日新聞デジタルマガジン&w)、「ある日、逗子へアジフライを食べに〜おとなのこたび」(幻冬舎PLUS)、「遠回りの読書」(『サンデー毎日』)他連載多数。