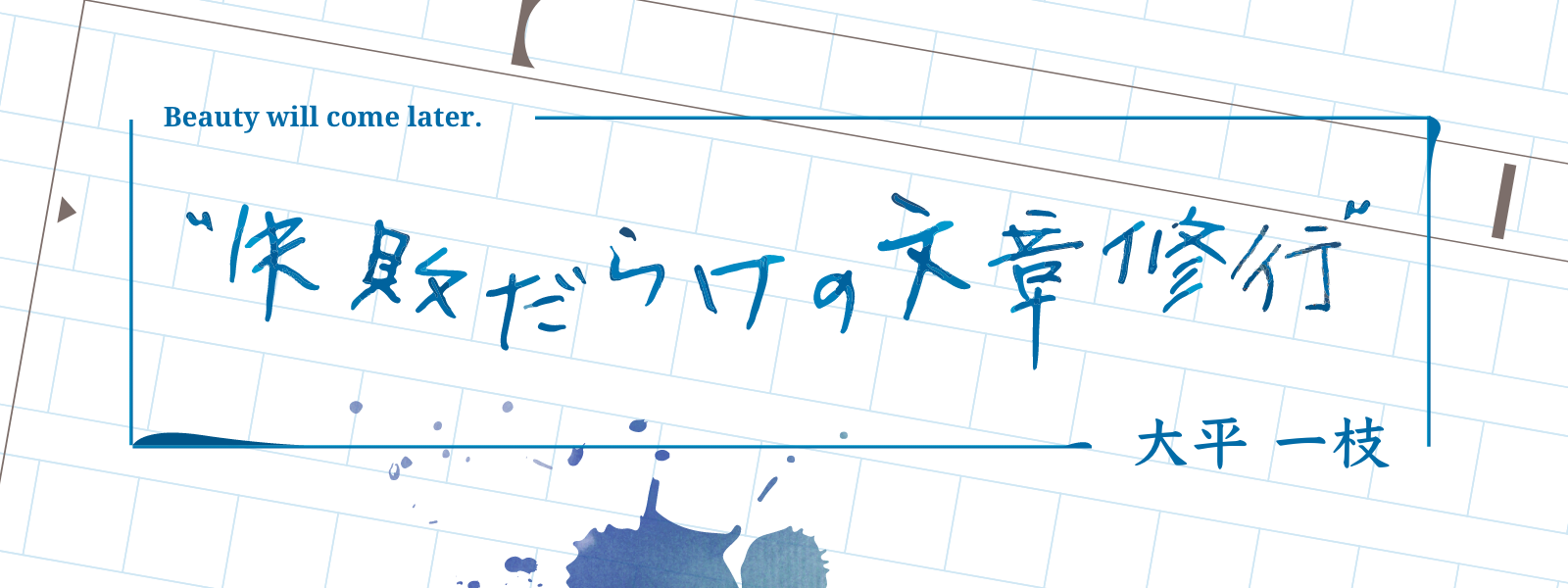文筆生活30年余。失敗からひとつひとつ記事やエッセイの書き方を学んでいった大平さんの七転び八起き。「人柄は穏やか、仕事は鬼」な編集プロダクションのボスの教えから始まる文章修行の日々には、普遍的で誰にも役に立つヒントが満載です。
齟齬(そご)を生まない仕事スタイル
先日、新連載の打ち合わせをした。初めて仕事を組む編集者で、どういうスタイルで進める方なのかは存じ上げていない。
この仕事はそういうことの連続なので慣れているが、連載は長い付き合いになるため、キックオフのときは少々緊張する。万一進め方や相性が合わなかったら、作品の仕上がりを左右することにもなりかねない。今のところ、そういう経験はないけれど人対人の仕事、慢心や奢りは禁物だ。
ひと通り打ち合わせをした最後に、その女性が手帳を開き、あらためて言った。
「最後に、これだけはやめてほしい、これだけはこうしてほしいという要望はありますか」
そういう質問をされたのは初めてなので、とまどった。
「ええっとそれは、たとえばどういう」
「私もまだまだ気づかないことがあるので、仕事をするうえで大平さんが編集者にこれだけはやめてほしいとか、逆にやってほしいとか、お考えがありましたら先にお聞きしておきたいのです」
私より二〇ほど下の人だった。身を乗り出し、メモをとる体制で私の回答を待っている。
「ああ、それだったらひとつだけ……。原稿がついたら、内容の確認はあとでいいので、とりあえず安着の旨だけメールで教えてもらえますか?」
1分でも早くメールを確認してほしいということではない。ご自分が見たタイミングでいいので、ひとこと「届きました」だけもらえると大きく安心できる。その瞬間が本当の意味で「仕事納品完了」の合図になる。
最近、多くのメールサービスでセキュリティチェックが強化されており、迷惑メールフォルダに仕分けられるケースが増えている。締め切り日に送って二日後くらいに「まだ届いていません」と連絡をいただくことが稀にある。先方も、気を使って二日間は我慢して待っていてくれたのだ。
彼女は「なるほど、それは大事ですね。わかりました」とメモしていた。
ほんの二、三分の会話だったが、いろいろと感じ入り印象深く思った。
じつは同世代の仕事仲間と話していて最近よく出る話題が、「原稿を送っても連絡がなくて不安になる」という愚痴である。
昔は、という言葉を使わないようにしたいのだが、どうしてもこの話をするときは出てしまう。昔の編集者は、「とにかく原稿がついたら、“着きました”とひと言を伝えろ」と教えこまれた。自分が発注した原稿を相手が納品してくれている。礼を言うのが礼儀である、と。
私はもちろん御礼を言ってほしいからではなく、メールエラーがゼロではない時代だからこそこの慣習はなくしたくない。
とはいえ、それが教えられない時代になりつつあるのも承知している。
出版不況で、どこの編集部も最小の人数で最大の仕事を一人ひとりがこなしている。どうしても後輩指導まで手が回らないのが現実だ。
そんなときほど、初めてのチームで新しい仕事を組むとき、この質問が有効になる。
教えられていないからわからないこと、慣れないためにわからないとは誰にもある。私にもある。顔ぶれやフィールドが違えば当然だ。
だったら先に聞いてしまえばいい。
こちらも言わずに、陰でネチネチと「あの人は原稿安着の連絡をしない」と愚痴を言うのはフェアじゃない。
聞かれた側は、たったそれだけのやり取りでも大きな安心感と信頼を抱く。なんと合理的で、賢明な方法だろう。すぐ真似しようと心に刻んだ。
言えばわかる。言わなければわからない。それだけのことなのだ。些細な違和感が最後まで解消されないのはもったいない。
どんな仕事にも応用できそうだが、とりわけ文章を介在にした仕事では、編集者と書き手の間には赤字のやり取りがある。修正依頼もあれば、稀に全書き直しもある。相手をひとつでも多く理解したいという気持ちを示す行動は、必ずのちのちいい関係を育む土壌になる。長丁場ほどこの効果は計り知れない。
文章修行から離れてしまい恐縮だが、若い世代から学んだばかりで、私の仕事場修行はまだまだ続く。ますます奢り禁物なのである。
失敗からの教え
文章添削のやり取りは信頼感から。互いに相手に寄り添う姿勢がいい作品を生む
-
第1話結婚式前夜の鬼特訓
-
第2話人は長文が嫌い
-
第3話自慢禁止
-
第4話五感を表す言葉と、固有名詞にコツあり
-
第5話美文は邪魔になる
-
第6話校閲に学ぶ
-
第7話推敲のヒントーー‟書き立て”の熱は勘違いしやすい
-
第8話「偏り」と「独りよがり」
-
第9話きれいや可愛いは、情報ではない
-
第10話宇野千代さんの料理エッセイとツレヅレハナコさんのインスタ
-
第11話事実確認作業は、書き手の生命線
-
第12話仕事の場面での、手紙の効用について
-
第13話「で、結局何言いたいの」と自分に問う
-
第14話なにをどんなふうに読めば、自分の肥やしになるのか
-
第15話齟齬(そご)を生まない仕事スタイル
-
第16話推敲の大前提に据える最も重要なオキテ
作家、エッセイスト。1964年、長野県生まれ。編集プロダクション宮下徳延事務所を経て、1995年、出産を機に独立。『天然生活』『別冊太陽』『チルチンびと』『暮しの手帖』などライターとして雑誌を中心に文筆業をスタート。市井の生活者を描くルポルタージュ、失くしたくないもの・コト・価値観をテーマにした著書を毎年上梓。2003年の、古い暮らしの道具を愛する人々のライフスタイルと価値観を綴った『ジャンク・スタイル』(平凡社)で注目される。
主な著書に『東京の台所』『ジャンク・スタイル』『それでも食べて生きてゆく 東京の台所』、『注文に時間がかかるカフェ』『人生フルーツサンド』『正解のない雑談』『こんなふうに、暮らしと人を書いてきた』『そこに定食屋があるかぎり』「台所が教えてくれたこと』など30冊余。「東京の台所」(朝日新聞デジタルマガジン&w)、「ある日、逗子へアジフライを食べに〜おとなのこたび」(幻冬舎PLUS)、「遠回りの読書」(『サンデー毎日』)他連載多数。