「キラキラじゃないニューヨークが読みたい」
そう言ってくださった大和書房編集部の藤沢さん。それなら私も嘘をつかなくていいやと胸をなでおろし、連載を始めることにしました。
ニューヨークに移住するからといって全員がキラキラするわけではない。
でも住んでみたいから住んでみた。
そんな人生があってもいいじゃないかという、根拠は特にない自己肯定の日々を綴りました。
口下手な私の接客術
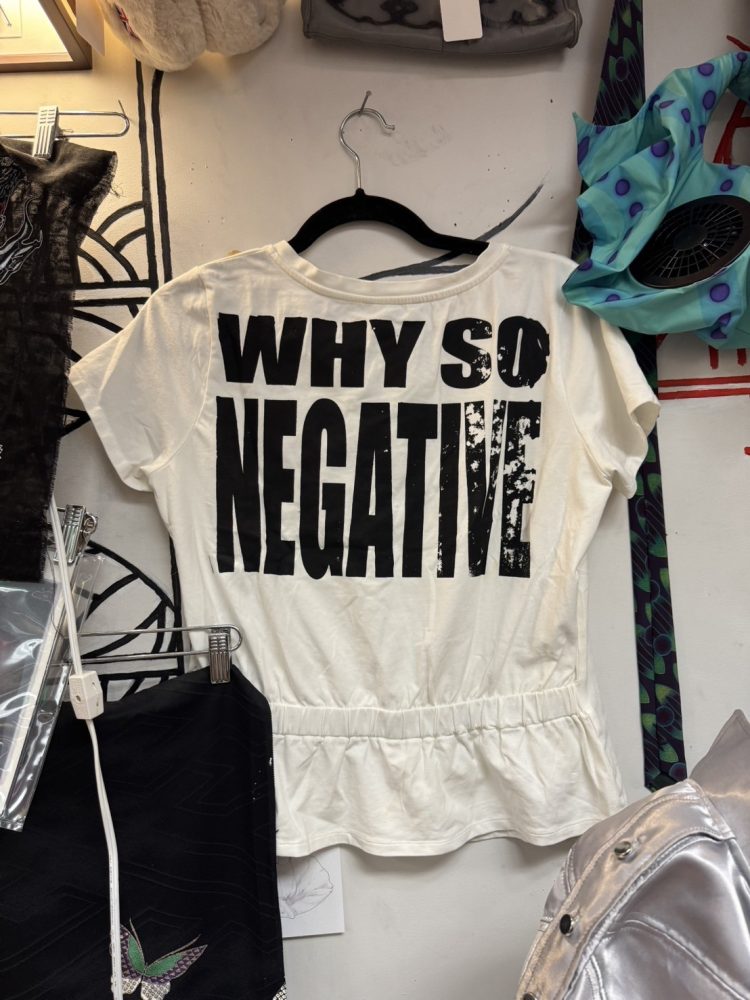
バイト初日、私は緊張していた。16時からなのに、もう午前中からソワソワして昼ご飯もあまり喉を通らない。店はアパレルショップではあるけれど、客と店員の関係が濃密で店主アーロンと話すのを楽しみにやって来るお客さんも多い。つまり大事なのは会話力。会話力。会話力……。もう逃げていっそ出国してしまいたいくらい緊張していた。
私は元々話すのが苦手だったからアナウンサーを志したのだ。アナウンサーになった後に再会した中高の同級生が「みほ、高校時代無口やったやんな!」。この職業に就いたのは意外だったと口を揃える。
子どもの頃から、話している最中に、自分がどの部分を話しているのかわからなくなって会話迷子になることがしょっちゅうあった。そんなときに、相手のつまらなさそうな顔を見るのが怖かった。あ、目から光が消えた、もう飽きてるな、とか、そういうことだけは強烈に察知してしまう性分で、焦れば焦るほど出口を失った。
さらに中高は、私の故郷・神戸出身の生徒だけではなくて、笑いの聖地・大阪から猛者が集まる学校でもあった。「おもろいやつ」が市民権を得る関西において、私はいつのまにか劣等感の鬼に醜変。自分のことが大嫌いで、だから他人にも嫉妬してしまうし、最終的に人までも嫌いになってしまった時期があったのだ。
思春期真っ只中。当時の日記に「生きていくなら人と関わることは避けて通れない。それができないなら消えてしまいたい」と残していたのは穏やかではない。浪人してさらに劣等感を増幅させ、灰色の服ばっかり着て、予備校ではトイレの個室でサンドイッチを食べていた当時の私。やっと変わることができたのは、荒療治に成功したからだと思う。
アナウンサーになって、いっそ話すことを仕事にしてしまって、べったり付き合っていこうと思ったのだ。本当は怖くて逃げたいけれど、仕事だと思うと逃げられない。そんな状況下なら、自分を変えられるかもしれないと思った。まるで歯列矯正みたいだった。なりたい自分の型をまず決めて、そこに無理やり自分を嵌めて、体に覚えさせる。不思議なことに、落ち込むことや気分がのらないときでも、仕事に行って口角を上げてしまえば、脳が楽しいんだと勘違いをしてくれることに気がついた。仕事から帰ると気持ちが晴れているのだ。
ちなみにそんな暗いやつがアナウンサー試験に合格するのかと思われるかもしれないが、人の顔色に一応気づくタイプでもあったので、そこは向いていたのかもしれない。
性格の矯正、荒療治を繰り返して15年、最終的には、そもそも落ち込んでいることさえも自分の勘違いかもしれないなんて考えるようになった。もちろん、根っからの社交人間ではないから、人間関係で心が疲れることも多々ある。かといって自分を卑下しないようにはなった。自分を好きになるための努力だけはちゃんとしてきた気がするから、もう自分を許している。最終的に、インスタで、アメリカ人にDMを送りつけて就労するくらいの社交性を身につけ、家族からは、ちょっとは落ちこめよと言われるまでに成長を遂げた。
でも、もちろん初めての場所はいつもホラーだ。初対面の人とは日本語でもドギマギしてしまう。ましてや英語で接客。2年も住んで、まだ語学で悩むの?と思われるかもしれないが、ネイティブの若者日常会話はまったくの別物なのだ。早いし音が繋がってるしスラングだし、英語のニュースがどれほど聞き取りやすいか。
ええぃ聴覚でダメだなら視覚でぶちかまそう。アパレル店員が何を着て店頭に立つかは店の印象を左右する。そこで選んだ仕事着が、母のお古の白い革ジャン。なぜ母が白い革ジャンを着ていたのかは、家族の中でもまだ誰も恐ろしくて触れられていないが、お古を私が受け継いでニューヨークに持ってきていた。私はシルバーブーツデビューするのに3年かかっているのに、子持ちで白革ジャンを着ていた母・佐知子にはあっぱれである。佐知子ジャンならガツンとかませるだろう。
鎧を身にまとい、いざ出勤。するとチャイナタウンの露店街を抜けたあたりでアーロンから連絡があった。
「15分くらい遅刻する! 1階に中華料理屋があるから、そこで飲み物買ったりして時間潰しておいて、あとで払うから! ごめんね!」
No Worries! こちらでは時間通りに来る人は天然記念物並みにめずらしい。ましてや、遅れて来ることに、もはや誰も罪悪感など持っていない。なのに、謝ってくれる上に飲み物も奢ってくれるなんてなんて奇特な! 人に対する期待値ハードルが下がり切っている私にとっては、神の思し召しくらいありがたい。その後アーロンはしっかり20分遅れてきて、特に奢りについては言い出してはくれず、結局、自腹ラテ6ドルでやや肩透かしを喰らったけども、気持ちだけでもありがたい。なんせ、これで私のバイト初日の緊張が和らいだ。

今日の店員は、アーロンと私だけかと思っていたら、もう1人いるらしい。ただ彼女はいつも3時間遅刻して来るとのこと。3時間!? それ遅刻っていうか半休…。でも、ここでもまた私はラッキーだと思った。だって、遅刻してくる人がいるなら、時間通りに来るだけで、私の信頼度も上がるし強みになる。こんなふうに細やかな安心を拾い集めていなければ、弱気な私が顔を出してくる。
するとアーロンが言った。
「ただその子、遅刻はするんだけど、コミュニケーション力があって、売るのが上手いんだよね」
グサッ。心臓に何かが突き刺さった音が聞こえた。
今、一番聞きたくないことを言われてしまった。コミュニケーション力が彼女の武器。
今の私に一番ないもの。
さてどうしよう。
自分がなりたい店員像を想像してみる。私は、買い物をするとき店員に話しかけられるのが好きではない。マイペースに買い物をしたいタイプ。私と同じようなお客さんも中にはいるんじゃないか。そうなればいいんじゃない?
実際、知らない人同士のおしゃべりがめちゃくちゃ盛り上がるニューヨークにおいて、店員に話しかけられたくない客なんてほぼ皆無に違いない。でも、そうでもして自分を励ましていないと、焦りが顔に出てしまいそうだった。焦りを顔に出すのは禁物だ。初対面の人に会うとき、日本人はもちろん礼儀正しいけれど、負けず劣らず、アメリカも第一印象がBe Niceであることがとても重要だというのはこの2年の生活で心得ている。Stay Positive & Be nice と心で呪文のように唱えた。
ということで、私はあえて、あえて、お客さんとあまり話さない孤高な店員風を決めこむ。そして、アーロンから頼まれた、値段タグ付けや、ラックの整理に精を出した。口角を斜め上に固定して、テキパキと。でもその作業も終わってしまうと、途端に存在感が薄くなる。
こいつ使えないなと思われて、クビになってしまうのではないか……。不安に駆られ始めた。私はこの店が好きなのだ。ドルも好きだ。だから働いていたい。どうにか、お客さんと自然にコミュニケーションをとるきっかけはないものか。
ラックの陰からお客さんを観察する。口角を上げながらジーッと。すると片手にコーヒーを持っているお客さんが多いのだ。そして、服を見ながら飲み干している。で、飲み終わったカップを持て余しているぞ? おおっと試着のときに邪魔そうだ! はいはいはいはい! 待ってました! 私の出番です!
「If you don’t mind, can I throw it away ? もし必要ないなら、カップ捨てましょうか?」
するとお客さんは、満面の笑みでありがとう! と言って私にゴミを預けてご機嫌な様子で買い物を続ける。よっしゃこれだ! 店員感出てる! それからはゴミをひたすら狙うようになった。めざとく客のゴミを見つけては、
「飲み終わってるなら捨てましょうか?」
「買ったストッキングの包装をその場で剥いだから捨てましょうか?」
「他の店で買った物をバッグにまとめて入れましたよね、その袋が邪魔になったなら捨てましょうか?」
ひひひひひーーーーーー!!!!
泣く子も黙るゴミ捨て妖怪。あなたの街にも出るかもしれない。
よしこの調子だ。存在感を発揮できているぞ。またラックの影からお客さんを観察する。口角を上げながらジーッと。

すると、試着を待っているお客さんがなんと多いこと。店内はいつも混み合っているのに、試着室が1つしかない。そういえば、私も客として初めてきたときに、試着をしたくて永遠待っていたのを思い出した。日本みたいに、順番待ちで番号札を渡す文化なんて、アメリカでは一生お目にかかれないだろう。
そのとき、ある若い女性のお客さんは、試着を待ちきれなくて、試着室じゃない場所で下着になって着替えていた。下着がセクシーな黒レースで、たまたま目にしてしまった私はドギマギしたのだが、そこに居合わせた男性客も含めた誰も気に留めるそぶりもない。
いや視界の端では捉えていたかもしれないけれど、スルーを決めこんでいたのだろう。この場での正解は2つしかない。そのセクシーさをリスペクトを込めながら、粘度&湿度0%で(ここが重要)スマートに褒めるか、もしくは風景の一部のようにやりすごすか。これがマナーとされる。前者は難易度が高いから、たいていやりすごす。どちらにしても、ファッションの肌の露出度がいかに高くとも、いやらしい目で見るほうが悪なのだ。
実は私も試着を待てなかったので、試着室の外でささっと早着替えをした。私の場合は、なんだか、小学校のときのプールの着替えを思い出した。
というわけで、今度は試着室案内妖怪になった。
片手に試着希望と思われる服を複数枚持っている客をめざとく見つけては、声をかけ続ける。
「If you wanna try them, can I keep them inside of the cashier. I will let you know when fitting will be available.
もし試着されるなら、その服キャッシャーの中で預かっておきましょうか? 試着室が空いたらお知らせしますね」
これも効果があった。試着を待ってやきもきしていた客が、瞳をキラキラさせながらお礼を言ってくれる。しかも、試着室に案内するとき、預かっていた服を私が持ち「please follow me」などと言っていると、抜群に店員感が出た。
さらに靴を試着しようとしていた男性客がいたので、座って試着したいかなと思い小さな椅子をすかさず持って行ったら、彼は「Thank you my love」と言って、名前を聞いてくれた。名前を聞かれるのは信頼の証。嬉しかった。彼の名はドミニク。職業スタイリスト。引き締まった体と、切り揃えられた襟足に高い美意識を感じる。試着したら「Miho what do you think?」と意見も聞いてくれて、私が褒めるとその服もまとめて全部で3点計185ドルも買ってくれた。
「ここは最高よ。ニューヨークでもこんな店あまりないわ。他人とファッションが被りたくないと思ってる人には最高の店なのよ」
それそれ! この店の品揃えは、イマジネーションを刺激する何かがある。いや、解き放っているのかもしれない。

自由なセレクトももちろんだけど、この店を愛してやまないもう1つの理由は、アーティストが作った服を売っているところ。店が放つ得体の知れないオーラの源泉はここにもあると思う。デザイナーを志す若者の夢や、自分を表現しないと生きていけない人間のエネルギーが溢れんばかりに詰まっているのだ。アーティストにとっても、作品が評価されて、お金に変わる場所を提供してくれるアーロンは、とてもありがたい存在だと思う。
店主アーロンは、2年前にこの店を始めた。前職はなんと保険勧誘のオペレーターをしていたらしい。てっきりずっとファッション業界にいたのかと思っていたから驚いた。彼の妻がすでにアパレルショップを持っていて、その店の隣のテナントが空いたから一念発起して店を出した。
思い切った転身に「怖くなかった?」と聞くと、
「特に怖くないかな。やってみて、修正していけばいいし」
そうなのだ。アメリカでは起業が日本より身近なものに感じる。まず立ち上げてみて、その都度状況に応じて形を変えていけばいい。生存戦略によって色彩を変えるカメレオンスタイル。
私は起業の先輩にアドバイスを求めた。来春、夫が共同経営者としてニューヨークにアウトドア用品店を出す。
「何かアドバイスあるかな? だってこの店いつも繁盛しているし。人いっぱい来るじゃん」

「最近はね。でもオープンしたてはそんなことなかったんだよ。インスタで変わったかも。お客さんが試着したり、買ってくれたりしたときに、服と一緒に写真撮ってダグ付けしてインスタに挙げるの。そうすると、友達がそれを見て、また友達が友達を呼んで、お客さんがすごく増えた」
とても親切に教えてくれた。なるほど友達の輪で広まっていたのか。確かに、客としてこの店を二度目に訪れたとき、いきなり私の名前をアーロンが呼んだのには驚いた。一度しか来店していない客の名前を覚えているなんて。今私も見倣って、客の名前はメモをしている。
アーロンは最後に「でもこれはアパレルの話だから。Mihoの場合はスポーツギアを売る店でしょ? 当てはまるかはわからない」と付け加えた。確かに人からの紹介はあくまでも入り口であって、その後はやはり商品のプレゼン力がものを言うのだろう。他の客はアーロンのことを「とてもknowledgeable(博識)。だから話していて楽しい」と言っていた。やはり、何かを売るなら、その商品について学ぶことが最優先だ。
ラックの商品を見て回る。その中に、ツィード生地のプリーツスカートがあった。ちょうど冬になりツィード素材が気になっていたのだ。するとバイト仲間のジョーダンが駆け寄ってきて「それ私が作ったの!」声を弾ませた。
ジョーダンはデザイナーズ学校をまもなく卒業して、デザイナーになるべく就職する予定らしい。就職先が決まるまでここで働くとのこと。彼女はとても勤勉で、バイトに遅れて来るのを見たことがないし、いつもお客さんと気持ちの良い距離感で接客している。私は彼女が好きだったし、彼女が作ったスカートはとても気に入った。ツィードというクラシックな生地なのに、デザインはハイウエストで、素材もラメが入っていて遊び心がある。ジョーダンは「安くするよ」とちゃめっ気たっぷりに言う。母性を持て余している私は、もちろん買ってしまった。これでバイト代の半分が消えた。とほほ。アーロンに後でシフト増やしてもらおうなどと考えていると彼女は言った。
「アーロン! Mihoは私のお客様第1号だよ!」
私はやっぱり、いい買い物をしたなと思った。
ただのものなら世界に溢れている。お金を払ってよかったとお客さんに思ってもらえる物語や付加価値を提供できるかどうか。そして、それがニューヨークに住む人に受け入れられるかどうか。こちらで店を開くなんて、チャレンジングな展開だけど、こんなときこそこの言葉。
It’s worth it. やる価値があると信じて。
それではよいお年を……

-
第1回眠らないニューヨークと眠れない私
-
第2回私が外出する理由
-
第3回英語が話せない
-
第4回SheやHeではなく、Theyを
-
第5回宝物に救われる
-
第6回わけありの女
-
第7回できないことがたくさんあってよかった
-
第8回アメリカ大統領選、あまりに濃厚な1日のこと
-
第9回そんなわけでマッチングアプリ
-
第10回こんなに違うアメリカと日本の働き方
-
第11回ニューヨークのアパートメント事情
-
第12回実録! 愛と情熱の「家探し」
-
第13回「ニューヨークの奇跡、25’夏」
-
第14回入国審査で、愛を問われる
-
第15回そして今、古着屋の店員をしています
-
第16回口下手な私の接客術
-
第17回この街に来て、今話したいこと
1978年兵庫県生まれ。
2002年テレビ東京入社。スポーツ、バラエティー、情報番組を中心に多くのレギュラー番組で活躍する。
2013年1月脳梗塞を発症し、休職。療養期間を経て同年9月に復帰する。
2017年12月テレビ東京退社しフリーアナウンサーとして活動を始める。
2023年アメリカ・ニューヨークに住まいを移し日米を行き来しながらテレビやイベントなどを中心に活動する。


