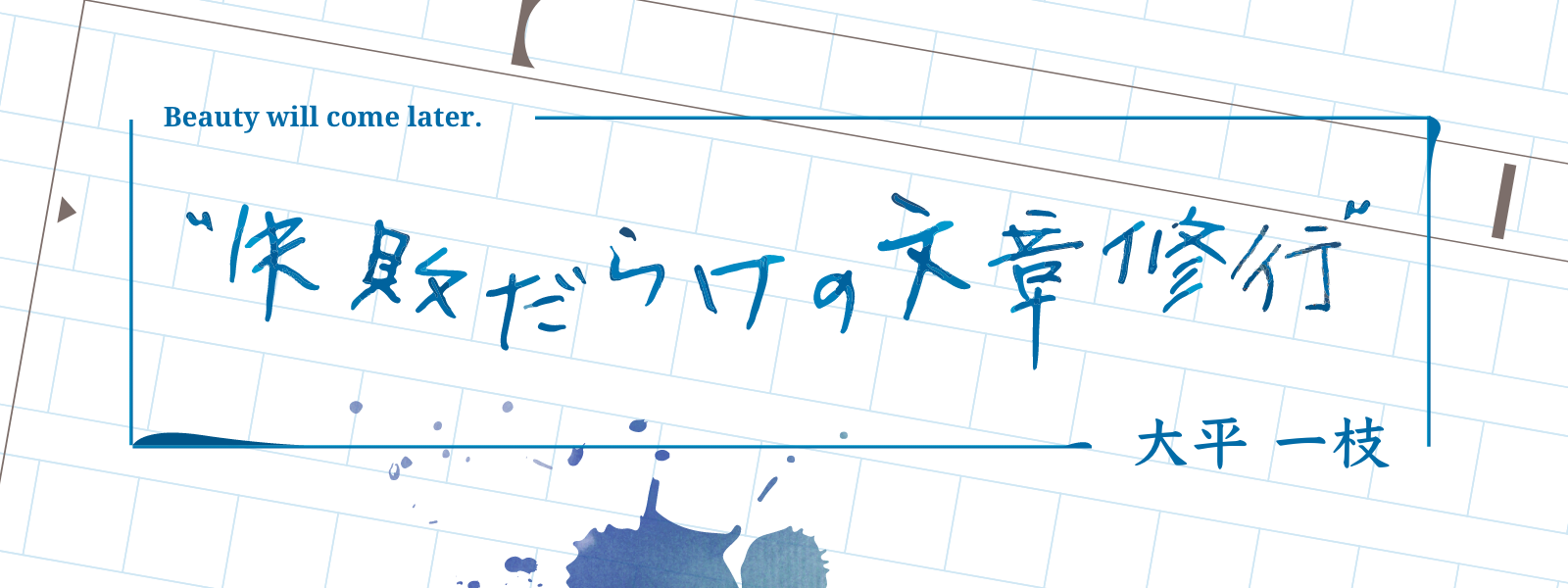文筆生活30年余。失敗からひとつひとつ記事やエッセイの書き方を学んでいった大平さんの七転び八起き。「人柄は穏やか、仕事は鬼」な編集プロダクションのボスの教えから始まる文章修行の日々には、普遍的で誰にも役に立つヒントが満載です。
推敲の大前提に据える最も重要なオキテ
どうにもだらしない話だが、私は誤字が大変に多い。メールやSNSはとくにひどい。友人や家族は、たぶんこういうことだろうと予測して読んでくれている。とりわけ編集者には心底すまなく思っている。
デスクトップ型パソコンの端に「誤字禁止」「送信前に読み返す」と書いた付箋を貼り付けているが、小学校の壁に貼りっぱなしにされた書き初めの「努力」「根性」くらい景色に溶け込んでしまっている。急いで返信する癖はなかなか直らない。
今回は文章の推敲について綴りたい。しかし上記のような誤字ではなく、内容や整合性、言い回しに関わる推敲法である。誤字は、「丁寧に見直す」しかなく、それさえできていない私には言う資格がない。
原稿を書いたら一度寝かせる、たとえばひと晩冷蔵庫に寝かせるようなつもりで時間を置くというのは以前も記した。それができないときは、音読だけでも文章の通りの悪いところをチェックをできて有効だ、とも。
最近、音読の効果をあらためて実感したことがある。
映画製作業の家人が、チラシの文章に四苦八苦していた。ふだんは互いの仕事にノータッチだが、今回は自主制作で予算がない。外部ライターも雇えず、何もかも自分で担っている。いよいよ苦しくなったようで、草稿を「頼むからチェックだけしてくれ」と懇願された。
渋々読み始めて、後悔した。とんでもなくひどかった。
私は数行直したところで赤ペンを放り出した。
「これは徹夜しても無理なレベル。忙しいのでもっと推敲してから再提出して」
思い切り上からの嫌味炸裂でもしかたないほどのクオリティだった。
夫は珍しく下手(したで)に出て、「どこがどう悪いのかだけでも教えてくれよ」と言う。
「あんた、読み返してないでしょ」
「……うん」
「書いたら書きっぱのまま、私に渡したでしょ。そんなの一読でビシバシにわかるんだよ。失礼です」
「わかった。わかったから、ちょっとだけでもヒントをくれ。自分じゃ気づかないんだよ。マス埋めたら、これはこれでいいんじゃないかって思えちゃって」
私はどうにか荒い息を抑えつつ命じた。
「だったら今、ここで声に出して読んでみ」
彼は音読を始めた。
1行目でつっかかり「あ、」と言った。
2段落も3段落も、書き出しが西暦で始まり、歴史の教科書を読まされているようなつまらなさが初めてわかったのだろう。西暦のところで止まるようになった。
<世界でプロレタリア文学運動の弾圧が始まった1920年代という状況において、日本でもその影響とは関係なく運動が始まっていったことは、当時の特徴として注目される>で、とうとう吹き出した。
自分でもいかにひどいのか、腑に落ちたのだ。
「ね、音読するだけでもわかるでしょ。修飾関係がずれてたり、主語と述語が噛み合ってなかったり、そもそも長すぎて読みづらいってのが、一読だけで」
駆け出しの頃、夫と同じことを私は編集プロダクション(以下編プロ)という現場で、給料をもらいながらしていたわけで、あのとき、よくボスは今の私のように怒りのリミッターが外れなかったものだと、今さらながら頭が下がる。
夫はそれから書き直し、やっと添削できるレベルになった。
もちろん赤字だらけであった。
誰もあなたの文章など読まない
音読は、発声という行為を通すことで、原稿と自分との間に客観的な距離ができる。黙読は、自分で書いたものだけに無意識に飛ばして読んでいたり、“わかった気”になって読み進めたりする確率が高い。つまり、後者にはない作用を推敲に利用した方法のひとつだが、そもそもなにを前提に、どんなものさしを基に読み直せばいいのか。
その答が、『君のクイズ』(朝日新聞出版)など数々のベストセラーで知られる小説家、小川哲さんの近刊にあった。
『言語化するための小説思考』(講談社)で、小説解体新書ともいえるような斬新な内容の書籍だ。小説の書き方、表現のあり方を切り口にしているが、創作術ではない。
そのなかに、小説家に必要とされる“想像力”とは、「物語を創作するためもの」以上に、「顔の見えない読者を想定」する能力のほうが欠かせないかもしれないという内容が記されていた。
これは、対価をいただいて読んでもらうノンフィクションやエッセイにも通じる。
昔、編プロのボスに「誰もあなたの文章など読まないと思って、書きなさい」と言われた。(第3話『自慢禁止』)
だからこそわかりやすく、伝わりやすく書かなければならない。書き手のエゴや主張したいこと、こんなことも知っているんだぞという自慢、主旨に関係ないがどうしても使いたい気持ちの良い表現も不要だ。
ひたすら、わかりやすく伝えるにはどうしたらいいか工夫を重ね、読み手の立場で想像力を目いっぱいはたらかせて、点検をする。
読み手の気持ちや理解力を想像しながら読み直すことが、推敲作業で最も重要なオキテなのだと、小川さんの書で再確認できた。
ボスの教え
誰もあなたの文章など読まないと思って、書きなさい
-
第1話結婚式前夜の鬼特訓
-
第2話人は長文が嫌い
-
第3話自慢禁止
-
第4話五感を表す言葉と、固有名詞にコツあり
-
第5話美文は邪魔になる
-
第6話校閲に学ぶ
-
第7話推敲のヒントーー‟書き立て”の熱は勘違いしやすい
-
第8話「偏り」と「独りよがり」
-
第9話きれいや可愛いは、情報ではない
-
第10話宇野千代さんの料理エッセイとツレヅレハナコさんのインスタ
-
第11話事実確認作業は、書き手の生命線
-
第12話仕事の場面での、手紙の効用について
-
第13話「で、結局何言いたいの」と自分に問う
-
第14話なにをどんなふうに読めば、自分の肥やしになるのか
-
第15話齟齬(そご)を生まない仕事スタイル
-
第16話推敲の大前提に据える最も重要なオキテ
-
第17話文章が散漫になりがちなときの道標(みちしるべ)
-
第18話忘れられないあの本棚
作家、エッセイスト。1964年、長野県生まれ。編集プロダクション宮下徳延事務所を経て、1995年、出産を機に独立。『天然生活』『別冊太陽』『チルチンびと』『暮しの手帖』などライターとして雑誌を中心に文筆業をスタート。市井の生活者を描くルポルタージュ、失くしたくないもの・コト・価値観をテーマにした著書を毎年上梓。2003年の、古い暮らしの道具を愛する人々のライフスタイルと価値観を綴った『ジャンク・スタイル』(平凡社)で注目される。
主な著書に『東京の台所』『ジャンク・スタイル』『それでも食べて生きてゆく 東京の台所』、『注文に時間がかかるカフェ』『人生フルーツサンド』『正解のない雑談』『こんなふうに、暮らしと人を書いてきた』『そこに定食屋があるかぎり』「台所が教えてくれたこと』など30冊余。「東京の台所」(朝日新聞デジタルマガジン&w)、「ある日、逗子へアジフライを食べに〜おとなのこたび」(幻冬舎PLUS)、「遠回りの読書」(『サンデー毎日』)他連載多数。