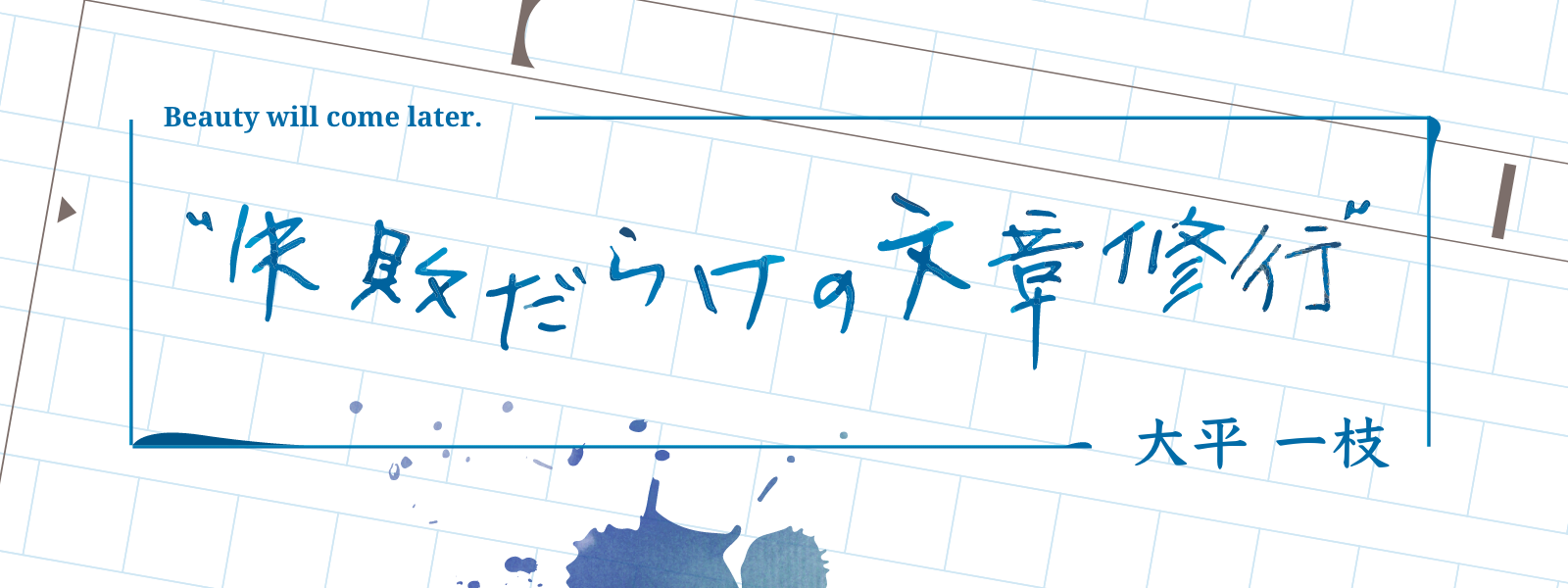文筆生活30年余。失敗からひとつひとつ記事やエッセイの書き方を学んでいった大平さんの七転び八起き。「人柄は穏やか、仕事は鬼」な編集プロダクションのボスの教えから始まる文章修行の日々には、普遍的で誰にも役に立つヒントが満載です。
忘れられないあの本棚
荻窪駅から10分ほど歩いたところに、児童文学作家の石井桃子さんの自宅がある。2008年の逝去後は、東京こども図書館分室・石井桃子記念かつら文庫として運営。図書室の閲覧は無料、貸し出しは年間1000円の登録料で、利用できる。
『くまのプーさん』『ピーターラビットのおはなし』『うさこちゃん』シリーズの翻訳、『ノンちゃん雲に乗る』などの著作で知られる石井さんは、自宅の一部を開放し、1958年からかつら文庫という私設図書室を開いていた。
子どもに良質な読書体験を、という子ども文庫運動のさきがけもある。
20年ほど前であろうか。すいぶん昔、雑誌の取材でかつら文庫を訪ねた。そのときのある光景を、私は忘れられずにいる。
広報の方に案内されて、石井さんの書斎を見た。
どっしりとした木製の机の背後の壁に、大きな本棚がある。たしかその棚だったと思うが、石井さんの作品が出版年別に整然と並んでいた。
お話を聞きながら、私はその棚の中の本が気になってたまらなくなった。
なぜなら、同じタイトルの本──どの作品だったかは覚えていない。赤い表紙だった──がずらりと並び、そのすべてに、おびただしい数の付箋が貼ってあったからだ。
なぜ資料でもない著書、しかも同じ作品にあんなにたくさん付箋が貼ってあるのだろう。インタビューをしながらそわそわしだし、せっかちな私はとうとう、取材がひとごこちついた隙をねらって、スタッフさんに願い出た。
「貴重なものだと思うのですが、一冊だけ見せていただけませんでしょうか」
快く、特別に一冊だけ見せてくださった。
やはり同じ作品である。20冊以上あった気がする。巻末をめくると、重版の回数が90番台だった。98刷だったか99刷だったか。
「この付箋は石井さんが貼られたんですよね」
「そうです」
「なぜ何冊も同じ作品に?」
「重版がかかるごとに読み直し、句読点の位置や言葉のひとつひとつを検討。校正を加えていたようです。時代によって呼称が変わるものもありますし、これでいいと満足することなく、文章の流れも確認されていたのでしょう」
私は呆然とした。
99刷なのに? 世界中で翻訳されている児童文学作家が、重版のかかるたびに、この表現が本当に適切であるか一行ずつ、推敲を?
頭をガツンと殴られたような気さえした。付箋の数だけ、石井桃子さんの作家としての圧倒的な矜持が伝わる。
奢らず、現状に甘えず、謙虚に、緻密に、誠実に。創作に対する妥協のなさに打たれた。
当時、私は著書が三、四冊で、一冊だけ重版がかかったことがあった。しかし、さあっと目を通す程度だ。初版のとき一生懸命推敲したんだし、これでいいでしょうと。
おそらく石井桃子さんは、重版云々は関係ない。言葉に対し、それだけの責任感と厳しさを持って向き合っておられたのだろう。
情熱などという言葉は、どこか薄っぺらくてそぐわない。あのずらりと並んだ本の付箋を見たとき、表現を生業にするとのはこういうことだと強烈に実感した。
どんなにその時はベストと思っても、創作に正解はない。さらに前よりもっとよく、という志の高さにうちのめされた。
書いた文章をある程度推敲すると、よしこれでOK、直すところなしという気持ちになる。だれかにちょっと褒められでもしたら、私などもっと調子に乗って自分に甘くなる。
まっさらな紙、もしくは画面を文字で埋めると、それだけで、書ききったような達成感が生まれる。
だが待て。人に読んでいただく文章にするには、そこからが勝負だ。何度でも推敲して、揉んで叩いて磨いて、髙みを目指せ。
文学の神様の声が聞こえた。付箋だらけの本棚は、それくらい雄弁だった。
重版がかかったときの修正は手間と費用がかかることがあり、出版社あるいは作家ごとに考え方が違う。
付箋が日本で普及したのは八〇年代初頭の模様。きっと石井桃子さんは、付箋がない時代は別の方法で同じように校正を重ねてきただろうし、肩書や売れる売れないにかかわらず、自分の言葉に対して厳しく、また書き手としての矜持を自分できっちり守ってきたのは間違いない。
推敲の姿勢について大切なことを教えてくれた本棚は、予約制で見学できる。ぜひ足を運んでいただきたい。私もあの作品が何だったか確認に行こう。
失敗からの教え
推敲にゴールはない。妥協なき追究を。
-
第1話結婚式前夜の鬼特訓
-
第2話人は長文が嫌い
-
第3話自慢禁止
-
第4話五感を表す言葉と、固有名詞にコツあり
-
第5話美文は邪魔になる
-
第6話校閲に学ぶ
-
第7話推敲のヒントーー‟書き立て”の熱は勘違いしやすい
-
第8話「偏り」と「独りよがり」
-
第9話きれいや可愛いは、情報ではない
-
第10話宇野千代さんの料理エッセイとツレヅレハナコさんのインスタ
-
第11話事実確認作業は、書き手の生命線
-
第12話仕事の場面での、手紙の効用について
-
第13話「で、結局何言いたいの」と自分に問う
-
第14話なにをどんなふうに読めば、自分の肥やしになるのか
-
第15話齟齬(そご)を生まない仕事スタイル
-
第16話推敲の大前提に据える最も重要なオキテ
-
第17話文章が散漫になりがちなときの道標(みちしるべ)
-
第18話忘れられないあの本棚
作家、エッセイスト。1964年、長野県生まれ。編集プロダクション宮下徳延事務所を経て、1995年、出産を機に独立。『天然生活』『別冊太陽』『チルチンびと』『暮しの手帖』などライターとして雑誌を中心に文筆業をスタート。市井の生活者を描くルポルタージュ、失くしたくないもの・コト・価値観をテーマにした著書を毎年上梓。2003年の、古い暮らしの道具を愛する人々のライフスタイルと価値観を綴った『ジャンク・スタイル』(平凡社)で注目される。
主な著書に『東京の台所』『ジャンク・スタイル』『それでも食べて生きてゆく 東京の台所』、『注文に時間がかかるカフェ』『人生フルーツサンド』『正解のない雑談』『こんなふうに、暮らしと人を書いてきた』『そこに定食屋があるかぎり』「台所が教えてくれたこと』など30冊余。「東京の台所」(朝日新聞デジタルマガジン&w)、「ある日、逗子へアジフライを食べに〜おとなのこたび」(幻冬舎PLUS)、「遠回りの読書」(『サンデー毎日』)他連載多数。