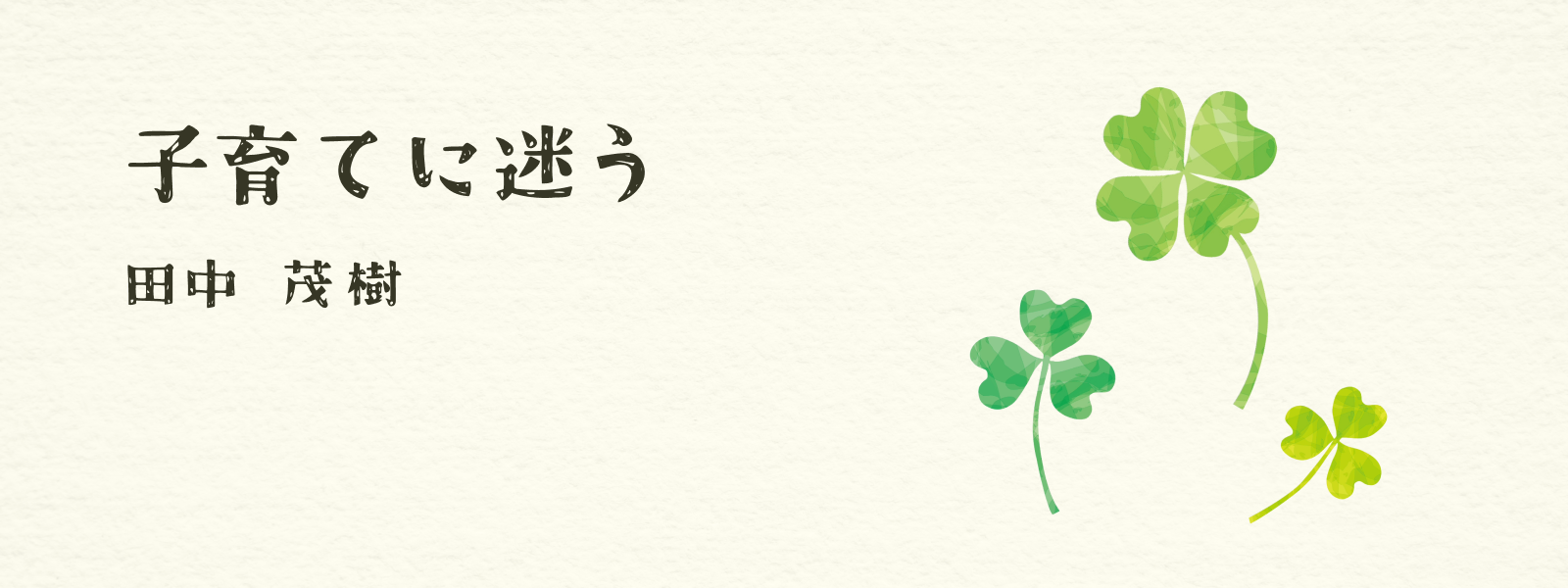自分も子育てでいろいろ悩みながら、子どもの問題について親のカウンセリングを長年続けてきました。また、地域の診療所で外来診察や訪問診療も担当しています。育児の悩みや家庭でのコミュニケーション、そのほか臨床の現場で出会ったこと、考えたことなどを書いてみます。
あんたもたいへんやなぁ
カフェで聞こえてきた会話シリーズです。今回は少し深刻な内容でした。
おそらく70代後半と思われる二人の女性。体格のいい人が話し手で、小柄な人が聞き手。私は近くの席で、いつものように『暮しの手帖』を読んでいましたが、「発達障害」という言葉が聞こえ、それまで聞こえていなかった会話が急に耳に入ってきました。
「発達障害とかなんとか言うてるけど、食べ物を扱ってるんやから、髪はくくらなあかんやろ。でな、そう言ったら、ふわふわしたものをつけてきたけど、そんなんではあかんやん? ワタシがゴム買ったげたいわ、ほんまに……」
「ワタシは20年、調理の仕事をしてきたやんか。食べ物は見た目も大事やねん。きれいに盛り付けてくれたら、食もすすむやんか。でも、適当に盛り付けはんねん。今はさ、ワタシは洗い場の手伝いだけなんよ。体もしんどいしな。でも気になるやん。床に髪の毛も落ちてるし、いつもワタシが片付けてるんよ」
少し離れていても聞こえるほど、勢いのある声です。話し手の人は険しい表情になっています。よほど腹に据えかねることがあるようでした。それに対して聞き手の人は、「あんたも、大変やなぁ……」と、かなりおっとりした口調で返しました。
「主任さんにも言ったんや。ちゃんとさせなあかんよって。『言うときます』とか言って、そのままや。もう一回、この前言ったんよ。そらな、人手も足りないねん。あんな子でも、やめられたら困るんやろ。でも、仕事やねんから。ちゃんとせな。もう言うていくとしたら、所長しかない。所長のところに行くってことは、ワタシがやめるってことやろ。それでは部署も困る。でも、もうええ加減限界やねん。体もしんどいし。引退する年もとっくに過ぎてるんやから」
聞き手の人は、さっきと同じようにおだやかな調子で、「あんた、ようやってんなぁ」とだけ返しました。
僕は聞きながら、話し手の人はもう会社を辞めるのかな、とか、ご高齢でも働かないといけない事情があるのだろうか、とか考えました。相談されたのが自分だったら、何ができるのだろうとすこし苦しくなるほどでした。自分なら何とアドバイスできるだろうかと。
そのとき、「新しいパンが焼けました」というベルが鳴りました。話し手の人は、さっと立ち上がり、小さな焼きたてパンをいくつも皿に盛って戻ってきました。ちらっと見ると、それほど険しい表情ではなくなっていました。
しばらく静かでした。そして、さっきよりおだやかな声が聞こえてきました。
「ああ、でも、アンタに聞いてもらって、ちょっとスッとしたわ。ありがとうな」
という話し手の人の言葉に、聞き手の人は「まあ、無理せんときや」と、やはりおだやかに返しました。
話し手の人は、もともと聞き手の人に「なんとかしてほしい」「助けてほしい」とは言っていません。ただ、言わずにはいられないことを、信頼できる相手に話しただけ。聞き手の人は「あんたも、大変やなぁ」ぐらいしか言っていません。そのおだやかな返し方には、「あなたにはなんとかできるよ」という口には出さないメッセージが含まれていたのだと思います。
彼女たちの話を聞きながら、子どもからこういう感じで話を聞いたことがあったことを、僕は突然思い出していました。いつもはあまり話しかけてこない子でしたが、そのときは険しい表情で話し始めたのでした。
「あのさぁ。新しい部活の顧問が、ほんま鬱陶しいねん。『声出せ、声出せ』って。一人さぁ、声を出すのが苦手なやつがいるねん。わざとじゃなくて、ほんまに大きな声が出せへんねん。でも、その顧問はな、いやがらせみたいにそいつをいびるねん。全員を、校庭の端に立たせて、『お疲れさまでした!』って叫ばせる。顧問の許可が出たら、帰っていい。みんな叫んで帰っていくやろ。そいつだけが残される。がんばって声を出すけど、そんなに出ないねん。反抗してるんじゃない。本当に出ないねん。それなのに、顧問は『聞こえんなぁ』とか言っていじめてるんや。俺らが待ってたら、『お前らは早く帰れ!』って、こっちにも怒る。アイツ、もう部活やめるかもしれん」
改めて書いてみると、ひどい話です。今なら虐待としてニュースになるレベルかもしれません。あのとき、子どもやその友人をどう守ったらいいのか。自分に何ができるのか。そういうことを考えながら、必死で子どもの話を聞いていたはずです。こうして思い出して書いていても、怒りでドキドキするほどです。そのときだって、心をかき乱されて聞いていたでしょう。
それでも、聞き手の女性のように、「キミらも、結構大変やなぁ」と、まずはちゃんと受け止められたのだったか。そうやって「キミたちなら乗り越えられるよ」というメッセージを、言葉にせずにしっかりと伝えられたか。できなかったでしょう。どう返したか覚えていません。でも、もしも今度そういうことがあったなら、今朝の聞き手の女性のように、相手の話を聞いて、そして言葉を返してみたい。
-
第1回小言を言わないということ
-
第2回鼻血の教訓
-
第3回誰が息子に現実を教えてくれるのですか
-
第4回子どもを本当に励ます言葉
-
第5回今のままではダメなんですか?
-
第6回乾燥機は使わないで
-
第7回ある幸福な一日
-
第8回吹雪の中を
-
第9回この子はどんな形の木になるのだろう
-
第10回鼻クソを拭かせてください
-
第11回徳島で一番の蕎麦
-
第12回迷ったり悩んだりするあなたを信じます
-
第13回なぜ子どもが話をしてくれないのか
-
第14回孫もワンオペ
-
第15回誰の気持ちが中心になっていますか?
-
第16回これだってすごくジェンダーな状況だよ!
-
第17回お父さん!お母さん!キャンプに行きませんか?
-
第18回規則正しい生活
-
第19回子どもの成長を尊いと感じること
-
第20回とうちゃんのようになりたいと思います
-
第21回娘が家にお金を入れない
-
第22回お父さんをどうしたらいいでしょう?
-
第23回結果ばかりにこだわる子ども
-
第24回山空海温泉のこと
-
第25回子どもの機嫌をとることへの罪悪感
-
第26回ごはん一杯おかわりするならゲーム15分
-
第27回理由も聞かずに味方になる
-
第28回いわゆるゼロ日婚約の知らせ
-
第29回子どもを叱るとき暴力はダメ
-
第30回「豚の珍味出てる」というLINE
-
第31回ゼッケンは毎年、つけ替えること
-
第32回反抗期を長引かせる方法
-
第33回この不幸を手放したくない?
-
第34回あえて甘えさせるという育児のぜいたく
-
第35回お話はうけたまわっておきます、という姿勢
-
第36回Eテレ出演と満里奈さんとの対談
-
第37回カビテ州立大学獣医学部
-
第38回あけましておはよう
-
第39回ちょっと待って! 寅さん!
-
第40回ツメハラと世間話ハラ
-
第41回おなかがすいた
-
第42回親への感謝
-
第43回去っていく後ろ姿の強さ
-
第44回あんたもたいへんやなぁ
-
第45回人に頼ることと、断られること
-
第46回子どもを見守ること
-
第47回スライダープールとスパイダーマン
-
第48回母さんも、いつもありがとうな
-
第49回人材という概念のない国
1965年東京都生まれ。医師・臨床心理士。京都大学医学部卒業。文学博士(心理学)。4人の男の子の父親。
現在は、奈良県・佐保川診療所にて、プライマリ・ケア医として地域医療に従事する。20年以上にわたって不登校やひきこもりなどの子どもの問題について、親の相談を受け続けている。
著書に『子どもを信じること』(さいはて社)、『子どもが幸せになることば』(ダイヤモンド社)、『去られるためにそこにいる』(日本評論社)、『子どもの不登校に向きあうとき、おとなが大切にしたいこと』(びーんずネット)がある。