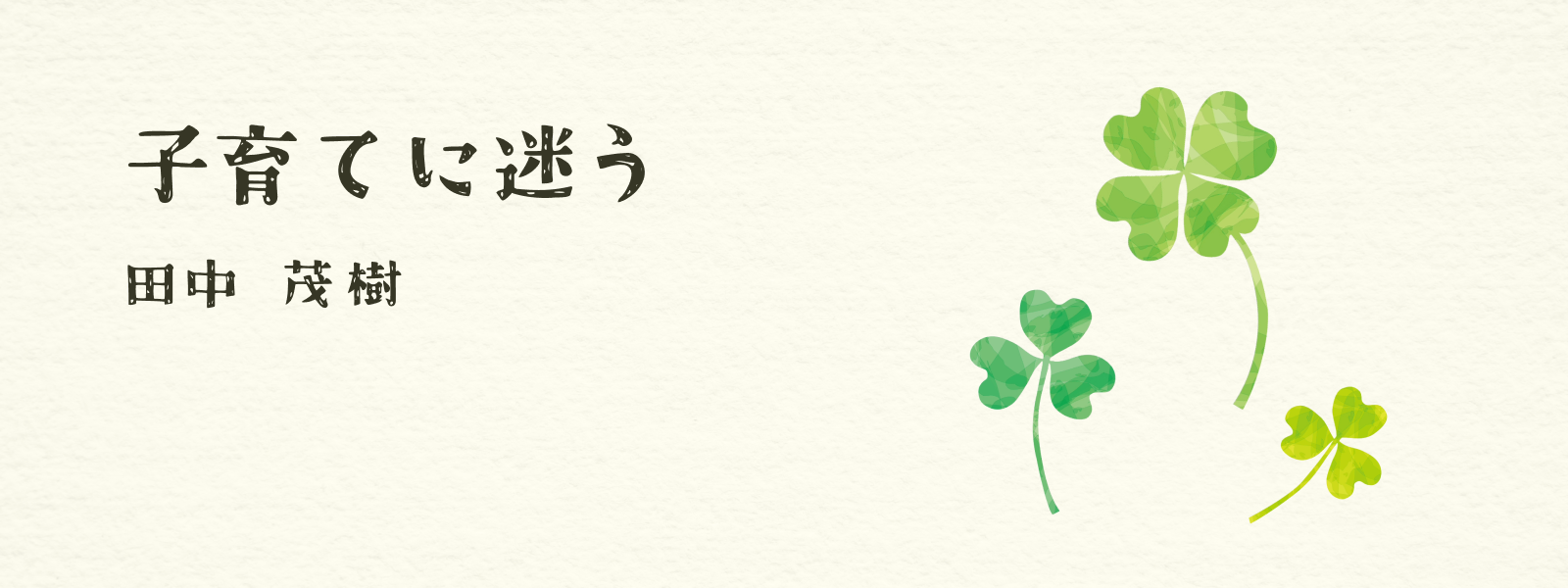自分も子育てでいろいろ悩みながら、子どもの問題について親のカウンセリングを長年続けてきました。また、地域の診療所で外来診察や訪問診療も担当しています。育児の悩みや家庭でのコミュニケーション、そのほか臨床の現場で出会ったこと、考えたことなどを書いてみます。
子どもを見守ること
不登校の親の相談を受けていて、よく出会う言葉「見守る」について書いてみます。ポイントは、子どもを見守ることは、やらねばならないこと、課題や義務ではなくて、子育てを楽しむうえで大切なことだということです。
そばにいて、子どもがケガをしないように、危ない目にあわないように、気をつけておくこと。子どもを見守るという場合には、そのような意味合いも、もちろん含まれているでしょう。でも、そのように好ましくないことから遠ざけておくために、子どもを見張っておく、という意味のほかに、もっと積極的な意味があると私は考えています。
ほかの子と喧嘩しないように、周囲に迷惑をかけないように、そのように「何かをしないように」見張っておく、という意味ばかりにおいて、子どもを「見守る」という言葉を使っている人は多いようです。子どもの安全を確保することは、もちろん大切です。しかし、私がここで書きたいのは、子どもの行動を禁じるのではなく、いろいろな配慮をしながら、スリルや驚き、不安を一緒に感じながらそこにる。そんな「見守る」もありますよ、ということです。
子どもが難しいことに挑戦している。それは大人にとっては、やる価値があるようには思えないことだったりします。それでも、何も言わずに子どもの邪魔をしない。そういう「高度な」見守り方というのがありますね。大人が干渉することを最小限にして、子どもの挑戦や体験を見守る。そうやって近くにいることで、子どもの感じているいろいろな気持ち、興奮や期待、ワクワク感やくやしさなどを、親も一緒に味わうことができます。
子どもを見守っているだけでよいのですか
講演のあとや面接で、「子どもを見守っているだけでいいのですか?」という質問をよく受けます。それは次のような内容です。
「アドバイスしたり、促したりして、子どもが『もっとうまく』できるように、よりよい方向に進めるように、何かこちらから働きかけたほうがいいのではないですか。何もせずに、放っておくのは、親としてすべきことを、放棄しているのではないでしょうか」
このような質問をする人が、「見守っているだけでいいのですか?」と言うとき、本当に聞きたいことは、「見守ってさえいれば、子どもは私が思うようなことをやり始めますか?、(私が)望ましいと思っている方向にちゃんと進んでいくでしょうか?」ということのようです。
そういう親にとっては、口を出さずに見守るということは、「何も構わないで放っておく」とほとんど同じ意味のようです。子どもの近くにはいるけれど、気持ちは寄せていません。子どもが何を考えているのか、どう思っているのか。そういうことへの関心が乏しいのです。その一方で、子どもが何をしているか、していないか、もっと言えば、親の望んでいることをしているか、していないか。そちらにばかり、注意や関心が向いてしまっています。それは「見守る」ではありません。見張る感じでしょうか。
逆に、子どものそばにいなくても、たとえば、子どもを家に残して仕事に行っていても、子どもは今どういうことを思っているかな、と気持ちを寄せることは、「見守っている」というあり方だと僕は思います。心を寄せる。
「見守ってさえいたら、子どもはちゃんと動き出すのでしょうか?」とたずねられることもあります。ここで言う「ちゃんと動き出す」というのは、たとえば不登校の子どもであれば、「ちゃんと」学校に行きだすのかという意味のようです。「何も言わずに見守る」という、その人にとって「なかなかたいへんな努力のいること」を頑張ってやれば、子どもが「親の望む行動」をお返ししてくれるんですか? と聞いているかのようです。つらいことに耐えた見返りとして神様が望みをかなえてくれる。そんな思いで「見守る」をとらえている人に出会うこともあります。
私の考えは違います。見守るときに、親が子どもの気持ちに自分の気持ちを寄せること、そこに見守ることの本質があると考えています。子どもは何を見つめているのか。何を思っているのか。そのような、子どもの思いや気分に焦点を当てながら、子どもの存在を感じることです。
小さな子と遊んでいると、子どもがすぐに「ねえ見て! パパ見て!」などと言いますね。子どもは、自分が見ていること、やっていることを、親がちゃんと見てくれているか、何度も確認したがります。自分が感じている興奮を、親も感じているか、その表情や反応で、確認したいのですね。親に見てもらうこと、一緒に驚いたり喜んだりしてもらうこと。それは子どもにエネルギーを与えます。大好きな親に自分を見てもらう。それだけで子どもは力が出ます。子どもを見守ることの本質は、ここにつながっているはずです。
親は自分に関心を向けてくれている。自分が感じることに親は寄り添ってくれている。そう感じられること。それこそが親に見守ってもらうことで、子どもが得るものです。逆に、子どもを無視すること、親が子どもに関心を払わないこと。それは愛情をかけないということです。
不登校になって、ずっとゲームばかりしている子どもがいるとします。その場合に「子どもを見守るだけでいいんですか?」というとき、ゲームをしているという外側しか見えていません。なぜこんなことばかりして、やるべきことをやらないのか、とイライラしながら子どもを「見張って」います。でも、それは「見守って」いるのではないと私は思います。どんな気分でゲームをしているのか、何を考えているのか。子どもの思い、気分を感じてみようと心を寄せるのが「見守る」ということです。
そんなふうに言うと、「じゃあ、そうやって、子どもの思いを感じようとしていたら、そのうちに、子どもはゲームをしなくなりますか? ゲームの時間を守るようになりますか?」などと、質問が返ってくるでしょう。子どもの気持ちを気にかけたら、その見返りに、親が望んでいる結果を得られますか? というわけです。見守ることが、親にとって望ましい方向に子どもを操縦するための手段になってしまっているのです。
この点は、とにかく子どもを自分が思う方向に進ませようとして、焦っている、何も見えなくなっている親には、とても伝わりにくいところです。子どもを見守るということは、そうすることで、勉強するとか、宿題するとか、親の期待するように子どもを動かすためではないのです。そうではなくて、せっかく子どもと暮らしている、その限られた時間の素晴らしさをしっかりと味わうために、親は子どもを見守るのです。
それは、子どものためであると同時に、親自身のためでもあります。それこそが、子育てをすることで親が得られるものです。大人になることで忘れてしまった、子どものときの気持ち、子どもから見えている世界を、親はもう一度子どもを通して味わうことができます。そうすることで「子育てをしている幸せ」を、親は感じることができます。
子どもが何を見ているか、何を感じているかは、しっかり気持ちを寄せないと親にはわかりません。しなければならないことが、たくさんある毎日の暮らしの中で、それはなかなか難しいことです。それでも、子どもを見守るということはそういう、とても難しくて、贅沢なことです。そしてそこから得られるものは、子どもにも親にも大きなかけがえのないものです。
少し離れたところに住んでいる長男が、ときどき孫を連れて遊びにきます。孫は3歳半です。先日、孫が遊びに来たときのこと。虫が好きな彼と一緒に庭で虫探しをしました。敷いてあるレンガをひっくり返すと、アリ、ミミズ、ヤスデ、ダンゴムシなどが出てきます。彼は興奮して、台所からザルを持ってきて、その上に並べていきました。捕まえたミミズのうちの1匹がザルの網目の隙間に頭を突っ込んで脱出しようとしていました。ミミズの体はすごい作りになっていて、かなり小さな隙間に頭を差し込んで、そこから半分ほど既に体が逃げ出していました。彼は、ずっとそれを興奮しながら見ていましたが、ミミズが動けなくなって困っていると思ったのか、ザルの裏に出ているミミズの体をつまんで引っ張りました。そんなに引っ張ったら切れてしまうのではないか、と僕は思いました。けれど、彼は小さな指で実にやさしくミミズをつまんで、ゆっくりと引っ張ってうまく出してやりました。(子どもは生まれついて生き物をいたわる力というのがあるんですね。)
こういうときに、見守るというのは何も手出しをせずにただ彼を観察しているということではありません。レンガを持ち上げられなければ手伝ってあげますし、指を詰めたりしないように気をつけることだってそうです。場面場面で彼が何をしたい、見たい、楽しいと思っているか、何をこわいと思っているか、そういうことを近くで感じます。子どもが感じていることを近くで一緒に感じようとするのです。できるだけ誘導しない、できるだけ禁止しない、そして子どもの先に進もうとしない、それが子どもと遊ぶときに、大人が楽しむこつだと思います。
その日はそれに続いて、化石を発見しました。庭のあるところに以前はコンポストの中身を埋めてあったのですが、そこから、茶色く変色した骨の一部が出ていました。豚足の骨でした。だいぶ時間が経ってきれいに茶色い骨だけになっていました。孫は、それを土の中に見つけて、取り出して手に持って見ていましたが、突然、家の中にそれを持って入っていきました。まぁ、そんな汚いものを家に持って入られて困ったなと思ったのですが、やがて彼は自分の本を持って戻ってきました。それは恐竜図鑑でした。その図鑑のはじめのほうに、ステゴサウルスの骨格の精密な図が出ているのです。彼は、そのページを私に見せながら、「じーじ! これは化石だ!」と言いました。たしかに、豚足の名残の骨は、図鑑に出ている恐竜の脚の骨と同じ形でした。見つけた骨が、自分の好きな図鑑に出ているということに気がついて、飛んでいって図鑑をとってきて、私にも見せてくれたのでした。そのような子どもの心の動きは、近くで一緒にいなければわからないことです。見守っていなければ味わえないことです。
蕗の葉に蟻ゐることも子の歳月
(ふきのはにありいることもこのさいげつ)
という細見綾子さんの句があります。人生の中で、ほんの短い時間だけ、アリや小さな虫に子どもは惹きつけられる。子どもと一緒にいなければ、見向きすることもない世界です。蕗の葉にいる蟻に小さな指を伸ばす幼いわが子のそばにいて、母親である細見さんは、このような時間が(子の歳月が)あっというまに過ぎ去ってしまうことを感じていた、味わっていたはずです。
見守ることはとても時間や労力がかかること、贅沢なことです。見守らなければならない、のではなく、見守ること自体が楽しみであり、喜びをもたらすのです。なにか好ましい結果をもとめて辛抱して見守るのではなく、生き生きと動く子どもの心を近くで感じること。それは、子どもと暮らすことが与えてくれる幸せそのものです。
-
第1回小言を言わないということ
-
第2回鼻血の教訓
-
第3回誰が息子に現実を教えてくれるのですか
-
第4回子どもを本当に励ます言葉
-
第5回今のままではダメなんですか?
-
第6回乾燥機は使わないで
-
第7回ある幸福な一日
-
第8回吹雪の中を
-
第9回この子はどんな形の木になるのだろう
-
第10回鼻クソを拭かせてください
-
第11回徳島で一番の蕎麦
-
第12回迷ったり悩んだりするあなたを信じます
-
第13回なぜ子どもが話をしてくれないのか
-
第14回孫もワンオペ
-
第15回誰の気持ちが中心になっていますか?
-
第16回これだってすごくジェンダーな状況だよ!
-
第17回お父さん!お母さん!キャンプに行きませんか?
-
第18回規則正しい生活
-
第19回子どもの成長を尊いと感じること
-
第20回とうちゃんのようになりたいと思います
-
第21回娘が家にお金を入れない
-
第22回お父さんをどうしたらいいでしょう?
-
第23回結果ばかりにこだわる子ども
-
第24回山空海温泉のこと
-
第25回子どもの機嫌をとることへの罪悪感
-
第26回ごはん一杯おかわりするならゲーム15分
-
第27回理由も聞かずに味方になる
-
第28回いわゆるゼロ日婚約の知らせ
-
第29回子どもを叱るとき暴力はダメ
-
第30回「豚の珍味出てる」というLINE
-
第31回ゼッケンは毎年、つけ替えること
-
第32回反抗期を長引かせる方法
-
第33回この不幸を手放したくない?
-
第34回あえて甘えさせるという育児のぜいたく
-
第35回お話はうけたまわっておきます、という姿勢
-
第36回Eテレ出演と満里奈さんとの対談
-
第37回カビテ州立大学獣医学部
-
第38回あけましておはよう
-
第39回ちょっと待って! 寅さん!
-
第40回ツメハラと世間話ハラ
-
第41回おなかがすいた
-
第42回親への感謝
-
第43回去っていく後ろ姿の強さ
-
第44回あんたもたいへんやなぁ
-
第45回人に頼ることと、断られること
-
第46回子どもを見守ること
-
第47回スライダープールとスパイダーマン
-
第48回母さんも、いつもありがとうな
1965年東京都生まれ。医師・臨床心理士。京都大学医学部卒業。文学博士(心理学)。4人の男の子の父親。
現在は、奈良県・佐保川診療所にて、プライマリ・ケア医として地域医療に従事する。20年以上にわたって不登校やひきこもりなどの子どもの問題について、親の相談を受け続けている。
著書に『子どもを信じること』(さいはて社)、『子どもが幸せになることば』(ダイヤモンド社)、『去られるためにそこにいる』(日本評論社)、『子どもの不登校に向きあうとき、おとなが大切にしたいこと』(びーんずネット)がある。