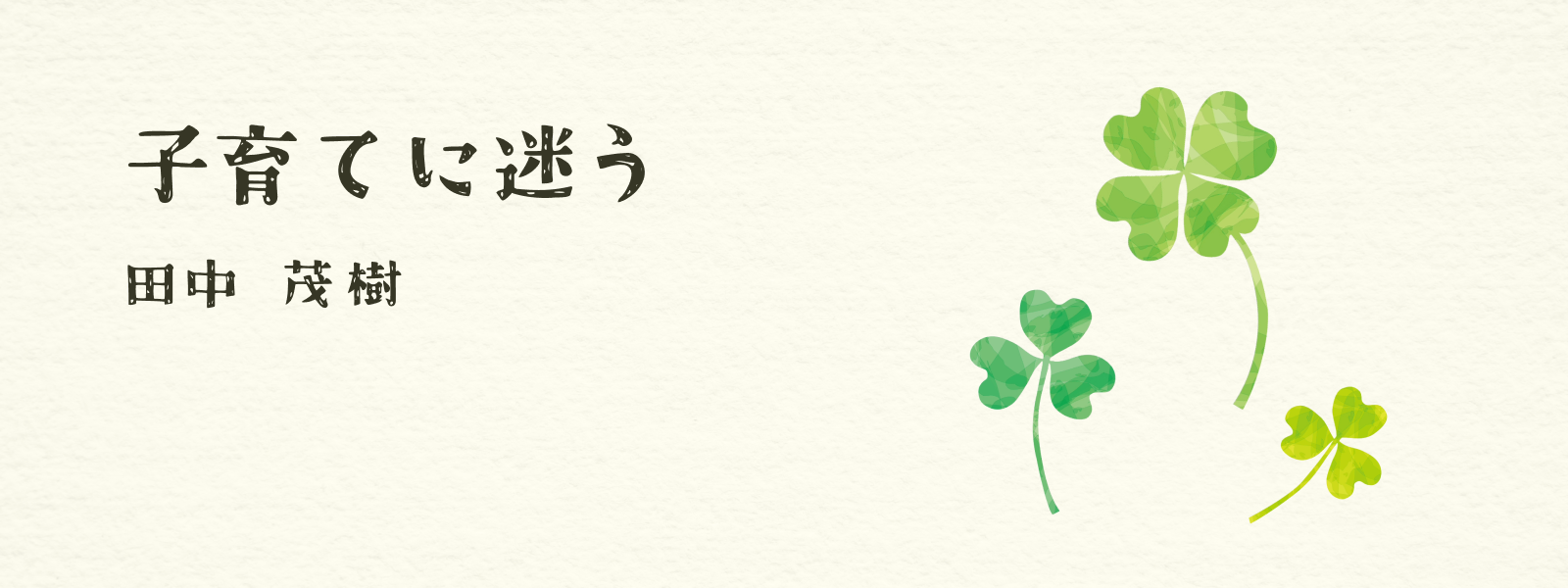自分も子育てでいろいろ悩みながら、子どもの問題について親のカウンセリングを長年続けてきました。また、地域の診療所で外来診察や訪問診療も担当しています。育児の悩みや家庭でのコミュニケーション、そのほか臨床の現場で出会ったこと、考えたことなどを書いてみます。
なぜ子どもが話をしてくれないのか
飲み会で友人がつぶやいていました。
「一緒に暮らしている子どもがほとんど口を聞いてくれない。すれ違っても挨拶もしない。もうそのことで悩んだりはしていないけれど、なぜそうなのだろうか」
まず思いついたのは、いわゆるマンスプレイニングの「親子版」。マンスプレイニングは、ひところよく話題になったのでご存知の方も多いと思います。男性が女性に対して、上から目線で説明をすることです。しばしば相手のほうが知識が多かったりするにも関わらず。女性より男性のほうが立場が上だ、知識が多いのが当たり前だ、というような偏見が根底にある現象ですが、親子だって似たようなことが起こり得ます。子どもは物事を知らないから、知識や経験の豊富な親が、教えてあげるのは当たり前だ、という「偏見」によって、子どもに対して上からの説明をしてしまう。そして親にはそういうことをやってしまっているという自覚がない。
こう書きながら、私も同じことをやっているのではと怖くなります。読み手よりも書き手のほうが、多くのことを知っているから、説明してあげるのだ、という思い込みで、こういうことをえらそうに書いているのでは……。
私は医師なので、患者さんにいろいろ説明をすることが多いのです。学校や塾の先生もそうでしょう。自分の持っている専門的な知識を相手に与えることが、仕事で求められていることなわけです。なので、説明する癖がついているようです。自分が知っていて、相手が知らない(と思われる)ことを説明してしまう。友人仲間も医師や教員が多いのですが、みな多かれ少なかれそういうところがあります。
子どもにしたらうっとうしい話です。聞きたくて質問したことに、簡潔に答えてもらうのはまだ辛抱できます。それだって(誰でも経験があると思いますが)、相手の説明を聞いているうちに、わかった、もういいです、十分です、という気持ちになりませんか。
対策としては、相手に「教えよう」としている自分の姿勢をよくよく意識することでしょうか。思い当たる節がある人は、あえて「相手のため」と思って情報を与えることを、自分に禁じてみるのもいいでしょう。知っているのに教えてあげないなんて、不親切じゃないか、不誠実じゃないか、と思うかもしれません。聞かれたら、答えたらいいでしょう、ごくごく簡潔に。けれども、そうでない場合は、相手の話を聞くことに徹してみましょう。相手の話でわからないところがあったら、そこだけを質問したらいいわけです。こっちからは情報を出さないようにする。こちらが話を主導したり、話題を変えたりしない。そういう聞き方、会話の仕方をしてもらうと、話しているほうは心地がいいものです。
上に書いたことに関係することですが、親が自分の話ばかりしてしまうパターンもよくあります。たとえば、子どもが「今度、キャンプに行こうと思っている」と話したとします。まだそれ以上、何も話していないのに、親のほうが「どこのキャンプ場に行くつもりなの?」とか、「来週は天気がよくないらしいよ」など、頭に浮かんだことをすぐに話してしまうような場合です。もしも、子どもの行き先が、親が行ったことのある場所だったりしたら、「自分が何年前に行ったときはこうだった、ああだった」などと、一気に自分の話にしてしまいかねません。
自分が子どもの立場だったとして、親にそういう話し方をされても、それでも話を続けたくなるでしょうか。そこが考えるべきところだと思います。ここまでで思い当たる部分がある人であれば(えらそうな書き方になってすみません)、すなわち、自分を顧みることができる人であれば、子どもとの会話を変えていくことができるかもしれません。
どちらが自分の話をするか、聞いてもらうか。それは子どもが小さいころの親子の会話を思い出すと、わかりやすいです。子どもはその日にあった出来事や、自分が感じたこと、考えたことを、親に聞いてもらいたいのです。話を「聞いてあげる」ことは、愛情を与えることと同じです。愛情を与えるという抽象的な言葉の具体的な例が、子どもの話を聞いてあげる、子どものことを見てあげる、子どもに関心を向ける、ということなのです。
「ママ! 見て!」という子どもの言葉は、「僕を愛して!」と同じです。子どもが幼いころは、子どもの関心はほとんどすべてが親に向いていますので、親は子どもに愛情をもらっています。やがて子どもの関心はほかのいろいろなもの、ほかの人に移っていく。子どもが大きくなって、親が子どもに小言を言ったり注意をするとき、「ちょっと聞きなさい!」「ちゃんと聞いてるの!」などと言いますね。表面的な意味の奥には、「私の話を聞いて」という、愛情を求める思いも入っているように、私には思えます。
親子で話をするときに、親はどうしても、昔の話、自分の話をしてしまいがちです。子どもに甘えているのです。子どもはやさしいので、聞いてくれることも多いでしょう。このとき、愛情のやり取りは子どもから親に向けられているといえます。年とった親と会って話をしたり、電話をしたりするときに、前に何度も聞いた話を聞きながら、これも親孝行だなと感じる人は多いでしょう。
親が自分の話をしてしまうことが、まったくだめだと言うつもりはありません。「今、自分は子どもに話を聞いてもらっているなぁ、ありがたいなぁ」というようなことに、親が自覚的であれば、節度も出てくるでしょう。私が言いたいのは、そういうことです。そうであれば、親の話を聞いている(聞かされている、聞いてくれている)子どもの気持ちについても、少しは考える余裕が出てくるでしょう。そういうスタンスで子どもと話ができれば、「うちの子は全然話をしてくれない」という状態にはなりにくいと思います。
まずは、子どもと話すときに自分の話をしないように意識してみる。今回はそういうチャレンジの話を書いてみました。
-
第1回小言を言わないということ
-
第2回鼻血の教訓
-
第3回誰が息子に現実を教えてくれるのですか
-
第4回子どもを本当に励ます言葉
-
第5回今のままではダメなんですか?
-
第6回乾燥機は使わないで
-
第7回ある幸福な一日
-
第8回吹雪の中を
-
第9回この子はどんな形の木になるのだろう
-
第10回鼻クソを拭かせてください
-
第11回徳島で一番の蕎麦
-
第12回迷ったり悩んだりするあなたを信じます
-
第13回なぜ子どもが話をしてくれないのか
-
第14回孫もワンオペ
-
第15回誰の気持ちが中心になっていますか?
-
第16回これだってすごくジェンダーな状況だよ!
-
第17回お父さん!お母さん!キャンプに行きませんか?
-
第18回規則正しい生活
-
第19回子どもの成長を尊いと感じること
-
第20回とうちゃんのようになりたいと思います
-
第21回娘が家にお金を入れない
-
第22回お父さんをどうしたらいいでしょう?
-
第23回結果ばかりにこだわる子ども
-
第24回山空海温泉のこと
-
第25回子どもの機嫌をとることへの罪悪感
-
第26回ごはん一杯おかわりするならゲーム15分
-
第27回理由も聞かずに味方になる
-
第28回いわゆるゼロ日婚約の知らせ
-
第29回子どもを叱るとき暴力はダメ
-
第30回「豚の珍味出てる」というLINE
-
第31回ゼッケンは毎年、つけ替えること
-
第32回反抗期を長引かせる方法
-
第33回この不幸を手放したくない?
-
第34回あえて甘えさせるという育児のぜいたく
-
第35回お話はうけたまわっておきます、という姿勢
-
第36回Eテレ出演と満里奈さんとの対談
-
第37回カビテ州立大学獣医学部
-
第38回あけましておはよう
-
第39回ちょっと待って! 寅さん!
-
第40回ツメハラと世間話ハラ
-
第41回おなかがすいた
-
第42回親への感謝
-
第43回去っていく後ろ姿の強さ
-
第44回あんたもたいへんやなぁ
-
第45回人に頼ることと、断られること
-
第46回子どもを見守ること
-
第47回スライダープールとスパイダーマン
-
第48回母さんも、いつもありがとうな
-
第49回人材という概念のない国
1965年東京都生まれ。医師・臨床心理士。京都大学医学部卒業。文学博士(心理学)。4人の男の子の父親。
現在は、奈良県・佐保川診療所にて、プライマリ・ケア医として地域医療に従事する。20年以上にわたって不登校やひきこもりなどの子どもの問題について、親の相談を受け続けている。
著書に『子どもを信じること』(さいはて社)、『子どもが幸せになることば』(ダイヤモンド社)、『去られるためにそこにいる』(日本評論社)、『子どもの不登校に向きあうとき、おとなが大切にしたいこと』(びーんずネット)がある。