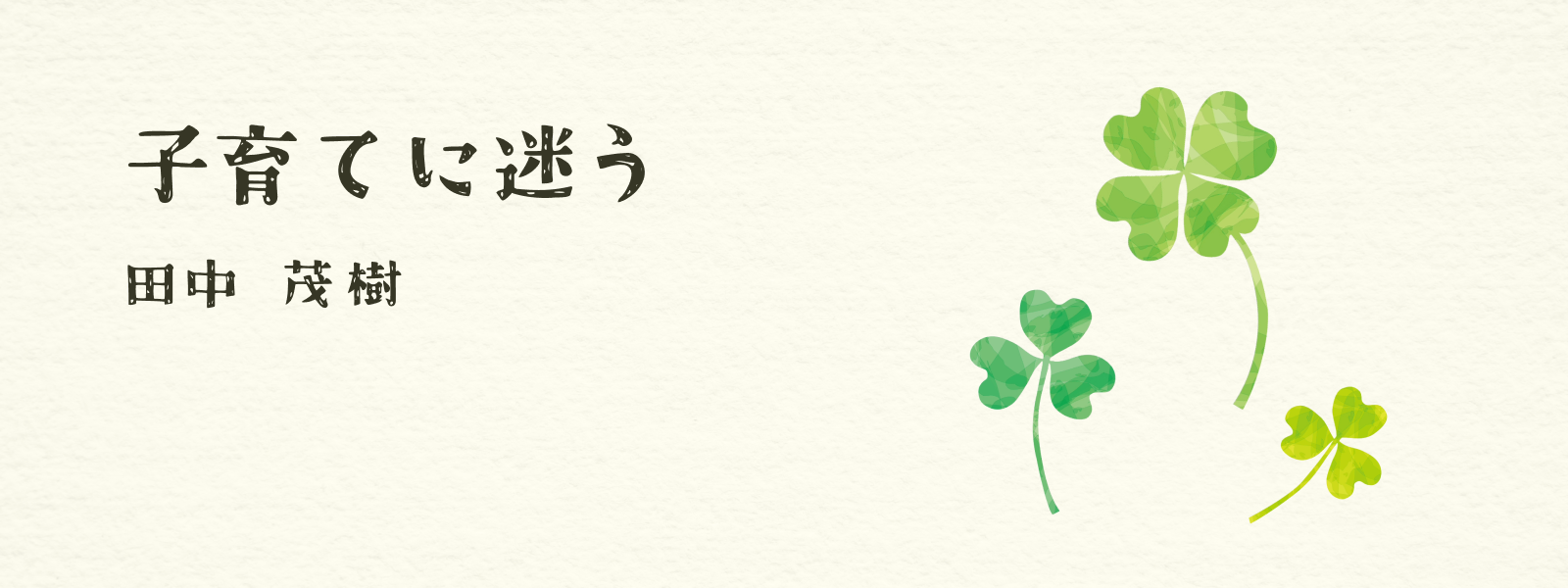自分も子育てでいろいろ悩みながら、子どもの問題について親のカウンセリングを長年続けてきました。また、地域の診療所で外来診察や訪問診療も担当しています。育児の悩みや家庭でのコミュニケーション、そのほか臨床の現場で出会ったこと、考えたことなどを書いてみます。
人に頼ることと、断られること
買い物に行き、目当てのものを見つけられないときに、すぐに店員さんにたずねる人がいます。僕の妻はそういうタイプです。僕の買い物であっても、すぐに聞こうとするので、「いや自分で探すから。いいから」と引きとめることがよくあります。
出かけた先で、道をたずねるなども同じです。僕は、自分で探したい。彼女はすぐに誰かにたずねたい。たいていの場合、たずねられた人は、いやがることなく親切に教えてくれます。店員さんならそれが仕事だから、当たり前です。でも、僕は他人に質問すること、教えてもらうことに抵抗があり、ほとんどの場合、スマホで調べようとします。それだって、他人の(自分以外の)力に頼っているわけだから、同じことなのに。結局のところ、面と向かって相手にお願いすること、教えてもらうことが苦手のようです。もっと言うと「相手は面倒だと感じるだろうな」と僕が思ってしまっていること、そして、もしも断られたら大袈裟にいうとショックだと感じていること。その二つの理由で、他人になにかを頼むことを、僕は恐れているようです。でも、妻はそうではありません。なんでも、ずばっと頼んで、よく断わられています。一緒にいて、そういう場面に実によく出くわします。
妻が断られた場面は、すぐに思い出せます。
たとえば、先日、東北に旅行したときのこと。寝坊して朝食の時間にすこし遅れました。食堂で働いていたのはアルバイトの外国人の若者何名かと、彼らのリーダーをしている地元の高齢の男性でした。その男性は僕たちを席に案内しながら、「はい、あんたたちが最後だよ」と、訛りのある言葉で言いました。とくに怒っている感じはなく、むしろコミカルで和む感じがしました。東北の言葉は実にあったかいですね。遅れた手前、申し訳ないなと僕は思いながら食べ始めました。妻は気にするでもなく、このお味噌汁おいしいね、などとうれしそうに言って、お茶を持ってきてくれたその男性に「このお味噌汁、すごくおいしいですね! 自家製の味噌なんですか?」と聞きました。その男性はにこりともせず「そうですよ」と答えました。妻は「このお味噌って、買えたりするんですか?」と、ひるむ様子もなくさらにたずねました。男性は無表情のまま「売ってません」と言いました。「せん」がぶちっと切るような言い方で、思わず僕は吹き出しました。遅れてきてなにを言っとるんだ、という感じではなく、忙しいし、疲れてるんだから、愛想なんかないですよ、という感じでした。でも、不思議と感じは悪くなかったのです。
言い回しや表情に愛想がないだけで、率直に事実を言っただけ、というのでしょうか(関西なら「すみませんね、お分けしてないんですよ」などと表面的には笑顔で言いそうな場面でした)。横でヒヤヒヤしながら僕は聞いていました。ところが、妻は平気で「なんや買えないんか、残念。まあ、駅でも似たようなのは買えるよね」などとつぶやいていました。僕だったら、そんなことたずねて、あんなにストレートに「売ってません」と言われてしまったら(勝手に相手の怒りまで想像して)、しばらく凹みそうです(こうして今でもはっきり覚えているほどです)。
その翌日、別の宿でのことです。朝食付きの予約しかとれなかったのですが、僕たちは早朝に出なければなりませんでした。朝食の時間には間に合いません。夕食のときに、スタッフの女性に、妻がまたしてもたずねました(相談したら、僕が「やめとけ」と言うから、僕に相談はありません)。
「あのぉ、私たち、明日早く出ないといけないので、朝食は食べられないんです。おにぎりとか作ってもらうことなんかできませんか?」
小さな宿で、その女性は近所から通って来られている人のようでした。その女性も、「申し訳ないですね、それはできないんですよ」などと、表面的にやさしい口上はいっさいなし。ずばっと「できません」と、前の日と同じく「せん」の語尾は短く高く、僕には愛らしく聞こえる抑揚で答えました。「わかりました」と妻は返して平気でした。おにぎりぐらい、コンビニで買ったらいいやんか、あの従業員の人、そのために朝早く来ないとあかんやん、そんなことしてくれるはずないやん、などと僕は思い、そう妻に言いました。しかし、妻は、まあ、聞いてみたっていいやん、となんでもないという感じでした。
どちらの場面も、言われた相手は、「こいつはなにを言っとるんだ」と思いそうな状況です。僕は少なくともそう感じていて、とてもそんなことを頼む気にはなれませんでした。でも、妻には違うように見えているのだと、そこが不思議でありおもしろく感じました。これは、世界のモデルの違いでもありますね。僕から見えているのは、まわりの人は助けてくれない世界。妻が見ているのは、頼んだらなんとかなるかもしれない世界(実際にはしょっちゅう断られているのですが)。
僕は、断られるのはみっともないし、ショックなので、頼むぐらいなら自分でなんとかしようとします。でも、自分が頼まれたら、その頼まれたことがよほど面倒なことでないかぎり、やってあげるのは嫌ではなく、むしろ気持ちのいいことだと感じるでしょう。頼んでくれたことに感謝さえします。そういうふうに(この人になら頼んでみようかな、と)思ってもらえたことをうれしくも思うからです。それは妻も同じようです。ただ、周囲の人たちも頼んだらやってくれそうだと彼女には見えているようです。そして、断られても、とくに気にしない。タフであり、楽観的だということなのでしょう。
これは人に頼る力であり、断られることを怖がりすぎない力、そういう能力、資質だなと思いました。そういうことを妻に話すと、「だから私は二浪もしたんだろうね」と明るく言いました。
自分の子どもたちに、周囲の人は、世の中は、どういうふうに見えているのかなと聞いてみたくなりました。
-
第1回小言を言わないということ
-
第2回鼻血の教訓
-
第3回誰が息子に現実を教えてくれるのですか
-
第4回子どもを本当に励ます言葉
-
第5回今のままではダメなんですか?
-
第6回乾燥機は使わないで
-
第7回ある幸福な一日
-
第8回吹雪の中を
-
第9回この子はどんな形の木になるのだろう
-
第10回鼻クソを拭かせてください
-
第11回徳島で一番の蕎麦
-
第12回迷ったり悩んだりするあなたを信じます
-
第13回なぜ子どもが話をしてくれないのか
-
第14回孫もワンオペ
-
第15回誰の気持ちが中心になっていますか?
-
第16回これだってすごくジェンダーな状況だよ!
-
第17回お父さん!お母さん!キャンプに行きませんか?
-
第18回規則正しい生活
-
第19回子どもの成長を尊いと感じること
-
第20回とうちゃんのようになりたいと思います
-
第21回娘が家にお金を入れない
-
第22回お父さんをどうしたらいいでしょう?
-
第23回結果ばかりにこだわる子ども
-
第24回山空海温泉のこと
-
第25回子どもの機嫌をとることへの罪悪感
-
第26回ごはん一杯おかわりするならゲーム15分
-
第27回理由も聞かずに味方になる
-
第28回いわゆるゼロ日婚約の知らせ
-
第29回子どもを叱るとき暴力はダメ
-
第30回「豚の珍味出てる」というLINE
-
第31回ゼッケンは毎年、つけ替えること
-
第32回反抗期を長引かせる方法
-
第33回この不幸を手放したくない?
-
第34回あえて甘えさせるという育児のぜいたく
-
第35回お話はうけたまわっておきます、という姿勢
-
第36回Eテレ出演と満里奈さんとの対談
-
第37回カビテ州立大学獣医学部
-
第38回あけましておはよう
-
第39回ちょっと待って! 寅さん!
-
第40回ツメハラと世間話ハラ
-
第41回おなかがすいた
-
第42回親への感謝
-
第43回去っていく後ろ姿の強さ
-
第44回あんたもたいへんやなぁ
-
第45回人に頼ることと、断られること
-
第46回子どもを見守ること
-
第47回スライダープールとスパイダーマン
-
第48回母さんも、いつもありがとうな
-
第49回人材という概念のない国
1965年東京都生まれ。医師・臨床心理士。京都大学医学部卒業。文学博士(心理学)。4人の男の子の父親。
現在は、奈良県・佐保川診療所にて、プライマリ・ケア医として地域医療に従事する。20年以上にわたって不登校やひきこもりなどの子どもの問題について、親の相談を受け続けている。
著書に『子どもを信じること』(さいはて社)、『子どもが幸せになることば』(ダイヤモンド社)、『去られるためにそこにいる』(日本評論社)、『子どもの不登校に向きあうとき、おとなが大切にしたいこと』(びーんずネット)がある。